
0:59:48
割引情報をチェック!

AI BUSINESS SHIFT 第8回 機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第8回です。 第8回「機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル」では、AIが営業現場にどのような変化をもたらしているのか、営業担当者・営業マネージャー・組織としての役割や戦略が、AIによってどう進化していくのかを、営業プロセスの分解や実際の現場事例を通じて学びます。 ■こんな方におすすめ ・AIを活用した営業活動の最新動向や現場のリアルを知りたい方 ・営業現場の変化に直面している営業マネージャー・現場リーダーの方 ・AI時代における営業戦略や営業マネジメントのあり方を学びたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年2月制作)
会員限定

マネジャーのための仕事の任せ方
「仕事を任せると失敗が怖い」「自分でやった方が早い」マネージャーとしてメンバーやチームの力を引き出しながら成果を上げるには、どのように仕事を任せていけば良いのでしょうか? 変化の激しい時代において、マネージャーとして成果を上げ続けるためには、メンバーの個性や特性を理解し、それに合わせた効果的な任せ方を身につけることが重要です。このコースでは、ソーシャルスタイル理論を活用してメンバーごとに最適なアプローチを学びます。「任せる力」を高めることで、チーム全体の成長を促進し、自身のリーダーシップを発揮できるようになっていきます。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2024年12月制作)
会員限定

AI時代の個人力
AIが仕事や社会の前提を変え続ける今、最も求められるのは「他者に代替されない個としての力」“個人力”です。 本コースでは、澤円氏の著書『個人力』をもとに、AI時代をしなやかに生き抜くための「前向きな自己中戦略」を学びます。 テーマは、「Being(ありたい自分)」を中心に据え、自ら考え(Think)、変化し(Transform)、協働する(Collaborate)ことで、自分らしい価値を発揮していくこと。 リスキリングやAI活用が叫ばれる今こそ、スキルより先に“自分の軸”を問うことが重要です。 あなたは何を大切にし、どんな未来を描きたいのか? このコースは、あなたが“ありたい自分”として生き、キャリアをデザインしていくための思考と行動のガイドになります。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年11月制作)
会員限定
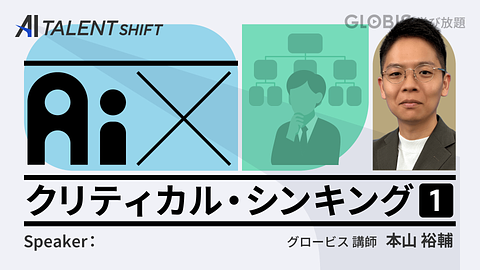
【AI×クリティカル・シンキング】①イシューと枠組みでプロンプトを磨く
生成AIから期待する回答を引き出せず、試行錯誤を重ねていませんか。 本コースでは、生成AI活用の質を高める鍵として、クリティカル・シンキングの視点からイシュー設定と枠組みを押さえる重要性を解説します。 目的に直結する問いの立て方や、プロンプトに落とし込む際の実践ポイントを具体例とともに学ぶことで、AIをより思考のパートナーとして活用できるようになります。 生成AIを業務で使い始めた方から、活用を一段深めたい方まで、再現性あるプロンプト設計を身につけたい方におすすめの内容です。 さらに学びを深めたい方は、こちらも合わせてご覧ください。 【AI×クリティカル・シンキング】②AIの弱点との向き合い方 https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/cdfe41e3/learn/steps/62198 ※本コースは、AI時代のビジネススキルを学ぶ「AIタレントシフト」シリーズの一環として提供しています。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
会員限定

リーダーの挑戦⑤ 藤田晋氏(サイバーエージェント代表取締役)
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第5回目のゲストは、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋氏。起業の理由、経営をどうやって学んだか、アメーバブログ・ABEMAの立ち上げ、経営チームづくりについてなど聞いていきます。(肩書きは2020年12月11日撮影当時のもの) 藤田 晋 サイバーエージェント 代表取締役 堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
会員限定

ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 前編 なぜ眠れないのか?~
「仕事が終わらないから睡眠時間を少し削ろう…」「業務時間中なかなか集中できない…」「毎日朝起きるのがつらい…」。 あなたはこのような経験をしたことはありませんか? 仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削りがちなのが「睡眠」時間。 実は今、日本社会は世界と比較して「最も眠らない国」だということもわかってきています。 慢性的な睡眠不足は、心身の健康に悪影響なだけでなく、仕事のパフォーマンスにも当然大きな影響を与え、社会全体の経済損失につながります。 このコースでは、基本的な睡眠リテラシーを学んだ後の「問題解決編」として、「なぜ多くのビジネスパーソンは眠れないのか?」について解説していきます。 ▼本コースで学べる主な内容 ・そもそも眠れないことは何が問題なのか? ・眠れなくなってしまう原因とは? 睡眠不足の原因は認知機能の問題にありました。 自身の睡眠不足に対し、正しく「気づき・理解し・行動を変える」第一歩を踏み出しましょう。 ▼関連コース ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~リテラシー編~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/24575c03/learn/steps/53129 ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 後編 どうしたら眠れるのか?~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/4ba981e9/learn/steps/62042 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

大阿闍梨 塩沼亮潤が死の手前で見つけた「生き方」
あすか会議2018 第4部分科会B-1「極限の世界で見つけた人生の歩み方」 (2018年7月7日開催/国立京都国際会館) 1300年間で2人目となる大峯千日回峰行満行を果たした塩沼亮潤大阿闍梨。48キロの山道を1日16時間掛けて歩き、それを千日間に亘って続ける過酷な行の中で、どのような悟りを得たのか。そして、9日間、断食・断水・不眠・不臥を続ける四無行満行という極限の世界で何を見つけたのか。塩沼氏が「創造と変革の志士」へ贈る「人生の歩み方」とは。(肩書きは2018年7月7日登壇当時のもの) 塩沼 亮潤 慈眼寺 住職
無料
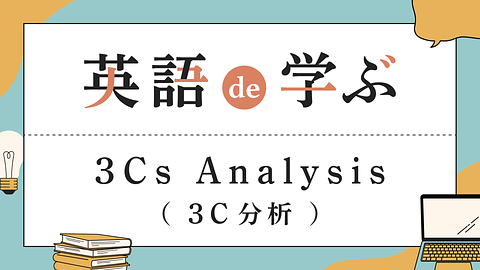
英語 de 学ぶ!3Cs Analysis(3C分析)
このコースでは、グロービス学び放題の英語版である『GLOBIS Unlimited』のコースの中から、ビジネスで役立つ頻出の英語表現をピックアップしています。英語ネイティブの方が実際に見ているコースなので、リアルなビジネス英語の表現を学ぶことができます。 今回のコースは「3Cs Analysis(3C分析)」です。一緒に『英語で』ビジネス知識を学んでいきましょう! ▼今回扱ったUnlimitedコース続きは下記からご覧いただけます 3Cs Analysis https://unlimited.globis.co.jp/en/courses/da5ca962/learn/steps/36362 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
コメント8305件
tttomy
「不満足がみたされる」の反対は「満足になる」のではなく「不満足なし」という理論はなるほどと思った。教育設計をする上で大事な理論ですね。
negimiso
満足と不満足が対義語ではない、というのが新しい視点でした。
tkrsbt
不満が無い≠満足 というのは考えなければいけないと思いました。仕事に慣れてきて安定した成果をだせるようになると、不満が無いという人が増えてくるが、仕事に満足しているという意味では無いということなので、安心してはいけない。
tohru
・例えば社内のライバルが表彰される場合なども衛生要因を下げる原因になるのかなと感じました。
・社内の衛生要因を図る際など、「満足」の反対は「不満」でなく「満足でない」という考え方は忘れないでおこうと思いました。
shizhi
業務だけでなく、子育てなどでもなぜ子供のやる気がないのかなど考えるときに使えそうな考え方だと思いました。
norinori_hr
ハーツバーグの衛生要因、動機付け要因は初めて学んだわけではないが、理解が不十分なところがあり、端的に復習する事ができた。実務に応用するとなると、理解が不十分では話にならない事を実感した
htnakaga
僕個人としては昇給は動機付け要因にも入ってくる!笑
つまり、項目はその人それぞれだから、相手にとって何が衛生要因なのか?動機付け要因なのか?
考えてあげることは、必要なのかな?
hiro_0214
衛生的/動機付け要因が自分の中で混在していたが、切り分けられる事ができた。
留意点については、正しく成果を上げる為に、利益を意識する事の必要性は感じた。
tsuguto
不満の解消が必ずしも満足に繋がらない事を学びました。ありがとうございました。
fujifuji
マイナス面とプラス面
どちらかだけでもダメということで整理されました。
生産性や利益に必ずしもつながらないとのことですが
リーダーの戦略やコンセプトが正しければこのようなことをケアすることで
メンバーのやる気やロイヤリティが高まれば
その戦力によって成果は見込めると思いますので
すごく重要な観点だと思いました。
常日頃から意識していきたいと思います。
いいですね。このカリキュラム。
takky
満足の反対は不満足 ではない。との考え方参考にあります。
yamada_5000
『個人の満足』と『企業の利益』の両方に目を向けることが大切。
また、今の自分が満足しているからといって、組織の全員が満足しているわけでは
きっとない。個人と組織、そして企業の利益と、全体と見られるようになっていきたい。
eiric_ride
マズローとの関連はどうなのか?
低次のものは衛生要因、高次のものは動機付け要因になる傾向があるか?
owh_jinji_ex
各個人の衛生要因、動機づけ要因には計り知れないものがある。生い立ち、キャリアなどが大きく影響している。
shinichi-689
動機付け要因と衛生要因をよく分析し、バランスよく施策を打つことが重要ないことが理解できました。
akimichi-saito
衛生要因と動機付け要因に分けることにより、スタッフのモチベーションにアプローチすることができる。両方のバランスが大事であり、満足の反対が不満足ではなく、不満がないというのはとても勉強になりました。顧客への商品開発にも応用できる重要な理論であります。
koji-1258
衛生要因について、強く共感しました。
hirata_eriko
仕事の動機づけ、衛生要因双方を意識しながら人事制度を考える必要があると感じた。多くの大企業では衛生要因に目立った欠陥はないが動機づけの部分で改善できる点があると感じた。
wkiymbk
「動機づけ要因には、仕事の達成感、責任範囲の拡大、能力向上や自己成長、チャレンジングな仕事などが挙げられる。 衛生要因には、会社の方針、管理方法、労働環境、作業条件(金銭・時間・身分)などが挙げられる。
動機づけ要因を与えることにより、満足を高め、モチベーションを向上させることができる。一方、衛生要因に対して手を打つことにより、不満は解消されるが、そのことが満足感やモチベーションを高めるとは限らない」ということを学びました。満足と不満は別であり両方に着目するという視点をチーム運営に活用します。
yameeee11
私が直面している問題だったのでとてもよくわかりました
ryu-papa
満足の逆は不満足ではない。
motomi0024
満足⇔満足なし、不満⇔不満なし。
という考え方が新鮮に感じた。チームに関する不満と満足している点をチームメンバーにアンケートしてみたいと思いました。
takeru_
・よくインセンティブについて考えるが、内発的動機と外発的動機に着いても考えさせられた。
内発:社会や組織に貢献したい、人の成長を促したいといった自発的なモチベーション
外発:金銭的報酬や昇進(ポスト)
・衛生要因や動機付けについても、両サイドから部下が働きやすい環境を整備することがマネジメントも役割。
bbr
職務満足度を上げる方法として給与を上げたらという意見もあるが、それは不満でなくなるだけで満足度が高くなるわけではないことを理解しました。
不満があるのか、不満はないが満足していないのかを理解した上で何を補うか対策する必要がある。
kounoy4347
ありがとうございました。
kusa3563
理解しました。
yu-ji
最終的には会社に利益を残さなくてはいけない。が前提である。
とにかく、バランスが大事。モチベーションのUPは個々の性格にも寄るのではと。
ishii201
衛生的な要因は対比していないことに注意
santaku
衛生と動機付け要因のバランスの難しさと重要性が理解出来ました。
kami5
動機付け要因、衛星要因を自分にあてはめて考えるとなるほどと納得でき、理解が深まる。
kachin
モチベーションは、動機付け・衛生要因のバランスが非常に大事であることが
理解できた。今後意識しながら所属員と接していきたい。
ke_20190513
不満なし=満足でないということは気付きになった。
sue_0120
仕事に対する満足、不満足の要因を知って、自分自身で思っていたことと違っていた部分もあり、満足なし、不満なしの考え方も知って学びとなった。
chagezo
米フレデリック・ハーズバーグの提唱した2要因理論で、職務満足感は動機付け要因(昇進や表彰、チャレンジ)と衛生要因(給与や労働時間)で高くなったり低くなったりするというもの。衛生要因は取り除いても不満がなくなるだけでモチベーションアップに直結しないところが注意点。また衛生要因が解消されていない中で動機付け要因を改善してもモチベーションにつながらないことも重要。部下の満足度合いが低い時に、何が足りていないのかを考えるにあたって活用したい。
mrst_990421
長年、決まったポジションで同じ業務を担当していると、「その業務は自分にしかできない」「任されている」という高度な「動機付け」につながる一方、年数が経つにつれ、「それしかやらせてもらっていない」「他の仕事にチャレンジしたい」という欲求が出てくる。この場合、業務に「満足はしていない」が、長年の経験から、「高い生産性は残せる」という結果をもたらせることもある。
dask-k-22
自分の職場で考えた時に、衛生要因は上位の判断で決まってしまう事が多く今の職位だと関与できる事が少ないと感じます。
たか、動機付け要因は自分の仕事の裁量で決めてる事(チャレンジングな仕事の割り振り等)もあるので、周りのメンバーへ働き掛けができそう。
hacchan
入社まもなく退職してしまう人などを減らすために、動機付け・衛星要因を意識することが大事だと思う。
ilovetosucity3
近年、正規社員と非正規社員の処遇の格差が話題になっている。企業現場においては、正規社員であるからといって、能力が高く、モチベーションが高い、というような理想的な社員だけでないこともある。また、非正規社員であっても能力が高く・モチベーションが高い方々も多い。個々の処遇を、納得性のある形で決めることができる会社でありたいが、その制度設計はなかなか難しい。一方、現場の管理者・マネージャーは、衛生要因と動機づけ要因のような観点で不満を抽出・改善しつつ、適切な動機づけを行いモチベーションを維持することを、常に意識しておく必要がある。
bs-hide
年初に異動した新しい職場にて、業務改善(より働きやす職場環境の構築)を担当している。1Qに本部内の全員から多くの不満、要望を募集した結果、多くの意見を集めることが出来た。
当初は、これらの優先順位をつける際に、緊急度と重要度の2軸で整理し、更に、物理的な課題なのか、対人・組織の課題なのかを層別して、取り組むべき順位を決めようとしていた。
しかし、今回の学びでは、我々の本部では、衛生要因と動機付け要因では、衛星要因を取り除くことを優先して着手したほうが良いと感じたので、その軸も加えて実施の優先順位を決めていければと考えている。来週早々に、これらのFWで課題を整理してみる。
sakuranohana
まさに「動機付け」「衛星要因」のミスマッチが当社だ。
どちらか一方だけを解決してもダメなのだ。両方をきちんと回していく方法を編み出す必要がある。
「不満がないから満足」という勘違い。「不満がないのは、単に不満無し状態なだけ」これは深い。働く人の満足をどうやって上げていくかを真剣に考える。本当に重要だと思った。
i___k
・衛生要因が満たされていない人に動機付けを行ってもモチベーションは上がらない、というのは経験したことがあるのでしっかりくる。これを繰り返さないためには、部下の状況をしることが大切。
・動機付けを行う際の留意点である、組織の目標とリンクしているか、という観点は重要。ここでも、何のためにやるのか、が大切。
getting-better
会社の利益との相関を考えるという視点は気づきだった。
衛生要因を取り除き、動機付けを付与することの両方を考える必要があることが分かった。
ueta_k
メンバーに対し、「ここまでやっている(譲歩している)」「条件を出している」「特別に評価した」等、一方通行になりがちである。メンバー一人ひとり、何が衛生要因なのか動機付けなのかを把握することで最適解に導ける。その視点を持ちつつコミュニケーションしたいと思います。
kazuro_f
今、私の手元に人間関係的に問題有りの人間がいます。仕事のキーパーソンであり、気難しく、接触するのにとても気を遣います。ですので、この方法を早速試してみようと思います。
ya1
「衛生要因」の具体例として、チャレンジングな仕事の付与は当てはまらないとされているが、チャレンジングな仕事は一歩間違えればパワーハラスメントの6類型の過大な要求につながりかねない。個人を完全に見極めないと適切なチャレンジングか否かの判断は大変難しいと感じた。
yama_4988
パートタイムの皆さんにチャレンジングな業務をお願いする際に、動機付け要因衛生要因の関係を十分理解しておくことが必要だなと思いました。
「不満」の反対は「満足」ではないんですね…今回も勉強になりました。
hasegwa86
不満でない≠満足
という主張からは多くの示唆を得ることができる
自分の仕事に関して社内のモチベーションを上げるための施策をうつときに忘れてはならないことだと学んだ
ただ、動機付けと衛生って対になる概念なのかな?
マズローの5要因でいうところの低いレベル(ブラック職場)では衛生は適切な言葉といえるかも知れないけど、もうちょっと適切な言葉はないものか?
mat09
衛生要因と動機付け要因を混在しないように理解したい。
ringo_6
不満の解消≠満足という視点を学びました。
動機づけをいう言葉はよく聞きますが、衛生要因については初めて学ぶことが出来ました。
akiranaga17
「満足ではない」は、「不満足である」とは限らない、
「不満足ではない」は、「満足である」とは限らない。
これは重要である。
mitsuo_1860
「利益につながる施策か」「不満なし≠満足」を意識いたします。
tm03
単に給与を挙げても動機づけ要因が無いとモチベーションが上がらないという考え方はなるほどと思いました。
yuki_0719
ハーズパークの動機付け要因、衛生要因の考え方は部下の管理にも有効と考える。自分でチャレンジングな目標を設定して、挑戦させることで動機付けさせるて、主体的に生き生きと仕事をさせることができる。但し、これが業績を連動しない、自分の趣味や思い込みの方向に行かない様に注意しなくてはならない。
kzhr2358301
不満でない≠満足ということではない・・・
お客さまの声を聞くとき肝に銘じとかなければならない。
seuta_r
自分が、部下のモチベーションをあげるときにどちらの項目に向けてのアプローチなのか、バランスを考える上でも非常に参考になった
oikawa_t
満足と不満足が対義語ではない事になるほど!と思いました。自分に無かった考えで今後この言葉を忘れず大切にしたい。
ga_0608
動機付け要因と衛生要因の関係が理解できたが、衛生要因を満たすためには会社の状態にもよると思うので中々バランスを取ってモチベーションを上げる方向に持って行くのは難しいと思う。
tadayuki631129
衛生要因と動機付け要因に分けることにより、スタッフのモチベーションにアプローチすることができる。両方のバランスが大事であり、満足の反対が不満足ではなく、不満がないというのはとても勉強になりました。顧客への商品開発,従業員教育にも応用できる重要な理論であります。
kei0415
職務環境に付随する衛生要因よりも、個人の職務内容に付随する動機付け要因を重視したほうが業績に寄与するのではないか?と考えています。
具体的には職務充実を図ることがモチベーションアップにつながると考えます。
kameco
「不満はない」は「満足している」とは違う。これは、まさに今の私だと思います。上司との面談で「今の仕事に満足ですか」と聞かれ「特に不満はないけど、満足とは少し違う」と思いました。マネージャーはこの点に気づくべきだと思いました。
yasuhiro68
メンバーの不満がどこにあるのかを考えながら業務を遂行していきたい。
hiro_yoshioka
たとえば、自分は、同僚は、それぞれ、
どういう点を不満に思ったり、満足しているのか 考えてみようと思いました。
mk57
一概に動機付け要因を満たせればモチベーションがあがるわけではないこと、衛生要因の解決も合わせて考えることが必要
gantetsu
自分の組織を俯瞰してみてみることが大事と感じた
xkayano
エンゲージメント向上の施策考えるにあたって、チームから上がってくる要望をどのように分析し実行していくかを組み立てるためのフレームワークとして活用できると考えました。
saito-yoshitaka
不満足ではない の反対は満足であるとは限らない点が参考になりました。
llasu_ito_0502
”動機付け”、”衛生”、と言葉では簡単ですが、要因と付けると、意味が深いですし、全く別の概念になるのですね。今まで、偏った見方(考え方、一面しか見ていない)で行動していました。しっかりと復習、理解して、自分の手の内にしっかりと入れたいですね。教えて頂き、ありがとうございます。感謝申し上げます。
r-s-
弊社の経営陣が寝る時にリピートで流してあげたい動画でした。
yuhi1211
不満の原因(衛生要因)と満足でない原因(動機付け不足)は、それぞれ別々のものであるというのは新たな発見であった。部下や組織の運営を考える際に、それぞれ分けて考えるよう注意していきたい。
また今回の考え方を、今の自身にも当てはめてみて、良い点と改善点を以下と分析した。
衛生要因)
・良い点:給料や福利厚生は他に比べて良い方、おだやかないい人達に恵まれている、テレワーク推進など働き方の自由度が高い
・改善点:会社の場所が辺鄙な所にある、経営幹部との距離が遠い(意見交換する機会があまりない)、最近はあまり給料が上がっている気がしない
動機付け)
・良い点:社会インフラというやりがいのあるものづくりに主体(大企業)として携われている、これまでの研究成果が形になるのを見届けられている達成感がある、今年度になって目新しい仕事を追加してもらえた
・改善点:入社時の目標を達成しかけていて燃え尽き症候群の懸念、社内の大先輩方の各キャリアを見ても魅力を感じるものがあまりない、海外や社外出向など要望がなかなか通らない、企業研究所員のわりに突飛な研究にあまり携われていない
kaki_077
動機付け要因、衛生要因双方が満たされないとモチベーション向上につながりにくいというのは面白い。
chiho03
幹部や経営層から提示された施策に対し、「そこじゃない」と困惑している社員をよく見ます。
衛星要因が満たされていない状態で、動機付け要因の施策を提示されているせいで、このような反応になるんだな、と非常に腹落ちしました。
部門やチームのメンバが、どの位置に存在しているのか確認するのも手だなと思います。
w-colon
仕事の動機づけはデリケートでもある
test_
動機付け、衛星要因が多様化していることにも注意が必要であるように感じた。昇進やチャレンジングな仕事を必ずしもすべての人が望んでいるわけではない。画一的な取り扱いをしないようによくコミュニケーションをとることが必要だと思う。
minotakayuki
動機付けと衛生要因について、勉強になったので、日頃の業務に取り組みたいと思った。
jiro049
組織の運営において意識して取り組みたいと思います。
piri6
動機づけ要因として、まだまだやれることの工夫はできるだろうし、衛生要因の吸い上げは必要だと思った。
tk_26
組織だって業務遂行するにあたり、衛生要因だけでなく動機付け要因とのバランスを適切にたもち、一人ひとりがやりがいやモチベーションを高くもてる職場環境を整備していこうと思います。
eshima46
動機付け衛生理論とは、アメリカの臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグが提唱したモチベーション理論で、仕事に対する満足感と不満の要因を分析したものです。仕事への満足度を高める要因を「動機付け要因」、不満を引き起こす要因を「衛生要因」と呼び、二要因理論とも呼ばれます
inada-makoto
動機付け・衛星要因は各々全く違うので自分と比較をして話をしない
年齢や働く目的や家庭の事情などによって全く違うので、日ごろのコミュニケーションでアンテナを張っておく
tomoyaaaaa
「満足の対義語が不満ではない」ことは新たな気付きでした
seniti77
衛生要因ばかりの人間が多い気がする
fuku-jin
自己の満足度は、人によって感じ方が違うので、それを見極める目が大事だと思った。見極めるためにも、常日頃からのコミュニケーションが必要であり、信頼関係を築くことも必要だと思った。
hippo-yam
しばしば、社員のモチベーションを上げるために、どのようにすれば良いかという議論がされる事がある。これまでは、いろんな事項をごちゃまぜにした形の内容を聞いていたが、動機付け要因と衛生要因を分けて考えることで、具体的にどのようなアプローチが有効であるかをイメージしやすくなった。
manjimaru_
動機づけ要因の向上すれば、衛星要因が上がるわけではない。その逆もしかり。
衛星要因の状況、不満を改善しつつ、動機づけ要因となるチャレンジングな仕事等も必要という・・・なかなか難しいと感じた。
yasuzawa_shohei
動機付け・衛生要因を学ぶ良い機会であった。
akaikushita
不満を取り除くだけでも、満足度を上げるだけでも問題は解決しないことを学んだ。両方をバランスよく満たすことが大切であり、気配り、目配り、心配りと声掛けが大切になると感じた。
fujisawa1213
「不満足でない」は「満足」であり、「満足でない」は「不満」であるという認識を持っていた。どちらかが解消すれば、モチベーションアップにつながると思っていた。個人の不満を明確にし、更にどうすれば満足に持っていけるのかを考えていく必要がある。
k-m-k-
衛生要因は改善するとモチベーションが上がると思っていたが、動機付け要因も一緒にバランスよくみないと上がらないということを改めて認識した。また不満足が満たされると満足になるのではなく、不満足でないということも気づきであった。
hatenahatena
不満足と不満なしと満足と3ステップあることは納得した。
不満足の解消のみならず、満足の追求も心がけたい。
mr_tomas
動機づけ、衛生要因について、理解が深まりました
narahei11
衛生要因と動機付け要因の両組み合わせが必要であることを意識し続ける。
koo-k2
何方も大事とわかりました
shuma_iwata
何が相手にとって不満を解消するのか、何によってモチベーションが上がるのかを考えて、伝えなければならないと思った。
sdkk
業務に対してやらされるのでは無く、理解してもらうことがやる気に繋がるのだと感じた。
yk_st
不満がないからといって満足しているわけではない、ということは改めて認識しなければならないことだと思いました。
yoropiko
衛生要因と動機付け要因のバランスでモチベーションが上がるということ、
なるほどと思いました。
誰もが認められたいという承認欲求があるのを理解し自分の居場所を作っていかねばならないと
思いました。
takeuchiii
今後制度を考えることがある場合も衛星要因と動機付けのバランスを考えながら取り組んでいきたい
maiko-ono
自分の仕事のやる気を振り返る上でも役に立つと感じた。
kengo_teramoto
今回学んだ「動機付け・衛生要因」の理論は、チームマネジメントにおいて非常に実践的な視点を提供してくれると感じた。
例えば、プロジェクトの進行中にメンバーのやる気が低下していると感じた場合、まずは衛生要因の確認が必要だと気づいた。労働時間が過度になっていないか、上司や他メンバーとの関係にストレスがないかなど、丁寧に確認することで不満の原因を取り除くことができる。
その上で、動機付け要因として「新しい技術に挑戦できるタスクを任せる」などといった施策を取り入れることで、メンバーのモチベーションを高められると考える。
maeda-takahiro
人に適切な業務を任せるとモチベーションは上がると思っていたが衛星要因の不満も聞いたりしながらそれを解決する方法を考えてみる