
0:59:48
割引情報をチェック!

AI BUSINESS SHIFT 第8回 機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第8回です。 第8回「機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル」では、AIが営業現場にどのような変化をもたらしているのか、営業担当者・営業マネージャー・組織としての役割や戦略が、AIによってどう進化していくのかを、営業プロセスの分解や実際の現場事例を通じて学びます。 ■こんな方におすすめ ・AIを活用した営業活動の最新動向や現場のリアルを知りたい方 ・営業現場の変化に直面している営業マネージャー・現場リーダーの方 ・AI時代における営業戦略や営業マネジメントのあり方を学びたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年2月制作)
会員限定

マネジャーのための仕事の任せ方
「仕事を任せると失敗が怖い」「自分でやった方が早い」マネージャーとしてメンバーやチームの力を引き出しながら成果を上げるには、どのように仕事を任せていけば良いのでしょうか? 変化の激しい時代において、マネージャーとして成果を上げ続けるためには、メンバーの個性や特性を理解し、それに合わせた効果的な任せ方を身につけることが重要です。このコースでは、ソーシャルスタイル理論を活用してメンバーごとに最適なアプローチを学びます。「任せる力」を高めることで、チーム全体の成長を促進し、自身のリーダーシップを発揮できるようになっていきます。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2024年12月制作)
会員限定

AI時代の個人力
AIが仕事や社会の前提を変え続ける今、最も求められるのは「他者に代替されない個としての力」“個人力”です。 本コースでは、澤円氏の著書『個人力』をもとに、AI時代をしなやかに生き抜くための「前向きな自己中戦略」を学びます。 テーマは、「Being(ありたい自分)」を中心に据え、自ら考え(Think)、変化し(Transform)、協働する(Collaborate)ことで、自分らしい価値を発揮していくこと。 リスキリングやAI活用が叫ばれる今こそ、スキルより先に“自分の軸”を問うことが重要です。 あなたは何を大切にし、どんな未来を描きたいのか? このコースは、あなたが“ありたい自分”として生き、キャリアをデザインしていくための思考と行動のガイドになります。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年11月制作)
会員限定
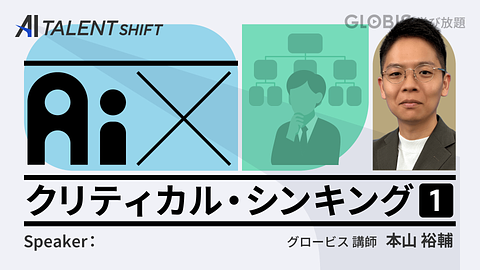
【AI×クリティカル・シンキング】①イシューと枠組みでプロンプトを磨く
生成AIから期待する回答を引き出せず、試行錯誤を重ねていませんか。 本コースでは、生成AI活用の質を高める鍵として、クリティカル・シンキングの視点からイシュー設定と枠組みを押さえる重要性を解説します。 目的に直結する問いの立て方や、プロンプトに落とし込む際の実践ポイントを具体例とともに学ぶことで、AIをより思考のパートナーとして活用できるようになります。 生成AIを業務で使い始めた方から、活用を一段深めたい方まで、再現性あるプロンプト設計を身につけたい方におすすめの内容です。 さらに学びを深めたい方は、こちらも合わせてご覧ください。 【AI×クリティカル・シンキング】②AIの弱点との向き合い方 https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/cdfe41e3/learn/steps/62198 ※本コースは、AI時代のビジネススキルを学ぶ「AIタレントシフト」シリーズの一環として提供しています。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
会員限定

リーダーの挑戦⑤ 藤田晋氏(サイバーエージェント代表取締役)
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第5回目のゲストは、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋氏。起業の理由、経営をどうやって学んだか、アメーバブログ・ABEMAの立ち上げ、経営チームづくりについてなど聞いていきます。(肩書きは2020年12月11日撮影当時のもの) 藤田 晋 サイバーエージェント 代表取締役 堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
会員限定

ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 前編 なぜ眠れないのか?~
「仕事が終わらないから睡眠時間を少し削ろう…」「業務時間中なかなか集中できない…」「毎日朝起きるのがつらい…」。 あなたはこのような経験をしたことはありませんか? 仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削りがちなのが「睡眠」時間。 実は今、日本社会は世界と比較して「最も眠らない国」だということもわかってきています。 慢性的な睡眠不足は、心身の健康に悪影響なだけでなく、仕事のパフォーマンスにも当然大きな影響を与え、社会全体の経済損失につながります。 このコースでは、基本的な睡眠リテラシーを学んだ後の「問題解決編」として、「なぜ多くのビジネスパーソンは眠れないのか?」について解説していきます。 ▼本コースで学べる主な内容 ・そもそも眠れないことは何が問題なのか? ・眠れなくなってしまう原因とは? 睡眠不足の原因は認知機能の問題にありました。 自身の睡眠不足に対し、正しく「気づき・理解し・行動を変える」第一歩を踏み出しましょう。 ▼関連コース ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~リテラシー編~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/24575c03/learn/steps/53129 ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 後編 どうしたら眠れるのか?~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/4ba981e9/learn/steps/62042 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

大阿闍梨 塩沼亮潤が死の手前で見つけた「生き方」
あすか会議2018 第4部分科会B-1「極限の世界で見つけた人生の歩み方」 (2018年7月7日開催/国立京都国際会館) 1300年間で2人目となる大峯千日回峰行満行を果たした塩沼亮潤大阿闍梨。48キロの山道を1日16時間掛けて歩き、それを千日間に亘って続ける過酷な行の中で、どのような悟りを得たのか。そして、9日間、断食・断水・不眠・不臥を続ける四無行満行という極限の世界で何を見つけたのか。塩沼氏が「創造と変革の志士」へ贈る「人生の歩み方」とは。(肩書きは2018年7月7日登壇当時のもの) 塩沼 亮潤 慈眼寺 住職
無料
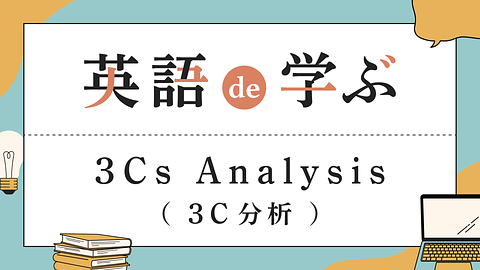
英語 de 学ぶ!3Cs Analysis(3C分析)
このコースでは、グロービス学び放題の英語版である『GLOBIS Unlimited』のコースの中から、ビジネスで役立つ頻出の英語表現をピックアップしています。英語ネイティブの方が実際に見ているコースなので、リアルなビジネス英語の表現を学ぶことができます。 今回のコースは「3Cs Analysis(3C分析)」です。一緒に『英語で』ビジネス知識を学んでいきましょう! ▼今回扱ったUnlimitedコース続きは下記からご覧いただけます 3Cs Analysis https://unlimited.globis.co.jp/en/courses/da5ca962/learn/steps/36362 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
コメント3200件
hiro_yoshioka
ブルイップ効果 おそろしいと思いました。
末端に行くほど影響が拡大することが実感できました。
各工程、在庫含めた全体量は一定に保つのが理想ということですね。
一方で、成長や衰退が予想、計画されているものは、
その計画に合わせた増減で全体量を管理するのが良さそうです。
そのような計画も含めて、末端工程まで共有されている必要がありますね。
一つの企業内であれば、実現しやすいですが、他社を含めると実現の難易度高いと思います。放っておくと、自然にブルイップは起こってしまう。
ブルイップ効果って製造工程以外にも、あるあるな本質的な課題ですね。
様々なことで思い当たります。
上位目標に対し、下位になるほど必要以上に厳しい目標が求められるとかw
まさに鞭! 愛のムチです
yunnyutan
中小企業診断士の資格取得の際に学習した運営管理の科目について、体系的に復習することができて非常に有意義だった。
harn
自社で扱っているものが無形商材であることもあり、理解が難しい部分もあったが、一方で会社としてオペレーションマネジメントが進んでいないことも理解した。生産管理や内製/外製など、商材にあてはめて考え直したい。
kzhr2358301
ブルウィップ効果や内製するか外製とするかを検討し、商品特性に応じた生産管理について学べました。内製、外製についての判断は自分の職務にも活かしていけると感じました。
taku_0318
オペレーション戦略とは、経営戦略実現に向けてオペレーションの観点でQCDFを鑑みて対応すべきものであると学んだ。QCDF観点で、生産方法やその管理方法を考え、サプライチェーン全体で見たときにどういったあり姿が最善であるかを考える必要がある。在庫管理観点も考慮しつつ、製品特性からどういった生産方法を取るのかや、生産自体を内製でやるのか外製でやるのかを判断するためにも、価格は納品までのタイムライン、自社のコアコンピタンスも考慮しなければならないのだと学んだ。業務上は上記事項を意識して日々働いていく所存。
kiyonori_0905
ブルウィップ効果等、初めて学んだことがありました。今後の業務に生かしていきたい。
qa_ay
前職は消費財事業部門(勤務先は輸入総代理店)だったので、自部門では販売予測と製造LTとのにらめっこばかりでした。
定番商品は販売予測に従って定期的に仕入れ、欠品しないようにするという、至極単純なものですがこれが難しい。なぜなら工場の供給が常に一定ではなく、原材料部品のサプライヤー(別の国の別会社)のMOQ(最低発注数量)の都合で、定番商品なのに供給が3ヶ月先ということがしばしば起こるからです。部品サプライヤーの供給状況はブランド側でコントロールするものだ(してくれ)と思っていましたが、やはりSCM全体を見渡し、どこがボトルネックかを見極めることの大切さをあらためて学びました。
これに加えて季節性のある限定商品の入荷時期管理、生産の進捗状況確認も必要でした。ラザニアアイスの比ではないですが、季節を逃せば不良在庫になるものなので入荷を焦った(そして早く売り切る)当時を思い起こします。
さらに半期ごとの棚卸しに向けて、定番商品のみを残し極力棚卸し残高を減らすことも求められていました。そのため在庫を限りなく絞り、棚卸し直後にまとめて入荷させるよう輸入の出荷コントロールをしなければなりません。(棚卸し金額は売上総利益に関わる売上原価を下げてしまうことをここの別コンテンツで学んだのでやっと理由がわかりました)
一方、ブランド側は総代理店に輸出する本数、金額目標があったので、このFiscal Term(棚卸し)に関連したブランド側との入荷コントロールの交渉がシビアだったことを思い出しました。
ここは体系的に学べるコンテンツとしてたいへんよく学びになるし、今は関わりのない仕事ながら自身の振り返りとなってとても有効です。
ただしかし、「実務って色々絡んで教科書通りではない」のでそこをどうやりくりするか、が悩みどころです。「だからビジネスは面白い」と言えるようになりたいものです。
kuromegane03
QCDに加えてFが大切。
Fが求めるのは改善・変化。仕組の構築時でも、日々の業務でも、改善可能性・可変性を考慮にいれて、日々の業務の実行・構築設計に臨みたい。
あと、在庫をコントロールする/できる/最適化するという理想はわかるが、販売を読んで購買量をコントロールことが必要という考え方は疑問。販売は予測できないので、それに基づいての購買もコントロールはしづらい。販売という前提があやふやなので、結局購買増で在庫増えるか、欠品するかの振れ幅が大きくなる。結果会社も販売量の予測精緻化にパワーを使い、無駄な努力が発生する。いわゆるコンサル入れてアルアルな状態になりそう。より生産的なのは、内部工程の改善で、生産や物流などの内部機能の改善、特に瞬発力でないかと考える。MAXの能力までに達する時間とそれ継続できる期間を把握しつつ、たりない数量をどれくらい在庫で持つか・許容するかの方針設定が必要。
この方針ですすめると、結果として欠品が発生すること場面も発生するので、それを許容できるか経営層の腹の座り方で効果がでるか決まる。
よくあるのが、在庫を減らせでも欠品するな、という号令で、それができた苦労しないよというため息ばかり。
本講座の表面的な理解では、在庫を減らせでも欠品するな、になりそうなので自社の能力をよくよく考えたい。
telme-tora
カンバンについてはサプライチェーンの川下に近い所では必ず在庫を抱えなくてはならない欠点有り、VMIにしてもかなりのノウハウを必要でそこにかかるコストも考えなくてはならないので余り有効な手段ではない気がします。
先ずは前半に会った製造のキャパシティを製販が理解し、生産性に見合った効率的な販売をすることを目指すべきと考えます。
saito-yoshitaka
サプライヤーチェーンから自社の強み・弱みは常に考える必要がある・
kaki_077
委託元の利益のために行動できるインセンティブをつくる...重要ながらも難しい項目だなと思いました。普段の業務でもエージェンシー契約の視点にたって仕事を作っていきたいと思います。
yamato2016
サプライチェーンマネジメントを
しっかりと学習できた。
外製および内妻の違いや判断の基準も
大変興味深い内容だったので、今後
意識していきたい。
最初に受講できて光栄です!
jin-kun
外製、内製の判断軸が整理でき、よかった。
yuchan-1220
サプライチェーンについて、久しぶりに思い起こすことが出来、勉強ができました。常に、効率化を図り、全体最適の観点から、得意先と生産計画を立てる重要性を再認識いたしました。
andy_bucci
在庫は多すぎても少なすぎてもダメ
raimuku
身近なものすべてにオペレーション戦略があることが理解出来ました。
taakao
学生時代にスタバのアルバイトをしておけばよかった。働きながらオペレーション戦略の成功事例に包まれ学べ、語学経験やステータスも得られる。なんて一石四鳥なバイトなのであろうか。子供には英語を学ばせ、スタバでのバイトを勧めよう。
ラザニア味でぱっと思いついたのは赤城乳業のガリガリ君コンポタージュ味、自社のマンネリ化ににリスクを顧みず一石投じ、話題性とその後に繋がる開発力を培った実績には脱帽である。
daisuke1924
管理系部署の業務がシェアード会社への外注などが行われている中で、内製と外製の考えである、オペレーション視点と経営戦略視点が役立った。経営戦略視点と仕事を任せて本業に集中できる、などの視点でしか考えられておらず、オペレーション視点の高いQCDFを実現できるかの視点が足りていなかったと思う。
この外注化は進みそうなので上記の視点での現在の委託業務の再考、これからの業務委託について考えるよい視点となった。
ブルウィップ効果も学べてよかった。商品の売上から原材料メーカーの発注量に至るまでに影響がどんどん大きくなり、恐ろしく感じた。上流の方が下流よりビジネスのリスクが少ないと思っていたが、このブルウィップ効果を考慮するとそうでもないように思える。このような視点、知識の獲得ができたことが非常にためになった
inada-makoto
ブルウィップ効果等、初めて学びました
kenkenqtr
普段意識が薄いオペレーションについて学べた。
外製や内製、在庫管理など市場予測を立てながら生産計画を立てる方の苦労がわかったような気がする。
マーケティング等の市場調査や顧客の反応など、生ものを扱うように情報の鮮度が必要と思いました。
QCDFのFが入っている意味はそこなんだと思います。
imatoku
委託している業務の見直しと、委託すべき業務の整理。今の担当業務のQCDFは経営理念、経営戦略にあっているものか振り返りを行う
fuminori-iwsk
社員業務効率化の観点から業務のアウトソーシングを検討する際には、コアインピーダンスの他経営戦略との合致性をも考慮して判断すべきだと思った。
プルヴィップ効果を学ぶと、市場の原理では必ずしも経済合理性のある現象が起きるわけではないことに気づいた。
you_can_do_it
QCDFの意識をもって業務にあたるようになりました。
robby1111
サプライチェーンに於ける、ブルウィップ効果を意識したオペレーション、各社どの様に対応しているかを意識し、それらを業務に上手く活かす手法について探求したい。
juko01
ブルイップ効果は初めて学んだ。
全体的に大変興味深い内容だったので、今後意識していきたい。
ag044581
自分の部署では関係のない項目ですが、会社全体を考えると沢山あるので、提案していきたい
nishimu_
サプライヤチェーンマネジメントについて学びました。ブルウィップ効果については非常に参考になりました。
sti_imd
知らない事も多く学べた
h-sekiguchi
商品毎に仕入れ方法を効率的に工夫することの重要性を学びました。
的確な需要を把握し良い仕入れや展開を実践していきます。
makosasa_ptd
開発品を製作するため、一品ものになることが多く、受注生産に近いものがあるが、共通部品などはあるため、きちんと整理して把握しておく必要がある。
yoshizaw
生産性向上に役立つと感じた
f_mari
外製、内製の判断軸が整理でき、よかった。
hase-san
需要の変動に対する過剰な反応を避け、安定した供給と予測精度の向上を図ることが重要です。リアルタイムで情報を共有し、無駄な在庫やコストを減らすことが効果的
c-hirai
計画を立てる際、これまでのやり方を踏襲する形で対応してきたが、売れ方や商品によってお客様の動向が変わる場合は生産方式も見直す余地があることがわかった。
kodai_matsumoto
ブルイップ効果 おそろしいと思いました。
末端に行くほど影響が拡大することが実感できました。
mekkom
顧客が要求する納期を満たす為に、どうしても不要な在庫をかかえてしまうことがあるが、もっと機械的に、もっと効率よく開発を進められないか考えたい。ブルウィップ効果、QCDFは初めて聞く言葉で勉強になった。
kobori990020
経営戦略を理解した上で業務を行う必要があると感じました。
kazukiyo7772
業務のパフォーマンスデータを分析し、問題点を特定して改善策を講じることで、より効率的な運営が可能となりそうです
gamow
コアコンピタンスを意識した内製戦略やサプライチェーンマネジメントの視点でのオペレーション戦略、在庫ショートリスクと余剰在庫リスクとのバランを考慮するなど、内部のオペレーション戦略だけでなく、外部のオペレーション戦略の大切さも学んだ。実務で活かしていきたい。
taichinishimura
内製と外製は非常に難しい問題だと感じています。
asazawa
ブルイップ効果について知識を得ることで、なぜ川上企業では受注量の変動が大きくなるかを理解することができた。
hi_autumn
横文字だと分かりにくいですが、配慮の問題だと理解した。
takuma214
これまでにない考え方を理解することができた。
t_sugasawa
世の中の全体的な様子を理解することができた。
34575_kinoue
重要なパートなので復習必須。
asamaaa
多種多様な製品を扱っているため、今回学んだ手法を実施出来ていないものがある。
一度見直しを行い最適化を目指したいと思います。
junji_jun
身近なものすべてにオペレーション戦略があり、経営戦略にあったオペレーション戦略が必要だと思った
zzzxxxcccvvv
ブルウィップ効果は初めて聞いた用語でした。全体を通して非常に有意義な講義でした
hata_honami
ブルウィップ効果や内製するか外製とするかを検討し、商品特性に応じた生産管理について学べました。内製、外製についての判断は自分の職務にも活かしていけると感じました。
aky69517
営業は過小なサービスだけでなく、過剰なサービスをすることなく、得意先に対して適切なサービスをする必要がある。
masashi_30
ブルウィップ効果等、初めて学んだ。
前編と一緒に振り返りながら所属している組織の状態と照らし合わせたい。
takeaki_seto
理解が難しい部分があった
kkatagiri
委託先の利益も考えた外部委託が必要であることを学ぶことができました。
souichi22
小売業でないため、在庫等の感覚が無かったが、生産設備=施工班の確保と考えると、イメージしやすかった。
toshi1976
他部署でやっている判断が分かるようになりました。より良い連携が出来るように意識します。
kaori_230
自分の業務でサプライチェーン全体を考慮することは正直なかったが、今後は意識していきたいと思う。
dpec1
理解して取り組んでいく
mfujiu
ハードウェアだけでなく、サービス、ソフトウェアなどでは複雑な管理と運営が求められるはずだが、今回SCMの基本を学べ、理解するためのベースができた
takahiro_otani
ブルウィップ効果は初めて知りましたが非常にインパクトがあり恐ろしい物だと思いました。
内製や外製の判断などの知識は今後生かしていけそうな知識でした。
sunao_fujii
自分の取り組んでいる業務の中で、他の企業とも協力しながらより経営戦略に沿ってより高い価値を出すことはできないか検討したい。
r_tsubota
あまり聞いた事がない内容が多かった。内製/外製の判断については業務で活用していきたい。
t03290512
オペレーションも経営戦略にとって大事です。
staka3
内製と外製のバランスを考えて、業務に活用できる様に日々に活かしていきたいと思います。
mochida54863
協働会社との業務委託の見直し
azuma_mochida
やり方に均一化が必要な場合とそうではない場合を分けて考え実行していきたい
monmon555
エージェンシー問題についても一般論として起こりうる事案であることを学び、対策を講じたいと思う
masa_yana
オペレーション戦略とは、経営戦略実現に向けてオペレーションの観点でQCDFを鑑みて対応すべきものであると学んだ。QCDF観点で、現場管理方法を考え、サプライチェーン全体を見通し効率化を考えて生産性を高めていかなければならない
okumoto_3
自部署のミッションを果たすための業務内容をすべて内製するのではなく、戦略的観点からノウハウになるものは
多少リスクがあっても自部署で実施すべき ノウハウにならず、当社で実施するより他の方が成果品質やスピードが高いものは
外製で実施すべきと感じた
顧客課題に寄与する解決方法など、創り出すところは内製、そのドキュメント政策は外製など
ma_55
生産計画において、何を重視するのかを明確にしておくことの重要性がよく理解できた。
在庫の持ち方に関しても、需要変動や生産LTを意識するおことで、損失を少しでも減らして運営していくことが重要であると理解した。
matsuzawa_yuki
Synergy!の新商品やエージェント案件の外注などで参考にできそう
a_soga
業務で活用するためには、現在自分が実施している業務の流れを再認識することが大切だと思います。具体的には、顧客から注文をうけ提供するまでのプロセスにおいて、事務手続きに時間がかかるのか、または商品の発注に時間がかかるのか、基本的な内容の見直しすることが、業務効率化につながると思いました。
okawa777
限られたリソースにおける試験業務の内省、外省は重要な視点と考える。
watashiyo
業務でかかわったことがない領域で、新鮮だった
wh_st104
営業視点から
サプライチェーン・マネジメントは一見関係ないように見えて、顧客との関係性に置き換えることができる。
特に販売代理店との関係性構築にはこの考え方が非常に重要である。
特にエージェンシー契約の内容は、裏切らない関係性の構築にはインセンティブの考え方が効いてくることを認識し、営業オペレーションエクセレンスを目指す。
k_oki
アマゾンと佐川急便の関係のように長続きしない関係性はお互いのためにならないと思いました。目先の自社の利益にとらわれないように気を付けないといけないと思いました。
yutaka-nagamori
Q,C,D,Fを考えたオペレーションを考えることが重要
taka_shimo
最後に講師から「日常はオペレーションにあふれている」の一言があり、納得感がありました。
どこにでもオペレーションがあると意識することで、サプライチェーン全体をイメージする習慣や視点が持てるような気がします。
また、本質的に「そこにValueはあるのか、Valueがあるのか?」を問い続けることが必要ではないかと考えることができたため、業務の中で意識していきたい。
mi_________
サプライヤー全体での視点を持ちたいです。
k1dq
オペレーション マネジメント ブルイップ効果 経営戦略
keiichi_matsui
内製・外製の考え方、特に外製の部分についてはこれまでの考え方と違っていて、自社生産にこだわる必要はないことを認識した。売り上げの変動により上流側での発注量が減るブルウィップ効果については、変動として時間(期間)の概念も取り込んで考えないと、実際のの運用で考量すことは難しそう。
---hide---
基本を学んだ。知らない知識もあり役に立った
taki_yuko_5122
始めてオペレーション戦略を学びました。稼働率と生産性について現状とうなっているのか確認したいと思います。
sakanababy
サプライチェーンマネジメント自体をきちんと学んだことが初めてでした。
ryousuke0529
オペレーションの重要性について学べてよかった。
shintaro59928
取引先との関係も含めて考えていきます
naty
効率化の基本を学んだ
nao2tak
実体験として認識していたことが「ブルウィップ効果」という名前がついていることに驚きました。
investar-k
オペレーションの基礎が理解できた。
seha1212
内製、外製の使い分けを学ぶ事が出来た。オペレーター戦略は、QDCFのどれを経営戦略で重要としているか?から決め、戦略を取り組む事が必要だ。と、理解しました。
k_y_a_s
内製・外製は既に設計・開発業務でも行われていることだが、その判断基準を体系的に学ぶことができ、現状の内製・外製している項目について、見直すきっかけになりそう。
ブルウィップ効果については、まさに顧客との仕様を交渉する中で、ちょっとした仕様変更が、設計から製造まで影響することもあるケースに遭遇したことがあったので、納得した。一方で、そのような仕様変更要望に強い製品、というのも目指していかないといけないと感じた。
ssuw129
直接オペレーションには携わっていないが、事業部門のオペレーションが適切になっているか、経営戦略の要請にこたえているか、オペレーションの視点で合理的な対応になっているかの双方の視点から把握できるようにしたい
fuji3164
身近なところにオペレーション戦略があることが理解出来ました。
rierieman
ブルウィップ効果とF:柔軟という観点が勉強になりました。在庫調整時には意識をしたいと思います。
diguard
受注案件の中に客先Webサイトの制作・運営がある。
新たなサイト立上げの際は、客先や市場の知見を活かし、内製を主として、更新・運営のフェーズになる段階で、外製を活用していく。
ako_k
状況は理解していても、名称など知らないものが多かったので参考になった。
symh
サプライを意識して、オペレーションを整理していきたいと考える。
yoshiyuki_chiba
目先の売れの増減だけに捉われるとブルウィップ効果が大きくなってしまう。ある程度の受注の予測を立てて、原材料の調達量を考えないといけないと思う。外製化する際には必要以上にコストダウン要求をしないように適正値の提示は必要だ。
takada_1996
サンドウィッチの例のように何事も数値化されて見えていると判断できるが、実際のオペレーションはそのように単純ではない。
いかに見える化・数値化し即座に判断できるようにするかが大事だと理解した。
leo36
内製、外製について改めて理解が出来た。商品には販売期間があり(鮮度)もある。共有と在庫のバランスは非常に関連している。常にリスクも伴う為、単品管理で商品動向に注視する
cana3
サプライチェーンで消費者に近い側の変動が、川上では想定以上の影響を受けるブルウィップ効果は非常に恐ろしい。