 議論を適切にファシリテートするためには、そのための準備が不可欠です。むろん世の中にはその場でいきなりファシリテーションをできる人もいますが、極めて稀です。また一見、事前の準備をしていないように見えても、それは、数多くの議論の場に立ち会った経験が「仕込み」になっていて、議論の現場での成果につながっていたり、実は、どのように議論を組み立てるのか?進めるのか?を深く考えていたりすることが多いものです。ただ、それがとても早く行われているので、即興でやっているように見えるだけなのです。
議論を適切にファシリテートするためには、そのための準備が不可欠です。むろん世の中にはその場でいきなりファシリテーションをできる人もいますが、極めて稀です。また一見、事前の準備をしていないように見えても、それは、数多くの議論の場に立ち会った経験が「仕込み」になっていて、議論の現場での成果につながっていたり、実は、どのように議論を組み立てるのか?進めるのか?を深く考えていたりすることが多いものです。ただ、それがとても早く行われているので、即興でやっているように見えるだけなのです。
(前回はこちら)
「仕込み」と所定の結論に誘導することは異なる
「議論の仕込みをする」と言うと、「現実の議論ではいろいろな意見が出るので思ったようには進まないのではないか?」「議論の進め方を考えてしまうと、かえって議論を型にはめてしまい、活発な意見交換にならないのでは?」などと思われる方もいるでしょう。確かに現実の議論では、様々な意見が出てきますので、全ての意見を予想することはできません。また常に当初思い描いたように進められるとは限りません。
しかし、だからといって仕込みをしないで議論の場に出て行くと確実に失敗します。むしろ、議論の現場では様々な意見が出るからこそ、仕込みなしでは適切に対応することができないのです。仕込みをすることは、必ずしも当初思い描いたシナリオ通りに議論を強引に進めることではありません。むしろ参加者の状況や意見の出方に臨機応変に対応するためにも、議論の仕込みが必要なのです。
「議論を仕込むとは、自分の考えている結論に誘導することではないのか?それで良いのか?」と思われる方もいます。ビジネスにおいてファシリテーターを務める際には、自分自身もある意見を持っていることがほとんどであり、ファシリテーター自身もつい「自分の思い描く結論どおりにまとめたい」という欲求に囚われがちなので、確かにそうした懸念はもっともです。
しかし、ここが重要なポイントなのですが、「仕込み」とは「自分の考えている結論に向けて仕込む」のではありません。「結論に向けて」ではなく、「その場で議論をする目的を達成するために、考え、議論すべきこと」を考え、そこに参加者の思考を誘導するのです。そうすると、結果としては自分自身が考えていたものとは異なる結論に到達することもあります。むしろ参加者から新しい情報や優れた意見が出されることで、自分が当初描いていた結論よりも優れた結論、皆が納得できる結論に至ることができれば、まさに集団で考えるメリットがある、と捉えるべきです。
ビジネスにおける議論の目的
では、議論の「仕込み」をするとは、何のために、何をどのように考え、準備することなのでしょうか?それを考える前に、そもそもビジネスにおいて議論とは何のためになされるのか?に遡って考えてみたいと思います。「会議の場」はもとより、デスク周りでの簡単な打ち合わせ、上司と部下の面談など、何かについて話し合う場面をイメージしてください。Face to Faceでの会話だけでなく、メーリングリストやWebの掲示板など、ネット上のコミュニケーションでも同様です。
我々は日頃多くの時間を会議や打ち合わせに使っています。連絡事項の伝達など、情報共有を目的に行われる場合もありますが、それらも含め、議論は最終的には何のために行なわれるのでしょうか?
議論すること自体は直接価値を生むものではありません。いろいろ議論した結果、何らかのアクションをとることが意思決定され、その意思決定に沿って誰かが行動する。そしてその行動が価値を生み出すのです。つまりビジネスにおける議論の最終目的は、こうした「行動の決定」です。
議論などコミュニケーションをすることは多大な時間を使うものであると同時に、それ自体は直接価値を生まないとすれば、できるだけ議論に費やす時間を少なくすることがビジネスにおける効率を高めることになりそうです。たとえば優れたリーダーが意思決定をし、その決定内容を他の人に伝えて実行させる。もしその意思決定が正しいのであれば、それで良いはずです。にもかかわらず、わざわざ議論をするのには、それに見合った効果が期待されます。ではその期待効果とは何でしょうか?
ひとつは、現実的に一人の人間が全ての情報を処理し、正しい意思決定ができるとは限らないため、多くの人が各自の専門性に基づいた知恵や情報を持ち寄り、様々な考え方をぶつけることで優れたアイデアを生み出し、「よりよい結論を導く」ことが期待されます。「決定内容の合理性を高める」ことです。
もうひとつは、たとえ同じ結論に到達するのであっても、関係するメンバーが議論に参加し、決定に関与することによって、決定事項に対する納得感を高めること。つまり「決定プロセスの納得性を高める」ことが期待されます。
ビジネスはあちらを立てればこちらが立たずというトレードオフに満ちているので、組織全体としては正しい決定であっても、それぞれの立場からすると不利益が生じることもしばしばです。その不利益を超えてもやはりその意思決定に従い行動すべきだ、とメンバーが感じるには、単に結論が正しいだけでは不十分です。意思決定のプロセスに自分が関与し、意見を述べ、納得するプロセスを経ることが必要です。
また、必ずしも利害の対立が無い場合においても、なぜそうしなければならないのか?その決定以外の策は考えられないのか?等をメンバーが深く理解・納得することで、より適切な行動が取られる、命じられなくても各自が自発的に行動するようになる、といった効果も期待できるでしょう。(他にもメンバーのチームとしての一体感を高めるなど、「メンバーの関係性を密にする」ことを目的とする議論もありますが、これは別途触れたいと思います)
このように、議論とはメンバーが一人で考えるよりも優れた結論を生み出し、また議論のプロセスを通じて各自が納得に至るための営みと言えます。これを「アクションに向けての合意形成」と言いましょう。では、この合意形成はどのように行われるのでしょうか?次回はそこを丁寧に見ていきたいと思います。
(次回はこちら)



















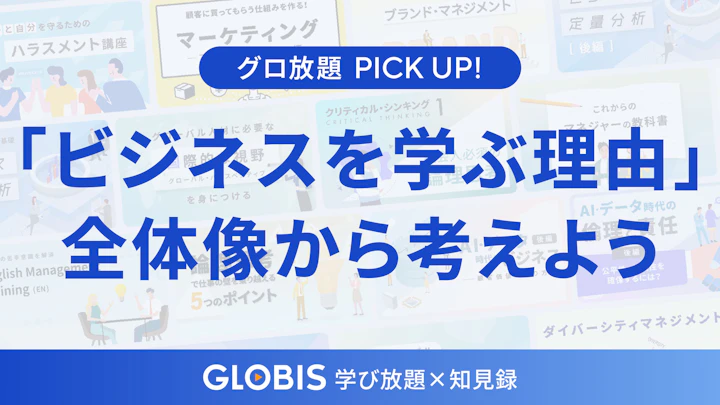










.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


