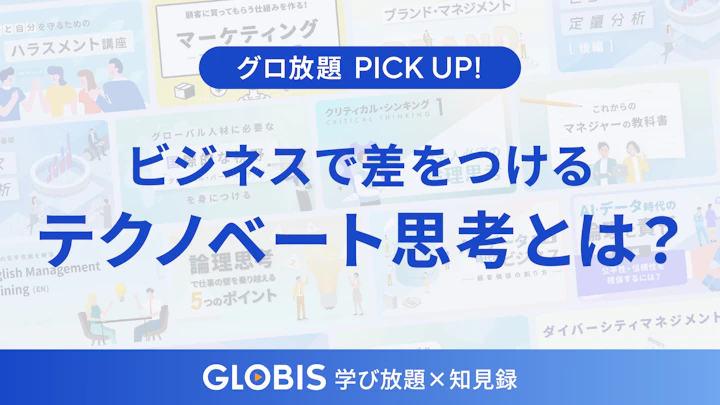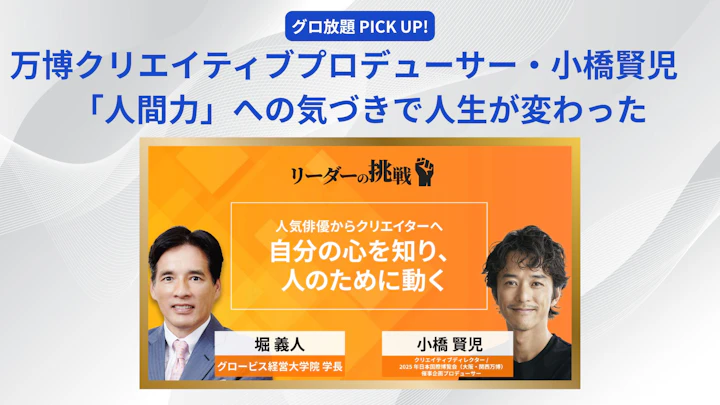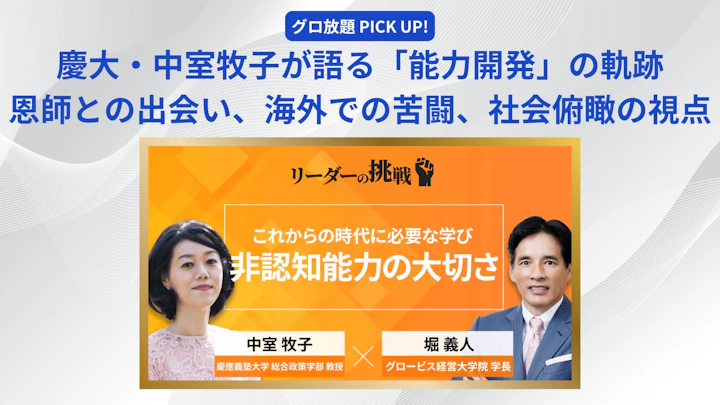日常のビジネスシーンに潜む数々の“落とし穴”。なかでも、営業先でのプレゼンや得意先へのメールなどコミュニケーションにおける転ばぬ先の杖を中心に、グロービス経営大学院で教鞭を執る嶋田毅が紹介する。第10回は、交渉の現場でも多用されている「アンカリング」のケースを見ていこう。(この連載は、ダイヤモンド社「DIAMOND online 」に寄稿の内容をGLOBIS.JPの読者向けに再掲載したものです)。
今回も、前回に引き続き、交渉に関連する落とし穴について紹介していく。テーマは、交渉の現場でも多用されている「アンカリング」だ。アンカリングという言葉は聞き慣れない人もいるかもしれない。しかし、次に挙げる事例を見てもらえば、ビジネスシーンでよくあるケースだと理解してもらえるはずだ。
【失敗例】ITコンサル会社 荒川人事部長のケース「最初の提示に引っ張られすぎた」
荒川氏は中堅ITコンサルティング会社の千住ソリューションで人事部長を務めている。業界の特性上、どうしても従業員は多忙となってしまうのだが、その結果、体を壊して辞めてしまう人も少なくない。あるいはより良い条件を求めて転職するなど、人材の流動性も非常に高い。
そうした中で、どれだけ従業員に魅力的な職場環境を提供するかが、荒川氏の目下最大の懸案事項である。同時に、「人」こそが競争力の源泉となるビジネスゆえ、いかに優秀な人材を獲得するかも、荒川氏に課せられた重大な課題である。
もともと千住ソリューションは新卒採用を重視していたのだが、最近は中途採用にも力を入れている。人事の仕事が長かった荒川氏は、従業員の悩みを聞いたり、部下に懇切な指導をしたりするなどは得意としていたが、正直、交渉ごとはそれほど得意ではない。千住ソリューションには組合がなく、人事担当者としてタフな組合交渉に臨む必要がなかったのもその一因であった。
今日、荒川氏は、まさに中途採用の面接に臨んでいた。候補者は尾久氏という男性で、これまでに数社のIT企業でプロジェクトリーダーを務めている。プロジェクトの切り盛りだけではなく、コンサルティング営業もこなし、売上げの数字も上げられるとあって、人材市場における価値は高い。
今回、縁あって千住ソリューションへの転職がほぼ確定し、あとは条件を詰めるだけである。細かな条件ももちろんあったが、最大の争点は、仕事内容と年俸である。仕事内容はほぼ両者合意に至っており、残された最大の争点はズバリ「年俸」を残すだけであった。
荒川氏には社長から、「高くても1300万円、できれば1100万円程度で」との枠をはめられている。今から他社に移る可能性は現実的にはほとんどない状況ではあったが、やはり気持ちよく働いてほしいからあまり値切りたくはない。かといって、突出した先例を作りたくもないため、あまり高額にはしたくない。荒川氏は、何とか落とし所として1150万円程度にしたいと考えていた。
そうした心積もりを心の奥に押し込め、ゆっくりと切り出した。
「ところで、尾久君はどのくらいの年俸を希望する?」
尾久氏はさらっと言った。
「そうですね。最終的には御社の常識からあまりに離れた額は無理だと思いますが、自分の市場価値にはそれなりに自負もありますので、1500万円を希望します」
「(1500万円!)」荒川氏は驚いた。「それは無理だよ」という言葉が喉元まで上がってくるのをぐっとこらえ、冷静に切り返した。
「希望は確かに了解したが、我々にも社内の基準や懐具合もある。そこはもう少し相談させてもらえないだろうか」
すでにこの段階で、荒川氏の頭の中からは、当初抱いていた落とし所の1150万円という額は消え、妥結額を社長から与えられたキャップである1300万円にまでどうもっていくかということしかなかった。そして2時間に迫るかという時間を使って、さまざまな説得を試み、何とか1300万円の額で了承を得た。
「君にはやや不満の残る数字かもしれないが、実績を残せば必ず給与も上がるから、そのつもりでがんばってほしい」
「・・・わかりました。とにかく早い段階で結果を出せるようにがんばります」
尾久氏が去った後、荒川人事部長は自分を納得させるようにつぶやいた。
「社長から言われていた上限ぎりぎりになったのはやや問題かもしれないが、当初の希望を200万円下げてこちらの許容範囲に抑えたのだからまずは良しとしなくてはな」
同時刻。尾久氏も先ほどの交渉を振り返っていた。
「1300は十分な成果だな。1200でも仕方ないと思っていたのだから。それにしてもあの部長、こういう交渉になれていないのかな? 1500という数字を出したとたん、顔色が変わっていたからな。だいぶあの数字に引っ張られたようだ。まずは多少自分に有利すぎるくらいの数字を出すのは商談では珍しくないと思うが、彼は商談などはしたことがないのだろうか?」
【解説】今回の問題点 相手の術中にハマってしまった・・・
今回、尾久氏が使ったのは、交渉の定番テクニックとも言える「アンカリング」である。これは、最初に与えられた情報や数字に大きく引っ張られてしまう、という心理であり、「係留効果」とも言う(なお、アンカリングはアンカーからきている。アンカーとは船の錨のことで、最初にどこに錨をおろすかで、船の行動範囲が決まってしまうことになぞらえたものである)。アンカリングは特に、自分が不慣れな領域で悪影響を及ぼしやすい。
ここでは、筆者が最近行った実験結果をご紹介しよう。被験者を2つのグループに分け、まず設問1についてイエス/ノーを答えてもらった後に、設問2を投げかけるという単純なものだ。
【被験者グループAへの質問】
質問1「ラオスの人口は75万人より多いか少ないか」
質問2「ラオスの人口は何万人か」
【被験者グループBへの質問】
質問1「ラオスの人口は1000万人より多いか少ないか」
質問2「ラオスの人口は何万人か」
注目されるのは、グループAとグループBで、質問2に対する答えに大きな差があったことだ。すなわち、グループAが質問2に対して平均でおよそ400万人と答えたのに対し、グループBは質問2に対しておよそ700万人と答えたのである(ラオスの実際の人口はおよそ600万人)。
言うまでもなく、質問2だけを見れば、聞いていることは同じだ。にもかかわらず、これだけ大きな差が出たのは、質問1での、75万人と1000万人という数字に引っ張られてしまったからにほかならない。
交渉でも、この心理効果は強く働く。最初に相手の心の中に、うまくアンカーを下ろすことができれば、それだけで最終的な合意地点が自分にとって有利になることが期待できる。事実、アンカリングは交渉の途中における駆け引きよりも相手に与える影響力が強いとも言われている。
ケースの荒川人事部長はまさにこの術中にハマったといえよう。本来、人事部長であるから、年俸の話は決して不慣れな領域ではないはずなのだが、交渉の経験に乏しいこと、大事にしたい相手だということなどが相まって、「1500万円」というアンカーに強く影響される結果となった。
必要以上にアンカーに影響されてしまう 落とし穴を避けるには?
アンカリングは多かれ少なかれ、誰しもが影響を受けるものであり、まったくそこから逃れることは不可能である。たとえば、最も当たり前に用いられているアンカーは、売り手が不特定多数の潜在的買い手に提示している「定価」あるいは「表示価格」である。この数字を頭の中から完全に追い出して交渉に臨める人間はまずいない。
しかし、少なくとも、自分が不慣れな領域の交渉に臨むとき、あるいは初めての交渉相手の場合、あるいは、「高額」「無形」「目新しい」などの特徴を持つ商品・サービスに関する交渉など、「勝手が分からない」度合いが高いときには、相手が出してくる条件について、「これは自分に不利なアンカーではないか」と疑いながら交渉を進めることが重要だ。
可能な範囲で事前に下調べをすることで、大まかな相場や交渉相手の置かれた状況(特に代替の取引先があるかどうか)などを把握しておくことが望ましい。
なお、交渉当事者ではない第三者の何気ない一言や、たまたまその日発売の雑誌に載っていた、取り立てて重要とも思えない統計数値なども、その日の交渉当事者の心理状態次第ではアンカーとなりえる。老練な交渉者になると、自分でアンカーを伝えるのではなく、第三者からさりげなく相手に漏らすように仕向けることもあるという。これは、「交渉相手から与えられる情報に比べ、たまたま漏れ聞いた情報の方がより信頼性が高い」と思い込む心理を使ったものだ。
重要な交渉になればなるほど、自分が必要以上にアンカーに惑わされていないか、あるいは、相手の出してきた数字は交渉テクニックとしてのアンカーではないのかなど、客観的に自分を眺める視点が求められる。
次回も『交渉の落とし穴』について紹介します