グロービス学び放題(グロ放題)で公開された全6回の『分析の基本のキ』シリーズが、好評を博している。ビジネスパーソンにとって<分析>とはどういう存在になりうるのか、またその一歩をどう踏み出せばいいのか。グロービス経営大学院でファイナンス系の講師として登壇し、今回のシリーズへの出演ほか分析にまつわる発信を続ける鷲巣 大輔に、本動画シリーズの企画・制作に携わったグロービスの太田が聞いた。
経営を動かすインパクトまで持つことこそが「分析」
太田:『分析の基本のキ』シリーズですが、視聴したユーザーからは「参考になった」「自分の分析の足りない部分がわかった」など多くのポジティブな声が届いています。またビジネスパーソンが身に付けるべき分析ツールとしてのExcelについて解説する書籍も刊行予定だそうですね。なぜ鷲巣さんは人々の「分析」スキルに問題意識を持たれているのでしょうか。
鷲巣:僕のバックグラウンドはファイナンス、中でも特にFP&A(ファイナンシャルプランニング&アナリシス)と呼ばれる分野です。アナリシスとの名前の通り、この役割のミッションは分析そのもの。具体的に言えば、財務情報、非財務情報を分析してインサイトを出し、意思決定権者に対して提供する役割となります。
つまり、僕は分析を生業としたキャリアを歩んできたんです。先輩方の分析、あるいは自らの分析が経営を動かす場面をいくつも体感してきました。
しかしその一方、世間一般では「分析」の定義があいまいだということに気づきました。例えば報告書やレポートでのコメントを「分析」と言う方もいますが、それはあくまでも「報告」です。そう考えると、<経営を動かすインパクトを持つほどのポテンシャルがある>という意味での「分析」について、一度多くの人と共有したいと思ったのが一番大きなきっかけです。
目的と目指すインパクトの大きさで、分析手法は変わる
太田:経営を動かす分析、となると壮大な感じがして、イメージがわきにくい方も多いかもしれません。ご経験の中で、分析によって会社が変わった具体的なエピソードを聞かせてください。
鷲巣:化粧品事業に携わっていた時にひとつ印象的な経験があります。当時、その事業は利益が伸び、販売額も大きくなっており、皆が好調だと信じていました。しかし改めて分析すると、ブランド軸で見れば非常に儲かっているが、販路軸で見ると儲かっているとは言えないと分かったんです。
調べてみると、収益が高い販路は百貨店の一部のほか、非常に小規模な独立系小売店でした。ではなぜ後者の利益が高いのか追究すると、そういった店舗には将来性がないと、会社が美容部員を派遣するのをやめていたんです。その分、人件費が浮いていたんですね。
つまりこの分析は、「この収益増は今後も続くわけではない、今のやり方は変えなければならない」というメッセージとなりました。
聞けば極めて分かりやすい話に思えますが、固まった分析ダッシュボードのフォーマット通り数値を入力するだけであれば、絶対にわからなかった。この分析を経てその後、組織も全社戦略も変わり、当然のことながらモニタリング資料も変わりました。まさに会社が変わったんです。分析によってスポットライトの当て方を変えると、今まで見えなかったものがこうして見える瞬間があるんですよね。
太田:このエピソードからは、何を目的にどこまでインパクトを出したいかによって、分析方法は異なってくるということもわかりますね。どんな方法が適しているか判断するには、本人の嗅覚やセンスが関わってきそうな気がします。このあたりはどうやって鍛えられたんでしょうか。
鷲巣:即座に身に付くものではありませんが、日々常にあるべき姿を心がけるというのは大きかったと思います。ただ、自分1人で身に付けたかというとそうではありません。やはり先輩、上司から高いスタンダードを植え付けられた経験は活きていると思います。
FP&Aの分析は結局、経営層に「なるほどね、そっちのほうが正しそうだ」「じゃあこっちの方向で戦略を組んでみよう」と思ってもらって初めて価値があるんです。逆に言えば、そう思わせられない分析しか出せなければ価値がない。これはキャリアの浅い頃、上司から言われましたし、自分たちも強く認識していました。そういう環境に上手くトレーニングしてもらったというのは大きいかもしれません。
太田:自分はこうしたいという意識、そして周囲に求められるものを合わせて嗅覚やセンスを磨いていくということですね。
鷲巣:一方で、分析の人間というのはいわゆる“現場”とは少し距離のある本社のスタッフ部門や専門チームに属すことも多くあります。そういう場合ではやはり、適切な分析方法を選ぶための前提となる、報告相手や状況に実際に必要とされていることを理解するのが難しいということは確かです。
そういった時は、データだけ見ていても意味がないので、現場に行ってそこにいる方々の肌感覚とすり合わせることも必要だと思いますね。
バイアスは当たり前 分析担当と現場のすり合わせをどうするか?

太田:私自身も事業企画としてデータを分析する立場にありますが、結果を現場に見せてみると、お互いの考えや認識にギャップが多く、すり合わせが難しいように思っています。こういった現場とのすり合わせで意識されていることがあれば教えてください。
鷲巣:データ分析担当は、多くが自分の知らない領域のデータを分析することになります。それが肌感覚と合致しているかを現場と一緒に確認することは、必須の作業と言えるでしょう。
噛み合わない理由のひとつにはバイアスがあります。現場の人間は、データを出されたところで、でも俺の感覚と違うんだよな、となれば思考がシャットダウンしてしまいがち。対してデータ分析担当は、現場はそう言うけど数字はこう言っている、と主張し続けてしまう。結局それはお互いに接点を設けず、自分の意見に固執している状態ということです。
そういった時に重要になるのが、出てきたものを解釈しようとする互いの<意志>です。分析担当にとってはデータが示すもので、現場担当にとっては自分の経験値ですが、それぞれに大きな価値があり、互いにそれを信じることは悪いことではありません。ですが、新しいアイディアとは大抵、今の延長線上ではないところにあります。一歩踏み込んで「本当にそれでいいのか」「違う角度で見たらどんなメッセージがあるのか」と自分にもう1回問いかけ直す。お互いの意見を合わせた第三の意見は出せないか、解釈して昇華させようとしてみて頂きたいのです。それは相手を否定しているわけではありません。本当に何が起こっているのかを突き詰める姿勢なんです。
太田:お互いが持っている考えや違和感は場に出してすり合わせていくことが大切だし、そうしようとする共同意志がなければ良い分析は基本的にはできないと。
鷲巣:1人ですべてがわかることはほぼありません。であれば、集まるそれぞれがデータや相手の見解を尊重しつつ、何が言えるのか考える姿勢が大事だと思います。これはもう意志によってでしか実現しないんですよね。
狙うべきは「なるほど」ゾーン
太田:今回、シリーズ6本の動画でも語って頂きましたが、改めてあるべきデータ分析の姿とは?という問いがあった時、鷲巣さんはどう答えますか?
鷲巣:僕はそもそも、分析とはある問いに対して、事象を分解し、比較し、その意味のある差を解釈することだと定義しています。冒頭に「報告は分析ではない」と申し上げたのは、報告は往々にして解釈が入っていないからです。例えば今月の売上は先月に比べてこれだけ増えましたとか、昨年比これだけ増えました、といった報告は、比較はしていますがそれが何を意味するかの解釈までいっていない。何が実際起きたのか、なぜその差が生まれたのか、まで言えれば、次に打つ手がわかるんですよね。逆に言えなければ、頑張れよ、で終わってしまう。だからこそ解釈までいって初めて分析なのだと思います。
更に言えば、やはり解釈のあとに経営を動かすことこそが分析のパワーです。動かなければ分析ではない。「分析十カ条」と題した動画中でお話をしたんですけれども、動かすためには単にSo Whatじゃ駄目なんですよね。「ふーん、そうだね、だから?」で終わってしまうと誰も動かない。
更に言えば、「サプライズ」まで行っても駄目なんです。「そもそも分析の手法が違うんじゃない?前提条件に何を置いたの?」と、犯人捜しになってしまう。これではいつまで経っても先に進みません。
ではどこを狙うかというと「なるほどゾーン」です。「今まで気がつかなかったけど、言われてみたら」という言葉が出てくるゾーン。そこに加えてファクトに基づいた裏付けを語れると、じゃあ今までのやり方を変えてみよう、と「経営が動く」わけです。
太田:僕は以前企業向けコンサルティングの部門に在籍していたのですが、当時は「いかにWhat's newを出してサプライズを作るか」を意識していました。しかしそれだと行き過ぎる、というのは新しい発見です。
鷲巣:サプライズも良いサプライズと悪いサプライズがあるのではないかと思っています。なるほどゾーンは良いサプライズに近いかもしれません。やみくもなWhat's newだと悪いサプライズになって、粗探しが始まってしまうことがあるんですよね。
太田:良いサプライズを与えるコツはどこにあるんでしょうか。
鷲巣:身も蓋もないと思われるかもしれませんが、やはり経験の中で何度もそれを繰り返すしかないとは思います。何度も、だから何?と言われる。何度も、サプライズに思われて議論がスタックする経験を繰り返していく。この分析では悪いサプライズになってしまうと経験する。これらをこなしながら、いい塩梅のゾーンを事前に察知して最終的な提案まで持っていくことが出来るようになるのだと思います。
太田:分析というと、どうも機械的な印象を持たれやすいのではないでしょうか。しかし鷲巣さんのお話の節々からは「いかに相手に対して納得感を持ってもらうか」「いかに共同意思を持ってもらうか」といった考えが伺えます。情緒的な一面がかなり重要なんですね。
鷲巣:組織を動かす、自分じゃない人に動いてもらうには、その人にとって意味があると思ってもらい、納得してもらう必要があります。そう考えると、分析もコミュニケーションなのだと思いますね。
(後編に続く)

















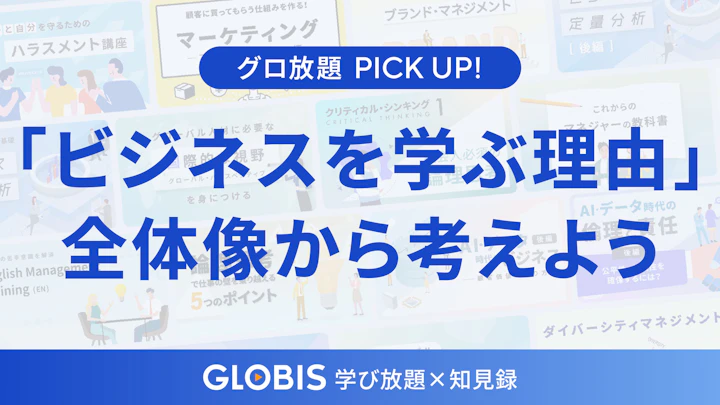


















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

