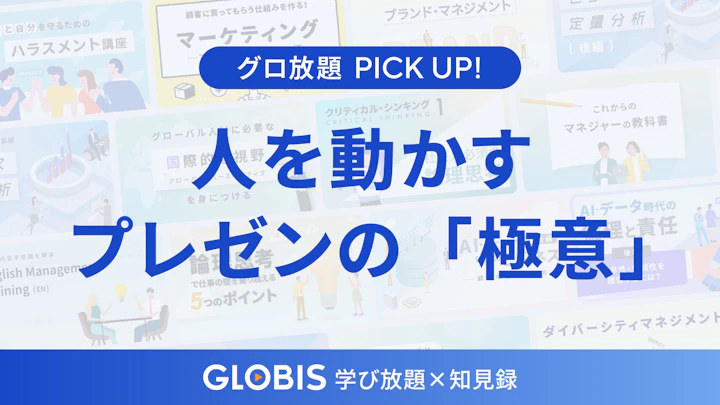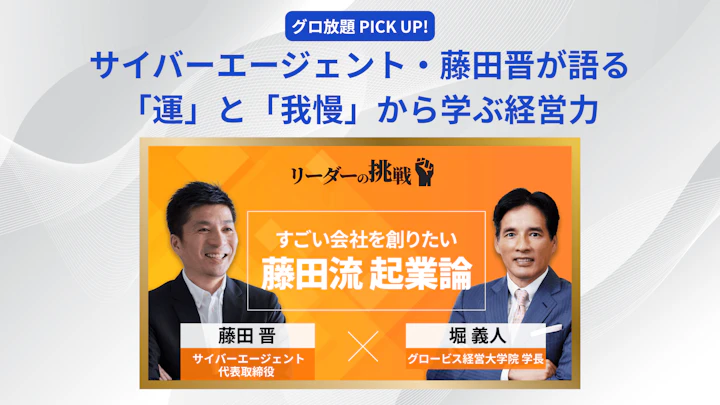日常のビジネスシーンに潜む数々の“落とし穴”。なかでも、営業先でのプレゼンや得意先へのメールなどコミュニケーションにおける転ばぬ先の杖を中心に、グロービス経営大学院で教鞭を執る嶋田毅が紹介する。第8回は、コンプライアンス委員会の「議論の質が高まらない」会議を例に会議運営の落とし穴をみていこう。(この連載は、ダイヤモンド社「DIAMOND online 」に寄稿の内容をGLOBIS.JPの読者向けに再掲載したものです)。
前回は、「議論の脱線」による時間の浪費という落とし穴について紹介した。今回も引き続き、会議運営に関連する落とし穴について紹介していく。テーマは、「社会的手抜き」だ。社会的手抜きという言葉は聞きなれない人もいるかもしれない。しかし下記の事例を読んでもらえれば、あなたの周りでもよく起きている現象であることを実感いただけると思う。
【失敗例】コンプライアンス委員会のケース「議論の質が高まらない」
神田デザイン印刷は書籍や雑誌、販促ツールなど、さまざまな紙媒体のデザインや印刷などを手がける中堅企業である。最近ではWEBのデザインも手がけている。もともと小さな個人事務所であったのが、ここ数年急拡大したということもあって、ルールや作業手順の整備・標準化は遅れており、仕事のやり方なども属人的な部分が多い。
そうした中、近年のコンプライアンス(法令順守)に関する意識や法的リスクの高まりもあって、遅まきながら神田デザイン印刷でも、コンプライアンスを組織に徹底させるべく、ルール作りとその組織への浸透を進めることになった。部門横断のタスクフォースが作られ、上野、田端、大塚、目白の4人がメンバーに選ばれた。
本日は、顔合わせも兼ねたキックオフミーティングである。タスクフォースの目的やスケジュールを共有するとともに、目指すべきコンプライアンスのレベル感や、今後の作業分担などを決めることになっている。進行役を務めるのは、管理室長で今回のタスクフォースのリーダーを務める田端だ。最初の目的やスケジュールの共有まではよかったのだが…。
田端 「さて、今回の目的などは概ね共有されたと思う。引き続いて、目指すべき具体的なレベル感についてラフに決めてしまおうと思う。特に、データの管理や盗用防止などについて議論したい。一応、僕の方でたたき台は用意したが、先日メールで連絡した通り、皆もアイデアを持ってきてくれたと思うので、まずそれをシェアしようか」
田端はたたき台の資料を配りながら、切り出した。早速大塚が口を開いた。大塚はデザイナー出身で、多くのデザイナーを束ねる立場にある。田端とは長い付き合いだ。
大塚 「悪い悪い。何か考えてこなくてはと思ってはいたけど、ちょっと仕事が忙しくて…。田端のたたき台を元に議論させてくれ」
田端は一瞬顔をしかめて何かを言おうとしたが、すぐに営業課長の目白が続いた。
目白 「実は僕もあまり考えてきてはいないんだ。ただ、いま、田端さんの資料をパラパラと見た感じだとかなり完成度が高いようだから、ほとんどこれを基本に微調整すればいいんじゃないかな」
田端と同じく営業担当の上野が続く。
上野 「僕も同感だ。さすがに田端さんの几帳面さが出ている。完成度高いと思うよ。ほとんどこれをベースにしていいんじゃないかな」
こうした反応を聞いて田端はややムッとしながら言った。
田端 「おいおい。みんなもう少し当事者意識を持ってくれよ。本当にこれでいいのか? 確かにある程度は時間を使ったが、俺だってそんなに深く考えたわけじゃない。あくまで、議論のたたき台だ。例えば、盗用防止の件だけど、コピーからのトレースは原則禁止としているが、本当にそれでいいのか? これを実際にやっているデザイナーは多いと思うが、彼らは納得するのか? まさか、ルールはルールで決めたけど、見て見ぬ振りをするというわけじゃないよな? 大塚、どうなんだ」
大塚 「確かにそうかもしれないが、皆、田端のセンスは信頼しているから」
田端は少し気色ばんで言った。
田端 「そういう問題じゃないだろ。このままだと、ほとんど俺が決めてしまうことになりかねない。もっと真剣に考えてもらわないと、本当にとんでもない結論になってしまうかもしれないぞ」
【解説】今回の会議運営の問題点 低いコミットメント
「三人よれば文殊の知恵」という有名な諺がある。複数の人間で議論することにより、1人で考えるだけでは出てこなかった良いアイデアが出てくるという意味である。事実、参加者に十分な準備や意欲があれば、どんなに優秀な人間であろうが彼/彼女が1人で考えるより、彼/彼女を交えグループで考えるほうがアイデアは出るし、思考も深まるものである。
しかし残念ながら、いつもそうなるわけではない。グループで考えているにもかかわらず、いやむしろ、グループで考えているからこそ議論の質が上がらず、いたずらに時間を浪費する、あるいは間違った意思決定をしてしまうという事態がしばしば起こる。
今回のミーティングでは、まさにそれが起きている。幹事の田端だけが真剣で、他の3人は忙しさからかコミットメントが小さく、その結果、グループで考えることが必ずしも成果に結びつかない状況である。これは「社会的手抜き」と言われる現象で、参加人数が増えれば増えるほど、個々人の責任感が薄れ、手抜きをしてしまうというものだ。こうしたことが起こる代表的な原因は以下のようなものだ。
■課題遂行に対する責任や圧力が分散される結果、各人が自己に求められる努力を小さく感じてしまう
■個人の努力と集団の成果の関係が分かりにくくなる結果、多少怠けていても責任を回避できると考える。逆に、最小の努力で全体の恩恵にあずかろうとするフリーライダーが生まれる
お心当たりの方も多いだろう。実は、この「社会的手抜き」は、程度の差こそあれ、ほぼ普遍的に見られる現象なのである。それだけ人間の本性に根ざした落とし穴といえよう。