 『グロービスMBAクリティカル・シンキング コミュニケーション編』から「会議の前に意識合わせを行う」を紹介します。
『グロービスMBAクリティカル・シンキング コミュニケーション編』から「会議の前に意識合わせを行う」を紹介します。
会議は通常、さまざまなアジェンダ(議題)を取り上げます。その中には意思決定が必要な項目もあれば、ルーティーンの情報共有もあるでしょう。定例会議などは通常、メンバーもあまり変わらないことが多く、慣れもありますから、「しまった!」となるケースはそれほどありません。一方、部門横断会議や社外の方を交えた会議では、往々にして予期せぬ行動や成果を求められることがあります。準備不足は、自分自身や所属部署の評判を落とすことになりかねません。また、参加者だけでなく、会議の主催者側も、必要に応じて事前に連絡を徹底する必用があります。参加者の事前の意識が合っていることこそが、実りある会議につながる土台となることを忘れてはいけません。
(このシリーズは、グロービス経営大学院で教科書や副読本として使われている書籍から、ダイヤモンド社のご厚意により、厳選した項目を抜粋・転載するワンポイント学びコーナーです)
◇ ◇ ◇
会議の前に意識合わせを行う
非効率的な会議によく見られるのは、参加者が漫然と参加し、特に明確な目的意識もないまま参加し続けるパターンだ。仕事では期待役割や目標が与えられるのが普通だが、なぜか会議ではそこが曖昧になってしまう。この点を改善するだけでも会議の生産性は大きく向上する。
以下、この点について考えていこう。

会議のゴールイメージ・期待成果を共有する
会議で議論すべき中心的な話題が理解されているにもかかわらず、議論が錯綜する場合に多く見られるのが、何を目的(期待する成果・会議が終わったときの像)とした会議なのかが参加メンバーに共有されていないという状況である。期待成果のすり合わせができていなければ、参加者の行動もばらばらになってしまう。これは、クリティカル・シンキングの基本中の基本がおざなりになっている状況といってもよいだろう。
たとえば、ブレーンストーミング(アイデア出し)が目的だと思って参加したメンバーに、いきなり意思決定を迫っても、みんなの考えがまとまるはずがない。あるいは逆に、意思決定することが目的だと思って参加したところ、単なるアイデア出しの会議だとわかった場合も、良いアイデアはなかなか出てこないだろう。
心理的な準備ができていないためトップギアに入れないだけでなく、「そんなつもりではなかった」「不意打ちをくらった」など、手続き的公正の部分に不信感を持たれ、参加意識が下がるおそれもある。いったん不信感を持たれると、払拭するのには苦労を要する。
したがって、当たり前のことではあるが、生産的な会議を行うためには、議論する内容はもちろんのこと、その会議で何を実現したいのかを、会議の始まる前に参加メンバーと共有しておくことが重要だ。これは、会社が中長期の計画を立てる際に、ビジョンを視覚的イメージを喚起するようにビビッドに表現したり、達成目標を数値で表すのと同じことである。
会議の種類
では、通常、会議のアウトプットとして何か期待されるだろうか? ここでは、期待する成果や、会議が終わったときの到達イメージの観点から、典型的な7パターンに分類してみた。当然のことだが、会議のタイプによって、会議の成果を測るための指標も変わってくる。

現実には、会議のたびにこれらの指標を測定するわけではないのだが、参加者に意識させるだけでも、発言や行動などは変わってくるはずである。あるいは、「今回のブレーンストーミングでは、○月○日の会議の時よりも多くのアイデアを出したいと思います」といった文言を会議の案内に明示するだけでも、参加者は会議のイメージを明確に持てるようになり、スムーズに議論に参加できるはすだ。
なお、図に示した分類とは違う観点から、以下のように会議を分類することも可能である。それぞれのケースで、会議の目的や到達イメージを周知することの重要性は微妙に異なってくる。
●定例会議/非定例会議
一般に定例会議は、会議の性格が参加者にとって既知である。また、メンバーもほぼ固定されており、アジェンダも事前にわかっていることが多いため、会議の目的共有化の重要性は相対的に下がる。
とはいえ、定例会議に慣れてしまうと、性格の違う会議(例:通常は情報共有と意思決定がメインの会議でブレーンストーミングを行う)を開こうとすると、参加者が戸惑ってしまうことにもなりかねない。また、生産性の低い会議が常態化してしまうと、なかなかそこから抜け出せないという問題もある。
なお、会議に参加するメンバーのポジションにもよるが、ある程度高位のポジションのメンバーが参加する定例会議では、緊急のアジェンダがないからといって流会にするのはもったいない。彼らのスケジュールを合わせることは難しいし、近況報告をしたり、将来ビジョンについてフリーディスカッションを行う場にして、経営陣の感覚値をすり合わせる機会とすることもできるからである。
●部門内会議/部門横断会議/全社横断会議
参加者が多様になればなるほど、会議の目的について共通の認識を持つよう働きかけておくことが重要となる。一方で、内輪の会議になるほど、安心感ゆえの「ダレ」が発生することもあるので、状況に応じて引き締めを行うことも必要である。企業によっては、あえて他部門のオブザーバーを参加させることで、そうしたダレを防ぐとともに、情報の透明化や人事交流も図っているという。
『グロービスMBAクリティカル・シンキング コミュニケーション編』
グロービス経営大学院 (著)
2800円(税込3024円)














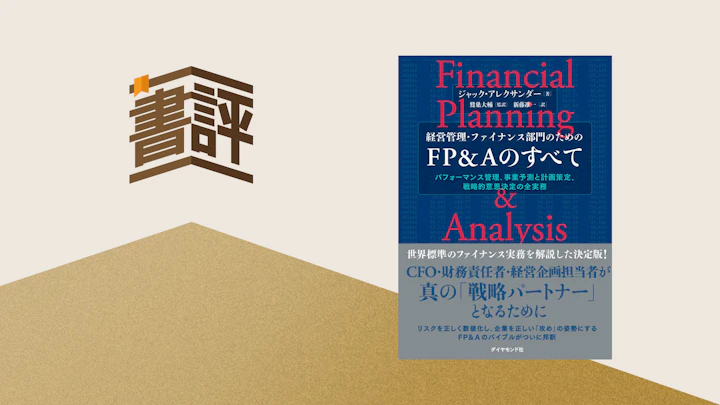


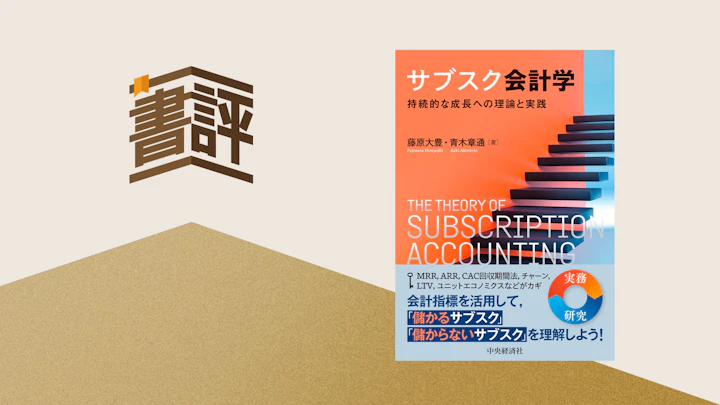













.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)



