 『グロービスMBAクリティカル・シンキング コミュニケーション編』から「コミュニケーションの構成要素と目的」を紹介します。
『グロービスMBAクリティカル・シンキング コミュニケーション編』から「コミュニケーションの構成要素と目的」を紹介します。
コミュニケーションを構造的に捉える上でまず意識したいのはその目的です。われわれが普段何気なく行っている「コミュニケーション」という行為は、「目的」「伝え手」「受け手」…とさまざまな要素に分解することができます。それらが変われば、当然、効果的なコミュニケーションの方法や盛り込むべき内容、さらには「キャッチボールの仕方」なども変わってきます。
たとえば、プライベートにおけるカップルの相談も、男性が問題解決を意識することが多い一方で、女性は共感を得ることをより重視するといわれます(これはあくまで一例であり、ジェンダーを例示することが目的ではありません)。「正しく考える」ことのベースとなるクリティカル・シンキングの第一原則が「イシュー」を押さえること、つまり「そもそも何を考えるべきなのか」「そもそも目的は何なのか」を押さえることであるのと同様、「正しいコミュニケーション」のためには、まずはしっかり目的を押さえることが重要なのです。
(このシリーズは、グロービス経営大学院で教科書や副読本として使われている書籍から、ダイヤモンド社のご厚意により、厳選した項目を抜粋・転載するワンポイント学びコーナーです)
コミュニケーションの構成要素
コミュニケーションはさまざまな捉え方が可能だが、本書では、ビジネスパーソンが活用しやすい捉え方という観点から、以下の7つの要素にブレークダウンして議論を進めていく。
●目的:何のためにコミュニケーションをするのか。コミュニケーションをすることで何を実現したいのか
●伝え手:誰がコミュニケーションをするのか
●受け手:誰にコミュニケーションをするのか
●コンテンツ:コミュニケーションの内容
●トーン:コミュニケーションの調子や表情など
●メディア:コミュニケーションに用いる手段
●伝える状況:どのような状況でコミュニケーションをするのか
これらの要素の関係は、図のようにコミュニケーションの全体像の中で捉えると明確に理解しやすくなる。

このうち、最初の3つはすでに決まっている前提条件であることが多い。ただし、「伝え手」は状況によっては変数となる。すなわち、そのコミュニケーションに最適な人材を戦略的に選ぶことも可能だが、本書では、特に断らない限り、基本的に自分自身が伝え手である場面を想定しながら議論を進める(なお、誰が伝えるのがよいかという議論も簡単に行う)。
それに対して、後の4つの要素は、前提条件をしっかり理解したうえで、最も有効なものやその組み合わせを考えるべきである。本書ではその組み合わせを「コミュニケーション・パッケージ」と呼ぶ。コミュニケーション・パッケージについては、第2章で詳述する。
目的
クリティカル・シンキングの第一の鉄則どおり、コミュニケーションの一番重要な要素は、コミュニケーションの目的であり、それをしっかり押さえることが肝要だ。
ビジネスシーンでは、どうしても説得や合意形成などをコミュニケーションの目的と考えやすいが、場合によっては、相手の話を傾聴し、共感を示すことで安心感を与え、相手の精神状態を落ち着かせることが目的となることもある。仕事で悩んでいる部下の相談に乗ったり、顧客のクレームに対処したりするようなシーンがこれに該当する。
ケースでは、部長は、せっかく考えついたアイデアが消えてしまったことに腹を立てたせいか、本来の目的であるべき「部下の淡野にしっかり仕事をしてもらうように指導する」というポイントを見失い、感情的な対応になってしまっている。ちょっとしたことであるが、こうした対応は、長い目で見た時に職場の生産性を落としていく。特にポジションの高い人ほど気をつけたいポイントである。
目的は、最初に一度考えておけばよいというものではない。常に頭の片隅で意識し、自分の考えていることや行っていることが、目的からずれていないかをチェックしなければならない。
そのためには、クリティカル・シンキングの原則に立ち戻り、自分の置かれた状況を客観的に眺める習慣をつけることが望ましい。ある程度重要なコミュニケーションでは、面倒くさいようでも紙に書き出し、視覚化しておくと有効だ。その時、目的を振り返りやすいような形に工夫しておくといい。具体的には以下の3つのやり方が有効だ。
1) 立場と状況を明確にしておく
まず、目的の前提となる立場と状況を明確にしておくことだ。同じような状況でも立場が違えば考えるべきことは違ってくるし、同じ立場の人でも、状況に応じて目的を柔軟に変えるはずである。
ケースでは、淡野の立場は「部下」であり、状況としては、「ソリューションを求めている上司に、そのソリューションの候補について説明する機会が来た」と考えたようだ。しかし、淡野が忘れていたことに、「部長は忙しく、また、システムに必ずしも詳しくはない」という付随状況がある。であれば、ここでの当面の(マイルストーンとしての)目的は、いきなりすべてを理解してもらうことではなく、まずは関心を持ってもらい、ラフな像をイメージしてもらう、としたほうがよかったかもしれない。
2) 目的を具体化する
ここで言う目的とは、到達点のことである。到達点は、具体的なレベルで考えることが不可欠だ。たとえば、上司にナレッジマネジメント・システムの現状を伝えようとする場合は、「ナレッジマネジメント・システムの現状を伝える」という抽象的なレベルではなく、「ナレッジマネジメント・システムの問題点を上司が正確に把握し、次の打ち手として何をすべきか判断できるような状態にする」というレベルまで具体化しておくとよいだろう。
そうすることで、何を伝えればその目的を達成できるか、そして目的達成のためにどのような伝え方が効果的か、ということが明確になる。
3) 受け手の現状から目的を考える
もうひとつのポイントは、先述した「状況」とも関連してくるが、「受け手の現状」から目的を考えるということだ。それによって伝えるべき内容を絞り込むことができるし、伝え方もより具体性をもって考えることが可能になる。
たとえば、新サービスを顧客に提案しようと考えている場合であれば、「顧客が納得するような提案をする」という表現ではなく、「受け手である顧客が現状で不便に感じている○○を、新たに提案するサービスで解消する」などと、受け手の現状とのギャップが見えるような形で目的を考えると、コミュニケーションすべきことが絞り込まれてくる。
(本項担当執筆者:グロービス出版局長 嶋田毅、HRデザインスタジオ代表 生方正也)
次回は、『グロービスMBAクリティカル・シンキング コミュニケーション編』から「伝え手」を紹介します。
https://globis.jp/article/5182













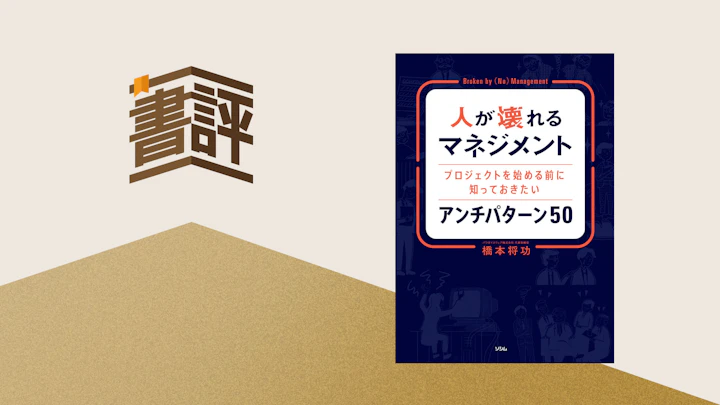
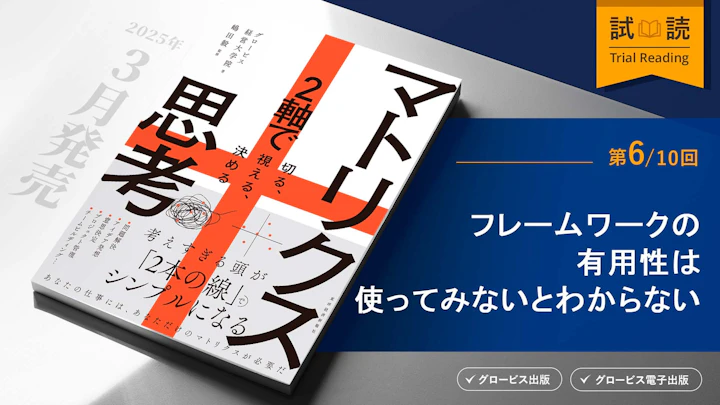



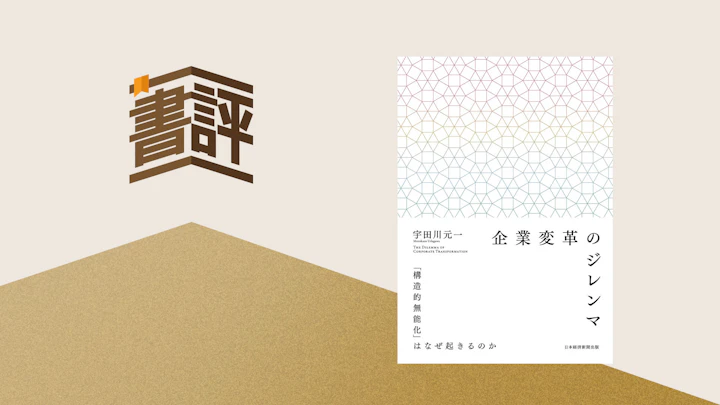
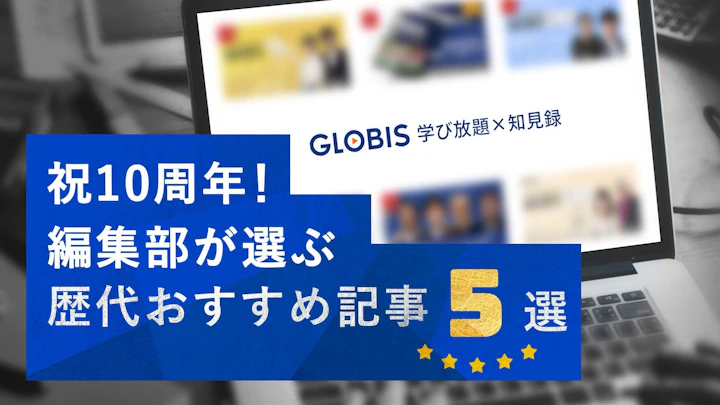





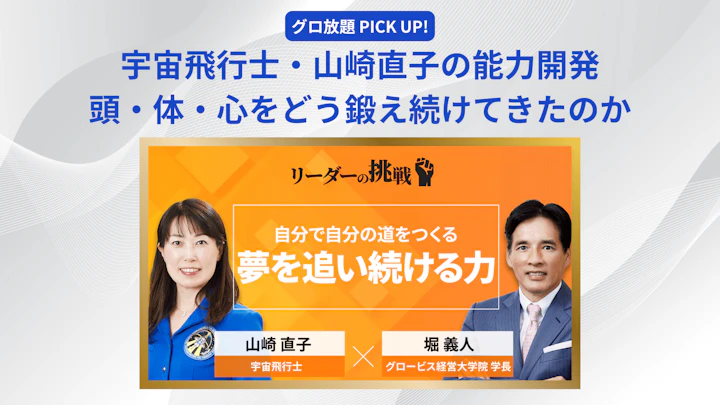
.png?fm=webp&fit=clip&w=720)







