 ここ最近、「長時間労働問題」を機に、日本人の働き方に注目が集まっている。管理体制や労働生産性の低さなど、企業側で解決しなくてはいけない課題は多く存在する。
ここ最近、「長時間労働問題」を機に、日本人の働き方に注目が集まっている。管理体制や労働生産性の低さなど、企業側で解決しなくてはいけない課題は多く存在する。
ただ、これは企業だけでなく、日々働く私たち自身の問題でもある。私たちそれぞれが、働き方だけでなく「人生そのものをどう生きたいのか?」と自身に問うことも必要なのではないだろうか。人生を生きる意味について、深い問いを投げかけてくれる書籍『モリー先生との火曜日』を紹介したい。
本書は、1994年頃『デトロイト・フリープレス』の人気スポーツコラムニストとして活躍していたミッチー・アルボムと、ALS(筋萎縮性側索硬化症)という難病に侵されたモリー・シュワルツ教授の人生をテーマにした対話を「卒業論文」として出版した、ノンフィクションの書籍である。
2014年に世界中を巻き込んで展開された「アイス・バケツ・チャレンジ」で、ALSという病気を初めて耳にした方も多いかもしれない。ALSとは体の感覚や知能、視力等が健全のまま、手足などの体中の筋肉や呼吸に必要な筋肉が徐々に痩せて力がなくなっていく難病である。最終的には肺機能が停止し、意識があったままで死を迎えることになる。
モリーの病気をきっかけに16年ぶりに再会したモリーとミッチーの「ふたりだけの授業」は、モリー教授が亡くなる直前まで毎週火曜日に重ねられていった。
「小さなことはルールに従ってもいい。けれども大きなこと—どう考えるか、何を価値ありとみなすか—これは自分で選ばなければならない。」
「さよならが言える時間がこれだけあるってことは、すばらしいことでもあるよ。みんながみんなそれほどしあわせってわけではない」
迫り来る「死」の足音を聞きながら、ミッチーに対して語った胸に響く言葉の数々からは、死を受け入れ、今を生き切ろうとするモリーの力強さが感じ取れる。同じ状況を迎えたとして、どれだけの人がモリーと同様の強さで、死と向き合う事ができるだろうか。
私自身、数年前に近しい人を病気で失ったとき、「どのように生き、どのように終えたいか?」という問いを突きつけられた。その人の仕事ぶりを直接見たことはなかったが、死の床でも自身の責任を全うしようとしている姿、そして共に働いた、影響を受けたという方々からの賞賛の数々に強烈な衝撃を受けた。私はこのように人生を終えることができるのか――この出来事をきっかけに自身に向き合い固まった私の人生に対する考え方は、その後の仕事や家族、仲間たちに対する向き合い方の礎となっている。
本書の著者であるミッチーは、モリーと再会する前はがむしゃらに働きながらもどこか満たされず人生の意味を見失っていた。私たち日本人とどこか重なる生き方が、モリーの言葉に影響を受け変化していく過程は、読者に大きな示唆を与えてくれるはずだ。
日本人の働き方において、企業側がすぐに変わることは難しいだろう。ただ、私たち個人が人生という道をどう歩みたいかを考えることはすぐにでも出来る。日々忙殺されている人ほど、是非一度立ち止まって本書を手にとってほしい。そしてモリーと対話から、自身の人生に想いを馳せてほしい。
「人生に『手遅れ』というようなものはない。モリーは最後のさよならを言うまで変わり続けた」のだから。
『普及版 モリー先生との火曜日』
ミッチ・アルボム (著)、別宮 貞徳 (翻)
NHK出版
1600円(税込1728円)


































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
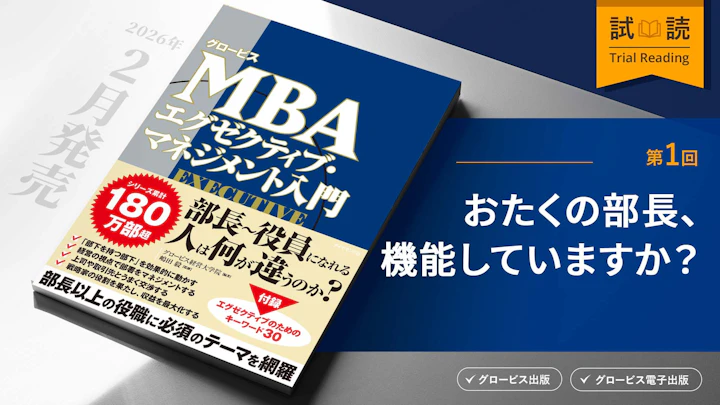
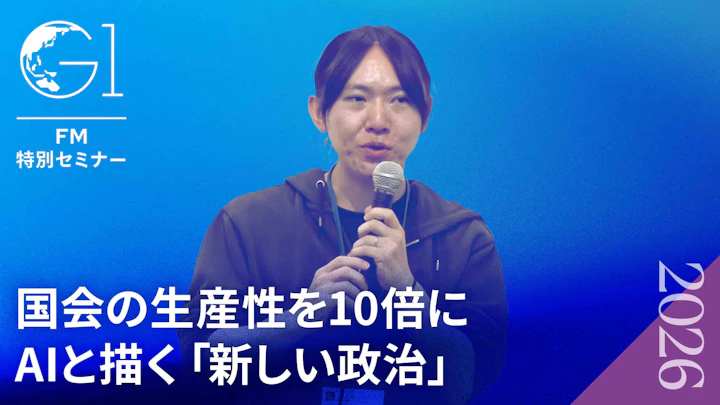


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
