 本連載「ストーリーで学ぶ経営戦略シリーズ」では様々な立場の現場のマネジャーのストーリーを基点に、古今東西の優れた戦略論から彼・彼女らの仕事をより良くするヒントが得られるかを具体的に考えていきます。
本連載「ストーリーで学ぶ経営戦略シリーズ」では様々な立場の現場のマネジャーのストーリーを基点に、古今東西の優れた戦略論から彼・彼女らの仕事をより良くするヒントが得られるかを具体的に考えていきます。
ストーリー概要:
1年前、石川は工作機械メーカーであるプレシジョン・マシナリー(PM)社において、中国駐在を任命された。PM社は、そのセグメントでは国内トップ3に入る高性能工作機械メーカーであった。
しかしPM社には課題があった。国内では競争力を持つが、海外においてはグローバルに展開する欧米企業や、中国を中心とする新興国メーカーに押され、シェアが伸び悩んでいたのである。
PM社において、今後力を入れていくと定めた市場は中国であった。中国市場は規模、潜在的な成長力など、いずれをとっても魅力的な市場であることは間違いなかった。しかも、昨今の人件費の高騰により工場の自動化要求は大きくなっており、コンピュータ制御の高性能工作機械に対する需要は日増しに高まっていた。しかし一方では、引き続く円高の状況により、今までのように単に日本で作った機械を輸出するだけでは欧米大手企業にコスト競争力で負けてしまうのは明らかだった。また、現地の細かいニーズ対応や、綿密なアフターサポート体制も必要になる。そのために、PM社は、中国を戦略拠点と位置付け、今まで営業機能しか持たなかった中国に対して、開発から生産、アフターサポートまでの機能を持たせ、「現地発のイノベーション」を創出する拠点としてその機能を大幅に拡張したのであった。
石川は、その中国法人における商品企画担当として現地赴任することとなった。
石川は元々、日本市場においてPM社の商品企画担当をしていた。商品企画担当といっても、自分でゼロから商品を考えるのではなく、生産や開発サイドの意見を聞きつつ、営業側の意向も汲み取りながら、関係者が納得できる最大公約数の製品を作ることが仕事であった。そういった調整能力においては周囲が一目置く存在でもあった。
中国市場はまだ不明確なことが多い。本社側にもまだ疑心暗鬼な雰囲気が漂っている。そんな中での中国の辞令であったため、石川自身は、自身の配置は、足場が固まっていない中国市場において、多くの関係者を巻き込みながら前に進めていくという彼特有の調整能力の発揮を期待されてのことであったと理解していた。
赴任直後から、石川は現地での製品コンセプト作りに励むことになった。しかし、それはそんなに簡単なものではなかった。そもそも良いコンセプトを作ったところで、現場で作れなければ仕方がない。仮に作ることが出来たとしても、実際に売れるかどうかは分からない。初めからあまり理想を高く掲げて前に進めなくなることを石川は恐れた。
また、石川は出来る限り本社と密に連絡を取るようにしていたが、本社の商品開発部隊からは「グローバルレベルでいかに規模を効かせるかを考えろ」ということを何度も言われていた。つまり、本社とは全く関係ない現地固有の商品を作ってしまうと、規模の経済が効かなくなる、ということだ。これは過去に商品ラインナップを過度に広げた結果として、需要予測の難易度が上がり、在庫がだぶつき、多くの商品で採算割れをしたという苦い経験がベースにあった。したがって、商品企画においても、グローバルレベルでどれくらいニーズが見込めるのかを慎重に考えるべき、という雰囲気があった。本社で長らく仕事をしていた石川にも、そのことは潜在意識に刷り込まれており、「現地発のイノベーション」というメッセージも、一足飛びではなくいくつかのステップがあると考えていた。
最終的に、石川が商品企画の段階で一番頼りにしたのは、本社側の意見と、本社開発部隊にあるデータベースであった。そのデータベースには、過去の商品企画における地域ごとの販売実績が豊富に残っている。石川はデータ分析のツールを駆使しながら、1つの商品コンセプト案を定義した。それは、現地のケイパビリティでもおそらく製造可能であり、過去の中国販売実績から考えても少なからず需要の見込みがあり、かつ今までの日本の製品と比較して不要な機能は可能な限り削ぎ落としたシンプルなモデルであった。社内関係各所からの反応も上々であり、最初の落とし所としてはいいコンセプトがまとまったと考えていた。
来週は中国法人のトップにこのコンセプトをプレゼンテーションする最初の機会を控えていた。石川は社内のデータや関係各所からのヒヤリング結果を分かりやすくビジュアルにまとめたパワーポイント資料を、時間を忘れて作っていた。
理論の概説:『知識創造企業』
『知識創造企業』は、1990年代に一橋大学の教授である野中郁次郎氏と同・竹内弘高氏によって書かれた経営書です。同書は最初にアメリカで出版され、すぐさま高い評価を得ることに成功しました(この書籍によってナレッジ・マネジメントの大家となった野中氏は、やがて2008年のウォール・ストリート・ジャーナル紙において「世界で最も影響力のあるビジネス思想家トップ20」に唯一のアジア人として選ばれることにもなります)。
この書籍が高く評価された理由は「なぜ日本企業が成長しているのか?」という問いに対して明確な解を提示したことにあります。
ご承知の通り、1970年代以降、数多くの日本企業は、一躍、成長軌道に乗り、欧米企業を脅かす存在になっていくのですが、欧米企業にとって日本企業はとても謎に満ちた存在でした。戦略らしい戦略も見られない。傑出したリーダーシップを発揮している人物がいるわけでもない。しかし、イノベイティブな商品やサービスが次々に出てくる。果たして日本企業のどこに、その原動力があるのだろうか?当時、欧米諸国では、その謎に挑戦した書籍が数多く出版され、販売数を稼ぎました。その中でも、今回紹介する『知識創造企業』は、日本企業における組織的な知識の生産力に着目し、「組織的知識創造の技能・技術こそが日本企業成功の最大要因なのだ」としたうえで、日本企業の優位性を非常に分かりやすいコンセプトにまとめたものとして高い評価を得たのです。
このコンセプトこそが、著名な「SECIモデル」というものになります。
詳説しましょう。知識には「暗黙知」と「形式知」の2つの次元が存在します。暗黙知とは、うまく言葉にはできない、もしくは存在すら認識されていない知識であり、形式知は言語や形に表現可能な知識と定義されます。

では、この2つの知識の次元は企業の経営にどう関係してくるのでしょうか。
企業の優位性は、一義的には目に見える商品やサービスによって決まります。つまり、良い商品やサービスという「形式知」を生み続けられる企業が強い、ということです。しかし、「形式知」というものは、組織が勝手に作ってくれるものではありません。組織の構成員個人が持つ暗黙知がその基盤にあるわけです。そして、その個人が持つ暗黙知を素早く、確実に形式知に変換し、またその過程で暗黙知を得て次の形式知を生み出せる、というスパイラル型のマネジメントが確立している企業こそ、優位性のある組織ではないか、ということです。
そして、このコンセプトを分かりやすく表現したものが前述の「SECIモデル」ということになります。なお、SECIは、4つの象限を成す「Socialization」-「Externalization」-「Combination」-「Internalization」それぞれの頭文字をとった造語です

1つずつ見ていきましょう。
(1) Socialization:共同化
共同化とは、組織構成員が日々の活動を通じて持っているなにがしかの暗黙知を、お互いに共通の時間を過ごしたり、空間をシェアすることによって、共有していくことを指します。典型的には、徒弟制度の下で親方のノウハウを弟子が体得するプロセスや、企業におけるOJT等が挙げられます。
ここで重要なことは、「五感を働かせて体得する」ということです。思い込みを持って現場を見るだけでは「共同化」にはなり得ません。その現場と一体化し、変に総括しようとせず、共感が持てるまで没入する、ということが重要になってきます。
(2) Externalization:表出化
表出化とは、共同化によって蓄えられた暗黙知を言葉や図、プロトタイプなどを活用して、具体的な形に変えていくことです。たとえば、現場体験を通じて、その手順をマニュアル化していくことや、顧客からの声をもとに新たなサービスコンセプトをパワーポイントで作成する、といったことが該当します。
ここで大事なことは、「対話」です。個人の暗黙知は、なかなか個人の力で表出化していくことは難しいです。なぜならば、暗黙知というのは、そもそも自分自身がその存在に気付いていないことも含まれているからです。したがって、他人と対話を重ねることにより、その本質が言語化され、磨かれていくのです。
(3) Combination:連結化
連結化とは、表出化された形式知をさらに結びつけて具体化し、最終的な形に「落とし込む」ということになります。たとえば、表出化のフェーズで形にしたコンセプトやイメージを、保有する顧客データからより事業イメージを具体化したり、既に定義されているオペレーションサイクルに適用できるように仕組みを定義する、といったことが該当します。
ここで大事なことは左脳を活用した論理的な分析です。存在するデータを駆使することによって、イメージやコンセプトレベルのものを、より「現実的」「実践的」なものにしていくことが求められます。
(4) Internalization:内面化
内面化とは、連結化によって完全に組織としての形式知にされたものを、再度個人の暗黙知として取りこんで行くフェーズになります。たとえば、新しく作ったビジネスを運用していくことによって生じる顧客からのフィードバック(顧客の表情、実際の生声等)は、個人の経験値として深く内面に刻み込まれることになります。
ここで大事なのは、「内省と実践の反復」ということです。内面化は単に実践するだけでは成功しません。自覚的に、意識的に内省をして、体の中に取り込んでいくことが重要になります。

解説:石川さんはどうすべきか?
では、SECIモデルを踏まえ、石川さんのケースを振り返ってみましょう
まず確実に言えるのが、石川さんの「共同化」に対する認識の不足です。つまり、現場にある暗黙知をくみ取るための意識に欠けている、ということです。もちろん、石川さん自身に、現場に対する意識がなかったわけではありません。サプライヤーを訪問したり、工場とやり取りを行っていたことは事実です。
しかし、「共同化」とは、そういうレベルのことを言うのではないのです。『知識創造企業』にある通り、「五感を働かせて共感し」、「思い込みを捨てて対象物と一体化するまでの感覚を持つ」ということが重要なのです。つまり、現場と単に会話をする、ということは、共同化にはなりえません。思い込みや前提を捨てて、現場の空気を体感する、もしくは、現地顧客の視点に立ち、顧客になりきって顧客の購買行動や価値観を理解しようとしなくてはならないのです。そのレベルまで「一体化」しようと努めることにより、ようやく現場にある暗黙知が理解できるのです。
特に、「現地発のイノベーション」を目指すPM社にとって、中国は「日本のやり方をそのまま持ち込む市場」ではなく、現地にある暗黙知を生かして、現地に即したアプローチを柔軟に取り込んでいくべき市場のはずです。しかし、今回の石川さんは、過去の経験にこだわり、そもそも「暗黙知から学ぶ」という意識が完全に欠如しています。現地にいながら、「共同化」が全く行えていない、というグローバル化に慣れていない企業によくありがちなパターンと言えるでしょう。
「共同化」に加えて、石川さんの認識に大きく欠けていることは、「表出化」になります。「表出化」とは、上記のとおり、暗黙知を何らかのコンセプトとして見える形にまとめていくことになり、そこで重要になるのは、「対話による本質追求」です。つまり、「どれだけ関係者と徹底的に対話をしたか」ということです。
当然ながら、その対話の相手は、出来る限り「本質的な問いを投げかけられる人材」であることが必要になります。そういう相手はえてして、同質的なキャリアを歩んできた人ではなく、全く異なるキャリアや立場の人間になります。つまり、「当たり前」と思っていることを疑うことから思考は深まるのです。自分自身が当然と思っていることに対して、「なぜこうなのか?」「これは具体的にどういうことなのか?」という本質的な問いを受け、その問いに対して分かりやすく説明をする過程で、自分自身が新たな発見を得て、思考がクリアにまとまっていくのです。
しかし、今回の石川さんは、過去のデータベースを参考にして、比較的同質な人と会話を繰り返したにすぎません。ひょっとすれば今回の中国法人トップに対するプレゼンテーションが、「表出化」の第一歩になるのかもしれませんが、万が一そこがスルーされるようなことになれば、「共同化」も「表出化」の過程もまともに行われなかったアイディアが世に出てしまうことになります。こんなことをやっているようであれば、真の「現地発のイノベーション」への道ははるか遠いと言わざるを得ないでしょう。
こうしてみると、石川さんのいる組織においては、SECIモデルのスパイラルはS(共同化)とE(表出化)のところで完全に目詰まりを起こしており、知識創造のスパイラルは停止している状態であるということが分かると思います。
ではなぜこうなってしまったのでしょうか。もしくは、このスパイラルを回すためには何が必要なのでしょうか。
『知識創造企業』において著者らが、このスパイラルを回すための最も重要な要素の1つとしてあげているのが「組織の意図」ということです。つまり、「どのような知識」を、「どこから」得るのか、という全体設計を意図しなくてはならない、ということです。
おそらく、このPM社ではその設計がなされていなかったのでしょう。もちろん、「現地発のイノベーション」というスローガンが出されてはいるのですが、それ以上の組織的な設計はなされていませんでした。こういう状態であると、組織は「慣性の法則」に引きずられます。つまり、何らかの極端な仕掛けがない限りにおいては、人間は無意識のうちに、今まで慣れ親しんでいた行動を取り続ける、ということです。石川さんが取った行動を振り返ると、結局は本社主導、データベース重視の行動モデルです。つまり、無意識のうちに本社のアドバイスを聞き、過去のデータを踏まえて理屈を考えてから動く、というものです。
想像するに、新規市場攻略は「日本の本社にいる優秀なマーケティング部隊や開発部隊が考えるべきこと」であり、「失敗しても説明がつくようにデータを重視すべき」、というマインドセットが少なからずあったのかもしれません。これはおそらく組織的にしみついている行動原理なのでしょう。それが強ければ強いほど、「慣性の法則」に打ち勝つだけの「組織の意図」を定義することが重要になるのです。
そう考えるならば、本来石川さんが働きかけるべき本質的なこととは、「現地発のイノベーション」とは具体的にどういうことを意図しているのか、それはいつまでに実現すべきことなのか、そしてそれを実現するということは、「どのような知識」を、「どこから」得るのか、ということを、マネジメントレベルと徹底的に議論することなのでしょう。
※なお、本題とはややそれますが、グローバル化において、PM社のように現地適応と統合をどう両立させるのか、ということは、多くの業界で直面する課題になります。この対応の仕方は業界によって異なりますが、一般論として言うならば、石川さんのように両方のバランスを取りながら進めていく、というのは結果的にどっちつかずになる可能性があります。今回のような場面であれば、まず統合は二の次として割り切って、徹底的に現地化を進めていくことが大事です。つまり、敢えて「現地適応と統合の不均衡を起こす」、ということです。そうすると、現場と本社において、「暗黙知の格差」が生じてきます。そのタイミングで、その格差や不均衡を解消し、統合度合いを高めていくための動きをしていくのです。現地適応と統合のバランスを最初から目的とするのではありません。その不均衡解消の連続によって、結果的に高い次元でのバランスにつながっていくのです。
ミドルリーダーにとっての意味合い
では、この理論のミドルマネジメントにとっての意味は何か。改めて考えてみましょう。
まず、重要なポイントの1つは、「現場主義と分析主義」「現場の体験と過去の経験」、そして「暗黙知と形式知」のバランスです。今回のケースで言えば、石川さんは分析的アプローチに偏り、結果的に現場主義を軽視することになってしまいました。「暗黙知」というのは、その名の通り目に見えないものであるために評価が難しいものです。そこを考えるよりは、形式知化されたデータをいかに分析するか、それを分かりやすく表現するか、ということの方が、説得力は増しますし、理屈が立ちやすいのは事実です。
しかし、暗黙知の力を侮ることはできません。たとえば、日本企業に先んじてグローバル化に成功したサムスンの原動力の一つに、「地域専門家制度」(新興諸国を中心にミドルリーダーを派遣し、1年間当該国で自由に生活をし、その国の文化やライフスタイルを理解する、という仕組み)があるのは有名な話です。サムスンはこの制度を既に20年近く運用していますが、ややもすると1年間人材を遊ばせることになりかねないこの一見非合理的な施策がこれだけ継続しているのも、「経験を通じてでしか理解できない知識」(=暗黙知)が結果的に同社のグローバル市場において成功の一要素になっている、ということの証に他ならないでしょう。
つまり、ここで改めて強調したいことは、ミドルリーダーだからこそ、データや分析一辺倒に陥るべきではない、ということです。トヨタ自動車の渡辺捷昭社長(2008年当時)は、「暗黙知を成長させないと形式知も成長しない」と述べました(野中郁次郎氏『流れを経営する―持続的イノベーションの動態理論』より)。つまり、五感を伴う現場経験や、暗黙知を交換する議論の場があってこそ、データや二次情報(=形式知)が生きてくるのです。有名なホンダのワイガヤ*1の事例を持ち出すまでもなく、優良な企業は暗黙知を交換し、涵養するための「場」を設定しています。ミドルリーダーとしては、自分の組織レベルでもこういう議論の場を自ら意図的に設けることを考えるべきでしょう。
*1 プロジェクトチームのメンバーが日常業務や職場環境から離れ、三日三晩夜を徹して語り合い、徹底的にプロジェクトの本質目的について議論し、課題や矛盾、解決策を見出していく場。(「流れを経営する」より引用)
そして、2つ目に重要な点は、その暗黙知を獲得する過程のことになります。つまり、単に「経験する」「感じる」「議論する」ということではいけません。上述のとおり、真の「共同化」においては、「思い込みを排除する」ということが不可欠です。「共同化」ということは、そこにある現場を、あるがままに受け入れ、感じる。つまり、現実を直視する、ということです。
しかし、野中氏は、グロービスにて行ったセミナーにてこのように述べています。「日本で一番大きな問題は、現実を直視する能力の乏しさでではないかと私は思っています。絶えず過去の成功体験の枠組みを見てしまい、それが真理であると考えてしまう」と。
まさにこのマインドセットこそが、真の「共同化」を妨げているとも言えるでしょう。
確かに、今、日本企業が置かれているグローバル競争環境や状況を重ね合わせてみると、海外の競合に比して、海外市場との「共同化」が出来ていないことに気付きます。グローバル展開している企業の話を聞くと、日本、もしくは欧米等の先進諸国で通用したモデルを、それ以外の拠点に押しつけていこうとする姿勢が見え隠れするのです。
野中氏は、「知識とは自分の想いを実現していくプロセスであるととらえると、マーケットは知の宝庫と考えられるわけです」と述べていますが、まさにその宝庫を活用する、という意識が欠如していると言えるでしょう。そのような企業が、これからの大きく変わっていく市場に対して長期的な視点で勝つことは難しいと言わざるをえません。この「共同化」ということは、日本企業が、そしてミドルマネジャーがこれからのグローバル競争において直面するひとつの大きな課題といえるかもしれません。
そして、3点目として、「表出化」や「連結化」ということも大きなハードルがあります。特に「表出化」は口で言うほど簡単なことではありません。「共同化」で感じたことの中から本質的な重要なことは何か、ということを抜き取り、言葉や図で的確に表現していく、というのはかなり高度な知的作業を要求します。この書籍において、「表出化」において重要なツールとして「対話」や「比喩」「アナロジー」といったことが書かれていますが、私はそれとともに現場のミドルマネジャーにとって重要になるのは、「論理思考」だと考えています。つまり、暗黙知から出てきた抽象的なイメージや大きな言葉を具体化していく作業においては、「物事を適切な切り口で分解をし」、「とある尺度の下に重要なものに焦点を絞り込み」、「残った部分に対してより具体的に問いを深めていく」というまさに論理思考そのものが必要になってくるのです。
単に漫然と「対話」をしても「表出化」にはつながりません。現場で紡ぎだされる言葉や表現に対して、どう具体化していくのか、というところに対して、論理思考は極めて有効な武器になります。論理思考に対する瞬発力がないミドルマネジャーにとっては、「表出化」ということは極めて難しいステップであるということを認識すべきでしょう。
さて、今回は『知識創造企業』を中心にご紹介してきました。おそらく今までの書籍が分析的なアプローチであったのに対して、「対話の重要性」や「顧客と一体化する」など、ちょっと違った色合いの書籍であると感じた方も多いと思います。しかし、まさにそういったある種の「人間臭さ」を含む理論であるということが、既存の分析的・スタティックな経営理論との比較における本書の特色なのです。
また、前回のコラムにて紹介したVRIOというフレームワークを思い出していただけると気付く方もいると思うのですが、VRIOの最後のO(=Organization:組織に関する問い)という項目は、このSECIモデルと大きく関係するところだと思っています。つまり、「企業の優位性が、一過性に終わらずに組織の行動に根付いているか」、という問いを考えるということは、この「知識のスパイラルが組織としてしっかり回っているか」、ということを考えることに他なりません。つまり、この「スパイラルが高速回転することによって、継続的に新たな知識が生み出されている企業」というのは、競合にとって非常に模倣困難性が高く、競争優位性を有している、ということが言えるのです。
既にこの連載も6回になりますが、過去説明してきた概念は様々なところで連関しています。そうした相互の関係性を考えながら読み進めていくと、更に理解は深まっていくでしょう。
■参考文献:
『知識創造企業』
『流れを経営する―持続的イノベーション企業の動態理論』
■参考記事:
一橋大学名誉教授 野中郁次郎氏 今の時代に求められるリーダーとは(2012年1月19日掲載)
■連載一覧はこちら
#ストーリーで学ぶ経営戦略シリーズ















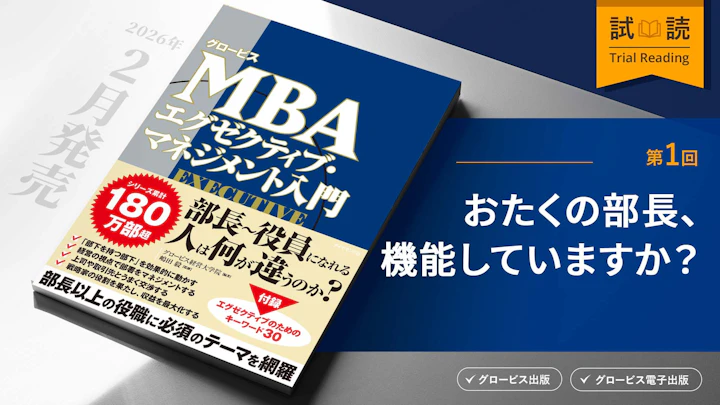






















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
