問題です
以下のA君の問題は何か。
A君はある外資系高級車メーカーの営業担当者。たまたま大学時代の友人のBさんと話をしていて、家の防犯の話になった。
A: 「最近はいろいろと物騒な事件が多いね」
B: 「確かに強盗とかのニュースをよく聞くわね」
A: 「だから、うちでもホームセキュリティをつけようと思ってるんだ」
B: 「心配性のA君らしいわね。でも、ご近所との付き合いなんかも減って我関せずの人が増えたから、A君がつけたいというのなら、つけたらいいんじゃないの」
A: 「いや、心配性ということはないさ。最近ではほとんどの家にホームセキュリティがあるから、遅まきながらうちでもつけようと思ったまでさ。実家ではもう10年前からつけてるしね」
B: 「えっ、ほとんどの家にホームセキュリティ?」
A: 「営業先なんか行くと、最近はホームセキュリティのない家なんてないよ」
B: 「・・・」
A: 「この前、付属の中高の同窓会でもセキュリティの話になったんだけど、やっぱりつけてるやつが多かったな」

解答です
 今回の落とし穴は、「半径5メートルの世界観」です。正式な名称はないようなので、ここではこう呼ぶことにします。これは、自分が直接触れている狭い世界の傾向やルールを、あたかも世の中全般の傾向やルールと錯覚するというものです。
今回の落とし穴は、「半径5メートルの世界観」です。正式な名称はないようなので、ここではこう呼ぶことにします。これは、自分が直接触れている狭い世界の傾向やルールを、あたかも世の中全般の傾向やルールと錯覚するというものです。
なお、ここでは「半径5メートル」と書きましたが、人によっては「半径3メートル」と言ったり「半径10メートル」と言ったりします。「君は半径10メートルの世界でしかものを考えられないのか」といった使い方です。具体的な数字に特に意味はなく、いずれも「狭い範囲」を指すものと思ってください。また、ここで言う「範囲」は、物理的な活動範囲に限定されるものではなく、人脈や情報源の広さ・多様さなども含意します。
お気づきの方も多いと思いますが、これはクリティカル・シンキングのクラスなどでよく言う「軽率な一般化」の1バージョンです。「軽率な一般化」は、少ないサンプルや偏ったサンプルから一般論化してしまうというものですが、そのサンプルが「身近な世界」に閉じているのがこの「半径5メートルの世界観」です。
冒頭のケースでは、A君はおそらく、資産家や高所得者との付き合いが多いことから、それを一般的な傾向と思ってしまったと考えられます。高級外車の顧客も、あるいは中高から一貫の学校に行かせるような家庭も、資産家や高所得者が多いものと思われます。確かに彼らはホームセキュリティを利用している比率が高いでしょうが、それは決して世の中全体の傾向ではないはずです(ちなみに、ある調査によると、日本でのホームセキュリティの普及率は、高目に見てもまだ2%程度となっています)。
A君の例はかなり極端な例かもしれませんが、経営者がこれに似たような落とし穴に陥ることも実際にあります。たとえば、身近な側近や経営者仲間の発言だけを鵜呑みにして好ましくない意思決定をしてしまうようなケースです。
このような現象が起こる原因にはさまざまなものがありますが、まず、人は同類——似たような出身や趣味の人間——を好み、彼らとの接触が増える(逆に言えば、同類以外の人間との接触が減る、あるいは減らそうとする)ということが挙げられるでしょう。これはリアルでの人脈もそうですし、SNSなどを通じたバーチャルな人脈でも言えることです。たとえば筆者もfacebookをやっていますが、向学心の高い前向きな「友達」が多いせいか、ときどき世の中、そういう人間ばかりのような錯覚に陥ることがあります(笑)。
もう1つ、単純に行動範囲が狭いということも原因となることがあります。これは特に、同じ場所で長い時間を過ごす人間に起きがちです。たとえば大学の研究室で長い時間を過ごす研究者や、同じ部署でずっと内勤の業務をしているビジネスパーソンなどです。これが先の原因と重なったりすると、非常に狭い世界が自分にとっての世界のすべてになってしまいかねません。
「半径5メートルの世界観」を防ぐ有効な方法は、まずは多様な人々と交わることです。性別や年代、業種等を超えてバックグラウンドの違う人と話をすることは非常に有効です。グロービス経営大学院でも、そうしたバックグラウンドの違い、言いかえればダイバーシティが学びを充実させる重要な要因と考えています。
とはいえ、忙しいビジネスパーソンにとっては、それすら難しい場合があります。その場合の次善の策は、情報源を増やすことです。常日頃からさまざまな物事に関心を持ち、さまざまな情報源に触れることが、「半径5メートルの世界観」を脱する鍵となるのです。たとえば普段自分が見ないような情報番組を見たり雑誌を読んだりするだけでも、様々な発見があるものです。
昨今は、BOP(BottomofPyramid)に代表されるように、自分の価値観や常識が全く通用しない世界とも関わりが発生する可能性がある時代です。グローバル化が進み、ダイバーシティが増す時代だからこそ、広い視野、多様な視点を持ちたいものです。
*本連載は、2012年2月16日が最終回となります。













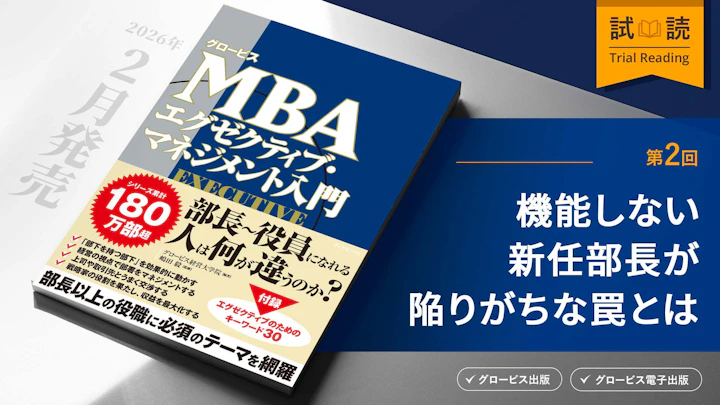























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
