本連載「ストーリーで学ぶ経営戦略シリーズ」では様々な立場の現場のマネジャーのストーリーを基点に、古今東西の優れた戦略論から彼・彼女らの仕事をより良くするヒントが得られるかを具体的に考えていきます。
ストーリー概要:法人向け英会話スクールの営業担当・安田の場合
安田は法人向けにビジネス英会話を提供する企業「イングリッシュ・パートナー社(以下EP社)」に勤めていた。EP社は単に企業向けに外国人英会話講師を派遣するのではなく、企業側の状況を的確に把握し、その状況に即し、実践性の高い英会話力を養成するプログラムを提案するカスタマイズ力を売り物としており、昨今の日本企業のグローバル展開に合わせて、業績を確実に伸ばしていた。
安田はその中で、EP社の最大のクライアントであるメーカー、エレクトロニクス社のアカウントマネジャー(営業担当)をしていた。エレクトロニクス社とは長いつきあいであり、EP社の成長はエレクトロニクス社あってこそと言っても過言ではない。設立当初に経営者の知己を通じ一部署だけの接点から始まったビジネスがエレクトロニクス社内で口コミを呼び、全社的な展開となったのである。
エレクトロニクス社は、この10年間でグローバル展開を急激に始めた企業であり、社員が英語を使う場面や地域は多岐にわたる。現地の政府の要人と直接、タフな交渉をすることが求められる社員もいれば、E-mailのやりとりさえできれば何とか仕事はまわるという社員もいる。非ネイティブのインド人のアクセントに対応できる英会話力を鍛えたいという人もいれば、ネイティブの英国人との電話会議でも確実に意見を表明したり、遜色ないプレゼンテーションができるようになりたいという人もいる。
一般的な英会話サービスであれば、それらをひっくるめて汎用的なレッスンを行うところ、EP社はエレクトロニクス社からの要望に基づき、その細かなニーズに確実に対応し、単なる会話だけでなく、その場での振る舞い方やマナー、はたまた現地ごとのカルチャーや陥りやすい落とし穴などをきめ細かく指導できる力を身につけてきた。
EP社のこうした細かなニーズへの対応力はエレクトロニクス社のみならず、大企業を中心に非常に高い評価を受けた。当然カスタマイズを行う分だけ他の英会話スクールと比較して費用は3割近く割高になるのだが、口コミで評判が広がり、EP社から営業をかけなくとも問い合わせが入ってくるようになっていた。やがて、ハイスペックのビジネス英会話であればEP社がNO.1というのが業界の認識となっていった。
安田はそのEP社の中でも大黒柱的な存在であった。アカウントマネジャーという立場であるが、EP社のマネジャーは、営業だけをするのではなく、サービスの開発にも携わる。安田の商品開発力は社内からも圧倒的な評価を受けていた。顧客からのニーズを正しく分析し、そこに合わせたトレーニングを設計することはなかなか出来るものではない。
社内も安田の商品開発力を見習うべく、「安田塾」という名前のトレーニングが週1回の頻度で行われていた。そのカスタマイズ力や設計力を持てるか否かがEP社における昇格の重要なポイントにもなっていた。
エレクトロニクス社も安田の手腕を高く評価しており、安田に対していろいろな相談を持ちかけていた。つい最近は、担当者が安田に「英会話に限定せず、異文化マネジメントも含めた海外でのコミュニケーション力を鍛えるサービスがあると嬉しいのだが」ということを伝えていた。これは全くの新しいサービスラインであり、EP社にとってもチャレンジであった。しかし、もしそれがうまく行けば、今までのエレクトロニクス社との関係で考えると、既存サービスの3割近いプレミアムが見込めると安田は考えていた。そうなれば、今年の業績は大幅に予算を上回ることは間違いない。社内は色めき立ち、リーダー陣が一丸となって開発体制を組んだ。
しかし、その一方で、順調であったEP社も、最近やや異変を感じるようになっていた。それは非常に安価なサービスを提供する企業の台頭である。中小企業はそれほど予算が取れないこともあり、英会話については、基本的に安価で最低限のサービスを提供する中小スクールを利用するのが普通であった。EP社にも中小企業から声がかかることはたまにあったが、手間ばかりかかって売り上げ規模はほとんど見込めない。それよりも、大手企業のより高度なニーズに対応する方が業績は確実に上がるし、何よりもEP社の将来的な競争力強化につながると考えていた。
しかし、その大手顧客が徐々に安価なサービスに目を向け始めていた。営業現場でEP社のサービスを提示する時の典型的な顧客の反応は、「このサービスは素晴らしいですね」と賞賛を示す一方で、「英会話にここまでの金額は出せません」というものが多かった。そして、結果として極めて標準的なサービスラインしか持たない競合に仕事を奪われてしまうのだ。
安田はその都度、「ちゃんとうちの良さを伝えているのか?カスタマイズのメリットをちゃんと訴求できていないんじゃないか」ということを営業ミーティングで伝えていた。そして一抹の不安を感じながらも、「あんな低レベルのサービスを使ったところで、金の無駄になるだけなのに。分かってないな」と感じていた。「それよりも、エレクトロニクス社向けの高度なサービスを開発すれば、大きなイノベーションにつながるぞ」と、期待に胸を膨らませていたのである。
そんなある日、安田は新たな提案を持参してエレクトロニクス社を訪問した。予想以上に工数はかかったが、間違いなくエレクトロニクス社の期待を上回るサービスになる手ごたえがあった。安田はその反応を聞くのが待ち遠しかったため、打ち合わせに入るなり、新たなサービスの提案を始めた。まさかこのタイミングで提案を持ってくると思っていなかったエレクトロニクス社は面食らったようだったが、安田のプレゼンテーションに引き込まれ、「面白いな」「さすが安田さん」という反応を示した。
ところが、である。価格の話をしたとたん、その流れは変わった。「このサービスの見積もりは、別紙のとおりです。ご覧ください」「・・・」先方は黙ったままだ。確かに既存サービスに対して4割プレミアムの金額は乗せすぎたかもしれない。しかし、エレクトロニクス社との商談はいつもこれくらいからスタートし、大抵は3割プレミアムくらいに落ち着くのだ。安田は沈黙に耐え切れず、「どうでしょう?」と聞いてみた。
「うーん、いや、良いサービスだと思いますよ。確かにね。でも、ここまでうちが払える余裕があるかと言うと・・・」そして、畳みかけるように担当者は話し始めた。「安田さん、実は言いにくいことなんですが、ご存じの通り、うちの業績がこの円高によって急激に悪化していることから、教育予算が取れなくなってきたんです。役員からも、英会話程度のことにそこまで予算をかける必要はないだろう、という意見が出てきて、ちょっと雲行きが怪しいのです。役員は、英会話が必要な社員は全社員に広がっているのだから、そんなに金のかかるEP社ではなくて、半額くらいでできるベンダーはいくらでもあるだろう、ということまで言っているのです。いや、正直、役員はよくわかっていないと思うのですがねぇ・・・。でも確かにあるんですよ、安いところは。ですから、新しい提案も金額を考えると、正直今は無理ですし、既存のサービスも一度値段を検討いただこうかなと思っていたのです・・・」
あまりに想定外のリアクションに、安田は最後の方はほとんど聞こえていなかった。最大のクライアントであるエレクトロニクス社を失注するかもしれない?いや、これは単なる交渉の一環のはずだ。でも・・・。もし、これが事実だったら、うちの業績はどうなるのだ?社内にこのことは報告すべきだろうか?もし失注したら、俺の立場はどうなるんだ?いろいろなことが安田の頭の中で回っていた。
理論の概説:『イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』
『イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』は、ハーバード・ビジネス・スクールの教授であるクレイトン・クリステンセンによって書かれた書籍であり、出版されるやいなや、大ベストセラーとなり、アメリカのみならず、世界中で賞賛されました。この書籍の何がインパクトだったのでしょうか。
それは、「なぜ優良と言われていた企業が失敗するのか」という問いに対し、原因を経営者の無能さや傲慢さ、官僚主義、技術不足といったことに帰着させるのではなく、「偉大な企業はすべてを正しく行うがゆえに失敗する」という見解を示したことにあります。
具体的に解説しましょう。本書が主張している失敗のメカニズムを簡単にまとめると、以下の通りになります。
優良企業は、顧客の意見に耳を傾け、顧客が求める製品やサービスを増産し、そのサービスを改良するために新技術(持続的技術)に積極的に投資を行う。その勝負においては、優良企業は競争優位性を発揮し、成長を続ける。一方で、時として「破壊的技術」というものが現れる。破壊的技術は、単純、小型、低価格、低性能といった特徴を有し、少数の新しい顧客にのみ評価される。
主流顧客は、性能の高い技術を評価するため、破壊的技術に対して、当初はまったく見向きもしない。したがって、その主流顧客を相手にする優良企業もその技術を導入しようとは考えない。当然のことながら、破壊的技術は、低性能、低価格という特徴を有するために利益率も低く、優良企業にとってその技術を取り組むインセンティブは短期的には見当たらない。
しかし、技術進歩のペースは、時として主流顧客が求める性能向上のペースを上回る。そうなった時、破壊的技術は主流市場で競争力を持つようになる。つまり、顧客は既存の持続的技術の過剰品質に気付き、全く異なる別の判断基準によって判断をするようになる。既存の「持続的技術」で成長を重ねてきた優良企業が、その破壊的技術に気付き、投資を始めるころにはすでに手遅れになっている。

出典:『イノベーションへの解利益ある成長に向けて』(クレイトン・クリステンセン・著翔泳社・刊 本文内容に即し、一部文言を変更
つまり、「失敗を引き起こすのは、誤った経営判断だけではない。企業が成功するために不可欠な行動――たとえば主要顧客のニーズを満たすこと、収益性から見て最も魅力的な分野に集中投資することもまた、失敗の原因となりうる」ということであり、これが「ジレンマ」とされるゆえんです。
では、このジレンマをどのように打破すればいいのでしょうか。クリステンセンは、そのソリューションを以下のように提案しています。
・破壊的技術は、既存の顧客のニーズの延長線上には見つからない。既存の顧客から離れること。そして過度に机上で考えすぎないこと。まずはスモールステップで、試行錯誤と学習を積み重ねていくことを心がけるべきである(いきなり壮大なプランをぶちあげないこと)
・破壊的技術を開発するプロジェクトを、主流組織から離れた独立した小さな組織で対応させること。そして、主流の組織における意思決定プロセスや、重要業績指標などは使わないこと(たとえば、主流の組織が、一社あたりの取引金額規模を重視していたとしても、それをそのまま使用するべきではない。たとえばコンタクト社数などに変更が必要になる)
・破壊的技術は、既存の顧客に売り込んではいけない。その破壊的技術を求める新しい顧客を自ら開拓し、その顧客のニーズに応えるようにすること
つまり、既存の持続的技術には、一度確立された勝ちパターンが、顧客との関係性や組織内部の仕組みまで浸透しているため、それを変えることはほとんど不可能に近い。したがって、それを変えようと無駄なあがきをするのではなく、ゼロベースで新しい組織、新しいやり方を模索すべきであるということです。
解説:安田さんは何をすべきだったのか?
さて、このセオリーを踏まえて、安田さんは何をすべきだったのでしょうか。ミドルの立場で考えると、本書のソリューションの一つである「新しい小さな組織を作る」のは、あまり現実性のあることではないでしょう。では、ミドルは日々の現場で何に気をつけるべきなのでしょうか。
そこで、イノベーションのジレンマの続編である『イノベーションの解利益ある成長に向けて』をひも解いてみましょう。この中でクリステンセンは、「顧客の過剰満足に注目せよ」と言っています。つまり、顧客に対して過剰な性能を提供してしまうことが、破壊的技術(破壊的イノベーション)を生み出す素地であり、したがって「過剰満足を早く見極めること」が何よりも重要ということです。
では、顧客の「過剰満足」はどうやって見極めればいいのでしょうか?同書にて、クリステンセンはいくつかのヒントを提示しています。それをまとめてみましょう。
まずは、顧客との直接的なやり取りを通じて、「性能向上に対して顧客が対価を払うかどうかの意思を確認すること」。つまり、過剰満足とは、「良いサービスだが、価格を払ってまで買うつもりはない」という状況に他なりません。そう考えるならば、安田さんがまずすべきだったことは、「そのニーズを満たすことができたら、追加でいくら払うつもりなのか」ということを、エレクトロニクス社とのやり取りを通じて確実に知ることだったと言えます。
しかし、これは言うのは簡単ですが、実際に現場で価格の話を出すのは気が引けるものです。「価格に関係なく、求められるものを作りこんでいく」という職人気質に走る気持ちも分からなくはありません。実際に安田さんも先方から新たな提案の種を出された時、価格のことは確認せずに話を進めています。しかし、このスタンスは「過剰満足」につながりやすいことを認識しておくべきです。
クリステンセンはまた、「利益率やシェアにも着目すべき」と言っています。一般に、利益率や価格が下落し続ける状況は、どのような企業にとっても好ましくないことは分かるのですが、同書では、さらに「売上が横ばいか下落傾向にあり、利益率が上昇傾向にある場合」も注意すべきと述べています。
つまり、利益率の上昇は、単に付加価値の向上だけでなく、低利益率のレンジの顧客が他社に流れることで、利益率の平均が増加しているケースがあるということです。
また、市場シェアの変化を分析したとき、「重要だと思われる特性において明らかに劣っている競合がシェアを奪っている状況」が見られるときは、過剰品質がもたらした過剰満足の可能性があります。たとえば、今回のケースでいえば、「サービスレベルで明らかに劣っていると思われる競合がシェアを伸ばしている状況」は、まさに過剰満足のサインであるということです。
もう一つ、忘れてはならないことは、「顧客の困っていることは何か」「その解決の際の評価軸は何か」に着目することです。
つまり、顧客が実際に何に困っているのか、その本質をまずはちゃんと定義し、同時に、それに対する解決策に関して、何を重視して評価すべきかを明確化する努力を惜しまないということです。
たとえば、今回、安田さんはエレクトロニクス社からの要求に対して、おそらくは彼らの困っている点に対する深掘りをすることなく、自社のサービスの視点から考え始めたと思われます。つまり、本質的に何に困っているのか、解決すべき課題は何なのか、ということの議論を十分にし尽くす前に、「うちのサービスラインでは何が売れそうなのか。そのサービスはどれくらいの工数でできるのか」という方向に考えが向いてしまったということです。こうした時に、過剰満足の種が蒔かれます。
ミドルとしてのさらなるチャレンジ
もし過剰満足だと分かった場合においても、ミドルにはさらなるチャレンジが待ち受けます。
それは、最終的に過剰満足が生じていることを認め、『イノベーションのジレンマ』に書かれたソリューションである組織変更や顧客ターゲットの変更などの意思決定をするのは、多くの場合はトップであるということです。したがって、トップと問題意識を共有しなくてはなりません。しかし、そこには大きな壁が立ちふさがります。
「お前らが頑張っていないだけじゃないのか?」「ちゃんと然るべきタイミングで先方のキーマンを巻き込んできたのか?」「あのリードクライアントからの要望に応えないのか?」などと言われた場合、多くのミドルリーダーは答えに窮するでしょう。
『イノベーションのジレンマ』は、企業の経営者に向けて書かれた書籍であり、これ対する直接的な答えは書いてありません。しかし、中身を咀嚼すれば、その解はうっすらと見えてきます。
そのキーワードは、「現場」ということです。この書籍において、クリステンセンは「過度に机上で考えるべきではない。市場機会を本当に理解したいのであれば、オフィスから出て顧客との対話を行うべきだ。そこでは驚くべきことを学べるだろう。」と書いています。つまり、ミドルの立場で言い換えるならば、「トップを顧客接点の現場にどれだけ連れていっているか」ということです。
もちろん、「顧客接点の現場にちゃんと連れて行っている」という方も多いでしょう。しかし、ここで考えるべきは、その「現場」がどういう場なのか、ということです。つまり、多くの場合、トップが行く顧客接点の現場は、いわゆる限られたリードクライアントとの重要な商談の場面などになります。もちろんそういう場はトップ営業として非常に重要なのですが、そういうリードクライアントとの接点だけしか見ていないトップは、それだけをもって「顧客接点」と捉えてしまう可能性があります。この状況はむしろ「過剰満足」を加速させる要因になりかねません。そうではなく、むしろ連れていくべき現場は、そのようなリードクライアントではない「その他大多数の顧客」(=取り扱い金額が少ない顧客や新規顧客、もしくは何らかの不満を持っている顧客)との接点の場なのです。そういう現場で、顧客が自社のサービスや商品を見て何を語っているのか、どのような不満やリクエストを出しているのか。そのリアルな状況をトップに理解してもらうこと。これを日頃から実践することが、「ジレンマ」を阻止するためのミドルからのアプローチの一つとなるのではないでしょうか。
■参考文献:
※この理論をよく理解するためには、以下の書籍を読まれることをお勧めします。
『イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』
世の中にこの理論を投げかけ、多くのリーダーに影響を与えた書籍です。まずはこちらから読まれることをお勧めします。
『イノベーションへの解 利益ある成長に向けて』
上記『イノベーションのジレンマ』は有名ですが、『イノベーションの解』は読まれた方は意外に少ないと思います。しかし、この書籍は個人的には『イノベーションのジレンマ』より分かりやすく、かつ実践的だと思っています。破壊される側ではなく破壊者となった立場で書かれた書籍でもありますので、理論を正しく理解するためにも欠かせない本です。
『イノベーションへの解 実践編』
タイトルの「実践編」の通り、様々な企業事例からより実践的な解決策、ワークシートやFAQなどが書かれている手引書です。
■連載一覧はこちら
#ストーリーで学ぶ経営戦略シリーズ















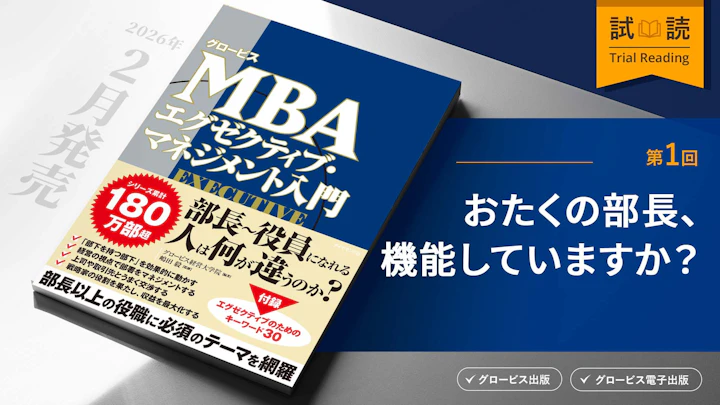
















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
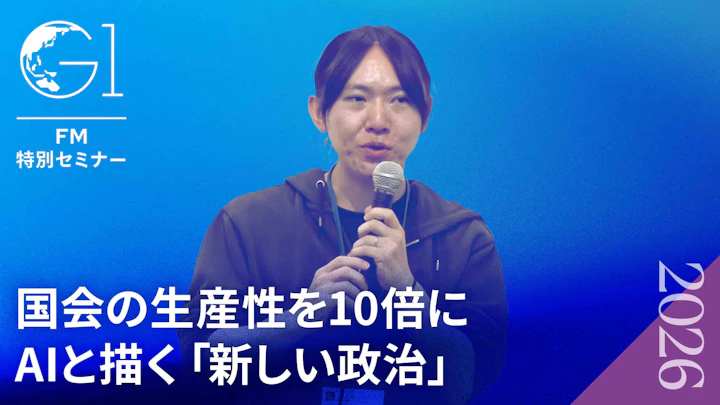


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)



