問題です
以下のAさんの考え方の問題点は何か。
「この投資信託だけど、初年度だった5年前は年15%、4年前は10%、3年前は▲20%、2年前は10%、去年も10%の利回りだったとか。平均すると、(1.15+1.1+0.8+1.1+1.1)÷5=1.05だから、5%の利回りか。5%の利回りなら、10年も預けておくと、1.05^10=1.63となるから、けっこうなリターンだな。この低金利の時代、他に良い投資先もないからこの投資信託にするかな」
(注:このケースでは、税金などは無視するものとします)

解答です
今回の落とし穴は、「算術平均の誤用」です。これは、本来、単純な算術平均(相加平均あるいは単純平均とも言う)を用いてはいけないシーンで算術平均を用いてしまうというものです。なお、今回のケースでは、そもそも、「過去の投資信託などの金融商品のリターンから未来のリターンを予測することはできない」という、投資判断における重要な経験則を無視しているという問題もあるのですが、今回はこの点については議論しないものとします。
さて、ケースの例では、将来のリターンを複利計算で見積もっている点はいいのですが、過去5年間の年平均利回りを求める際に算術平均で5%としてしまった点がミスと言えます。実際の販売の場などでもしばしばこうした説明がされることがあるようですが、ここで算術平均を用いるのは適切ではありません。数字で確認してみましょう。
もし、この投資信託の最初の価格が1だとすると、現在の価格はどうなるでしょうか。計算してみると、
1×1.15×1.1×0.8×1.1×1.1=1.2245
となります。ここでは、過去の年間利回りの平均を求めるためには、
1.2245^(1/5)=1.041
つまり、年平均の利回りは4.1%という計算が必要になります。これはいわゆる複利の考え方であり、この計算方法を幾何平均と言います。複利の金融商品の利回りや、年平均成長率(CAGR:CompoundAverageGrowthRate)では、この幾何平均の考え方を用いることが必須です。どんどん掛け合わせていく率(レート)の平均は、掛け算の平均である幾何平均を用いるということです。
ただし、ここで勘違いしたくないのは、金融商品の平均利回りの計算であっても、多数の商品の単年度のリターンの平均を求めるのであれば、算術平均を用いればいいということです。たとえば、ある投資信託会社A社に商品が6つあって、去年1年間の利回りが、それぞれ20%、30%、40%、▲30%、▲10%、10%であったとすれば、
(1.2+1.3+1.4+0.7+0.9+1.1)÷6=1.1
で、平均利回り10%と考えてかまいません。ここで利回りだからと言って機械的に幾何平均を用いるのは逆に誤りです。幾何平均はあくまで掛け合わせるときの平均と考えてください。
なお、上記A社の例は、顧客から見たラインナップとしての平均値を想定しています。そうした場合にはこうした単純な算術平均で構いませんが、A社として自社の投資信託商品の昨年のパフォーマンスを見る際には、各投資信託の運用額に応じた重みづけをして加重平均で見る必要があります。このへんは、どの立場でどういう目的に用いるかを強く意識する必要があります。
さて、冒頭のケースに戻ると、仮に過去の5年間の年間利回りの算術平均が同じ5%(1.05)と計算される場合、各年の数値のバラつきが大きい方が、真の年平均利回りを計算する幾何平均としては小さな値になります。冒頭のケースを含め、他に3パターン紹介するので(計算過程は省きます)、それと比較してみましょう。
冒頭ケース:1.15、1.1、0.8、1.1、1.1幾何平均1.04
ケースA:1.05、1.05、1.05、1.05、1.05幾何平均1.05
ケースB:1.1、1.3、1.5、0.75、0.6幾何平均0.99
ケースC:1.5、1.8、0.3、1.2、0.45幾何平均0.85
なぜこうなるかの詳細な説明はしませんが、バラつきが大きいということは、経営学的にはリスクが大きいということであり、評価は低くなってしまうのです。ケースCでは、各年のリターンが16ポイント向上したとして、ようやく冒頭ケースや、バラつきの全くないケースAと同じレベルの幾何平均となります。
ケースC‘:1.66、1.96、0.46、1.36、0.61幾何平均1.044
ご興味のある方は、ぜひファイナンスの基礎などを勉強されるといいでしょう。














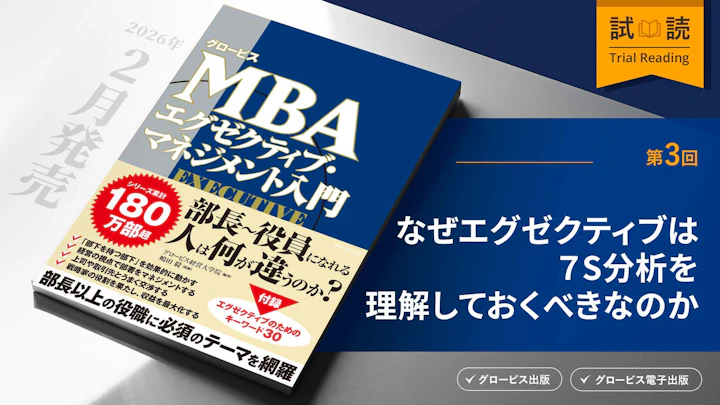

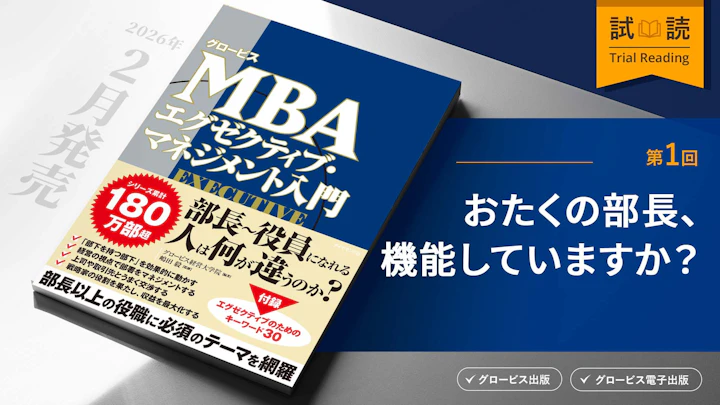


















.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

