
0:59:48
割引情報をチェック!

AI BUSINESS SHIFT 第8回 機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第8回です。 第8回「機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル」では、AIが営業現場にどのような変化をもたらしているのか、営業担当者・営業マネージャー・組織としての役割や戦略が、AIによってどう進化していくのかを、営業プロセスの分解や実際の現場事例を通じて学びます。 ■こんな方におすすめ ・AIを活用した営業活動の最新動向や現場のリアルを知りたい方 ・営業現場の変化に直面している営業マネージャー・現場リーダーの方 ・AI時代における営業戦略や営業マネジメントのあり方を学びたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年2月制作)
会員限定

マネジャーのための仕事の任せ方
「仕事を任せると失敗が怖い」「自分でやった方が早い」マネージャーとしてメンバーやチームの力を引き出しながら成果を上げるには、どのように仕事を任せていけば良いのでしょうか? 変化の激しい時代において、マネージャーとして成果を上げ続けるためには、メンバーの個性や特性を理解し、それに合わせた効果的な任せ方を身につけることが重要です。このコースでは、ソーシャルスタイル理論を活用してメンバーごとに最適なアプローチを学びます。「任せる力」を高めることで、チーム全体の成長を促進し、自身のリーダーシップを発揮できるようになっていきます。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2024年12月制作)
会員限定

AI時代の個人力
AIが仕事や社会の前提を変え続ける今、最も求められるのは「他者に代替されない個としての力」“個人力”です。 本コースでは、澤円氏の著書『個人力』をもとに、AI時代をしなやかに生き抜くための「前向きな自己中戦略」を学びます。 テーマは、「Being(ありたい自分)」を中心に据え、自ら考え(Think)、変化し(Transform)、協働する(Collaborate)ことで、自分らしい価値を発揮していくこと。 リスキリングやAI活用が叫ばれる今こそ、スキルより先に“自分の軸”を問うことが重要です。 あなたは何を大切にし、どんな未来を描きたいのか? このコースは、あなたが“ありたい自分”として生き、キャリアをデザインしていくための思考と行動のガイドになります。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年11月制作)
会員限定
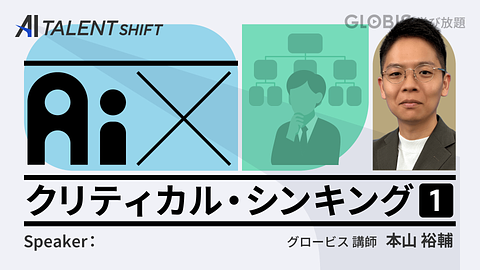
【AI×クリティカル・シンキング】①イシューと枠組みでプロンプトを磨く
生成AIから期待する回答を引き出せず、試行錯誤を重ねていませんか。 本コースでは、生成AI活用の質を高める鍵として、クリティカル・シンキングの視点からイシュー設定と枠組みを押さえる重要性を解説します。 目的に直結する問いの立て方や、プロンプトに落とし込む際の実践ポイントを具体例とともに学ぶことで、AIをより思考のパートナーとして活用できるようになります。 生成AIを業務で使い始めた方から、活用を一段深めたい方まで、再現性あるプロンプト設計を身につけたい方におすすめの内容です。 さらに学びを深めたい方は、こちらも合わせてご覧ください。 【AI×クリティカル・シンキング】②AIの弱点との向き合い方 https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/cdfe41e3/learn/steps/62198 ※本コースは、AI時代のビジネススキルを学ぶ「AIタレントシフト」シリーズの一環として提供しています。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
会員限定

リーダーの挑戦⑤ 藤田晋氏(サイバーエージェント代表取締役)
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第5回目のゲストは、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋氏。起業の理由、経営をどうやって学んだか、アメーバブログ・ABEMAの立ち上げ、経営チームづくりについてなど聞いていきます。(肩書きは2020年12月11日撮影当時のもの) 藤田 晋 サイバーエージェント 代表取締役 堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
会員限定

ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 前編 なぜ眠れないのか?~
「仕事が終わらないから睡眠時間を少し削ろう…」「業務時間中なかなか集中できない…」「毎日朝起きるのがつらい…」。 あなたはこのような経験をしたことはありませんか? 仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削りがちなのが「睡眠」時間。 実は今、日本社会は世界と比較して「最も眠らない国」だということもわかってきています。 慢性的な睡眠不足は、心身の健康に悪影響なだけでなく、仕事のパフォーマンスにも当然大きな影響を与え、社会全体の経済損失につながります。 このコースでは、基本的な睡眠リテラシーを学んだ後の「問題解決編」として、「なぜ多くのビジネスパーソンは眠れないのか?」について解説していきます。 ▼本コースで学べる主な内容 ・そもそも眠れないことは何が問題なのか? ・眠れなくなってしまう原因とは? 睡眠不足の原因は認知機能の問題にありました。 自身の睡眠不足に対し、正しく「気づき・理解し・行動を変える」第一歩を踏み出しましょう。 ▼関連コース ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~リテラシー編~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/24575c03/learn/steps/53129 ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 後編 どうしたら眠れるのか?~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/4ba981e9/learn/steps/62042 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

大阿闍梨 塩沼亮潤が死の手前で見つけた「生き方」
あすか会議2018 第4部分科会B-1「極限の世界で見つけた人生の歩み方」 (2018年7月7日開催/国立京都国際会館) 1300年間で2人目となる大峯千日回峰行満行を果たした塩沼亮潤大阿闍梨。48キロの山道を1日16時間掛けて歩き、それを千日間に亘って続ける過酷な行の中で、どのような悟りを得たのか。そして、9日間、断食・断水・不眠・不臥を続ける四無行満行という極限の世界で何を見つけたのか。塩沼氏が「創造と変革の志士」へ贈る「人生の歩み方」とは。(肩書きは2018年7月7日登壇当時のもの) 塩沼 亮潤 慈眼寺 住職
無料
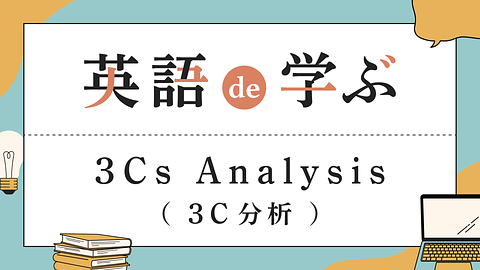
英語 de 学ぶ!3Cs Analysis(3C分析)
このコースでは、グロービス学び放題の英語版である『GLOBIS Unlimited』のコースの中から、ビジネスで役立つ頻出の英語表現をピックアップしています。英語ネイティブの方が実際に見ているコースなので、リアルなビジネス英語の表現を学ぶことができます。 今回のコースは「3Cs Analysis(3C分析)」です。一緒に『英語で』ビジネス知識を学んでいきましょう! ▼今回扱ったUnlimitedコース続きは下記からご覧いただけます 3Cs Analysis https://unlimited.globis.co.jp/en/courses/da5ca962/learn/steps/36362 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
コメント590件
a_7636
抵抗勢力のお話がでて、思い出したコースがあります。
もしこのお悩みがある方は↓こちらをおすすめします。
【耳で復習】学んでみたけど? ~現状維持バイアス~
【思考・コミュニケーション】【思考・コミュニケーション】0:13:52
https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/7578ae55/learn/steps/42526
hrdk
チェンジマネジメントにおいては、反映勢力を説得・エンゲージするだけでなく、勢力の割合を見ながら変革のスピードや段階を見直す必要性もある。自業務においても、①ネガティブな反応を示す層の意見を傾聴してエンゲージするポイントを掴みむ、②反対意見の割り合いを見極め、計画を改める(マイルストーンの達成を遅らせる判断をするなど)勇気を持つことに取り組みたい。
flex
リスクに対する反応度は人それぞれであり、なかなか考えを変えるのは難しい。リスクをとらない傾向の人には、リスクを取らないことでの更なる悪影響を示すのが有効か?(デメリットプレゼン)
回復力を保つために、自身は日頃からの体調管理と余裕を意識的に保つようにすること。対メンバーには傾聴や貢献への感謝を示しながら、、エンゲージメントを上げる働きかけが必要か?
maedakazu
回復力、挫折から立ち直る能力がほぼ持ち合わせていないので、最初から誤解は受けるもの、理解されないものであるとの前提で進めた方が良いと感じた。
shindy1004
変革への反対者分類を踏まえた対策を設定することが重要だと痛感。
ozawa_h
失敗した場合は早く気持ちを切り替えて同じ失敗を繰り返さないようにしながら、新しいことに挑戦し続けるようにします。
f_kawakami
回復力って、失敗してもそれを引きずらず気持ちを切り替えて前向きに進める力ということかな。PMBOKでそんなことをいちいち言うのは少し違和感はある。メンバーに対してメンバーを回復させることに注力するのはわかるが、自分自身の気持ちの問題にまで踏み込んできているのは以外だった。
tuessa
変革を行う理由をいかに理解して頂くように説明できるかがポイントになるように思います。いかにロジックに説明を行ったとしても、抵抗するメンバーは少なからずいると思われます。変化のスピードの調節も含め、取り組んでいきたいと思います。
mikio_3333
回復力が大切なことはわかるが、挫折すると立ち直れないことが多い。どうすれば良いか
user-juser
変革に反対はつきもの。そして、反対する動機を掴むのに根気が必要。プロジェクトマネージャーはそれを理解したうえで、変革に取り組むことで、成功に導けると思います。
yoshinori358
プロジェクトを進めるうえで、リスク見極め、適応と回復、変革の重要性を再認識
zennoh-t-usui
プロジェクトの予防が大切であることを理解した。
atuya
変革は、運用部署には受け入れずらい。それは、運用は何もないことが良いことだからだ。運用にもプラスになるような、ことが必要。例えば、これを導入することで、運用時間が効率化され、時短になるなど。
casetomo
チェンジマネジメントについて学べたのがよかった。
変革のスピードを変えたり、新たな打ち手により、前向きに対処できる方法を検討していこうと思った。
csl_kojima
理解が深まりました。
natsumi2022
変革に適応する能力というのは、常に自分に問い、相手の意見を否定したくなる場合に考え直すことができるのかなと思いました。回復力については、自分が立ち直ることが必要とされる役割であるとのアドバイスで、失敗は当たり前、受け入れて常に変化していこうという前向きな気持ちになりました。ありがとうございます。
stani
リスクと抵抗は注意していかなけばならない。
hikiyomi
変革を進めていく上での抵抗勢力は必ずいるので、まずは王道である「プロジェクトの目的・目標・成果」を理解頂くことからはじめたいと思います。
deco_4270
何事もバランスが大事と学びました。
sakiyam2
リスク選好。リスクと聞くと、片っ端から解消しようとしてしまいがちだが、良い影響を与える場合もあるということが気づきだった
miemie2020
業務の中で失敗してしまうと、気持ち的に引きづるタイプなので、失敗してもくよくよせず、できるだけ素早く回復できるように頑張ります。
karikomi-1011
大変参考になりました。
chang_shin
要は、周りの空気をよく読めということだと理解した。
具体的には、失敗してもクヨクヨせず、めげずに相手とコミュニケーションをとって、相手がどうしてほしいのか、みんなでどういう方向に進むべきなのかに気を配り続けよう、ということ。
kota817
変革を受け入れてもらうために期間を区切って少しずつ変革していきます
nb23
変革への反対・抵抗勢力の存在、変革に受け入れに有効な動機付け、変革を受け入れられるスピードも考慮し、時には変更する事も重要である。
jktaisuje
回復力の内容として同じ過ちを繰り返さないとありますが、なかなか難しいと思います。
混入、流出の原因を分析し、根本原因を払拭せねば間違いは繰り返すものですが、根本原因の分析は自分自身を振り返る事でしか出来ません。
これは非常に時間と根気、集中力の必要な作業であす。正しい分析結果を得るために必要な要素を考え、改善のプロセスとして組み込む必要があるように思います。
carmelbts
変革のところが印象的だった。以前プロジェクトで抵抗勢力の存在に悩まされたが、これはごく普通のことであることを当時知っていればストレスも少なくて済んだと思う。
k_yuna
大変勉強になりました。
noriko_chita
プロジェクトを進めるうえでの大きな壁の一つである「計画変更」「抵抗勢力」等の対応について学ぶことができた.自分の会社だけ変化に理解が無いと落ち込んでしまいがちだったので,普遍的な壁だと思うと気が楽になった.
nerimadaikon-3
対象次第で変革を行うスピードや段階を調節するという方法は、有効と思いました。
kawai_ryouta
講習を受けて、自分には回復力や、反対勢力を説き伏せるチェンジマネジメント能力が足りていないと痛感した。先ずは自身の意識改革が必要だと思うので、努力してみたい。
statuya
変革への抵抗勢力への対応もあるが、定められた納期を守るという期日の問題もある。
進め方の時点で変革への受け入れをしっかり考慮すべきだと改めて感じました。
moveon-s
チェンジマネジメント留意点があることが体系的に理解し、その対応がわかりました。
hbk66
変革は難しいケースが多いです。何なら自分が変革の抵抗勢力になってしまうようなケースもあります
umebryo
プロジェクトの進行にあたってはリスクのコントロールを意識し、適応力と回復力を身につけるように努め、変革を意識しながら進めていきたい。
westin4324
抵抗勢力に対する話し合いで大切なことは丁寧に説明し、理解してもらうことだと理解しました。妥協すると良い結果にならない。
また、回復力がリーダーの資質であると理解しました。リーダーはタフでなければいけない。リスクマネジメントはテクニックとしてもう少し掘り下げる必要があります。
ken_tenjin
特に適応力について、ポイントと考え、柔軟に変更事項に対処できるように心がけたい。
k--g--
プロジェクトマネジメントには先見性と柔軟性が必世であると感じました。
noriaki_08
変化を伴う業務を進める場合に、想定すべき事態、特に、起きるかどうかが確認できない種類の問題に対する対応力その分析、管理を上げるためのアプローチについて知識を得たことは有用であったと思う。また、実際にリスクが具体化する場合の対応について、また、そのために必要となる組織的な変化を進める上で、変革のスピードの調整、反対者に対する具体的な対処等について一定の認識が得られたことは、業務への対応する能力を上げてくれたと思う。有用な内容に感謝するところです。
aya_anne
変革に上手く相手をリードするのは時間が掛かると改めて再認識した
ka110
最初からうまくとは考えない。アンチはどこにでもいる。いろんな想像(先の先、起こりうる問題)をして業務を進めていくということは日々意識して取り組んでいる。
自身にプラスがないと積極的に変化は受け入れられないのは、人の心理であり自分にも思い当たるところがある。
いかにスムーズにマインドをチェンジさせるかイコール、メリットを訴求できるかだと思う。
tdi-ihara
リスクはどんなプロジェクトでも発生するものでいかに早く具現化し対策をとるかを考えています、また回復力、まさに仕様をお客様が変化させるとき、チーム内の雰囲気が変わり悩みがおおきくなるのですが、確かに気持ちを早く切り替えて小さくてもいいのでチームへの理解してもらうことができるよう取り組んでいます
korekara
変革のスピードをコントロールすることも手段のひとつであるとわかったのでよく観察したい。
yuri-se
理解が深まりました。
okamoto777
適応力と回復力、回復力については、クヨクヨと気にしない性格の部分も大きいかと思いますが、同じ失敗を発生させない為に行動できる適応力も併せ持っていないといけないので、その様な人材を探すなり育成するなりしないといけないと感じています。
bobby2490
現在も比較的大規模なプロジェクトに従事しており、あるあるな例ばかりで共感できます。
その上で具体的にどのような対処・対応方法が良いのか知りたい。
yayo0324
常に変革に対応できるよう取り組むことが大切です
dw000
変革を受け入れない勢力は一定数おり、むしろ変革が必要だと思っていながら、自分が避難されることを恐れて長いものに巻かれる文化がある、もしくは何か買えた方がよさそうだが、具体的にはよくわからない、という漠然とした不安をもっている層が大半だと感じる。
その勢力を一部の熱い人たち(数人)で変えようとするのは相当な戦略と目的、手順とスケジュールなどの綿密な計画が必要だと感じる
hr-sakai
原理・原則、リスク、もう一度深く考えて学習いたします。
toshi486
チェンジマネジメント上の留意事項の項目と理解した。抵抗勢力の存在とその対処法は理解できた。
00004519
「面倒くさい」が一番の抵抗勢力。
matsuyuki1210
リスク選好でスタークホルダーに応じた対応。メンバー変革は無理に急いで進めると危険。
ore-ore
抵抗勢力の説得は非常に面倒くさいが、説得と調整をしっかりやってかなければいけないと思いました。
yuya_yamada0618
各々の知識や価値観が違う中で、変革のスピード調整は変革を完遂するうえで重要と感じた。
まずは、価値観のベクトルを合わせていきたい。
ryuji_kawano
調整やらリーダーシップやら、プロマネは大変だなと感じた
koki_dayo
変革を行うことの難しさを学びました。人間は変化を嫌う生き物なのでスピードの大事だが、段階的にしていくことも大切だと思った。
kousei_yano
変革に対して反対する人はどこでも一定数はいると思うので、変革によるメリットをしっかり伝えることが重要だと感じた。
kata8909636
常に現状に満足せず、リスクに目配りすること、顧客満足やプロダクトの品質向上、チーム力の向上を目指し変革をする目線が必要だとわかった。
sugitaka-jp
抵抗勢力になるのは、かならずなにがしかの理由がある。そこをちゃんと認識することが大事
mochi_uj
リスクについては、どの程度までリスクを許容することができるか(選好)、低減することができるかの検討が必要。変革に対し反対勢力がある場合は、反対する理由を理解し、目標を具体的に伝えることが大切。まずは、行動しようと思う動機づけが必要となる。
omita_unounoki
チェンジマネジメント、変格への抵抗勢力への対処について学べた。
mokkun52
変革を恐れず、果敢にトライしたい。
hamada--
多くの人は、自分にとって大きなメリットがない場合や非常に困っていることがない限り、変化を受けるれられないケースが多く、一定数の抵抗勢力は必ず存在する。意識や行動を変化させることが目的のチェンジマネジメントは、体系的に繰り返し取り組む必要があり、反対の理由を理解した上で、エンゲージメントを行う必要がある。
kkkkssss
チェンジマネジメントにおいて、変革に対するメンバーの受容度に十分注意しながら進めるべきというところは、現実的な問題として非常に重要な要素だと感じました。
vegitaberu
プロジェクトにおいては、予定通りに進むことの方が例外なので、予定通りにいかないときに、その原因や状況を丁寧に把握し、それに合った対応をその都度考え、打っていくことが重要と感じます。
koichirou_k
変革に何となく反対する人に対する対処方法を学んだ。実務に活用したい。
norikoko
変革が避けられない状況下で抵抗する人に悩んでいたので参考になった。明確な理由をもっているのか、変革自体を敬遠しているのかで対応が違うのはもっともだと思う。
norihito
基本的には変化に対してネガティブな反応があるものだと改めて認識できた。
ryusho1118
日々様々なプロジェクトに参加しており、プロジェクトが途中で頓挫しそうなケースも何度かあった。今後はここで学習した適応力と回復力を使って、プロジェクトの立て直し時に役立てたい。
ta-mo-
リスク、適応力、回復力は、どれもプロジェクトを進める上でつきものである。如何に常に状況を認識し、未然に申し出来るかであるが、なかなかが難しいのが実情である。記載されている内容は理解はします。
yoshiki2355
失敗してもすぐに立ち直るレジリエンスを身に付けたい
senna4521
今後のプロジェクトの参加可能性も踏まえて、後続のコンテンツを視聴する
knjtkhr
リスクは好機にもなりえるので、リスクの特性を認識したうえで選択・対応する必要がある。
変化を促す取り組みは、ボトムアップに行うことは大変困難に感じるので、同じ思想を持った上層部を捕まえてトップダウンアプローチで攻めることも重要に感じる
azukawa
抵抗勢力への説得、取り込みを行い、同じ方向性を向けるように進めたい。
ibe_takeshi
今回の講義の中でプロジェクトをマネージメントしていくためにメンバーの適応力と回復力を考え適切な振り分けをする必要性を改めて感じた
これらの作業振り分けもリスク選好のひとつであると思った
t-isaka1983
反対の理由を理解したうえで、解決、動機づけというのは確かに大事だと思いました。
yasaka12
変革を受け入れるには、目に見えるメリットが示されている、もしくはまさに困っている、という状況でないとなかなか難しい。
したがって、ある程度トップダウンで実施することも場合によっては大事となると思う。
luckyjene
リスクはいつも付きまとい発生しうる可能性があるものについては、事前にどのように手を打つかを想定して取り組んでいます。今後も継続して取り組んでいく課題と認識しています
gobau
プロジェクトを行うこと自体が変革への取り組み姿勢を示すことになる。プロジェクトメンバー外のステークホルダーは自分にどんな影響があるかわからないため、反対勢力になり得る。プロジェクトの透明化、開示できる情報提供を丁寧に行う必要性を感じた。
sugi_asa
プロジェクトを成功させるために、スキルアップを図りたいと思います。
takeuch-i
プロジェクトが計画通りに進まない時ついペースをあげることを考えてしまうが、結論を急ぎすぎずチームメンバーやステークホルダーとも丁寧なコミュニケーションを取りながら、その状況に応じて柔軟に進めることが大切だと感じました。
noritsuu
変革をするためにはメリットデメリットを明確にして説明をして納得しもらう必要がある。
taku_asa
現在プロジェクト運営を行っており、チーム員の誤解や反対の意志が強く厳しい戦いとなっている
tom-_-
適応力や回復力についての能力伸長を図っていきたい。
yuchin_i
変革には抵抗勢力がつきもので、相手の状況を分析しつつ、丁寧に打ち手を準備することが重要だと理解しました。
___l
変革スピードが急ぎすぎると、強い反対勢力が増えることもある
→スピードの見直し、打ち手を変える、等対応を工夫する必要がある場面もある、ということ
250871
プロジェクトは正に変革するために行うものも多々あると思うが、反対・抵抗勢力を如何に乗せるか、は大きなポイントと感じる。
プロジェクトに限らず、当方の事例で言うと、製造現場の改善を行う際に現場の方に如何に協力してもらうか?というのは同じ状況と感じた。
知らず知らずのうちに、プロジェクトと同様の取り組みをしていたことに気づいた。
これまでの経験も踏まえ、より早くリスクをキャッチし、ステークホルダーを乗せる、そしてどんどん巻き込んで皆で変革を進めていきたい。
shizukumari
反対勢力であったり、自分の力を誇示したいばかりに、理解するための質問を行ったりする人が日常業務でいます。そういう抵抗勢力に対してどう対処するのか?うまく質問に答えて意味のある議論を始められるように持っていくのか、改めて、ファシリテーションの難しさを感じました。
samurai0421
現状維持=停滞である を肝に銘じて変革をする際もメンバーとのコミュニケーションを通して理解を促して進めていきたいと思います
daiyuta
どのプロジェクトでもリスクはつきものですがタイミングを見定めて検討していくところは今後気を付けてハンドリングしたい。変革、適応力や回復力はPMにとって重要なので、引く続き継続していきたい。
toshi-iwai
変革に対する反対勢力、しぶしぶついてきているが他律的な考えのひとがいるなかで理解度に合わせた動きを調整する必要もあるのですね。
sho1111
反対勢力への対応方法が勉強になった。
hs_1031
チェンジマネジメントは繰り返し行う必要があるというのは納得できる。変革の動機づけにおいては、理由があり反対する人と、変革自体を抵抗する人で手法が異なることを理解した。いずれも、変化を強制することなく、目的や成果、必要性を丁寧に説明することが大切ということで、ぜひ実践したい。またスピード感も大切であることを理解した。人それぞれ受け止められるスピード感は異なるので、組織でどのようなスピード感を設定するべきか考えたい。
mshiraishi
リスク選好については、ステークホルダー全体に合意を得るのは非常に負荷のかかる仕事となるのではないかと考えた。
yyyddd
理解が深まりました。
yuji_fujii
変革ほどの変化でなくても反対・抵抗されることはある、諦めたり切り捨てたりせず、時間をかけ相手に合った対処法を実践するようにしたい。
ponpon__
人によって達成、人の原動力、気持ちを理解することが原理原則にあるということは心強く思った
そこに注視しながらマネジメントしていきたい
4294967295
リスクにはプラスとマイナスの要素があり、それぞれに応じた対応が必要になる。また、プロジェクトマネージャーは失敗から早期に立ち直り、再発防止する能力が求められる。
jerome
日頃の業務においても、価格改定や条件改定などチェンジマネジメントに触れる機会は多々あり、変革への反対・抵抗勢力は普通に存在する中、変革の受け入れに有効な動機づけ、そして変革を受け入れて頂ける時間軸は強く認識したいと思います。
kenta7070
「大きなメリットがある、非常に困っているということが無い限り、変革を積極的に受け入れるケースは少ない」というのは非常に腑に落ちる内容だった。
また、「変革を急ぐと強い反対勢力が生まれる可能性がある」という点も意識して進める必要がある一方で、プロジェクトの期限など、他の要素とのバランスをどのように取っていくかも考える必要があるため、改めてマネジメントの難しさを感じた。