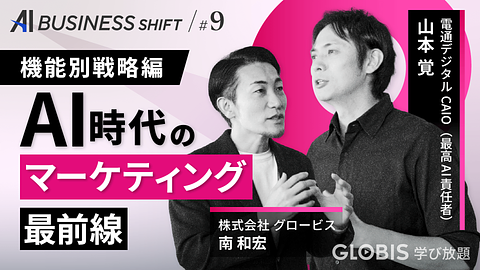
02月28日(土)まで無料
1:05:27
割引情報をチェック!
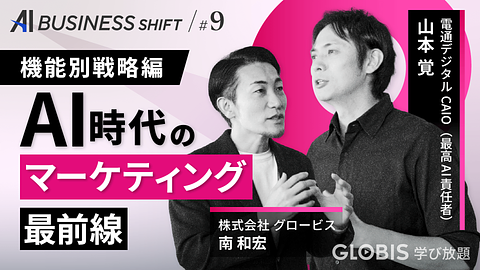
AI BUSINESS SHIFT 第9回 機能別戦略編:AI時代のマーケティング最前線
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第9回です。 第9回「機能別戦略編:AI時代のマーケティング最前線」では、マーケティング担当者が日々の業務の中でAIをどのように活用しているのか、AIの普及によってマーケティングマネージャーの役割や育成・評価の考え方がどう変わるのか、さらに、AI活用を前提としたマーケティング戦略の再設計について掘り下げていきます。 ■こんな方におすすめ ・AIがマーケティング活動に与える影響を知りたい方 ・マーケティング組織を率いるリーダー・マネージャーの方 ・AI時代におけるマーケティング戦略や人材育成のあり方を学びたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年2月制作)
02月28日(土)まで無料

マネジャーのための仕事の任せ方
「仕事を任せると失敗が怖い」「自分でやった方が早い」マネージャーとしてメンバーやチームの力を引き出しながら成果を上げるには、どのように仕事を任せていけば良いのでしょうか? 変化の激しい時代において、マネージャーとして成果を上げ続けるためには、メンバーの個性や特性を理解し、それに合わせた効果的な任せ方を身につけることが重要です。このコースでは、ソーシャルスタイル理論を活用してメンバーごとに最適なアプローチを学びます。「任せる力」を高めることで、チーム全体の成長を促進し、自身のリーダーシップを発揮できるようになっていきます。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2024年12月制作)
会員限定

AI時代の個人力
AIが仕事や社会の前提を変え続ける今、最も求められるのは「他者に代替されない個としての力」“個人力”です。 本コースでは、澤円氏の著書『個人力』をもとに、AI時代をしなやかに生き抜くための「前向きな自己中戦略」を学びます。 テーマは、「Being(ありたい自分)」を中心に据え、自ら考え(Think)、変化し(Transform)、協働する(Collaborate)ことで、自分らしい価値を発揮していくこと。 リスキリングやAI活用が叫ばれる今こそ、スキルより先に“自分の軸”を問うことが重要です。 あなたは何を大切にし、どんな未来を描きたいのか? このコースは、あなたが“ありたい自分”として生き、キャリアをデザインしていくための思考と行動のガイドになります。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年11月制作)
会員限定
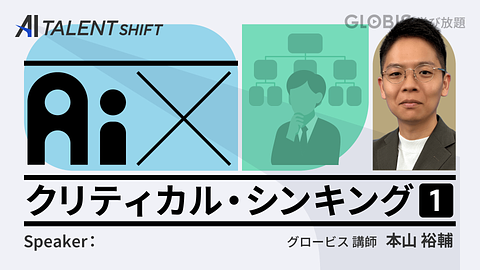
【AI×クリティカル・シンキング】①イシューと枠組みでプロンプトを磨く
生成AIから期待する回答を引き出せず、試行錯誤を重ねていませんか。 本コースでは、生成AI活用の質を高める鍵として、クリティカル・シンキングの視点からイシュー設定と枠組みを押さえる重要性を解説します。 目的に直結する問いの立て方や、プロンプトに落とし込む際の実践ポイントを具体例とともに学ぶことで、AIをより思考のパートナーとして活用できるようになります。 生成AIを業務で使い始めた方から、活用を一段深めたい方まで、再現性あるプロンプト設計を身につけたい方におすすめの内容です。 さらに学びを深めたい方は、こちらも合わせてご覧ください。 【AI×クリティカル・シンキング】②AIの弱点との向き合い方 https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/cdfe41e3/learn/steps/62198 ※本コースは、AI時代のビジネススキルを学ぶ「AIタレントシフト」シリーズの一環として提供しています。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
会員限定

リーダーの挑戦⑤ 藤田晋氏(サイバーエージェント代表取締役)
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第5回目のゲストは、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋氏。起業の理由、経営をどうやって学んだか、アメーバブログ・ABEMAの立ち上げ、経営チームづくりについてなど聞いていきます。(肩書きは2020年12月11日撮影当時のもの) 藤田 晋 サイバーエージェント 代表取締役 堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
会員限定

ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 前編 なぜ眠れないのか?~
「仕事が終わらないから睡眠時間を少し削ろう…」「業務時間中なかなか集中できない…」「毎日朝起きるのがつらい…」。 あなたはこのような経験をしたことはありませんか? 仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削りがちなのが「睡眠」時間。 実は今、日本社会は世界と比較して「最も眠らない国」だということもわかってきています。 慢性的な睡眠不足は、心身の健康に悪影響なだけでなく、仕事のパフォーマンスにも当然大きな影響を与え、社会全体の経済損失につながります。 このコースでは、基本的な睡眠リテラシーを学んだ後の「問題解決編」として、「なぜ多くのビジネスパーソンは眠れないのか?」について解説していきます。 ▼本コースで学べる主な内容 ・そもそも眠れないことは何が問題なのか? ・眠れなくなってしまう原因とは? 睡眠不足の原因は認知機能の問題にありました。 自身の睡眠不足に対し、正しく「気づき・理解し・行動を変える」第一歩を踏み出しましょう。 ▼関連コース ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~リテラシー編~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/24575c03/learn/steps/53129 ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 後編 どうしたら眠れるのか?~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/4ba981e9/learn/steps/62042 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

大阿闍梨 塩沼亮潤が死の手前で見つけた「生き方」
あすか会議2018 第4部分科会B-1「極限の世界で見つけた人生の歩み方」 (2018年7月7日開催/国立京都国際会館) 1300年間で2人目となる大峯千日回峰行満行を果たした塩沼亮潤大阿闍梨。48キロの山道を1日16時間掛けて歩き、それを千日間に亘って続ける過酷な行の中で、どのような悟りを得たのか。そして、9日間、断食・断水・不眠・不臥を続ける四無行満行という極限の世界で何を見つけたのか。塩沼氏が「創造と変革の志士」へ贈る「人生の歩み方」とは。(肩書きは2018年7月7日登壇当時のもの) 塩沼 亮潤 慈眼寺 住職
無料
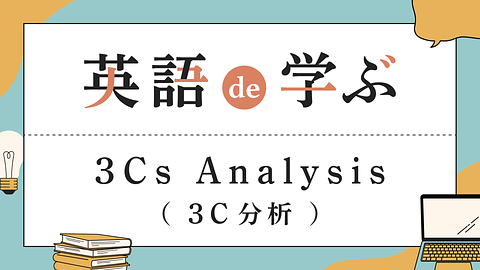
英語 de 学ぶ!3Cs Analysis(3C分析)
このコースでは、グロービス学び放題の英語版である『GLOBIS Unlimited』のコースの中から、ビジネスで役立つ頻出の英語表現をピックアップしています。英語ネイティブの方が実際に見ているコースなので、リアルなビジネス英語の表現を学ぶことができます。 今回のコースは「3Cs Analysis(3C分析)」です。一緒に『英語で』ビジネス知識を学んでいきましょう! ▼今回扱ったUnlimitedコース続きは下記からご覧いただけます 3Cs Analysis https://unlimited.globis.co.jp/en/courses/da5ca962/learn/steps/36362 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
コメント4653件
morritter
自己資本比率: 自己資本/負債+純資産 = 高い=安定(自分たちでなんとかできる)
固定比率: 固定資産/純資産 = 高い=不安定(CASH化できない)
流動比率: 流動資産/流動負債 = 高い=安定(CASH化できる)
当座比率: 当座資産/流動負債 = 高い=安定(CASH化できる)
リマインドも含め復習。勉強になります!
nptu_taro
非常に難しい。
1回聞いただけではわからない。
test_
安全性分析という名前にも関わらず、企業の安全性を必ずしも示したものではないというのは非常におもしろいと感じた。某タクシー会社のように事業は赤字なのにも関わらず、株価が高値を維持していたり、顧客データなど帳簿上には表れない資産を多く保有する会社が高値で買収されたり、会社の力、評価の指標が多様化しており、今後ますます会社の分析が難しくなっていくのではないでしょうか。
aspen_2019
数字から企業の財務体質が見えるが、その数字の意味は必ずしも一意ではない。多面的な視点から判断することが肝要。難しい。
kami5
安全性分析は新規の取引先の安全性を見るだけでなく、既存の取引先も定期的に観測することで安全な取引が期待できると思った。
mokumintosan
調達部門が取引業者の支払い能力の評価をしたり、
自社の借入金利の決定に安全性分析が活用されていることを理解した。
naka7494
固定比率が高いと不安定
流動比率が高いと安定
当座比率が高いと安定
uchida1969
各指標により財務諸表から支払い能力、安全性を見ることが出来ることを理解できた。この学びでは基準値は説明が無いが、多面的に見ることで一定の判断ができることが理解できた。同業他社の比較も有効だが最終結論付けは別。会社評価として借り入れ金利など評価につながっていることも理解できた。
joestar
安全性分析:企業の支払い能力より、その企業の倒産リスクを把握するための分析。
しかし、「倒産」の説明がない!
支払いができなくなった状態のことかな?
shark1209
自分が企業を評価する立場になることがないのでビジネスで利用する機会は少ないと思うが、株を買う時の参考にしてみようとおもった。
naono1025
企業の倒産リスクを把握するための分析として安全性分析がある。
指標は3つあり、
一つ目は「自己資本比率」総資産(負債+純資産)に占める「返済が不要な資金」の比率。
二つ目は、「固定比率」固定資産に対する資金調達がどの程度「返済が不要な資金」でまかなわれているか。
三つ目は、「流動比率」流動負債に対して流動資産をどのくらい持っているか。
ただ重要なのはこの数値だけでなく含み資産を保有している場合もあるので多面的に「講義の支払い能力」を見ることである。
sano365
取引先の安全性は大切なことだと思います。大きな取引が出来ても相手が倒産しては意味が無いと思います
y2001210m
むずかしい・・・
sako0830
安全性分析は新規取引先の判断材料として使う事が出来る事が判った。
kameco
私の業務では必要ではありませんが、企業にとってはとても大切だということが分かりました。むずかしかったです。
hoshi_pi
安全性分析とは、企業の経営の安定性を決算書の内容から分析する手法=資金繰りが安定しているか
企業は収益が出ていても、資金繰りが回らなくなると倒産リスクがある。
財務内容が悪化すると資金調達力が低下して資金繰りが悪化する。
代表的な指標は2つ
1. 自己資本比率
自社が持ってるお金
負債によって資本調達してる会社はこれが低くなる
2. 流動比率
1年以内に受け取るお金や出ていくお金が高いものをいう。100%以上が良いとされている
tsukao
取引先の安全性を確認する手法として覚えておきたい。
tonchi555
会社間の安全性分析により、
不安のない会社間取引が必要と再認識しました。
stknj0413
計算式だけでなく貸借対照表の左右をイメージすると覚えやすい
kobayat
実際に株式投資しながら学びを深めるのもいいのかもしれません。
daisuke1983
自己資本比率…総資産における自己資本の割合
固定比率…固定資産に対する資金調達がどの程度返済不要な資産で賄えているか
流動比率…1年以内に返済する負債と、資本との割合
含み資産…不動産や有価証券など取得時の価格から変動していることも多い
p-bone
急成長しているベンチャー企業などは安全性の指標が低い場合も多いはずなので、その点をどう見極めるかが難しいところだと思います。
jiza
あまり実務で自分て計算することはないが経理上の考えとして学ぶことができた。
tana-61
安全性分析で比較する事で、一般的に判断材料となる
oguogu
自己資本比率が高い方がよいと思っていたが、確かに成長企業は借入金による投資を多く行っている可能性は高いと思った。
zumisan
取り引きする企業の安全性は、まず貸借対照表の各数値から大まかに判断されている事を知った。
igaas23
銀行はお金を貸すにはきちんと返してもらわないといけないので、支払い能力があるのか、今後も安定しているのかを判断して金利を変えるということをしながら企業にお金を貸していることが良く分かった。
個人のクレジットカード審査や住宅ローンと似たようなところがある。
wkiymbk
企業の支払い能力より、その企業の倒産リスクを把握するための分析であることを学びました。
ここで得た学びは、会計・財務システムの保守業務、顧客担当者とのコミュニケーションに活用します。
saku545
業種によっては、安全性分析の値が、低であっても
必ずしも、悪いというわけではない点は、
留意しておきたい。
その業種特有の事情を勘案して多面的にみる
必要がある。
djmpajmpkm
投資によって得られる価値や現在のSNS上の価値は換算が難しいので、必ずしも安全性だけで判断しては行けない
egl
難しい
saito-yoshitaka
取引先の状況を把握する事も重要となる事を学びました。
as95
取引のある顧客に対し、その取引額に応じ、不良債権を未然に防止すべく、安全性分析を正しく理解し、活用する必要があり、その点において、大いに参考になった。
uno-t
自己資本比率=自己資本/総資本
固定比率=固定資産/純資産
流動比率=流動資産/流動負債
当座比率=当座資産/流動負債
inada-makoto
自己資本比率…総資産における自己資本の割合
固定比率…固定資産に対する資金調達がどの程度返済不要な資産で賄えているか
流動比率…1年以内に返済する負債と、資本との割合
含み資産…不動産や有価証券など取得時の価格から変動していることも多い
haradayud
固定比率:純資産(自己資本)に対する固定資産の割合
低い方が安全性が高い、100%以下が望ましい
※借金して設備投資するならば、返済計画重要
流動比率:流動負債に対する流動資産
高い方が安全性が高い、120%以上が望ましい
※借金返すための換金制の高い資産を持っておくこと
ads-tnk
難しいの一言。説明を聞いて分かったような気になるが、確認テストになるとよくわからなくなる。
それぞれの数値の関係性を正しく理解しないといけない。
取引先を評価している部門はこういう事も確認してるのか。
oriental-beach
取引先が倒産するかどうかの指標として、安全性分析をすることは有益である。但し企業の特徴を理解し、分析結果を評価する必要がある。特に大規模プラント施工に関わる企業としては、固定資産などが大きい場合があるため、収益が安定しているなどのデータもその内容に含んで検討する必要がある。
saito----
含み資産や技術優位性など、決算書に現れないナマの事業実態を多面的に捉える必要がある。
takahiro_1218
安全性分析について初めて体系的に学べて勉強になった。
kyo1227
急成長しているベンチャー企業などは安全性の指標が低い場合も多いはずなので、その点をどう見極めるかが難しいところだと思います。
satomi-0711
様々な取引先との関わりがある中で、負債の状況も把握しておく必要があると感じた。
船会社について分析してみたい。
irisa
取引先企業の経営状態を把握し、今後の取引を増やすべきか減らすべきか判断するのに活用できる。
tomachopu
難しい内容に感じました。
s_2020
安全性分析
貸借対照表 B/S 使用
負債:買掛金、銀行借り入れ、社債
期日までに返済が必要
純資産:自己資本、株式
返済が不要
自己資本比率
総資産に占める自己資本がどれくらいか
自己資本比率が低い=返済が必要な資金の割合が高い=安全性が低い
固定比率
固定資産に対する純資産(返済不要)がどれくらいか
固定比率が高い=純資産の割合が低い=資金調達が安定していない
流動比率
流動負債に対する流動資産
流動比率が低い=短期資金繰りが不安定
seizouman
営業時にやはり危ない得意先があり、上司に言われたことは、目先の状態にとらわれずに広い視野で観察して本来の在り様を凝視してしっかり判断して報告してほしいと言われました。支払い能力、含み資産、お店の回転率、仕入先の支払い状況などいろんな目線で判断するようにしています。
kohei-kobayashi
自己資本比率が高いほど安全性が高く、固定比率が低いほど資金調達が安定している。また、流動比率が高いほど資金繰りが上手くいっている。経営を進める上で、倒産リスクはしっかりと分析するべきである。
chiba-kenji
安全性分析は貸借対照表があれば分析できるため、気になる企業があれば試しにやってみたい。
shu-g
我が社の状態は安全性が低いと言わざるを得ないと思う。しかし常に好ましくないわけではない通り、倒産には至っていない。しかしながら、確固とした優位性もなく,成長しているわけでもない。我々には見えない何かが、取引先としてはうま味としてあるのだろう。一体それは何か、考えてみたい。
koichi72
資産に対する各種の比率の意味をもっとよく理解しようと思います
kaijyou
安全性分析は新規の取引先の安全性を見るだけでなく、既存の取引にも定期的に活用し安全な取引を担保できると思った。
t_n9999
自己資本比率=自己資本/総資本
固定比率=固定資産/純資産
流動比率=流動資産/流動負債
当座比率=当座資産/流動負債
fstlan0ps
様々な安定指標の意味合いがわかるがいざ聞かれるとどっちが分母化わからなくなる気がする。。。
yoshimi_ohno
『安全性が高い=好ましい』とは限らないのが、興味深かった。企業の分析をするためには、多面的に分析する必要があると感じた。
hide2tak
自社のケースで確認してみたい。
whamu
財務三表だけではわからないこともある。株の含み益や含み損、投資による成長性など多面的に分析することが重要。
koya-shin
非常に難しかったのでもう少し勉強します。
caho
新しい会社と付き合ううえで、その会社の倒産リスクを推し量ることは重要である。そのうえで、指標となるのが固定比率である、固定比率は貸借対照表の固定資産を自己資本で割ることで得られる。割合が少なければ少ないほど、自己資本をあまり使うことなく固定資産を取得できていることになり、自己資本が留保されていることになり、倒産リスクは低いことになる。
また、流動比率ももう一つの指標であり、これは流動資産に対する流動負債の割合をみることになる。これは1年以内に換金できる流動資産が多ければ多いほど割合が高くなり、倒産リスクが減ると考えられる。貸借対照表を深く読むことで、ここまで考えられることに数字の深さを感じた。
一方で、含み資産という考え方もあり、株式等は購入時点での評価が貸借対照表では用いられている、必ずしも貸借対照表がリスク判断の全てでないことも理解した。
mari-0310
新規取引先として安全な先か検討できる。また、現在取引をしている先が倒産のリスクが高まっていることを倒産する前に察知できる。
n-kume
取引先に対しても分析をすることでリスクを見る
手法として自己資本比率などあり。
kkc2119
ありがとうございました
shho
中々に難しい。
ただこのような観点で企業をみる事も重要であることが分かった。
takahashimogura
とても勉強になったと思う
gtop
業務上、経営危機に瀕している企業が取引候補先として浮上したことがあり、GLIOBISのレクチャーを思い出して独自に財務分析した。やはり実勢を通して身に付けることが肝要と感じた。
ugayakohei
流動比率は高いほど経営は安定しており、固定比率は低いほど安定している。
inoue_keisuke
これまで全く知らない内容だったので、取引先の信頼性を計る際には非常に有用な知識だと思った。
sakairi140
安全性分析は新規の取引先の安全性を見るだけでなく、既存の取引先も定期的に観測することで安全な取引が期待できると思いました
fuminori-iwsk
企業の倒産リスクを簡潔に把握する手法を学んだ。
一方で、BSだけでは支払い能力を把握できないこと(例:含み利益など)があるのでBS上の数字だけで判断するのは
適切ではないことも改めて理解できた。
tetsujinn
自己資本比率、固定比率、流動比率といった分析を多面的に分析することで、安全性が見えてくる。1つの比率だけで評価してはいけない。
j__m
固定比率は低い場合が安全で流動比率は高い場合が安全ということになるところが間違えやすいと思ったので注意しようと思いました。
smsmsmsmsm
業務において取引先の自己資本比率等をきちんと見直すことにした。
kks221521
難しい。時間を空けてもう一度復習。
masatouchikoshi
多面的に企業評価をするためにBS,PLだけでなく、安全分析の各指標も確認することが重要である
imato
取引先でも購入先と販売先では異なる尺度で財務体質を判断した方が良いと思った。
takayuki_sano
新しく取引を行う際の指標として活用できることを学びました。また、固定資産となる土地などの評価が変動するので、一概に安定や不安定とも判断できないことも勉強になりました。
hiroyuki_hanada
買収する際には、時価評価に着目して活用したい。自社評価の際には、無形固定資産など、数値に現れずらい企業価値の算出努力を図りたい。
kumakuma24
サプライヤーや協業先を検討する際に、参考に財務諸表を用いて特徴を見てみようと思う。
固定比率が高いと不安定
流動比率が高いと安定
当座比率が高いと安定
mofmof_gesshi
何回か復習して覚えていきたい
mitsu-ishihara
自己資本比率や固定資産比率など企業の安全性を図る指標は、実際に活用する場面が無いが、企業取引や自社の経営状況を判断するための重要な指標だと感じています。
yhayashibara
財務体質の健全性をはかるために下記の指標がある。
①自己資本比率(高いほうが安定)、
②固定比率(返済不要な純資産に対する固定資産の割合)、
③流動比率(流動負債と流動資産の比率)
④当座比率(現金や売掛金などの当座資産と流動資産の比率)
貸借対照表の数値だけでなく、多面的に支払い能力をみるべき 例→含み資産
安全性が高ければよいというわけではない 例→既存体制に固執している場合がある
取引先の安定性で話を聞くので確認していきたいと思った。
morita5
安全性分析が理解できました。
kentaro_terui
改善にかつようするのが大事です
kanjishin
他者と取引する上で安全税を分析することは重要
k_shiro
安全分析を行うことで、リスク回避が出来る。
marin26
比率が絡んでくるとなかなか頭に入ってきません。
もう一度復習したいと思います。
ru_na
企業分析をするうえで、安全性分析を用いて行うことが一つの手段として有益だと思った。
hiroyuki_sano
覚えることが多すぎる。ポイントがなんなのかよくわからない。
shun-kobayashi
企業の支払能力・借入すべき金額が分かることは経営において大いに役に立つと思います。
daiki1215
資産の比率を確認することで企業体力が確認できる
tsuruta-haru
財務の安全性分析が理解できた。
tamura0808
固定比率が難しかったので、理解できるまで復習し、業務上で活用できるようにしたいと思います。
kagosh
日頃の業務で取引先の安全性を確認する必要がある為、参考となる内容であった。貸借対照表だけで安全分析をする事は不十分であるとの言葉を参考年、様々な側面から取引先の安全性を確認して行きたい。
takanaka-mi
安全性分析を理解することで企業健全性を見極める指標となることが理解できた。
yasuhikoseiki
安全性は重視しなければならない。倒産してしまえば売掛金を回収できない
naoki_f1991
安全性指標について改めて確認でき、勉強になった。
glomin
多面的に分析は必要であることを踏まえつつも、
株を購入するときの企業のひとつの見方としても役立つと思った
masami_ken
自己資本比率:自己資本/負債+純資産
流動比率:流動資産/流動負債
当座比率:当座資産/流動負債
固定比率:固定資産/純資産
固定比率は含み益は反映されていないことも注意
takuzoon
負債の比率や含み資産まで考慮するのは難しかった
komi2023
多面的分析をしないと、本当の企業の姿や課題を判断するのは難しいということ。
85201
企業の安全性と一口に言っても奥が深く、財務の勉強をはじめた自分が小手先の知識だけで判断する方が危険だと感じました…