
0:59:48
割引情報をチェック!

AI BUSINESS SHIFT 第8回 機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第8回です。 第8回「機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル」では、AIが営業現場にどのような変化をもたらしているのか、営業担当者・営業マネージャー・組織としての役割や戦略が、AIによってどう進化していくのかを、営業プロセスの分解や実際の現場事例を通じて学びます。 ■こんな方におすすめ ・AIを活用した営業活動の最新動向や現場のリアルを知りたい方 ・営業現場の変化に直面している営業マネージャー・現場リーダーの方 ・AI時代における営業戦略や営業マネジメントのあり方を学びたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年2月制作)
会員限定

マネジャーのための仕事の任せ方
「仕事を任せると失敗が怖い」「自分でやった方が早い」マネージャーとしてメンバーやチームの力を引き出しながら成果を上げるには、どのように仕事を任せていけば良いのでしょうか? 変化の激しい時代において、マネージャーとして成果を上げ続けるためには、メンバーの個性や特性を理解し、それに合わせた効果的な任せ方を身につけることが重要です。このコースでは、ソーシャルスタイル理論を活用してメンバーごとに最適なアプローチを学びます。「任せる力」を高めることで、チーム全体の成長を促進し、自身のリーダーシップを発揮できるようになっていきます。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2024年12月制作)
会員限定

AI時代の個人力
AIが仕事や社会の前提を変え続ける今、最も求められるのは「他者に代替されない個としての力」“個人力”です。 本コースでは、澤円氏の著書『個人力』をもとに、AI時代をしなやかに生き抜くための「前向きな自己中戦略」を学びます。 テーマは、「Being(ありたい自分)」を中心に据え、自ら考え(Think)、変化し(Transform)、協働する(Collaborate)ことで、自分らしい価値を発揮していくこと。 リスキリングやAI活用が叫ばれる今こそ、スキルより先に“自分の軸”を問うことが重要です。 あなたは何を大切にし、どんな未来を描きたいのか? このコースは、あなたが“ありたい自分”として生き、キャリアをデザインしていくための思考と行動のガイドになります。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年11月制作)
会員限定
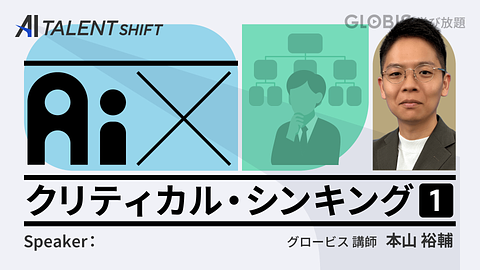
【AI×クリティカル・シンキング】①イシューと枠組みでプロンプトを磨く
生成AIから期待する回答を引き出せず、試行錯誤を重ねていませんか。 本コースでは、生成AI活用の質を高める鍵として、クリティカル・シンキングの視点からイシュー設定と枠組みを押さえる重要性を解説します。 目的に直結する問いの立て方や、プロンプトに落とし込む際の実践ポイントを具体例とともに学ぶことで、AIをより思考のパートナーとして活用できるようになります。 生成AIを業務で使い始めた方から、活用を一段深めたい方まで、再現性あるプロンプト設計を身につけたい方におすすめの内容です。 さらに学びを深めたい方は、こちらも合わせてご覧ください。 【AI×クリティカル・シンキング】②AIの弱点との向き合い方 https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/cdfe41e3/learn/steps/62198 ※本コースは、AI時代のビジネススキルを学ぶ「AIタレントシフト」シリーズの一環として提供しています。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
会員限定

リーダーの挑戦⑤ 藤田晋氏(サイバーエージェント代表取締役)
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第5回目のゲストは、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋氏。起業の理由、経営をどうやって学んだか、アメーバブログ・ABEMAの立ち上げ、経営チームづくりについてなど聞いていきます。(肩書きは2020年12月11日撮影当時のもの) 藤田 晋 サイバーエージェント 代表取締役 堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
会員限定

ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 前編 なぜ眠れないのか?~
「仕事が終わらないから睡眠時間を少し削ろう…」「業務時間中なかなか集中できない…」「毎日朝起きるのがつらい…」。 あなたはこのような経験をしたことはありませんか? 仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削りがちなのが「睡眠」時間。 実は今、日本社会は世界と比較して「最も眠らない国」だということもわかってきています。 慢性的な睡眠不足は、心身の健康に悪影響なだけでなく、仕事のパフォーマンスにも当然大きな影響を与え、社会全体の経済損失につながります。 このコースでは、基本的な睡眠リテラシーを学んだ後の「問題解決編」として、「なぜ多くのビジネスパーソンは眠れないのか?」について解説していきます。 ▼本コースで学べる主な内容 ・そもそも眠れないことは何が問題なのか? ・眠れなくなってしまう原因とは? 睡眠不足の原因は認知機能の問題にありました。 自身の睡眠不足に対し、正しく「気づき・理解し・行動を変える」第一歩を踏み出しましょう。 ▼関連コース ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~リテラシー編~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/24575c03/learn/steps/53129 ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 後編 どうしたら眠れるのか?~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/4ba981e9/learn/steps/62042 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

大阿闍梨 塩沼亮潤が死の手前で見つけた「生き方」
あすか会議2018 第4部分科会B-1「極限の世界で見つけた人生の歩み方」 (2018年7月7日開催/国立京都国際会館) 1300年間で2人目となる大峯千日回峰行満行を果たした塩沼亮潤大阿闍梨。48キロの山道を1日16時間掛けて歩き、それを千日間に亘って続ける過酷な行の中で、どのような悟りを得たのか。そして、9日間、断食・断水・不眠・不臥を続ける四無行満行という極限の世界で何を見つけたのか。塩沼氏が「創造と変革の志士」へ贈る「人生の歩み方」とは。(肩書きは2018年7月7日登壇当時のもの) 塩沼 亮潤 慈眼寺 住職
無料
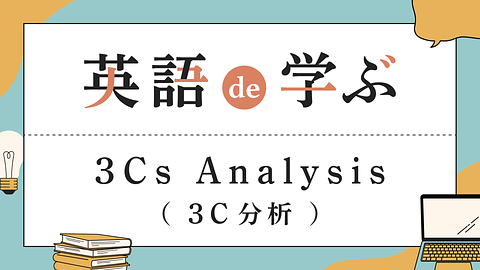
英語 de 学ぶ!3Cs Analysis(3C分析)
このコースでは、グロービス学び放題の英語版である『GLOBIS Unlimited』のコースの中から、ビジネスで役立つ頻出の英語表現をピックアップしています。英語ネイティブの方が実際に見ているコースなので、リアルなビジネス英語の表現を学ぶことができます。 今回のコースは「3Cs Analysis(3C分析)」です。一緒に『英語で』ビジネス知識を学んでいきましょう! ▼今回扱ったUnlimitedコース続きは下記からご覧いただけます 3Cs Analysis https://unlimited.globis.co.jp/en/courses/da5ca962/learn/steps/36362 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
コメント1367件
rykth
ジャムの法則は、アタマでわかっていても実践するのは簡単ではない。選択肢を用意する側は、あらゆるニーズに応えたくなるし、仕入れ担当であれば多数の取引先から買えば多数の営業マンに感謝される。絞り込んだ結果機会ロスを引き起こすリスクを営業に吹き込まれると判断を誤りがちであるが、こういったデータをもとにお客様視点で選択肢を絞り込む必要があると再認識しました。
hiro_yoshioka
選択肢は絞れ(嗜好品は別。選ぶのが楽しいから)
相手に選びやすく配慮するやさしさをもとう!
と思いました。考えたこと、できることを全部提示したくなるので、そんなときはジャムを思い出そうと思います。
hk-0126
自分にあてはめても選択肢が多いと面倒ですね
na_0094
提案を持ち込む場合は判断基準を絞ることが重要。
test_
ジャムの法則は非常に有名な法則だと思いますが、本動画で述べているほど適用範囲が広い、ということには疑問を持っています。例えば、ジャムの種類が24種類と言われると、一つ一つの区別がつかなくなり、選択が難しくなるが、契約の条項が24というのはそれほど多いとは思わないように感じます。
どういうところに対して、ジャムの法則が成り立って、どういうところでは成り立ちにくいのか、ということをその理由から考え直してみるとおもしろいように感じました。
kim_grgr
意図的に争点を絞ってデメリットを隠す交渉に注意したい
hanssy24
製品紹介などにおいても、客先の需要などを事前に把握して置き、優先順位で紹介件数を絞らして細田効果を狙いたい。
kameco
「選ぶのが面倒」と感じたときに、原因は何か、と考えるようにしようと思いました。
rapi1972
どの業務においても、選択と集中は効率の面から重要です。
uhiko
コミュニケーションの仕方においても「どうしましょうか?」ではなく「○○と××どちらがよいでしょうか」という方向性を持っていくことで、回答側もより答えやすく、スムーズでスピーディーなコミュニケーションができると感じた
harinezumiy
交渉、提案時には選択肢を絞る
saito-yoshitaka
適切な選択肢とタイミングが重要である事を学びました。
au-08
ジャムの法則という言葉を知った。選択しが多い方が良いと思ったがストレスを感じるという事なので、お客様へのヒアリングも絞って行いたいと思った。
jasza66
趣味的要素がある嗜好品と大量消費品では選択肢の考え方を明確に変えたほうがよい。
my-name-is
そう簡単な話ではない。
論点・争点を外さない状況であればいいが、論点・争点を外すとスベるリスクも高まる。
max_ichi
展示会時のユーザーアンケートは選択数を絞り答えsストレスを与えないよう注意する
haruom
なるべく客には選択肢をださない
mattari
常に実現したいことの中で、ここだけは妥協できない
という点を理由と共に明確にして
業務に取り組む。
yoshida_0929
アンケートのお話は分かりやすかったです。シンプルな内容に変える必要性を感じました。
cocoli
ランチで良くあるなと思った
hirakazushi
購買意欲が上がるように、ジャムの法則を上手く取り入れていきたい
makie-natural
相手が何がいいか選びにくいだろうなと思った時は、
選びやすいポイントを数個用意してあげて、
相手が決めにくいと思うであろうストレスを減らしてあげる。
明日の朝食を頼む時、
「すぐ食べれて、洋食で、消化にいいもの」
と、言っておけば、
比較的、何を作ろうか決めやすくなる。
ykw_first
スマホのデータプランやネットカフェの料金の設定で「複数あるプランから使ったデータ量や利用時間に応じて一番得になるものが自動で選ばれる」システムは非常に安心感があります。迷っているお客様への提案として、単純な値引きではなく、どちらにするのが得なのかわからないのであれば、損になった場合には差額を補填するような形の値引き提案が有効かもしれない。
a26
相手が説明しやすいか、という観点も必要ということに気付かされた
tamackey
ジャムの法則はすべてに適用されるものではなく、「安価な商材」という限定がつくことが学べた。
今までジャムの法則は万能ではないと思っていたが、業務において軽微な課題に限って実践することで、他者への提案における意思決定の速度は上がりそうだと感じた。
michakan
担当業務においても短い時間での意思決定をしなければいけない場面でも多数の争点を列挙してしまっていました。
慎重、考えすぎ、相手にもベストな選択をする為、想定問答も含めて、情報過多、不要な列挙が多かったと学習で気がつきました。
ありがとうございました。
hide1117
ジャムの法則は、仕事以外の日常の交渉にも応用できます。
motonori_m
他者の説得などに活用が見込まれる
big-shika
メールなどでのヒアリングの際には、こちらで選択肢を絞り込んでから送ることで、回答しやすく返答も早いのではないか。
shimizu__shiho
選択肢が少ない場合は何かしら選んでしまうことが多いので、ユーザーが選択しやすい項目の提示や根拠付けしやすい要点を伝えることが大事だよ
miarai
倉庫作業において選択が多いとパフォーマンスに影響すると推測できます。なるべく業務はシンプルに、思考せずに作業できる仕組みを作っていきたいと思う。
kojiro-biz
販売だけではなく、交渉ごとについても当てはまるという視点はなかった。
交渉をするということは、いくつか決めなければいけない事案があるということ。内容はさることながらその事案の数がベストな数なのかというのは、うまく進めるために非常に重要なことなのかもしれない。
具体的に言うと、会議などでみんなが好き勝手に思いつくままに議論するよりも、議題を絞って話し合った方がスムーズに話がまとまりやすいと思った。
10087117
選択肢が多すぎると迷ってしまうというのは自分でも感じるし、話に聞いたこともあるのですが「ジャムの法則」と言う名前があるのですね。日常生活でも、たとえば「週末はどこに行こうか?」ではなく「週末は、〇〇と△△のどっちに行こうか?」などと選択肢をしぼって質問することで「どこでもいいよ」というような回答にがっかりすることがないかもと思います。
mukai_tatsu
通常業務で、高価な商品を取り扱うことが多いので、購入理由をいかに説明しやすく提案することが重要です。その際、競合との差別化をどのように説明するかも常に検討しておくことも必要です。
kenken48
単純に選択肢が多い方が
良いと思っていました
選択する楽しさ
選択するストレス
この事も考えて
お客様に選択しやすい状況をつくることが重要だと思いました
この考えは合っているのだろうか?
ito-n1355
非常に勉強なりました。
商談で確認項目はついつい増えてしまいますが、絞り込むことを意識したいと思います。
aloha_alpha
消費者の立場として、また業務上の思考ツールとして、応用できる法則だと思った。短い動画で簡潔で分かりやすかった。
eizan_1000
ジャムの法則があると理解したうえで、適切な選択肢を設定するのは難しい気がします。
tomotoshi_reiji
仕事で発揮していきます。
fletcher
上司に判断を委ねるとき、考え得るすべての可能性を出すのではなく、選択肢を絞り、聞いてもらう時間と考える時間を減らせるようにし、負担をかけないようにする
starstarstar
お客様ニーズと心理が必ずしもイコールでないことを鑑みると、商談において多数の商品を用意することや、争点を多数用意することは結果的に判断を難しくさせていることが分かりました。商談においては、商談内容に応じて、商品の数や争点をよく検討していくことが重要だと思います。
nogtomo
自分もスーパーマーケットでポテトチップスを買う時、種類があまりにも多すぎると、どれ買うか時間をかけすぎて結局買わなくなってしまうことがあります。こういう時にジャムの法則を用いて、常時販売するポテトチップスの種類を6種類と、期間限定で1種類追加する事で、買いたいポテトチップスの種類を選びやすく且つ、期間限定の味もついでに楽しみたいというメリットを得られると思います。
u-654258
業務で活用するためには、お客様のニーズを把握し、絞り込んで商材を紹介することが大事であると感じました。
jannedaarc
交渉の際は、多数の選択肢を提示しすぎると決裂するため、選択肢を見極める必要がある。
athushi
業務では、選択肢を3つ4つそれ以上与えるより、2択に絞って選択肢を与える方が選ぶ側もストレスを軽減できて話し合いも円滑に進むことを学びました。
yamakazu95
社員アンケートに活用。設問を少なくするとともに「その他」の設問をもうけて選択した人には「理由」を記載してもらうことでアンケートを企画した担当か気がつかない答え、視点を洗い出す。
l2
AとBならどちらがよいかというような質問を行うことで、相手にすぐに回答いただけるようになると思う。
iwoas-mtm
日常生活で、よく体験するだけに、耳が痛かった。
eisukes
選択するのはストレスを感じるので販売アイテム数を絞る
sugiyamanana
アンケート作成への応用
akira_55
えらびやすくするのも大切
marusho140
お客様に商品をご案内する際、多くの情報を伝達しがちであるがそこをよく考えてお客様の購入意欲に沿った絞った提案を実施する事で購買率向上につなげていきたい。
yoshim888
日常で見かける光景であり、意識せずに自分も遭遇している内容であった。また、小売業では無いがサービス業であるため日頃より業務内容でジャムの法則に該当するであろう商品の棚卸を行ない、顧客提案時には絞る方が良いのか、逆に選択させたという意識をもって最終決定してもらうのかを判断する必要がある。
kouw
交渉やプレゼン時に選択肢を絞って提案する方が結論に導きやすいことを念頭において説明していきます
tanakatoshinobu
相手側の心理まで考え、営業や販売だけでなく
教育にも活用したいと思います。
ruitaka_kanribu
選択肢は多ければ良いという訳ではなく、選びやすいことが重要となる。
ただ単に製品ラインナップを増やすのではなく、松竹梅の3段階くらいに分けて提案するなど。
noginogi
営業活動を行う際に商品スペックをすべて提示、比較されても相手側はただ迷いが増えるだけの可能性があることを知れた。
相手が何に着目しているのかを知るため、まずはプロジェクトの概要や相手の人となりを知ることが重要であると感じた。
my_awamori
高級商材であっても、顧客からの問い合わせを獲得するフェーズではジャムの法則を活用できると感じた。営業面で活用し受注向上に繋げていきたい。
niwa_k8
報告において重要な情報のみを適切に選択する。
asae-iraga
・お客さまの選択肢を増やしすぎない工夫が必要だと感じました
okojo2023
選択肢を少なくして、答えやすいように工夫する必要であることは理解できました。
日頃の業務の中で学んだことを実践していきたい。
h_sakanashi
難しい
応用できる部分が想定できにくい
yusakuwatanabe
良い復習になりました
tuntun88
確かにと思う法則でした。
puffer
お客さまへのアンケートは問題も回答の選択肢も幅広く準備しがちです。一度のアンケートであれもこれもヒアリングしようと欲張った結果数が多くなりすぎ回答してもらえないのでは本末転倒です。適切な選択肢の数を念頭においておきたいと思います。
kenichi_1123
自身が日常を過ごす際にもこのジャムの法則を意識して様々な事に注目していきたいと感じました。また社内においても会議資料作成や社外へのプレゼン等においても選択肢を絞る事で交渉を上手く進める事に活用したいと思います。
ken175
プロジェクト推進において、複数案示すよりも、数案に絞って提示することで、スムーズに進めたい
matsuyama_mina
私自身は、ジャムが24種類あった方が楽しめるため、例店や購入しやすくなると感じたため、意外に感じた.自分の目線だけで考えずに「選択肢が多いことは煩雑である」という前提を意識していたい.
kosuke-hirano
品揃え強化などの商品企画に活かせる内容である。
_saki611
小さいことでも相手の心理を理解することによって、交渉が上手くスムーズにいく事が分かった。
また交渉の場面のみならず、日常会話の中でも選択肢や論点をある程度絞る事は有効だと思った。
yoshioino
お客様へ入替提案をする際に複数台の入替提案をする様に指示している。導入メリット、金額、納期など具体的なイメージが出来る提案の流れを整理させる。
ishisan143
改装などでのアイテム選定には非常に役立つ。嗜好性や単価などによりメリハリを付けて運用することが重要だと感じる
kaotom
選択肢が多いのはコトによって有効かどうかが変わるのがわかった。嗜好品等は品揃えで選択の楽しみを与えるか、そうではない場合は絞った方が購入率が上がる。交渉においても争点の多さに注意する。
111yu_yu_yu34
お客様側に選択肢がある時には、選定基準をこちらから絞ることにより、こちらの説明のしやすいさ、お客様の判断のしやすさを生む。
また、特に再現性のある事象においては、選定・判断の基準を決めておくことで、提案のための時間を効率化することにもつながると感じた。
k-shindou
シャムの法則はビジネス上で非常に利用範囲が広いと思う。
k__run
高級品や嗜好品には当てはまらない理由があまりうまく飲み込めなかったです。(ジャムの法則と同様のことは起こらない?
koichi-tanaka
以前、学習したので復習になりました。
3110-saito
選択肢が多いと購買側にストレスがかかることは、なるほどと思いました。重要なのは、どこに争点を絞り込むかだと思います。買う側と売る側お互いがwin-winで行くためには、おすすめプランを用意しておくのもアリだと思いました。
yudofu
直接活用できそうなことはすぐには思い浮かばないが、(高額で選択に時間をかけられる場合を除いて)選択肢が多いより少ない方が良い、というのは、いろいろなシチェーションで活用できそうである。
2yoshi
具体例で応用しようと思います
ka-har
短期での意思決定が必要な場合には2~3個の選択しに絞って意見を求めるようにします。
akechin
早く答えが必要な交渉ごとには論点を絞って提示する。また相手が説明しやすいサマリーを用意すると、その先の交渉がスムーズになる。
takashisato-
ジャムの法則を初めて知識として得る事ができました。種類を増やす事で単価が上がるとばかり考えておりましたが、逆に選びにくくしている事もあり注意していきたいと思います。
hochibu10
考えるべき争点が多い場合、自身としてはそれぞれをしっかりと考える必要があるが、上司や他の人に説明する場合は争点の優先順位をつけて
ポイントを絞った説明を心掛けたいと思います。
sota-
選択肢は用意しつつ(考えつつ)示すものは絞るという形に落ち着くのではないか。
boo10109
日常品等については選択肢が多いことは、購買の妨げになる場合があることに気が付きました。それとは逆に高級品等に関しては、瞬時に判断すべきでなく購入検討する時間が多くある場合には、必ずしもこの法則に合致するということではないということも学びました。
inoue_mk
意見がまとまらない会議などこういうのも一因があると感じました。
ある程度方向性を決めておいて、最終は少ない選択肢からでもいいのかなと思います。
glob304
日常業務で軽微な判断を求める際の選択肢の提示
100864
業務で活用するには客先ニーズの正確な把握と具体的なシーンの考察が必要だと思いました。
satossy
検討は広い視野で多角的に、提案は争点を重要度で絞る
soramame7
あまり選択肢を広げ過ぎない
rie5
早速周囲に短時間で意見を求める際に選択肢を絞ったうえで意見が聞けるよう、意識する。
daichio
ジャムの法則に反してしまうが、自分のリスク回避のため、全ての選択肢とシナリオを説明したくなる気持ちが湧いてくる。相手目線に立つことも重要。
arai-ju
適度に選べる選択肢がある、というこが理解でき参考になりました。いろいろな場面で応用できると思いました。
yg___
法則を初めて知りました。
メールのやり取りや見積提示等ではわかりやすく早いのがよいかと思うので、選択肢を多く用意しすぎないよう気をつけたい。
umeimakoto
ジャムの法則を学んだが、活用するにはまだ判断が難しい。
matsumym
ジャムの法則について学んだ。
選択肢が多いと、選択肢が少ない場合よりも意思決定が難しくなり、購買に至る割合も減る現象をいう。
ランチタイムの日替メニューの設定や選択肢の多すぎるアンケートはジャムの法則の例と言える。
交渉においてもジャムの法則は活用でき、特に短い時間での交渉において、多数の争点を示されると瞬時に判断して交渉することが難しくなるため、争点を絞ることが大事になる。
なお、ジャムの法則は消費財にあたはまるもので、高価で選ぶ時間が十分にあるもの、選ぶことが楽しみな商材においては、選択肢の多さは問題になりにくいこと、また、人は選択理由を説明しやすいものを選びやすいこと、さらに、販売アイテム数を絞ることは、経営的なメリットもあることに留意が必要である。
ken175
ジャムの法則を意識して、欲しい結果を得られるようにする
shota__abe
現在の商品の陳列を色々な層に刺さることを早退して多くのラインナップを準備しているが、そもそもおかないという選択肢も必要。
min_beerlove
業務の改善提案を行う際に、色々な手法や考え方があるといって、それらすべてをフォローするような内容をプレゼンしたとしても、結果としては薄味になり、結局何がやりたいのだろうか、何を改善できるのかがぼんやりしてしまうと思いました。
選択肢を絞り込み、相手にとっては理解・選択がしやすい状況を作り、自分にとっては提案のしやすい状況を作っていきたいと思います。