
会員限定
基本を学ぶ!ヒューマンエラー防止の基礎講座(前編)
人間が原因となって起きてしまうミスや失敗、いわゆるヒューマンエラーは誰にでも起こりうることです。ヒューマンエラーは必ずしも個人の問題が起点ではなく、人間工学の視点や組織の問題など様々な要因が考えられます。 本コースでは、人間の特性を理解し、ヒューマンエラーをゼロに近づける為の基礎知識を解説します。人間はどのようなメカニズムでエラーを発生させてしまうのか、どのような対策を行えばよいのか等を学習していきましょう。 ※本コース視聴後、以下の関連コースを視聴することをお薦めします。 「基本を学ぶ!ヒューマンエラー防止の基礎講座(後編) 」 本コースはカイゼンベース株式会社よりご提供いただいたコンテンツです。 https://kaizen-base.com/







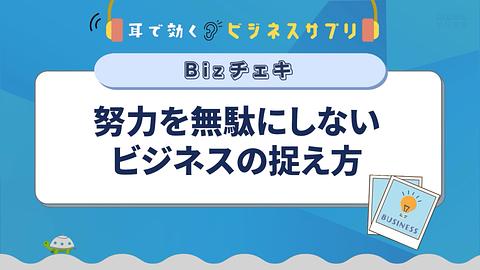









より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
100+人の振り返り
ozawa_h
IT・WEB・エンジニア
小さなことでも後回しにしていると大きな失敗に繋がる。障害だけではなく、ビジネスでも手間を抜くと将来に大きな失敗に繋がることがあるので注意するようにしています。
a_7636
人事・労務・法務
始業前点検、自主検査、内部監査での指摘、などなど。
チェック項目やルールが多くてウンザリ!という方も多いかもしれません。
でも、ルールは結局のところ、自分の生命、身体、信用などを守るために必要なものだと思います。
いざというときに、「自分はなすべきことをなした」と言えないのは、自分のためにならないです。
あとは、ルールにルールを積み重ね過ぎても、工数ばかり増えて形骸化するだけ。
ルールを加重するだけでなく、シンプルにしたり、目的達成したらルール撤廃というのも考える必要があると思います。
mgn0027
営業
日常業務での小さいミスも積み重なると大事故につながるかもしれない。そんな気づきを改めて教えてくれる内容でした
s_atmimi
メーカー技術・研究・開発
事故が起きやすい3Hについては、初めて知りました。安全環境委員として、意識しておこうと思います。
seii_koshikawa
その他
自職場では、トラブルやミスを未然に防止する目的としてPDCAの取り組みを毎週実施している。Error防止策としてはハインリッヒの法則等々を用いた対策を正しく取る事が大事だと改めて感じました。
ma-shi1022
営業
ハインリッヒの法則
1件重大自事故の背景には29件の軽微な自己と300件の異常があるという経験則(ヒヤリハットとも近い)
→これにより小さな以上や不注意を減らし大きな事故を未然に防ぐという理論である
事故が多い3h
└初めて・久しぶり・変更
例)車の免許の取り立て・ペーパードライバーの運転・車の買い替えなど
例)日本年金機構の事故
→メールによるサイバー攻撃
→125万件の情報流出事故があった
・メールによるサイバー攻撃による対応エラーが28件もあった
◆コツ
ハインリッヒ以外にもバードの法則・タイ=ピアソンの結果も同じ。結局は重大事故を起こす背景である軽微なエラー
※建設や医療など事故が大きくなる職場では当然、意識されやすいがオフィスや一般ビジネスにおいても同様である
hiro_a0208
販売・サービス・事務
普段意識しているところもあり、共感しました。
kfujimu_0630
マーケティング
工場、医療現場、建設現場など、人命に関わる場所では強く意識されていると思いますが、情報漏洩などオフィスでも当てはまることはあるんだというのは発見でした。勉強になりました。ありがとうございました。
gouda0922
経営・経営企画
軽微な事象にも気を付けて
重大事故を発生させないようにする
yyacupun
人事・労務・法務
軽微なミスが重大なミスに結びついている事わかりました。
mao-joan
経営・経営企画
重大事故を防ぐために、現場の意識を高めることが重要で、ハインリッヒ法則が分かりやすく説明できるので、早速使ってみたい。
wakizou
専門職
一つのミスで危険、災害が起こりうる現場のため、復習も兼ねて活かしていく。
70sp1208
その他
鉄道関係の業務に関わっているため、教育訓練の中で説明を受けています。ちょっとした気の緩みが事故につながるため、これからハインリッヒの法則を念頭に置き、業務を進めていきたいと思います。
sphsph
メーカー技術・研究・開発
分かっていても気が抜けているというか、中々真剣みが上がりません。
後から、危険と思っていた。とかは最悪です。
touto
営業
取引商材の品質管理の中で活用しています。
一件の重大不具合の背景には29件の軽微な不具合と300件の異常が存在する事をベースに対策を考えています。
t-ishiza
販売・サービス・事務
より個人情報の取り扱いに注意しようと思いました。
bad
建設・土木 関連職
ハインリッヒの法則を理解し、職場に生かしてしていきたい
teruhiko800
営業
ともすれば油断しがちだが軽微なミスで対応して重要なエラーをなくす姿勢が重要であると感じた。
yhs4112
営業
はじめて、久しぶり、変更、確かにこの時にミスは起こりやすい。
kuta_41
IT・WEB・エンジニア
実務でばりばり生かせそうである。
goanai
IT・WEB・エンジニア
システム障害を防ぐため、運用作業のヒヤリ事例を集めて対策を取る
reikou
IT・WEB・エンジニア
何事も異常出たら気にして注意すべき
if_1980
営業
小さなミスでもその背景を考え、問題があれば解決する。
mika-1016
専門職
知っていることが多かった。学べた
arashima
その他
大きな問題が発生した際、類似の小さなヒヤリハットが無いか調べる。また小さなヒヤリハットが発生したら、類似案件が発生してないか関係部署と共有する。
75475
メーカー技術・研究・開発
ヒューマンエラーを防ぐことに役立つ
pinewell
その他
異動時期は新規採用職員や異動者が新しく業務を行うため、事故やミスが起こりやすいので、大きな事故につながらない様、特に注意を払う必要があると思います。
14001
資材・購買・物流
ハインリッヒの法則の復習になりました。日頃から緊張感を持って小さなミスを対処していくことが重要だと思いました。
nishimurayuta
営業
一時は万事の言葉、
事故の場面のみならず
業務効率
人材育成
課題解決
小さなエラーを検出し、阻止改善
大きなミスを防止、
取り組む考え方も、大切かと
ma48458
金融・不動産 関連職
軽微な異常をスルーしてしまうことがあると思うが、そういう時こそ、一度立ち止まって見ることが必要だと思った。
y-shiraki
販売・サービス・事務
ヒヤリハットや細かな問題を無くすことで、重大な事故やミスを無くすことができるのであれば、普段から細かなミスや異常を発見して、対策を仕組みにしていくことが必要。
転記ミスなどは、自動化するなど人が関わらないようにすることも重要だと思う。
pontaro-
経営・経営企画
日頃から意識させているが、ヒヤリハット発生時、その原因の究明と再発防止策の構築並びに実行力の確認が重要である。
gosimakeizou
営業
慎重に仕事をするのはみんなわかっていると思いますが、緩んでしまうので定期的に確かめることが大事になると思います。
yasso
販売・サービス・事務
目安箱(ヒヤリハット収集するボックス)は必要だと感じました。管理職に対し、通報(警鐘)となったとしても、やるべきだと考えました。
kazu56209
営業
事故は初動が大切。だが忘れがちになってします。
慣れが怖い。初心に戻ることが必要。
3Hの法則を忘れずに
重大事故の背景には小さな事故がある。小さな事故を防ぐことが重大事故を防ぐ
意識改革が必要
mamisan
専門職
ヒヤリハット、3Hなど、日常で役立つ考え方でした。
ftomo
人事・労務・法務
軽微なミスがどのような重大事故に繋がるかを意識し、軽んじることなく日々の業務を管理する。
sumi2021
人事・労務・法務
思い込みをなくし、必ず確認していく
yiolite
販売・サービス・事務
事故になってはいないけどもヒャとかドキっとした体験を収集し、事例を交えて注意喚起することが大事
platon
メーカー技術・研究・開発
安全第一❗
健康第一❗
sakiyam2
IT・WEB・エンジニア
ヒヤリハットの法則という言葉の方が馴染が深い。些細なミスに対しても真剣に向き合うよう、自分だけでなく部下にも意識付けを行っていく必要がある。
o_s_
その他
小さなエラーから大きなミスを防ぐ
mo_o
その他
小さなヒヤリハットの情報を全員で共有して、大事故を未然に防ぐ対策を立てる。
tokyo-tokyo
その他
現業からのチョットした事象の報告を受けることにより、設備改善や取扱いの変更などに対応できる。
また、関係個所に情報共有を行い改善を迅速に対応できる。
aiko_gima
その他
製造業につとめているため、ハインリッヒの法則は意識することが多い。
ただ、労災以外にも、情報インシデントといった事故にも適用されるとのことで、製造現場以外でも気にしておきたい。
eiji1130
人事・労務・法務
日々の業務ミスをチェックして防止する仕組みを作ることで、大きな業務ミスを防ぎたい。ルーティンにミスをチェックする仕組みを導入したいと思った。
maruo_kazuhiro
営業
ハインリッヒの法則は、仕事のみならず、あらゆる危険に通じるものと言えそうだ。日頃のヒヤリハットを軽視しないことと、注意して臨むことをどのように習慣づけるかを検討しなくてはならない。
ksk_aiko
販売・サービス・事務
小さい事を見逃さない
h-n0329
営業
役立つ講義でしたので業務に活かしたいと思います
yukisawairi
経営・経営企画
1つの業務品質トラブルの裏には、もっとたくさんのエラーがあることを学びました。間接部門では、どんな事例に活用できるかアドバイス下さい。
anzeneisei
その他
教育で学んで理解していても実際に重大事故を起こしてからでないと意識を高く持てない。
yasukei
金融・不動産 関連職
重大事故をおこさないためにも、まずは軽微だと思われるトラブルから未然防止していくことが重要だと思う。
x0888
メーカー技術・研究・開発
研究開発での重大な設計不具合では、その他の多数の軽微なものにも目を向けて対策を考えてみる。
atago08
金融・不動産 関連職
職場において実践していることを再確認出来た。
kensaku_sumida
専門職
ヒヤリハット事例を軽視しない事が重要だと感じました。
redpine
IT・WEB・エンジニア
重大事故発生時には、その裏にある複数の軽微な事故、大量のニアミスが発生している。それを念頭におくと、ニアミス発生時点で1つずつの振る舞いを見直すことが事故の再発防止と考える。
n-kiri
販売・サービス・事務
3h
はじめて
ひさしぶり
へんこう
確かにそうであるように感じる。
事故のないように取り組むには、1人のチェックではなく、複数の目でチェックすることが大切
shimoosako
人事・労務・法務
個人の判断で軽微な事故や異常を報告せずに終わらせてしまう事が無いよう、改めて注意していきたい。
hidetoshi_c
メーカー技術・研究・開発
常日頃からハインリヒの法則を意識した対策が検討されている
podaison
営業
発覚した問題を点で捉えず、ハインリッヒの法則に従い、その背景を考え、線で捉えるよう再認識出来ました。
axtyu
IT・WEB・エンジニア
職場の不安全行動による作業事故をなくすために活用する
kazukix40
営業
例えば要回答の期日や、見込みの作成、議事録の項目漏れ、不備の解決への意識など、小さな気のゆるみがたくさんある職場では、大きな事故が発生する可能性があり、小さな一つ一つの取り組みをきっちり仕上げることが、平穏な日常への一里塚であると伝えていく
ab0110
専門職
日々物事をよく観察しておくことが重要。
bouyatetsu1978
メーカー技術・研究・開発
IT化が進むにつれ、チャットやメールの誤送信が増えてきているので、注意していきたい。
pondc12
人事・労務・法務
人はどのような作業でも間違える事がある。ただその間違いが蓄積して重大なミスに繋がらないよう、日頃から安全策を設けて、常日頃の業務において、間違いがないよう確認しながら進める事が大事だという意識を持って貰うようにしたい。
kenji1209
メーカー技術・研究・開発
tとくにございません。
yujihoshi
経営・経営企画
この考え方を持つことで書類一枚に関しても二重チェックをするなどしてミスを事前に防ぐことができる。たかが書類といえどもお客様に迷惑をかけることを防ぐことができ、事故ではないがクレームやクレームによるスタッフの精神的ストレスをかけないで済む
muramatsu-a
人事・労務・法務
小さなヒヤリハットを皆で共有する事で、大きな事故につながる前に注意を促すことができる。
hirano-tora
人事・労務・法務
重大な事故の背後には数多くの小さなミスがある。その為小さなミスを見逃さずに原因対策をすることが重要であることを学んだ。
ben3369
その他
社内では労災や環境異常が多発・再発している。
ハインリッヒの報告にならい、より軽微なヒヤリハットの段階で情報を吸い上げ、情報集約・分析を経て本質的な対策立案に繋げることが必要と思っている。(現実にはそうなっていない)
nk1225tk
営業
小さなミスの積み重なりが重大事故に繋がることを意識したい。
y_su
人事・労務・法務
職場の安全担当として、無災害が続いているからといって安全な状態とはいえないということを分かっていない人が多いと感じる。
いかに危険に関する感度を上げていくか、試行錯誤している最中である。
b1579585
金融・不動産 関連職
日頃発生する軽微な事故に対して対策を正しく取ることが大きな事故を未然に防ぐことにつながる。
daisaraken
その他
普段での業務でも意識している。
somosan_45
その他
軽微なミスやうっかりについても意識することが重要であることは認識していますが、人は間違いを起こすものであるとも考えているので、軽微なミスや間違いを如何に軽微なレベルで潰す仕組みを作るかにかかっていると思います。経費や労務管理など、規定や規則に対する誤りはシステム上でエラーとして検出可能であり、規則やルールも具体的に記述すれば、何が間違っているのかも把握しやすくなるものの、細かく規定し過ぎると運用が大変になるので、ミスを防ぐあるいは、ミスが生じたときの適切な対応について、意識やマインドセットの定着に時間をかける必要があると考えています。
kaotom
営業
1つの重大事故の背景には多数の異常や事故がある。事前に不注意を減らし事故回避に繋げる
takashi-n
経営・経営企画
重大なエラーにつながらないようチェックリストを作るなどして軽微なミスを未然に防ぐ
yuko625830
営業
営業業務に活用できると感じた。
hontake1202
人事・労務・法務
労働災害がハインリッヒの典型である。
phs
販売・サービス・事務
軽微なトラブルでも先には重大な事故につながる可能性を念頭に、異常に対して向き合っていく。
saitho
コンサルタント
ヒヤリハットをなくす
shinano777
人事・労務・法務
小さなエラーだからといって軽視しないこと、なぜそのエラーが起きているのかの本質的な部分を見れるよう意識することが大切と思います。
koji_wada
マーケティング
ハインリッヒの法則
1件の重大事故の背景には、29件の軽微な事故と、300件の異常が存在しているという経験則。ヒヤリハットの法則とも言う。ゴキブリみたい。3H、はじめて、ひさしぶり、変更。この3つが揃うと事故が発生しやすくなる。
事故が発生した際にそれを責めるのは簡単だが、なぜそれが起きたのか原因を究明すること、繰り返さないための暫定対策、恒久対策を施すこと。さらに類似の取組内容で軽微な事故の点検や異常を検知して対策していくことが重要だと思いました。
suzunce
販売・サービス・事務
ほんとにその通りです。
軽微なミスや異常が重なって、重大事故が起こっています。
ken175
メーカー技術・研究・開発
軽微なことを見逃さず、事故のない職場を目指す。
yasuo_san
メーカー技術・研究・開発
軽微なトラブルにも目を向けて、事が重大化するまえに初期の段階で対応することが大事だと学びました。
実務にも展開していきたいと思います。
satou_saori
メーカー技術・研究・開発
私の業務ではミスがあった場合に、お客さまの健康危害になることもあり、製品を回収につながるおそれがある。そのため、細心の注意をはらっているが、ヒヤリハットもあり、その裏には小さな不注意が隠れていると実感している。3Hを頭に入れ、ミスの蓄積、ミスの傾向を分析し、ミスに応じた対策を行うようにしていこうと改めて感じた。
k--g--
その他
軽微な事象と重大事故との関連性を「具体的にイメージ」できる能力を鍛える必要性を感じました。
taka-4
営業
軽微なエラーも共有して、対策を講じ、重大なエラーを回避できるようにしておく
2178
販売・サービス・事務
活かし方がいまいちピンときませんでしたが、この法則をチームメンバーに共有し、軽微なミスがあったときにも重大な事故につながることを認識してもらう・・であっていますか?
onishi123
その他
日常業務についてリスク評価を行い、ヒヤリ・ハットを洗い出し、対策を講じる。
aqueous
メーカー技術・研究・開発
ヒヤッとしたことはなぜ怖いと思ったのか、よく考えるようにしたい。
外部からの声も大切。
k_osada
販売・サービス・事務
ミスや事故が起きた場合の分析や整理の考え方の参考になりました。
eizan_1000
IT・WEB・エンジニア
異常をすべて防ぐことはできないが、その状況や情報を放置せずに共有することで大きな事故を防ぐことはできると思います。
yusakuwatanabe
販売・サービス・事務
ハインリッヒの法則の復習になりました。
shizu_na
人事・労務・法務
ヒヤリとしたりハッとすることは、人命を扱うような重大な現場以外でも時々生じるが、その都度留意するようにしたり確認を増やすといった些細なことの積み重ねが重大な事象の発生を抑えるのだと改めて感じた
eisukes
販売・サービス・事務
日頃から小さな異常を見逃さない
lotuspapa
メーカー技術・研究・開発
ハインリッヒの法則を意識することで、日々の軽微なエラーにも敏感になれる。
chiisai-kiba
人事・労務・法務
どこまでが正常でどこからが異常なのか、 明確な数値で敷居をつくることができれば統計的に事故を防ぐことは容易であり、機械学習やマニュアル化も納得感のいくものができる。
管理する側からは 今までは官能でしか識別できない物を、如何にコンピュータに解析、数値化させればよいかを、複数の指標から見出すことが求められる。
例えば下水道の破損による水漏れは、いまだに熟練の技術者が耳で聴いて判断している。大きく破断してからでは修理、復旧が手間である上、例えば震災で道路が傷んでいる場合には(下水は道路に沿ってつくられるので)全線の確認にも膨大な時間がかかる。
こういった技術を人ではなくコンピュータ管理にすることで、災害を最小限に抑え、早い復旧ができることを祈るばかりである。
athushi
その他
会社で過去に起きた労災やヒヤリハットの事例をもとに今後同じ事故を起こさない対策づくりとして役立てられる内容でした。