
会員限定
MECE ~抜け漏れなく分解・構造化して考える~
MECEとは、ある物事を「モレなくダブりなく」切り分けた状態のことです。例えば年代別など、全ての人がその切り分けのどこかに属するようにします。MECEは論理思考の基本で、物事を分解し、構造化する際に役立つ考え方です。 例えば、状況を調べて問題箇所を特定する必要がある場合に、いくつかのポイントに分解して考えることが重要になります。その際に、モレやダブリなく分解することができれば、分析や問題解決の効率性が高まります。 ロジックツリーやマトリックス、あるいはその他のフレームワークなどにも応用できる基本となるコンセプトであるMECEを理解しましょう。 ※2018年2月15日にコース内容を一部リニューアルいたしました。 リニューアルに伴い、コース動画一覧は全て未視聴の状態となります。 なお、リニューアル前に当コースを修了している方は、コース修了済のステータスに変更は発生いたしません。





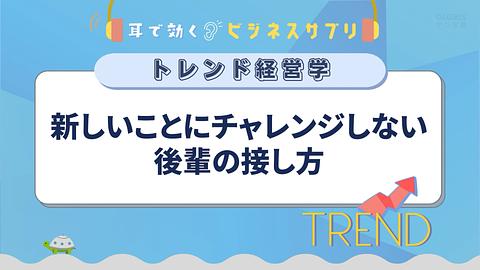









より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
100+人の振り返り
maverick8739
マーケティング
明らかなパワハラとなる質問は論外として、質問のつもりが詰問に捉えられてしまうズレについて考えていきたい。私が思うところ、当該案件において指導するする側、受ける側の定義の大幅なズレがあるからではないだろうか。質問する側が自身ででは当たり前のことが、受ける側にとっては当たり前でないこと。
物事に「なぜ」を5回繰り返して答えを導き出すことが必要と理解している人では「なぜ」が足りなかったことに反省できるが、そうでない人ではまどろっこしい、答えを教えてくれずいじわる、となってしまう。しかしコミュニケーションにおいては自分がどうしたか、ではなく相手がどう感じたかが大切であるため、質問が詰問に感じられたらそれは詰問となる。この辺りを埋めるための、問題解決についても併せて学ぶ必要がある。
あと1on1ミーティングが重要とされている中、個人にふさわしい対応が必要であると感じる。失敗を自責として捉えている人に詰問は絶対あってはならないが、他責にする人に対しては先の人とは対応を変えなければならない。教育は金太郎飴でないところが難しい。
muraichan
営業
うーん。詰問してるな。反省しないと。
何回も何回も同じ間違いするし、優しくせっすると出来ていないのに調子にのるし。難しい世の中になりました。
思考が老害ですかね。
test_
メーカー技術・研究・開発
まずは相手をよく知ること、そして信頼関係を醸成することが重要だと思いました。
相手のことをよく知らない状態で教育が上手くいくなんてことはないように思う。
tamu0513
マーケティング
現在リーダーの立場で新たに異動してきた後輩の教育担当をしている。後輩が1つ下の年次である程度経験もあり、プライドが高いため、資料確認などで細かく質問して答えに詰まるケースが多かった。キャッチボールになっていないケースが多かったので、資料確認や諸々の確認の際には、まずは相手の考えを受け入れ共感を示す。「でも」など否定形のワードは使用しないようにすることで、まずは心を開かせることを意識する。
04-30
営業
子供の教育にも参考にできると思いました。
しっかりと向き合って、詰問ならないように
しないといけないと改めて感じました
m_matsubara
その他
思いつきではなく、帰ってきてほしい答えまて全体コントロールが必要。油断すると詰問になっちゃう
kameco
販売・サービス・事務
上司を信頼できない、心を開けないのは、ノックばかりだからではないかと思いました。キャッチボールの経験はありません。
djmpajmpkm
営業
受け取る側の解釈の問題もあると感じた
xyz95
マーケティング
自分で考えて動こうとしない部下に対し、質問することで考えさせようと思っていたが、客観的にみたら詰問になっていたと気付かされた。
どこかで言い訳に聞こえる部分に共感したくないと思っているから、次の詰問が出てきてしまうのだと認識。
hariruri
金融・不動産 関連職
なんで、なんで? をよく使う上司がいますが、追い詰めてるとはつゆともおもわないんでしょうね
ks46
営業
最初は質問しているけど最終的には詰問してるなと思うところがあります。
見直さないと駄目ですね
fj_cfbd0b
その他
こういうシーンはよく見ますね。「なんで」と「でもさ」が正義になっている。その言葉禁止にしないとダメです。
j0252512
メーカー技術・研究・開発
自分の思う通りの回答がなかったり、あせってくると陥りがちな問題だと改めて感じた。
kk-kojima
販売・サービス・事務
一方的に話しがちになるので、相手の気持ちを考えながら話をすることが大事。
horie-m
メーカー技術・研究・開発
詰問になりがちな対話。相手の理解、共感できるポイントを見つけて、相手が答えやすい質問を投げかけるように心がけることが大切。
taoyuan
営業
まずは相手の考えを聞くことからですかね。一緒に考えるということが必要なんだと思う。
a_fujiyama
メディカル 関連職
共感しながら会話することを心掛けること、答えやすい質問に変換して問いかけるなど、意識していきたい。
uhhu
専門職
意図せず詰問になっているかもしれないと思ったので、キャッチボールや共感を交えていきたい
1089
その他
コミュニケーションは奥が深い。
部下からは報告・説明・相談をしているのはわかるが、最近の傾向としては語数は多いが断定を避けるため、裁可されなかった場合の逃げ道のことばを用意してことばをかざっているように感じてしまう。
君子は貞にして涼ならず、と家慶公や幕末の長州藩主ののように「そうせい」と肯定的なディシジョンを下したいが、説明を受ければ受けるほど焦点がぶれているように感じてしまうため、時間の節約とアイスブレークをかねて、報告等の冒頭に、シンプルに報告等の要旨と何を上長に求めているのか最初に話すよう意を尽くしている。説明を聞いたうえで、否定ではなく単に質問だと前置きしてシンプルに「質問」しても、人徳のなさから、質問の意図とは異なる、うがった返答をされてしまうため、こころして、共感と理解を示しながら、 ポジティブな効果を発揮できる、より考えやすいよう質問を工夫して投げかけていきたいと肝に銘じた。MBA的なプログラムも参考にはなるが、短くても「実践知」のプログラムは、こころにささる。
tomo-tom
営業
受け取り手がどう感じるかによるところが大きく、問題は受け取り手に原因があることもあるのです。
ruikai_
メーカー技術・研究・開発
質問方法と傾聴力が大事と感じました。
dia44
メーカー技術・研究・開発
まずは相手をよく知ること、そして信頼関係を醸成することが重要だと思いました。
相手のことをよく知らない状態で教育が上手くいくなんてことはないように思う。
memememememe
販売・サービス・事務
なぜの連続や否定ではなく、様々な角度から聞いていくことが重要。
mkk_saito
専門職
会話のキャッチボール、共感する、全くできていないので、これから意識していきたい。
hirokumakun
メーカー技術・研究・開発
相手が本当のことを話し易い雰囲気を意識して臨みたい。
muchan
人事・労務・法務
自分で考えてもらうように質問するということは今までしてこなかったので、原因や再発防止策などを自分で考えられるようにサポートをしながら質問していこうと思います。
uchis
金融・不動産 関連職
会話を深掘りしようとして、詰問にならないよう気を付けようと思った。
leftsider14
メーカー技術・研究・開発
部下に失敗の原因や再発防止策、改善策、次の打ち手を考えてもらうため、質問をすることは有り得るのですが、質問の行い方で相手を追い詰めてしまいことを学びました。
部下が答えやすいように質問の範囲を狭めたり、アドバイスを交えるなどしてしていきます。
また、「でも…」と相手の言ったことを否定してしまうことが、自分はよくあるため、相手に考えさせる場面では言わないようにしたいと思いおます。
kamemoto_suguya
建設・土木 関連職
相手のことをよく知り、信頼関係を築くことが重要だと思いました。
miyazaki526
建設・土木 関連職
会話のキャッチボールを意識して、相手の意見も確りと受け手ながら質問をしていきます。
wakaho
その他
相手の状況を把握するために進捗状況を聞き、それから今後の進め方を検討する。
miya3883
販売・サービス・事務
聞き方、言葉の選び方、様々なことに配慮しないと詰問になってしまいそうだと反省しました
atsuaki_sunada
その他
学んだ内容は、業務や日常において
shimo-g
営業
職種によって大きく異なると思うが、客観的な質問をするようにこころがける。
ryuichi_k
資材・購買・物流
詰問にならないよう意識して質問を投げかけるには相手の話に共感を示すことも重要。畳みかけて質問をしないように意識して相手との会話がキャッチボールになるよう心掛けたい。
ms-kawahara
IT・WEB・エンジニア
色々な1on1を実施しましたが、私自身からの話にエンジンがかかり詰問になってる時もあったなと反省しました。強めの言葉でなくても何で?という言質問が詰問になっているのだと気づき今後は改めたいと思います。
masshimo
営業
ありがとうございました。
you_can_do_it
営業
詰問しがちなので要注意だと思いました。キャッチボールを心がけます。
everest
営業
顧客の課題を深掘りし、本音を引き出し、決断を促す質問ができるようになることで提案の成功率を高めたい。
cmisaki
人事・労務・法務
聞く姿勢を大事にしようと思います。
komariri
メディカル 関連職
質問はクローズドクエスチョンから始めて、慣れてきたら思っていることや感じていることを聴く質問にしていきたいと思いました
han_solo
メーカー技術・研究・開発
相手が答えに詰まっている時に、畳み掛けるように質問することは避けたいと思います。
eizan_1000
IT・WEB・エンジニア
前向きに目的志向、ゴール思考で考えることで「なぜ?」という後ろ向き発言の発動時期を調整できるようにしたいと思います。
kayokayokayo
人事・労務・法務
考えさせることも成長に繋がるのですね。
ryont
その他
部下の立場として質問がキツめだなと感じることがこれまであったなと思い起こした。質問する側が正しいと思い行うことも、受ける側はその正しさに逃げ場を失うこともある。共感できないことであっても一旦は相手の考えを受け入れることを意識していきたい。
ume1010
金融・不動産 関連職
わかっていても言ってしまうことってよくあるので気を付けていきたいと思います。
k-mago
営業
詰問という単語を初めて聞きましたが、言われてみると結構してしまっていたので、意識しようと思いました。
minw
人事・労務・法務
とても興味深い話題でした。私自身、結構質問したがる傾向にあるかもしれません。まずは相手を受け止め、理解を示すこと、そしてより考えやすい質問をするよう心掛けます。
nattou-kozou
営業
相手との認識の差を理解しながら解像度を上げてもらう。傾聴と共感を繰り返していこうと思います。
k-kondou
営業
まずは受け止める、そして会話のキャッチボールになるようにする。同僚や後輩との会話で心がけて実践してみたいと思います。
kirinosuke-1st
販売・サービス・事務
自分が若手だったら、こう言われたら嫌だなあと思う言い方をしないのが大事だと思いました。
knagai79
建設・土木 関連職
詰問、気をつける。
質問はキャッチボール、まずは相手の考えを受け止める、を意識する。
相手から仕事の相談と依頼があった場合、情報の確認・整理の段階で、詰問してしまう。
iiduka_d
建設・土木 関連職
質問者は自身が確認したい内容にフォカースした質問になる傾向が高い為、
相手の思考を引き出すよう、意識的におこなうことが重要である。
相手に傾聴する姿勢を見せ、個々で異なる内部思考をいかに発信してもらえるかがキーポイントであると考える。
nb-take
専門職
質問する側は立場の強い方なのでハラスメントにならないように注意が必要だ。
h-shibayama
人事・労務・法務
部下への共感が重要だと感じた。
自身の理想(答え)を伝えるだけではなく、相手の行動、心情をくみ取り、そのうえで今後前向きに取り組みやすくする提案を行うことを意識する。
yamajinji
その他
振り返ると結果として詰問をしてしまっていることがあると思います。
会社でも家庭でも・・・反省です
doitsu
マーケティング
何故と考えることは大事だと上司に教わったが、何故を他人に執拗につきつけることは相手のためにも自分のためにもならないことがわかった。
子供に対してもよく何故何故と言ってしまうのでビジネスの場ではないが気をつけたい。
tuuuzy
金融・不動産 関連職
自身で導き出せる気づきが大事。能力があっても気づきが無ければ生かせない。
rickszk
マーケティング
詰問しないようにしたいと思います。
sekorin930
人事・労務・法務
対等な立場のメンバーに対しての「でも」「なぜ」ですら自分が受けると反対派からの反撃であると構えてしまうのにそこに上下関係があればなおさら圧迫的に感じるよな、と思いました。
yu-tnk
その他
私自身も詰問にならないよう受け止めて理解を示す、考えやすい質問を投げかけるとともに、
メンバー自身にも考える力を持ってもらい、思考放棄にならないよう、より会話を行うようにいたします。
tak_87
建設・土木 関連職
言い方によっても詰問と捉えられてしまうケースはあると考えさせられた。信頼関係を構築する事が、一番大切な様に思う。
k_oohata
営業
なぜ?は使わないように日々気を付けています。
どうすれば?とメンバーが自分自身の考えで話せる雰囲気を心がけています。
minomonta
その他
相手の考えを受けとめることを意識しながら、問いかけることをしてみます。自分だったらこう言われたらいだななと思うことを考えてみる
hoshikumay
建設・土木 関連職
質問をすることも会話の一つであり、会話とはキャッチボールという基本的なことを意識するだけでも、部下との接し方が良くなり、信頼関係構築に繋がっていくと感じた。
bisu20_kula16
販売・サービス・事務
仕事の現場ではつい急いで回答を出そうとしてしまい、試行錯誤の過程を否定的に見てしまう傾向があるが、まずは相手の考えを受け止め、より考えやすい質問を投げることを学んだ。この質問を考えることが自身のスキルアップにもつながる、と前向きに考えたい。
kaomaya
マーケティング
自分は詰問にはなっていないだろうと思っている。今回の動画でも自分自身では再確認できたが、それを受けてがどう捉えるかは別問題なので、相手の性格などを考えて対応していきたい。
530612
メーカー技術・研究・開発
原因を追究するために理由を問うことは必要ですが、聞きたいことが先走って詰問になるケースが多いと感じています。
yoshi_sugimoto
販売・サービス・事務
なぜなぜ解析という名のもとになぜを5回程度繰り返す手法を取る上司がいますが、フレームに拘っているだけに感じました。ゴールは相手に理解してもらうことなので、日ごろからコミュニケーションを取って性格に合った手法を選択できるようにしたいと思いました。
nyat
その他
なぜそうなったのかを確認しなければ、アドバイスも解決方法も見いだせないが、想定できる範囲をはるかに超えたミスを部下がした場合、なぜかそうなったのかを本人に聞かないと全く理解ができないときは詰問になりがちなので、気を付けようと思うが、聞き方を変えても、一緒に手順を振り返っても、説明が毎回変わる、なぜそう思ったのか聞いても全く理解できない思考回路の回答がきた場合、一方的にいいから言われた通りにやれというのは違うと思うので、これ以上どうしたらいいのかがわからなくなる。部下のレベルに応じたキャッチボールの仕方も教えて欲しい。
rinkomat
建設・土木 関連職
ミスをしてしまった際に次はどのようにすればいいか、どこが間違いやすい等部下に考えてもらう。またミスしやすい箇所には共感する、自分もしたミス等を伝える
sakura1111
専門職
課会の際、こちらの意見を聞かずに一方的に回答をだしてしまう上司がいます。すべての回答がすでに決まっていて、会話のキャッチボールをすることが難しい場面に遭遇することがあります。
koaramonster
販売・サービス・事務
業務でミスが確認された際、課員に対してどうしてミスしたのかと直接的に聞くのではなく、どこの作業がみんなつまずきやすいのかな?や、どういう手順にすれば、やりやすくなるかな?等柔らかい聞き方を行い、個人の問題としてではなく、課内の問題として取り上げるようにしたい。
brompton
マーケティング
質問によって双方の理解を深めることが重要だ
itokento
営業
質問ではなく詰問はいけないと理解した。
nao_toyo
メーカー技術・研究・開発
自分のことを振り返るいい機会となった。
sakuma_sasa
建設・土木 関連職
会話のキャッチボールは、どこでも使えるフレーズなので、あまり意識していなっかた。
今回受講して、「相手の内容を受け止める」ことを改めて認識しました。
jyakushiji
建設・土木 関連職
詰問はNGですね。ついつい感情的になってしまうことがある際に陥りやすいので冷静にしたいと思いました。
zenigameko
営業
質問から詰問となっていたケースがあるように思い、今後はまずは受け入れて共感し、言葉のキャッチボールを念頭に置いて質問するようにしたい
fujita_yuki
金融・不動産 関連職
まずは共感することで相手への理解を示す
kikuichihajime
営業
原因は何であったのか、を確認するための質問をすることであり、詰問にならないように気を付けたい。
mahco
人事・労務・法務
より具体的で答えやすい質問をするよう心掛けたい
kiyonot
建設・土木 関連職
今後一度自身が受け止めてから話そうと思います。
y-kanoh
IT・WEB・エンジニア
詰問になっていないか意識したい。
kozom
営業
質問は会話のキャッチボールが大事だと思いました。
roku78
営業
詰問になってました。
反省します。
asamikazuyoshi
金融・不動産 関連職
キャッチボールがしっかりできるように、相手のことも考えて進めていきたい。
kashimura-t
その他
繰り返しのミスであった場合、ミスそのものに対して追及してしまう事が多い。
なぜ繰り返してしまうのか?話を聞いて納得してから改善策を提案もしくは、考えてもらう事が必要と感じた。
kounosu01
その他
詰問になりがちなケースはあると感じました、相手の気持ちを聴き、いったん受け止めてから、一緒に考える姿勢を取ろうと思います。
hoshi-kazushige
販売・サービス・事務
質問が詰問になる状況は、業務を行う上で身近に陥りやすいことだと思います。誰でも失敗しますし、失敗することで成長していきますので良い経験ができたと真摯に受け止めてあげることが重要だと思います。
部下から失敗の報告を受けた時は失敗した本人が一番気に病んでいますので、一方的に咎めるのではなく、失敗した後の対応が一番重要だと思いますので、適切にアドバイスや一緒に解決策を考えてあげることが重要だと感じます。但し、同じ失敗を繰り返さないように配慮することも必要と考えます。
unkei
金融・不動産 関連職
私の場合、答えやヒントを与えすぎていると反省しました。
verbiest
販売・サービス・事務
相手のレベルに合わせた質問を事前に用意しておく必要があると感じた。また、質問だけにならないよう、相手に理解を示す言葉をかける意識が必要だと思った。
nobu1015
人事・労務・法務
よくある光景だ
詰問にならぬよう意識する必要がある
hiroyukihoshino
営業
そうだね!で受け止める
103371
販売・サービス・事務
1度は共感するのは大事だが、同じことが繰り返された時は、どうなんだろうか?
詰問して部下を追い詰めたくはないが、追い詰めてしまっている自分が実際に居てると思う。
部下の立場や気持ちをもう少し一旦は受け止めてみる努力をしてみようと思う。
na_naig
経理・財務
詰問ならないように気を付けていますが、より一層気を付けなければならないと改めて感じました。
自分に時間がないときに、詰問になってしまうことがあるため、冷静さに相手と向き合っていきたいと思いました。
m--h
IT・WEB・エンジニア
育成のためのコミュニケーションは、相手が答えやすいように勧めることが大事
takasato0401
コンサルタント
日常的に使用する際は、相手の立場になって、自身の発言がどう受け止められるかを意識して話すことが重要だと感じました。
tsutsumit
その他
詰問にならないよう心掛ける
k_imura
金融・不動産 関連職
何気ない質問でも尋問しているように感じさせてしまっている部分がある気がします。もっと会話を意識します。