
0:59:48
割引情報をチェック!

AI BUSINESS SHIFT 第8回 機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第8回です。 第8回「機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル」では、AIが営業現場にどのような変化をもたらしているのか、営業担当者・営業マネージャー・組織としての役割や戦略が、AIによってどう進化していくのかを、営業プロセスの分解や実際の現場事例を通じて学びます。 ■こんな方におすすめ ・AIを活用した営業活動の最新動向や現場のリアルを知りたい方 ・営業現場の変化に直面している営業マネージャー・現場リーダーの方 ・AI時代における営業戦略や営業マネジメントのあり方を学びたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年2月制作)
会員限定

マネジャーのための仕事の任せ方
「仕事を任せると失敗が怖い」「自分でやった方が早い」マネージャーとしてメンバーやチームの力を引き出しながら成果を上げるには、どのように仕事を任せていけば良いのでしょうか? 変化の激しい時代において、マネージャーとして成果を上げ続けるためには、メンバーの個性や特性を理解し、それに合わせた効果的な任せ方を身につけることが重要です。このコースでは、ソーシャルスタイル理論を活用してメンバーごとに最適なアプローチを学びます。「任せる力」を高めることで、チーム全体の成長を促進し、自身のリーダーシップを発揮できるようになっていきます。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2024年12月制作)
会員限定

AI時代の個人力
AIが仕事や社会の前提を変え続ける今、最も求められるのは「他者に代替されない個としての力」“個人力”です。 本コースでは、澤円氏の著書『個人力』をもとに、AI時代をしなやかに生き抜くための「前向きな自己中戦略」を学びます。 テーマは、「Being(ありたい自分)」を中心に据え、自ら考え(Think)、変化し(Transform)、協働する(Collaborate)ことで、自分らしい価値を発揮していくこと。 リスキリングやAI活用が叫ばれる今こそ、スキルより先に“自分の軸”を問うことが重要です。 あなたは何を大切にし、どんな未来を描きたいのか? このコースは、あなたが“ありたい自分”として生き、キャリアをデザインしていくための思考と行動のガイドになります。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年11月制作)
会員限定
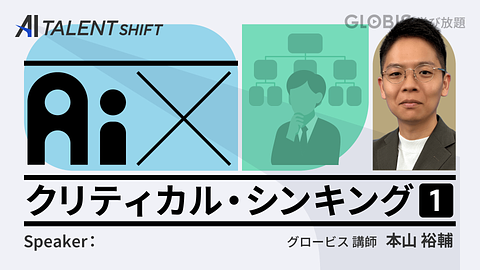
【AI×クリティカル・シンキング】①イシューと枠組みでプロンプトを磨く
生成AIから期待する回答を引き出せず、試行錯誤を重ねていませんか。 本コースでは、生成AI活用の質を高める鍵として、クリティカル・シンキングの視点からイシュー設定と枠組みを押さえる重要性を解説します。 目的に直結する問いの立て方や、プロンプトに落とし込む際の実践ポイントを具体例とともに学ぶことで、AIをより思考のパートナーとして活用できるようになります。 生成AIを業務で使い始めた方から、活用を一段深めたい方まで、再現性あるプロンプト設計を身につけたい方におすすめの内容です。 さらに学びを深めたい方は、こちらも合わせてご覧ください。 【AI×クリティカル・シンキング】②AIの弱点との向き合い方 https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/cdfe41e3/learn/steps/62198 ※本コースは、AI時代のビジネススキルを学ぶ「AIタレントシフト」シリーズの一環として提供しています。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
会員限定

リーダーの挑戦⑤ 藤田晋氏(サイバーエージェント代表取締役)
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第5回目のゲストは、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋氏。起業の理由、経営をどうやって学んだか、アメーバブログ・ABEMAの立ち上げ、経営チームづくりについてなど聞いていきます。(肩書きは2020年12月11日撮影当時のもの) 藤田 晋 サイバーエージェント 代表取締役 堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
会員限定

ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 前編 なぜ眠れないのか?~
「仕事が終わらないから睡眠時間を少し削ろう…」「業務時間中なかなか集中できない…」「毎日朝起きるのがつらい…」。 あなたはこのような経験をしたことはありませんか? 仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削りがちなのが「睡眠」時間。 実は今、日本社会は世界と比較して「最も眠らない国」だということもわかってきています。 慢性的な睡眠不足は、心身の健康に悪影響なだけでなく、仕事のパフォーマンスにも当然大きな影響を与え、社会全体の経済損失につながります。 このコースでは、基本的な睡眠リテラシーを学んだ後の「問題解決編」として、「なぜ多くのビジネスパーソンは眠れないのか?」について解説していきます。 ▼本コースで学べる主な内容 ・そもそも眠れないことは何が問題なのか? ・眠れなくなってしまう原因とは? 睡眠不足の原因は認知機能の問題にありました。 自身の睡眠不足に対し、正しく「気づき・理解し・行動を変える」第一歩を踏み出しましょう。 ▼関連コース ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~リテラシー編~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/24575c03/learn/steps/53129 ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 後編 どうしたら眠れるのか?~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/4ba981e9/learn/steps/62042 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

大阿闍梨 塩沼亮潤が死の手前で見つけた「生き方」
あすか会議2018 第4部分科会B-1「極限の世界で見つけた人生の歩み方」 (2018年7月7日開催/国立京都国際会館) 1300年間で2人目となる大峯千日回峰行満行を果たした塩沼亮潤大阿闍梨。48キロの山道を1日16時間掛けて歩き、それを千日間に亘って続ける過酷な行の中で、どのような悟りを得たのか。そして、9日間、断食・断水・不眠・不臥を続ける四無行満行という極限の世界で何を見つけたのか。塩沼氏が「創造と変革の志士」へ贈る「人生の歩み方」とは。(肩書きは2018年7月7日登壇当時のもの) 塩沼 亮潤 慈眼寺 住職
無料
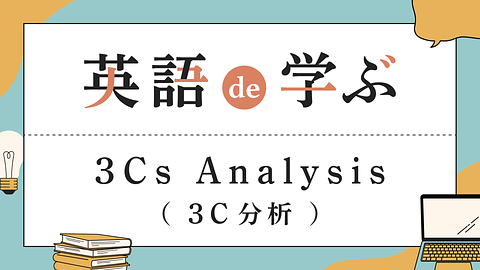
英語 de 学ぶ!3Cs Analysis(3C分析)
このコースでは、グロービス学び放題の英語版である『GLOBIS Unlimited』のコースの中から、ビジネスで役立つ頻出の英語表現をピックアップしています。英語ネイティブの方が実際に見ているコースなので、リアルなビジネス英語の表現を学ぶことができます。 今回のコースは「3Cs Analysis(3C分析)」です。一緒に『英語で』ビジネス知識を学んでいきましょう! ▼今回扱ったUnlimitedコース続きは下記からご覧いただけます 3Cs Analysis https://unlimited.globis.co.jp/en/courses/da5ca962/learn/steps/36362 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
コメント653件
hinadra
耳慣れない横文字のワードが頻出して正直ほとんど理解できませんでした。
動画以前にDXに関する用語から学習しなければ・・・
tomaru-aka
曖昧な意味で捉えていたので、DXを本質から知ることができたのはよかった
inotake
DX推進の中心となることは今までなかったが、一人一人が推進マインドを持つことが求められる状況下、AS ISの再認識がDX推進のため重要であることが再認識出来た。
doragon0611
内容が少し難しいと思いました。
murakami_tpd
DXという言葉の定義を明確に理解しなければ、会話の中でのお互いの理解のミスマッチが生じる恐れがあると感じた
sbsconts
体系的でわかりやすい説明であったため、DXの概念が良く把握できました。また、進まない要因や注意すべき点も認識できました。当講座は、何度も見返し、全ての内容を体得したいと思います。
tomo-tom
難易度が高かったと思いました。
h_inaba
当社もDX推進プロジェクトを作り活動しているが、本質を捉えていないと感じていた。今回の講座では失敗する要因も述べられていて大変参考になった。
oasis_noel
社内でのDXを進めるうえで、単なるデジタル化にならないよう気をつけたいと感じた
tsuyo-taniguchi
私の周囲ではまだまだDX化されていないと感じている。digitizationどまり、むしろデジタル化しただけで仕事は効率化されていないと感じる。仕事のやり方の根本から見直さないといけないと日々反省しつづけている。
erieri
DX推進、大きな課題となっているなかで自分自身は漠然としかとらえられていなかった。
推進するうえでの考え方などが学ぶことができ、今後に繋げられると感じた。
takuma-0614
DXの本質を理解している人はほとんどいないと感じました。だからこそ。これを理解して自分ならどうすればよいかを深く考えるが大事になると思いました。
hiro_migi
職場でもDXをすごく推進されるが、そもそもDXとは何か、何をしたら良いのかが分からなかったので勉強になった。
tiger_singapore
業務でDX推進が重要と理解しました。さらに勉強を重ねて実行に移します
masahito-inoue
DXを難しく捉えるのではなく、利便的に業務の効率化を図っていくものであることを理解した。
f-massa
DXについて差異確認できました。
k_kazz
当社でもDXに取組んでいる。まさしく2025年の壁に対応するためのスタートだ。しかし、失敗するDXプロジェクトの例にあったAs-Isを無視してTo-Beを目指しすぎてはいまいか。現場を知らないゼネラリスト集団が、夢物語を描いていまいか。講義を聞いていて怖くなった。今、私にでいることを考えていこうと思う。
wataru_11
AS ISの再認識がDX推進のため重要であることが再認識出来た。
asrada_no1
DXは業務改善、仕組み改善にとどまらず、ビジネス全体を改革する大きな取り組みであることを意識しながら、顧客と向き合ったり、社内の改革を進めるように意識を高める
konitan1152
なんとなく理解していた内容ではあるが、整理されていて腹落ち感がある講座でした。
今後DXを推進するにあたり、注意事項として考えながら実行していきたい。
goto703
DX推進が進まない理由がふんわり何となくではありますが感じ取ることができました。
理解するところまでは結局行っていないと思っています。
ただ、途中にあったインターフェースのスパゲティ化は体感的にもすごくよくわかり、
闇雲に進めた結果が技術的負債になっているということは分かりました。
201216
改めてDXの基本から学びなおす必要があると感じました
takayama-hokuto
DXの本質と難しさを再認識する動画でした。実際の業務ではデジタル情報が散在しアプリ間の連携が出来ず、DXとは程遠い状況です。今回の動画を参考にDXの推進を検討したいと思います。
isunz_
DXに関しては抽象的な把握程度でありました。使い慣れていないIT用語カタカナも吸収できるよう習得したいと思います。
nnmnn
現状を理解することの大切さを認識できました
hino-katsuhiro
DXプロジェクトを進める上では、AS-ISとTO-BEをしっかりと整理していく。また、プロジェクトのスコープは、システム → 製品・サービス、業務・運用 → 組織・ヒトまでを含んだ中長期の経営改革とし、中長期的な効果創出を訴求して進めていく。
tak_1968
アナログ対応/個別最適化の集合体である現状からの脱却を図るべく、経営トップが旗振り役としてスクラップ&ビルドを実戦する。
5179
この動画以前に用語を学ばなければならないと感じた
everest
単なるデジタル導入にとどまらず、業務や価値提供の在り方そのものを見直し、継続的な変革を主導できるようにしたい。
banana_2225
DX推進はプランの立て方が最も重要で、初期の活動やコンセプトが違っていれば、成功への可能性は高くはならないと思います。
したがって、進める上での初動における議論がとても大事です
kwtsk
知らない言葉が出てきましたが、整理された説明だったので、
今までぼんやりとしたDXのイメージが少しだけクリアになりました。
pontaro-
言葉の本質をしっかり理解せずDXというワードのみで動いてきた感があります。サイロ化、ブラックボックス化、スパゲティ化のいずれにも当てはまるシステム(負債)が負のレガシーとなってきた所以です。そのような反省点から、自社としてあるべき本来の姿をしっかり描き、ステークホルダー含むすべての人に利用価値のあるシステムつくりを進めてきたところです。今後も、引き続き推進していくべき課題であると思われます。
s_tsuboi
DXの本質をしっかりととらえてAS-ISとTo-Beに齟齬が出ないように話したいと思いました。
ukima
DXの背景や目的の理解が深まった。プロジェクト推進では、迷った時には原点に戻って考えたい。
sshirahama
コミュニケーションに役立ちます
ootata
DX推進は、以下の2点がポイントと考える。
①現場レベル:現行踏襲を強い気持ちで変革し、業務改革を実行すること
②経営レベル1:経営者として強いコミットを行う
③経営レベル2:経営改革を踏まえた組織の見直し・変更を行う
ykage
DXは実施することで優位な時代から、実施しないことでリスクとなる時代になっている。
積極的に導入を進める。
t_iky
現在私は体調不良のため、会社を休んでいます。
ようやく自身の体調が回復し、産業医•上司•人事との面談の結果業務復帰が決まりました。
今後も自身がメインとなって関わる業務は変更ありませんが、体調を崩してしまったことによりこれまでと同じ仕事の進め方は難しくなります。
このタイミングで上司より業務のDX化に取り組んでみませんか?との問いかけがあり、私自身も定時内にきちんと業務が回る仕組み•自部門だけでなく他部門からも私たちがお客様のために日々どういったことを行なっているのか?理解と発信「見える化」に取り組んでいきたいと考えていました。
今ある環境下でも「一捻り」することで
何か出来そうな?イメージは持っています。
今がチャンスと捉えて、業務のDX化への一歩踏み出してみたいと考えています。
lily_0611
大枠の話がメインであり、DXの概要を上手く自分の業務イメージまで落とし込めなかった。そもそもシーケンシャルとかビジネス用語の理解が不足していることを痛感。
kiyomi_k
DXの概要や、なぜDX推進に苦戦するのか、DXプロジェクトを進めるうえでの考え方などが学習できた。
今後、お客様サービスや社内でDX推進が活発になってくるため、引き続きDX推進・実行について学びたいと考えている。
chika_ziburi
段階的にDX化することの重要性がよく理解できました。
私はフリーランスとして働いているので自分自身が使うツールなどを会社さんのDX推進に合わせることもあります。社内だけでなく、社外の人にとってもDXリテラシーがないと、世の中のDXは進んでいかないと改めて認識することができました。多くの企業が推進から実行へと移っているところかと思いますが、現時点でも「推進」に苦労している企業も多くあると感じられます。現場のスタッフたちが「推進」の重要性を理解した上で、取り組んでいける体制にしていくことが重要だと感じました。
果たして2025年の崖は多くの企業が乗り越えていけたのでしょうか? また改めてDXについて学んでいきたいと思います。
nuematsu
DXと言う言葉を漠然と捉えていたことが再確認できました。
デジタル技術を活用してサービスやビジネスモデルの「変革」に繋げることを意識していきたいと思います。
技術的負債と感じるところが多々あることから、変革につなげていきたい。
km-ys
当社もシステムのサイロ化や個人に仕事がついて回ってしまっており、技術的負債が大きくなっているように思えました。
kunimako
DXの本質を知ることがきました。これまでデジタル化を推進🟰DXと思ってました。今の職場に当てはめてみると、進んでいない、技術的負債が多く存在します。何から手をつけていけば良いのか、大きなプロジェクト、経営判断が必要だと思います。このままだと競争に負けてしまう。DXがなかなか進まない理由も理解できます。こういった分野のコンサルが必要であり、これから益々伸びるビジネスだとも感じました。
s_uemori
DXの重要性は、昨今よく説かれ、その重要性は理解できます。DXの推進が大事なのは理解するが推進に苦戦するという話は多いようであり、正直、当社もその一つです。本講座ははその推進が進まない理由について言及されていました。技術的負債という概念を使った分析はDX推進を妨げる理由を的確に分析されていました。弊社もそうなのですが、この技術的負債をコントロールすることが組織として理解できない。また、理解したとしてもその優先度を上げられない(あげづらい)領域として映っていることが原因だと考えます。DX導入・推進にはIT技術の分野に精通した人員、組織が必要で、ITリテラシーや情報セキュリティへの理解とその遵守(ひいては経営全般的にかかるコンプライアンス)に対しての理解が不可欠だと考えます。これらが重要だという概念は比較的近年に起こった概念であり、それらの浸透が導入・推進で重要だと考えます。また、これらを進めるスキルを持つ人材の確保と組織の構築が困難(場合によっては経営層がこの領域を理解できない)であることから、経営課題として後回し(後回しになるのは、効果が中長期にならないと発現しないということもあると思います)になることだと考えます。このことが、技術的負債を取り扱えないことに繋がっているのではないかと考えます。正直、自分自身、この領域について、これまで述べた阻害要因を持っていると感じています。以前にリスキリングの振り返りの際に述べたように、まず、この領域での基本的なリテラシーから身に着けていかなければならないと感じました。
nk_55
DX化は社内でも積極的に推進しようとしていますが、それよりもスピード感をもって自ら取り組んで学び続ける必要があると感じています
kojwdrin
DXの本質の基礎理解が深まりました。
cia7880
業務で活用していくには、DXを推進と実行というステージに分解・義を行うことが第一歩である。
yujin_s_ts
As-IsだけにこだわったDX推進になりがちだと感じた。また技術的負債が返済できていないことが、DX推進の妨げになっている。非常に納得できる説明でした。
hirahara_nozomi
システムを導入してどう使うかが重要だと感じました。
mjr-121
DX化に向けた取り組みをしているが、再構築はかなり遠そう。各担当毎にシステムが違うサイロ化もありかなり厳しい状況。
maki4878
会社が段階的にシステムの変更を進めている意味が分かった。コロナが流行り始めた頃に出された「DX推進ビジョン」を改めて読んでみようと思った。
naoshibu
関わるメンバが多くなると思うので、情報と状況を確り共有しながら、中長期的な視点で推進していくことが重要だという事が分かった
asawayama
DXについて、改めて定義・背景を復習させていただきました。ともすると、製品・サービスやビジネスモデルの変革自体に発想が及ばないことがおおく、ゆえに局所的な業務プロセス効率化を積み重ねがちだと感じております。一方、背景としてIT人材不足といった待ったなしの状況の中で、「経営戦略」「業務」「IT」の三角形をバランスよく実現し、段階移行による着実かつリスク分散を図ることが大切だと痛感させられました。常にプロジェクトスコープを大きく捉えつつ、真のDXに到達できるようにしていきたいと思いました。
reiko_09
AS ISの認識が重要であること、サイロ状態であることや、レガシーシステムの絡まりなどが問題でDXが進まないこと、自社に当てはめても思い当たるところが多くあります。これらを一つ一つ丁寧にほどいていくことが重要に考えますが、時には荒療治で変革を進めないと、いつまでたっても進まないものでもあると思います。このバランスの見極めもリーダーがしていかなくてはならないと思いました。
tk_2525
DX推進における本質は....
・DXとは単なるシステム刷新ではなく、技術の選定・運用・返済を通じて競争力を持続的に強化する活動である。
・「見えない負債」と「組織・業務との連動性」をいかにコントロールするかがDX成功の鍵。
kasuya_take
DXという言葉は、今までもこれからもかかわっていく可能性があると思います。
部署内でも、一部、発注の仕組みが変更されました。
今までの仕組みと異なるので、違いに戸惑うこともあるのですが、どういった点に意識して対応していくと良いと思いますか?
twistserve
企業の97%が、DXステージの1段階目であることに驚きました。2025年の壁、という言葉が出ているものの、実際の企業の対応は間に合っていないことが分かります。今回のテーマは、今後働く上で必ずどんな職種でも関わる内容であると同時に、自分の考えも伝えられるようにしておくべきだと感じました。
makiyb
2025年はシステム、物流、建設などの業界で人手不足が深刻化している危機的状況となっているが、DX推進によって、社会の変革が進むターニングポイントになりそう。
kannnai
改めて、市場の変化に対応し勝者となるため、ビジネスモデルの変革を目指す必要があると強く感じました。
ttc_yamamoto-t
そもそもDXとは何かよくわかりました。その中でどのように社内に変革をもたらし、本当のDX化を実現できるか改めて考えたいと思いました。
saki1214
一部でDXと叫んでも会社全体で取り組まないと意味がない。やるのであれば強制的にでも全員参加させなくては…
hasebe_e
意味があいまいだったので、確認できました。
yamazatoy
かなり大掛かりな計画と予算が必要な事だと理解した。
hr_shibasaki
DX化をする必要性を改めて学びました。能力的、技術的にまだまだ未熟ですので、本講座を含め様々な動画や教材で学び知識を習得していきたいと考えています。
sbaba
DXの再定義や2025年の崖について特に興味深かった。まずは、自社の現状を把握し、あるべき姿を設定することが重要だと捉えた。技術的負債は、その後のメンテナンス等の意味だと理解したので、システム構築の段階で将来のことをきちんと考えることも重要だと知った。
h-matsuoka_mjp
社内でもDXとIT化を同じ意味として使用している人が多い気がします。DXについての説明は非常に分かりやすく理解できました。
tosan103
DXの本質を再確認した。
mt-chiba
DXはデジタルトランスフォーメーションだけと思っていたが違った。これからの仕事はますます重要性が増していくのでしっかりと取り入れていきたい
challo
企業の中で起きていることや課題に目を向けながら、DXの本質的な部分にフォーカスをして、推進していく必要があることを学びました
gami1976
バズワードですよね。
いずれなくなる。
nyiu
正直、難しくて付いていけていなかった。
ただ、DX化がIT化にならないようにしたいと感じた。
ka_nabe
DXの本質をとらえる事、今後のビジネスに大事な事を理解しました。
horiuchimasa
守りのDXと攻めのDXが印象的であった。攻めの印象が強かったが、守りをすることで、攻めが出来ることを確認できた。
na_oi
DXの本質を理解することができた。自分の業務でもDXにより業務効率化できないか検討するきっかけになった
teru_0216
DXの本質ということでしたが、正直まだ理解に至りませんでした。反復して視聴し習得へ繋げます。
hiro-tsuji
DXを学び、それをどのように活用していくかがとても重要と感じました。それぞれの業務課題に即したDXを導入し、実践していく事でより効率的な業務を遂行できると感じています。
ma-aoyama
DX化とひとえにいっても、AS-ISの事実とTO-BEの実現を描くとき理想だけではなく、着実にできるように段階を踏まえた移行計画が重要だと思いました。AS-ISを知るとき、潜在課題までしっかり記録可視化しないと関係者が多く存在するプロジェクトでは破綻。関係者の認識に齟齬がないようにしたい。
meet-pie-eating
.................
kai1985
DXを本質から知ることができたのはよかったです。
AS ISの考え方を理解することがDX推進のため重要であることがよくわかりました。
satos1517
DXの概念が理解できた
102kumagai
バズワードに成りがちのDXだが、AsIsとToBeの分解など進めて行くことを学んだ
240497
DXとIT化の違いがよくわかりました。
デジタル技術をうまく活用することで、業務の効率化や業務内容の分析を行ない、
将来的に仕事の変革に資する可能性を見出せることが理解できた。
mayumi_sugahara
DXとは、での解説で理解が深まりました。AIが必要になって来るの明確なのでいち早く活用して行きます。
ota7909
技術的負債という考え方は納得できた。DXを手段として捉えないよう引き続き啓蒙していきたい
ashi_kubi
自社で利用しているシステム、業務プロセスをレガシーとなっていないかどうか意識する必要がある。
akira_nagahama
as isとto beをバランスよく、かつ具体的に作成したうえで、DXのソリューション構築をすすめていきたい。
k2hirata
本日を知ることで自分の置かれている状況ややるべき事が可視化されました。
s_hym
最近、お客様により沿いDXの本来的な取組みや提案ができていないと改めて思いました。
AS-ISからのTO-BEはまさにそのとおりで、AS-ISに引っ張られてしまうことが多いのが、日本企業の特色のように感じています。
そういった中で、抜本的な、人モノ改革を推進するために、大胆な提案ができるといいなと思いつつも、その成功体験や事例が、お客様のビジネスモデルに近いところで、うまく拾い上げ、おみせできていないことにジレンマを感じます。
もっと、目線を上げ、国内にとどまらず、世界的な成功事例の収集に励みたいと思いました。
mouri_kaz
システムのサイロ化が正に起こっているのでとても危機感を感じました
you_maki
DXの現状と、今後の課題について学ぶことができた。
tauharu
正直言って難しい。ただし自身のDX認識が短略的であったことは理解した。
hkt050
DXを推進して既存業務の効率化を図り時間を創出して行く事が重要
kenichiro0319
DXについて理解が深まりました
yo403
業務について、現状維持での進行ではこの先成り立たない。
変革を意識して、DXの推進をしなければならないと考えます。
現状の状態を分析して、課題抽出しながらDXの思考を利用や意識して今後の業務推進につなげたいです。
pje253
DXという言葉は良く使うが、本質的なところは理解できていなかったと思うので、再確認できた
kokada21
DXという言葉はよく耳にするが、具体的な意味までは分かっていなかったが、本講座で少し踏み込んだ内容だったので、取っ付きにくかったが、抽象的に捉えていたものが少し形にはなりそうな気がした。
toda-taka
DXに関する基本的な知識について学べました。
bongore
守りで得た余力を活用すると言う意識が非常に重要だと言うことを感じました。また、既存のシステムが全て悪いわけではなく、本質を見失うと本末転倒となることが理解できました。
mt-kimura
デジタル化とDX化の違いをしっかりと理解しないといけないなと思った