
0:59:48
割引情報をチェック!

AI BUSINESS SHIFT 第8回 機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第8回です。 第8回「機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル」では、AIが営業現場にどのような変化をもたらしているのか、営業担当者・営業マネージャー・組織としての役割や戦略が、AIによってどう進化していくのかを、営業プロセスの分解や実際の現場事例を通じて学びます。 ■こんな方におすすめ ・AIを活用した営業活動の最新動向や現場のリアルを知りたい方 ・営業現場の変化に直面している営業マネージャー・現場リーダーの方 ・AI時代における営業戦略や営業マネジメントのあり方を学びたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年2月制作)
会員限定

マネジャーのための仕事の任せ方
「仕事を任せると失敗が怖い」「自分でやった方が早い」マネージャーとしてメンバーやチームの力を引き出しながら成果を上げるには、どのように仕事を任せていけば良いのでしょうか? 変化の激しい時代において、マネージャーとして成果を上げ続けるためには、メンバーの個性や特性を理解し、それに合わせた効果的な任せ方を身につけることが重要です。このコースでは、ソーシャルスタイル理論を活用してメンバーごとに最適なアプローチを学びます。「任せる力」を高めることで、チーム全体の成長を促進し、自身のリーダーシップを発揮できるようになっていきます。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2024年12月制作)
会員限定

AI時代の個人力
AIが仕事や社会の前提を変え続ける今、最も求められるのは「他者に代替されない個としての力」“個人力”です。 本コースでは、澤円氏の著書『個人力』をもとに、AI時代をしなやかに生き抜くための「前向きな自己中戦略」を学びます。 テーマは、「Being(ありたい自分)」を中心に据え、自ら考え(Think)、変化し(Transform)、協働する(Collaborate)ことで、自分らしい価値を発揮していくこと。 リスキリングやAI活用が叫ばれる今こそ、スキルより先に“自分の軸”を問うことが重要です。 あなたは何を大切にし、どんな未来を描きたいのか? このコースは、あなたが“ありたい自分”として生き、キャリアをデザインしていくための思考と行動のガイドになります。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年11月制作)
会員限定
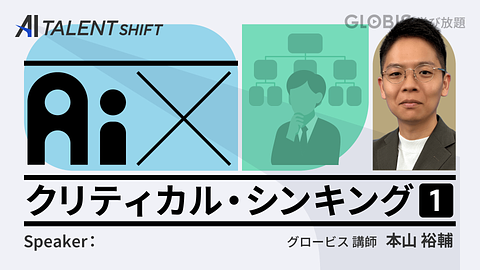
【AI×クリティカル・シンキング】①イシューと枠組みでプロンプトを磨く
生成AIから期待する回答を引き出せず、試行錯誤を重ねていませんか。 本コースでは、生成AI活用の質を高める鍵として、クリティカル・シンキングの視点からイシュー設定と枠組みを押さえる重要性を解説します。 目的に直結する問いの立て方や、プロンプトに落とし込む際の実践ポイントを具体例とともに学ぶことで、AIをより思考のパートナーとして活用できるようになります。 生成AIを業務で使い始めた方から、活用を一段深めたい方まで、再現性あるプロンプト設計を身につけたい方におすすめの内容です。 さらに学びを深めたい方は、こちらも合わせてご覧ください。 【AI×クリティカル・シンキング】②AIの弱点との向き合い方 https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/cdfe41e3/learn/steps/62198 ※本コースは、AI時代のビジネススキルを学ぶ「AIタレントシフト」シリーズの一環として提供しています。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
会員限定

リーダーの挑戦⑤ 藤田晋氏(サイバーエージェント代表取締役)
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第5回目のゲストは、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋氏。起業の理由、経営をどうやって学んだか、アメーバブログ・ABEMAの立ち上げ、経営チームづくりについてなど聞いていきます。(肩書きは2020年12月11日撮影当時のもの) 藤田 晋 サイバーエージェント 代表取締役 堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
会員限定

ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 前編 なぜ眠れないのか?~
「仕事が終わらないから睡眠時間を少し削ろう…」「業務時間中なかなか集中できない…」「毎日朝起きるのがつらい…」。 あなたはこのような経験をしたことはありませんか? 仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削りがちなのが「睡眠」時間。 実は今、日本社会は世界と比較して「最も眠らない国」だということもわかってきています。 慢性的な睡眠不足は、心身の健康に悪影響なだけでなく、仕事のパフォーマンスにも当然大きな影響を与え、社会全体の経済損失につながります。 このコースでは、基本的な睡眠リテラシーを学んだ後の「問題解決編」として、「なぜ多くのビジネスパーソンは眠れないのか?」について解説していきます。 ▼本コースで学べる主な内容 ・そもそも眠れないことは何が問題なのか? ・眠れなくなってしまう原因とは? 睡眠不足の原因は認知機能の問題にありました。 自身の睡眠不足に対し、正しく「気づき・理解し・行動を変える」第一歩を踏み出しましょう。 ▼関連コース ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~リテラシー編~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/24575c03/learn/steps/53129 ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 後編 どうしたら眠れるのか?~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/4ba981e9/learn/steps/62042 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

大阿闍梨 塩沼亮潤が死の手前で見つけた「生き方」
あすか会議2018 第4部分科会B-1「極限の世界で見つけた人生の歩み方」 (2018年7月7日開催/国立京都国際会館) 1300年間で2人目となる大峯千日回峰行満行を果たした塩沼亮潤大阿闍梨。48キロの山道を1日16時間掛けて歩き、それを千日間に亘って続ける過酷な行の中で、どのような悟りを得たのか。そして、9日間、断食・断水・不眠・不臥を続ける四無行満行という極限の世界で何を見つけたのか。塩沼氏が「創造と変革の志士」へ贈る「人生の歩み方」とは。(肩書きは2018年7月7日登壇当時のもの) 塩沼 亮潤 慈眼寺 住職
無料
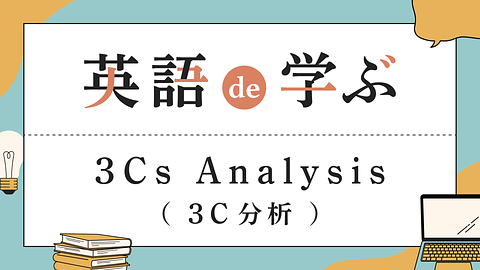
英語 de 学ぶ!3Cs Analysis(3C分析)
このコースでは、グロービス学び放題の英語版である『GLOBIS Unlimited』のコースの中から、ビジネスで役立つ頻出の英語表現をピックアップしています。英語ネイティブの方が実際に見ているコースなので、リアルなビジネス英語の表現を学ぶことができます。 今回のコースは「3Cs Analysis(3C分析)」です。一緒に『英語で』ビジネス知識を学んでいきましょう! ▼今回扱ったUnlimitedコース続きは下記からご覧いただけます 3Cs Analysis https://unlimited.globis.co.jp/en/courses/da5ca962/learn/steps/36362 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
コメント3760件
akatsuki_89
品質はなるべく高くすべき、ボトルネックはなるべく人を投入して解消すべき、稼働率はなるべく高くすべきと考えていたが、そうとは限らず、総合的に評価して全体としてバランス良いシステムを作るべきという事が新鮮な考え方であった。無理して稼働率を上げるのではなく、ボトルネックに合わせて無理なく生産を調整する事も必要。
higuchi_561
待ち時間の平準化は、どのように考えるのが良いのか、これが、アイデアの出しどころではあると理解はするのですが、参考事例が欲しいです。。
167983
Qualityを「質」ではなく「正確性」として解説をしている点が新しい気付きであった。顧客が求める質にフィットさせること(正確性)が重要であると感じた。
telme-tora
機会損失防止の為にはただただ投資をしてキャパを増やせという要求がありますが、今回の講義を学んで、そうした考えはおかしいと感じていた部分が論理的にクリアになり、今後の設備投資の方向性が見えたように思います。
saito-yoshitaka
必ずしもボトルネックが悪ではなく、戦略にマッチしているかが重要となる。
hiro_yoshioka
・全体生産性の観点では、どこがボトルネックになっているのか?を意識するうようにしたい
・全体を考えた上で、単工程ごとに稼働率を上げるべきかなど、QCDFのバランスを考えるようにしたい
・全体の方向性を考える際の大前提として、経営理念に実現が最優先である
kenfuru
具体的な状況と数値で稼働率と生産性の関係が、どのように経営に影響するかを関係者に説明するのに役立ちそう。
yosiaki
省力化の手段として機械化がまず思い浮かぶが、その前にきちんとボトルネックと経営戦略に基づく目標値を理解した上で判断したい。
jumbo_tanuki
オペレーション戦略って言われても何もイメージできませんでしたが、ぼんやり見えてきました。非常に大事なものであることは理解できました。
monkey_88
教育商材としての学びが大きい
eastvalley108
オペレーショナル・エクセレンスに貢献する4要素の整理、変動を少なくすることで待ち時間を短縮できること、ボトルネックをなくすことが最重要ではない、の3点を吸収できた。
j-o
事例がわかりやすく理解しやすかったです。
emi084
オペレーション戦略の基礎となる部分を知ることができた。
まだ自分の業務でどのように活かせるかは想像が出来ていないので、後半を見ながら考えていきたい。
hiromi-s
稼働率と生産性の違いが良く理解できた。また、ボトルネックを解消するかどうかの判断は経営戦略に基づいて決めるという事も印象的な話だった。ただ、実際の企業ではQ.C.D.Fは部門分けされている事が多い為、それぞれの方向性で仕事をしているのが現状ではないかと思った。
kzhr2358301
Q(正確性)D(スピード)C(コスト)F(柔軟性)を意識してボトルネックを探し、生産性が上がるような稼働率を実現することを学びました。
0829koba
稼働率と生産性のバランスをとることが大事だと学んだ。
test_
オペレーション戦略を実際に検討するにあたり、ボトルネックは何なのか、生産数量とコストの関係はどうなっているのか(規模の不経済となるのはどこからか)、必要な生産数量の年間での推移はどうなっているのか、、、、等々、非常に多岐にわたる内容を考慮しなければならないことを再認識した。すべての最適化が難しいからこそ、オペレーション戦略が競争優位性になりうるのだろう。
raimuku
QCDF勉強になりました。
firecat
業務設計のQCDFに活かす
hiroaki_kameya
稼働率は上げれば上げるだけ良いと思っていたが、そうではなく経営戦略との合致が必要だと目からうろこが落ちる感覚でした。
suya-hiro
オペレーション戦略を考えるうえで、幅広い視野がないと、偏った考えのみで戦略を立ててしまい、結果として現実的でないオペレーション戦略となってしまう可能性が高いと思う。
kaki_077
ボトルネック、全体最適な視点を意識して業務に取り組みたい
inada-makoto
必ずしもボトルネックが悪ではなく、戦略にマッチしているかが重要となる。
washitaka
オペレーション戦略を意識し、稼働率より生産性を高めたいと思う
cat94900
優れたポジショニング戦略であっても実行できなければ意味がない。優れたオペレーショナル戦略によって戦略は実効力を持つ。オペレーショナル戦略で重要なポイントは、正確性、コスト、スピード、柔軟性のQCDFである。
ma-s
オペレーション戦略を考えることは重要ということを知れました。
また模倣が難しいオペレーション戦略が他社へ競争優位性を持てる。ただしその戦略をどう練っていくのか、経営戦略とオペレーション、マーケットなど3つフィットするのが重要。またボトルネックは解消すれば良いというものでは無い、戦略の数値次第で解消する必要が無いというのは勉強になりました。ライン生産、セル生産の向き、不向きがあることは勉強になりました。稼働率も高すぎてもダメ「規模の不経済」に陥ることもある。ただし生産性は高くする必要がある。待ち時間を減らす平準化は色々な条件が重なり合うので相当に難しいと感じました。
j_shiomi
模倣が難しいオペレーション戦略により、業務スピードアップの仕組みづくり、またブランド力を高め、競争優位性を築く。
良い商材があれど、良いオペレーションがなければ売り逃しなど発生する可能性がある。
ボトルネックを把握して、効率の良い業務フローを作ることで売上拡大に繋がる。
keisuke--
業務の稼働率 生産性についても考えることができるのか転用して効率を上げれるか検討してみます
kanasuma
同じ生産工場であっても受注量の違いによって生産方式を変えることも重要な判断であると思います。多品種少数と同一品種大量生産では生産方式をライン生産とセル生産に分けたほうが良いと思います。
複数人で生産活動を行う場合は、一人当たりの持ち時間の平準化を図ることが大事だと思います。
isshiki0927
オペレーションを意識したい。
ichimaru-yuji
経営戦略とオペレーション戦略とをフィットさせることが重要と学びました。 ボトルネック解消に注力しがちですが、本当にボトルネックを解消するべきなのかの見極めることが重要であることが、新たな気づきでした。
tomoyatom
オペレーショナル・エクセレンスに貢献する要素を意識すれば、各社の戦略が見えてくる。
1123
幅広い視点でよく考えること
mikitohashima
ボトルネックを見直したい。
oka-shigetoshi
オペレーション戦略による業務の効率化を図るため、3つのフィットを意識したオペレーションを行いたい
marron_33
専門職の稼働率はひとすじなわではいきません。ライフイベントやフィジカル休業も考慮にいれつつ、顧客ニーズにどれだけこたえられるモチベーションを維持できるか。これができるのは私くらいですが。
fumiyamaeda
稼働率と生産性の違いを正しく理解できた。
ootsuka-nami
フレームワークでしっかり分析できても、経営戦略を実現するには、オペレーション戦略が重要だと思った。サンドイッチによる例は、わかりやすかった。
iiho
経営理念や経営戦略を達成するためには、ボトルネック、稼働率、生産性といったオペレーションの基本を学び最適に組み上げていくことが有効と感じた。
9045739
計画をやり切れないのは実行する力(オペレレーション力)への考慮が足りず、キャパシティを超えるものになっていることがあり、現場が初めから実施していないことがありました。今後はボトルネックを意識し、キャパシティを拡げること、アウトプットを意識した生産性を考えるようにします。また、機会損失の低減のため、平準化への工夫をしていきます。
mouri_kouki
ボトルネックはなるべく人を投入して解消すべき、稼働率はなるべく高くすべきと考えていたが、そうとは限らず、総合的に評価して全体としてバランス良いシステムを作るべきという事が新鮮な考え方であった。無理して稼働率を上げるのではなく、ボトルネックに合わせて無理なく生産を調整する事も必要。
yama460310
生産性を上げることは重要だと理解しました
nowman
ボトルネックについて、解消すればいいものと考えていたが、求められる生産性の上限があるため、インプットやアウトプットを拡大/縮小することで全体最適を考えるべきと理解した。
その他、稼働率や待ち時間など、新しい知識も得ることができ、有用だった。
1727
オペレーション戦略を考える際には、ボトルネックが何か、QCDFをわけて考え、生産性を重視した戦略立案を行いたい
mn_s
業務の生産性、オペレーション戦略は、担当業務のコールセンター運営におけるオペレータの配置、対応可能なスキル(多能工度)にて日常的に意識し向上に努めている内容である。
今回、経営戦略の一貫としオペレーション戦略を学べ、知見を広めることができた。
10001657
ボトルネックの見極めが大切だと思った
1002tofu
稼働率や生産効率を考える上で、各プロセスを分析し、ボトルネックの有無を確認することが必要。
一方で、必ずしも稼働率が高いことがよいこではなく、各プロセスの分析や販売状況も踏まえながら最適条件を探すことが必要。各部署の連携が必要になる。
kobashigawa
稼働率は高ければいいものではなく、生産性を見ながら調整することが必要である。
cs1960
稼働率の理解は深まったが色々な対策がある事に気付いた。
ishikaw
品質はなるべく高くすべき、ボトルネックはなるべく人を投入して解消すべき、稼働率はなるべく高くすべきと考えていたが、そうとは限らず、総合的に評価して全体としてバランス良いシステムを作るべきという事が新鮮な考え方であった。無理して稼働率を上げるのではなく、ボトルネックに合わせて無理なく生産を調整する事も必要。
sk_tp
ボトルネックの解消が生産性が向上には欠かせないことが分かった。
kh_krmt
▽学び
・オペレーション戦略とは提供価値のベースとなるQCDFを実現することで、戦略貢献をすること。
・稼働率を上げることだけを考えて、アクションバイアスに気をつける。生産性に目を向けることが大切
・すぐれた戦略に加えて、すぐれたオペレーション戦略がある場合にこそ競争優位が築ける。
▽置き換え
・組織デザインとして多能工かしやすいため、意図的にライン生産方式を検討していく
・売上における商談頻度や商談相手での生産性に着目して、商談座組の効率化を図っていく
s-sanada
業務を計画する際、オペレーション戦略や稼働率、工程を意識し計画することが重要だと学んだ。稼働している業務については、日々見直しを行い、ボトルネックの特定、業務全体の稼働率等を確認・検討し、最適化することを実施していきたい。
sakaki_tsuzuki
稼働率や生産性など言葉としては知っていても、それぞれの意味合いや関連性を考えると、
今までは気にしていなかったことに気づけました。
業務をこなすにあたり、先にアウトプットの必要な内容を確認し、
無駄の出ないよう稼働率を調整し、生産性を高めようと思います。
yuji-ike
私の会社ではライン製造であるためどこがボトルネックになっているか
探し出し改善していく事が重要だと思いました
tcs90208
製造業の勉強になった
tkomo
オペレーション戦略について理解できた。
smartaccess
業務を平準化できるよう待ち時間を減らしストレスの少ないオペレーション戦略で持続的成長を遂げる
safuru
オペレーション戦略について何も知らなかったので基本がわかってよかった。
tomoko45
ボトルネックを見つけることが難しいと感じましたり
h-rui-taka
工場・店舗経営に携わってなく、営業職のリーダーなので、各メンバーの外出時の訪問数やルート、訪問目的などに置き換えて感がるようにしました。稼働率を行動率、生産性を訪問率にまた、訪問ルートなど、時にボトルネックになることもあるので、いろいろ考えながら効率的な営業活動を行えるようにする。
taffu-licht
オペレーションの重要性を学んだ。ボトルネックが一つのポイントになることが
興味深かった。
ajitamacha-shu-
稼働率と生産性をそれぞれ正しく理解した。製造工程の改善に活用したい。
tomo2050
オペレーションの概要がわかった。
uno830
稼働率は高ければ良いものではなく、生産性を上げることが重要であるということは大切なことだと理解できた。オペレーション戦略をしっかり立てることでより効率的に利益創出ができる。
yukymura
ボトルネックの解消という課題に対する対策が活用できそうです。
shimazawa
1人での仕事がほとんどです。中でも事務処理を如何に効率的に行えるか、良いオペレーションによって解決していこうと思います。
fufufufufu
待ち時間の考え方が参考になった。いかに変数を減らすかについて意識し業務に活かす。
miyagata
総合的なバランスが大切なのだと改めて理解できた
igoman
過剰品質はいらない。ボトルネックは必ずしも悪では無く、戦略にマッチしているかどうか。待ち時間をコントロールする。
junko-m-n
生産部門ではないが、ボトルネックや生産性の考え方は、人員や業務量を見て普段の業務でもいかに効率的に進めるかを考えるうえで生かすことができると思う。
matsumym
オペレーション戦略について学んだ。
オペレーション戦略とは、経営戦略から要請される顧客への提供価値のベースとなるQuality、Cost、Delivery、Flexibilityを実現、貢献することである。模倣が難しいオペレーション戦略でこそ、競争優位性を示すことができる。
オペレーションは、経営戦略、マーケット、オペレーション同士と3つそれぞれがフィットすることが重要である。
業務の流れにおいても、最もキャパシティが小さく、全体の処理能力を決める部分がボトルネックである。ボトルネックを解消すべきかどうかは戦略に照らして考える、戦略からの要請次第である。また、オペレーション戦略は、アウトプットの最適化、プロセスの最適化、インプットの最適化の順に考える。
ガントチャートでプロジェクトの全体像を把握し、リソース配分を最適化することが重要である。生産方式によってアウトプット量や柔軟性が異なる商品の特性によって適切な生産方式(ライン生産方式、セル生産方式)を選択する。
稼働率は、忙しさの指標であり、稼働率が高いと規模の経済性が働く。ただし、一定数を超えると規模の不経済が発生する。高ければ高いほど良いとは限らない。
生産性は、どれだけ効率よくリソースを価値い転換したかを表す指標であり、アウトプットをインプットで割って算出する。高ければ高いほど良い。
顧客を待たせることにより、機械損失が発生する。一方、待ち時間を減らすためにキャパシティを増強するには、コストがかかる。双方のトータルコストが最小となるようバランスをとることが重要である。なお、顧客の来店タイミングやサービス提供時間の変動が大きいと待ち時間は長くなる。キャパシティの拡大やサービス提供時間の短縮だけでなく、平準化についても考慮する必要がある。
b15645yn
新卒でオペレーションやっとったけん、ばり納得した😤ワイの会社解決すべき課題多スギィ😤
tommy_8415
商品開発業務においてもいかにボトルネックを減らすかが重要である。
ka_suzuki0916
Qualityを「質」ではなく「正確性」として解説をしている点が新しい気付きであった。顧客が求める質にフィットさせること(正確性)が重要であると感じた。
hiraoka_yuzo
稼働率だけに目を向けてはいけない事が分かった。場面による対応が必要である。
ma-na-bu
オペレーション戦略は初めて聞く話で有用な講義だった。
4349
機会損失を減らすにはどうしたらいいですか?
cha86223
オペレーション戦略の概要を知ることが出来ました。事例がとてもわかりやすかったです。自分の業務へどのように繋げるか考えていきます。
kita-kawa
業務におけるボトルネックを把握し、ライン生産かセル生産のどちらを適用するかで生産力に大きく関わる事が理解できた。活かしたい。
kenji_maki
全体最適を意識し、ボトルネックを減らす事に取り組む。
kei_s_y
ボトルネックをきちんと見極めることで、最適な対策を考えることができることがわかった。また、稼働率は高い方がいいと思っていたが、不経済にならないように注意する必要もあると学んだ。
n_kawase
企業戦略に沿ったオペレーション戦略を行っているが、新たなオペレーション戦略を検討する前に我々のオペレーション力のボトルネックとなる部分は何かよく吟味し、そのボトルネックを変えることで生産性の向上につながるか真剣に考える必要性を感じた。
hill_book
稼働率の向上について注目してしまうが、生産性も考慮する必要があることを改めて理解できました。
ボトルネックの解消方法も多面的に考えることで、より最適な対応策を実施できるように普段から考えるようにできればと思いました。
tomoyann2023
稼働率が高いほど、生産性が上がると認識していました。
tarotaro_zzz
オペレーションは戦略に基づいて最適化すべき、という点は常に意識しながら計画を立てたいと思います。
また、自社の場合、戦略での観点では同業界で同じような戦略を取っているケースも多く、オペレーションで差別化し他社の参入障壁を上げるという方法が重要だと気付きました。
k_dashu
変動をどのように、抑えるかをもっと知りたいです。
gin04
稼働率を上げたとしても生産性向上には必ずしも繋がっていかないことが理解できた。
また、ボトルネックは必ずしも悪影響を及ぼしているのではなく、他の工程に余剰が生じている可能性もあると考えることが大事であるとわかった。
na-ma
何気なく業務で行っていたことが言語化されて良い振り返りになりました。
10391
稼働率と生産性の両立が大切ですね。 分けて考えるよりも、俯瞰して考える事が重要だと思った。
moveon-s
オペレーションとは骨格の重要な中枢的な無為の必然的なことだと思います、より重要度を感じオペレーションの問題点・効率化に取り組みます。
cd_shouta
稼働率の向上だけを求めず、経営方針や生産性の向上と整合性を合わせながら、オペレーションの流れを設計する必要があることに気づけて良かった。
ikuta_yuusuke
待ち時間、繁閑はネックです。
9032197
オペレーション戦略は、QCDFを意識して、ボトルネックを見つけ、生産性を向上することが大事だと認識しました。
j_nagashima
平準化により機会損失を減らすことでボトルネックを解消することができる。
tsp
全体のアウトプットはボトルネックが決めると新たな気づきになりました。
sk114
オペレーション戦略において、具体的な事例など分かりやすく理解できた。特にボトルネックなど自分だけの仕事の効率化は見ているが俯瞰したとき全体の把握がないと稼働率や生産性などすべてに影響してくるものだと感じた。
y_i-0
「ボトルネックはとにかく解消」「稼働率を上げる事が絶対」という考えを見直すきっかけとなった。
1207kobayashi
稼働率、生産性の重要性を認識できたが、販売数も考慮することも注視していきたい。
jk0521
qcdfを意識して業務に活かしていきたい。