
会員限定
ゆでガエル現象 ~環境変化がゆるやかな時、人や組織が陥る状態~
ゆでガエル現象とは、人や組織が、急激な変化には気がつきやすいのに対し、ゆるやかな環境変化には気がつきにくく、対応が遅れる現象をいいます。 企業、社会など、実はどこでも起きる可能性があるゆでガエル現象について、どのような場合に起こりがちなのか、どうしたら防ぐことができるのか、事例とともに学んでいきます。
割引情報をチェック!
すべての動画をフルで見よう!
初回登録なら7日間無料! いつでも解約OK
いますぐ無料体験へ
VUCAとも言われる変化の激しい現代において、これまでと同じビジネスをしていてよいのだろうか?と考えることはありませんか。
あるいは、変わらねばならないと感じていても、その必要性を周囲に理解してもらえない…なんてお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
そんなあなたにご紹介したいのが、変化に適応する経営戦略、「ダイナミックケイパビリティ」です。
今回は、その名のとおり既成概念から脱し新たなスタンダードでクリエイティブやコミュニケーションを生み出すNEW STANDARD株式会社の久志氏に、ダイナミックケイパビリティとは何かとその重要性について身近な事例から語っていただきました。
歴史上にも「生き残るのは強い種ではない。変化に適応できる種だ」という考え方があるように、変化の激しい時代をいかに生き抜くかを考えるにあたり、自社の変革のヒントを掴みましょう。
※本動画は、公開時点の情報に基づき作成したものです(2022年12月公開)
久志 尚太郎
NEW STANDARD株式会社 代表取締役
「この世界は、もっと広いはずだ。」をパーパスに、創作、経営、研究を行う。デザイン思考や意味のイノベーションが専門。外資系IT企業やソーシャルアントレプレナーを経て、2014年TABI LABO(現: NEW STANDARD株式会社)を創業。
(肩書きは2022年8月撮影当時のもの)

会員限定
ゆでガエル現象 ~環境変化がゆるやかな時、人や組織が陥る状態~
ゆでガエル現象とは、人や組織が、急激な変化には気がつきやすいのに対し、ゆるやかな環境変化には気がつきにくく、対応が遅れる現象をいいます。 企業、社会など、実はどこでも起きる可能性があるゆでガエル現象について、どのような場合に起こりがちなのか、どうしたら防ぐことができるのか、事例とともに学んでいきます。

会員限定
【AIと学ぶ】事業を生み出す5つの思考原則
新しく事業を立ち上げたいと考えているけど、「そもそも何から始めれば良いのかわからない」「思いついたけれど自信がない」「失敗したらどうしよう」など気が重くて最初の一歩が踏み出せないという方も多いのではないでしょうか。 そんな方にご紹介したいのが、新規事業を立ち上げるうえで役に立つ「5つの思考原則」です。これは実際に起業をする方だけでなく、組織の中で新たな事業を立ち上げたい方や新しい取り組みをされたい方にも役立つ考え方です。 楽しいストーリーを通じて「5つの思考原則」を学び、ぜひ新たな事業の立ち上げにチャレンジしてみてください! ※「AIと学ぶ」シリーズでは、OpenAIが提供する「ChatGPT」を活用し、グロービスの教育メソッドや幅広い社会人教育の知見を反映したフィードバックを受けられます。 ※AIによるフィードバック機能は現在、WEBブラウザ版のみで提供されています。

会員限定
現状維持バイアス ~変化を伴う選択に対処する~
これまでのやり方を変えなくてはならない時、また何かを手放さなければならない時など変化に直面した際に、よほど強い動機がない限りは「今のままが良いかもしれない」といった躊躇する気持ちや、漠然とした不安を感じることはありませんか? このコースでは、現状維持を望む人間の考え方の傾向である「現状維持バイアス」について紹介します。こうしたバイアスから完全に逃れるのは難しいものですが、そのメカニズムを理解することで、より良い選択ができるように学んでいきましょう。 ☆関連情報 フレームワークでニュースを読み解く、日経電子版の記事もぜひご覧ください。 「伊藤忠は原則出社に 在宅ワーク定着の壁とは」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61074900S0A700C2X12000/?n_cid=DSPRM5277

会員限定
価値を作るDX デジタライゼーションに必須のユーザーインタビュー方法論
DXには2種類あることをご存知ですか? ひとつはプロセスをIT化するデジタイゼーション、例えばFAXをEメールに代えるようなデジタル化のことで、もうひとつがデジタル技術を活用して新たな価値を創造するデジタライゼーションです。 いま世の中で必要とされているのは後者のデジタライゼーションですが、デジタライゼーションを進めるためにはユーザー起点で課題を発掘する必要があります。 ユーザー理解を深めるために有効な手法のひとつが、ユーザーインタビューです。 今回は、その名のとおり既成概念から脱し新たなスタンダードでクリエイティブやコミュニケーションを生み出すNEW STANDARD株式会社の久志氏に、ユーザーインタビューでユーザーのインサイトを探るコツを語っていただきました。 「なぜ?」ではなくあくまで行動を深ぼる手法を、ぜひ実践に生かしてください! ※本動画は、公開時点の情報に基づき作成したものです(2022年12月公開)

無料
ブロックチェーンが生み出す未来~國光宏尚×平将明×内藤裕紀×瀧口友里奈
G1サミット2023 第4部分科会T「ブロックチェーンが生み出す未来~」 (2023年3月18日開催/北海道ルスツリゾート) 2021年以降突如として大きな注目を集めたWeb3だが、その本質は15年ほど前に誕生したブロックチェーンの技術だ。固有の価値をブロックチェーン技術で証明するNFTや、分散型自律組織/DAOといったテクノロジーはこれからいかなるサービスを生み出していくのか。ブロックチェーンというテクノロジーによっていかなる世界が拓けるのか、その実態を探る。(肩書きは2023年3月18日登壇当時のもの) 國光 宏尚 株式会社フィナンシェ 代表取締役 CEO 平 将明 衆議院議員 自由民主党広報本部長代理 兼 web3プロジェクトチーム座長・AIの進化と実装に関するプロジェクトチーム座長・衆議院原子力問題調査特別委員会筆頭理事/自由民主党東京都支部連合会政調会長 内藤 裕紀 株式会社ドリコム 代表取締役社長 瀧口 友里奈 株式会社セント・フォース 経済キャスター/東京大学工学部アドバイザリーボード/SBI新生銀行 社外取締役 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年1月公開)

01月03日まで無料
マンガで学ぶAI入門⑥メール・ブログ作成
メールやブログの文章作成に時間がかかりすぎて、困っていませんか?ChatGPTやGeminiを活用すれば、効率的かつ丁寧な文章が短時間で完成します。「初手AI」がポイントです!文章作成に苦手意識がある方、AIを業務に取り入れたいすべてのビジネスパーソンにおすすめです。 ▼関連コース GPT-5 働き方を変革するAI活用講座① https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/d8d3f379/ GPT-5 働き方を変革するAI活用講座② https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/c36ffd56/ Gemini AIでブログ記事を書こう https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/125d199b/ Gemini AIでランディングページを作ろう https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/ee916b22/ ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
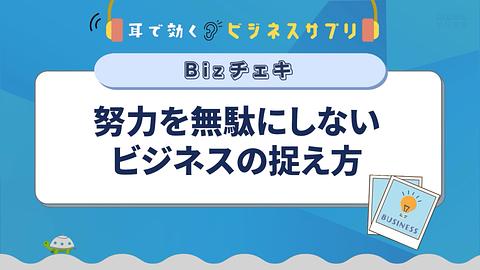
01月03日まで無料
努力を無駄にしないビジネスの捉え方/耳で効く!ビジネスサプリ Bizチェキ
1日5分で気軽に耳だけで聴いて学べる「耳で効く!ビジネスサプリ」。 Bizチェキのコーナーでは、好きなものにビジネスの視点で焦点を当ててお伝えします。本コースは日本最大のビジネススクール グロービス経営大学院による、ビジネスパーソンが予測不能な時代であっても活躍のチャンスを掴み続けるヒントをお伝えするVoicyチャンネルからの転載コンテンツです。意識しておくべきビジネススキルやキーワード、今後の時代のキャリアの考え方などを、1日5分で気軽に聴いて学べます。 Voicyチャンネルはこちら https://voicy.jp/channel/880 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月公開)

無料
グローバル展開を目指す経営戦略~アジアに攻め込むプロダクト戦略・GTM戦略・組織戦略とは~鈴木隆宏×十河宏輔×松本恭攝
G1ベンチャー2023 第3部分科会O「グローバル展開を目指す経営戦略~アジアに攻め込むプロダクト戦略・GTM戦略・組戦略とは~」鈴木隆宏×十河宏輔×松本恭攝 (2023年6月11日/グロービス経営大学院 東京校) グローバル市場への進出成功の要諦とは何か。異なる文化、異なる市場環境に対応するためには、高度な経営戦略が求められる。プロダクト戦略、市場進出戦略、組織戦略、それぞれにおけるベストプラクティスとは。アジア市場に焦点を当て、グローバル展開を目指す成功の鍵となる要素を深堀りする。(肩書きは2023年6月11日登壇当時のもの) 鈴木 隆宏 Genesia Ventures,Inc. General Partner 十河 宏輔 AnyMind Group株式会社 代表取締役CEO 松本 恭攝 ジョーシス株式会社 代表取締役社長 ラクスル株式会社 創業者会長 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月公開)

会員限定
ロジックツリー ~物事を把握する「分解」の考え方~
ロジック・ツリーとは、モレなくダブりなく(MECE)を意識して上位概念を下位の概念に分解していく際に用いられる思考ツールです。 問題解決で、本質的な問題がどこにあるのかを絞り込む場面や本質的な課題に対して解決策を考える場面で活用できます。 ※2020年3月30日、動画内のビジュアル、表現を一部リニューアルしました。 理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
MECE ~抜け漏れなく分解・構造化して考える~
MECEとは、ある物事を「モレなくダブりなく」切り分けた状態のことです。例えば年代別など、全ての人がその切り分けのどこかに属するようにします。MECEは論理思考の基本で、物事を分解し、構造化する際に役立つ考え方です。 例えば、状況を調べて問題箇所を特定する必要がある場合に、いくつかのポイントに分解して考えることが重要になります。その際に、モレやダブリなく分解することができれば、分析や問題解決の効率性が高まります。 ロジックツリーやマトリックス、あるいはその他のフレームワークなどにも応用できる基本となるコンセプトであるMECEを理解しましょう。 ※2018年2月15日にコース内容を一部リニューアルいたしました。 リニューアルに伴い、コース動画一覧は全て未視聴の状態となります。 なお、リニューアル前に当コースを修了している方は、コース修了済のステータスに変更は発生いたしません。

会員限定
貸借対照表 ~企業の財務活動と投資活動を読み解く~
財務諸表の要の1つである貸借対照表(B/S)は、ある時点(決算期末時点)での企業の資産内容を表します。継続的な経済活動を行っている企業の一瞬の姿をとらえたスナップ写真ともいえる貸借対照表を理解し、企業の財務活動と投資活動の結果を読み解く力を身につけましょう。 ☆関連情報 フレームワークでニュースを読み解く、日経電子版の記事もぜひご覧ください。 「米SPAC上場ブーム、引き金はコロナ禍の失業対策」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC27E130X20C21A4000000/?n_cid=DSPRM5277

会員限定
リーダーシップとマネジメントの違い ~違いと使い方を理解する~
リーダーシップとマネジメントの違いとは、主にそれぞれ異なる特性と役割にあります。リーダーシップは人と組織を動かし変革を推し進める機能、マネジメントは定められた戦略やルールに基づき効率的に組織を運営する機能とそれぞれ定義されています。このコースでは、リーダーシップとマネジメントの違いについて詳しく学んでいきます。2つの違いと意味を理解し、日頃の業務やコミュニケーションに役立てていきましょう。 ☆関連情報 フレームワークでニュースを読み解く、こちらの記事もぜひご覧ください。 「吉本興業のこれからに必要なのはどっち?リーダーシップ、それともマネジメント?」 https://globis.jp/article/7224 「日本電産の永守氏にみる有事のリーダーシップ」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58614190Y0A420C2X12000/?n_cid=DSPRM5277

会員限定
クリティカル・シンキング(論理思考編)
業種、職種、役職を問わずビジネスパーソンが業務のスピードとクオリティを効率よく高めるために必要不可欠な論理思考力。 論理思考のベースとなる考え方を学び、実務で陥りやすい注意点を理解することで、実践で活用する能力を養います。 論理思考の基本を身につけ、コミュニケーションや業務の進行に役立てましょう。 論理思考を初めて学ぶ方は、以下の関連コースを事前に視聴することをお薦めします。 ・論理思考で仕事の壁を乗り越える5つのポイント ・MECE ・ロジックツリー ・ピラミッド構造 ・演繹的/帰納的思考 ・イシューと枠組み ※2019年10月31日、動画内のビジュアルを一部リニューアルしました。 内容に変更はなく、理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
ロジックツリー ~物事を把握する「分解」の考え方~
ロジック・ツリーとは、モレなくダブりなく(MECE)を意識して上位概念を下位の概念に分解していく際に用いられる思考ツールです。 問題解決で、本質的な問題がどこにあるのかを絞り込む場面や本質的な課題に対して解決策を考える場面で活用できます。 ※2020年3月30日、動画内のビジュアル、表現を一部リニューアルしました。 理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
論理思考で仕事の壁を乗り越える5つのポイント
伝えたいことがうまく相手に伝わらない。仕事がなかなかスムーズに進まない。 仕事をしていると、そんな場面に直面することもあるのではないでしょうか。 そんな方に役に立つのが「論理思考」です。 物事を論理的に考えられるようになると、仕事の効率が格段にアップします。 このコースでは、論理思考のコツを5つに絞って説明していきます。 ビジネスパーソンにとって必須のスキルである「論理思考」をいち早く身につけましょう。 「クリティカル・シンキング」をまだ見ていない方にもお勧めのコースです。

会員限定
MECE ~抜け漏れなく分解・構造化して考える~
MECEとは、ある物事を「モレなくダブりなく」切り分けた状態のことです。例えば年代別など、全ての人がその切り分けのどこかに属するようにします。MECEは論理思考の基本で、物事を分解し、構造化する際に役立つ考え方です。 例えば、状況を調べて問題箇所を特定する必要がある場合に、いくつかのポイントに分解して考えることが重要になります。その際に、モレやダブリなく分解することができれば、分析や問題解決の効率性が高まります。 ロジックツリーやマトリックス、あるいはその他のフレームワークなどにも応用できる基本となるコンセプトであるMECEを理解しましょう。 ※2018年2月15日にコース内容を一部リニューアルいたしました。 リニューアルに伴い、コース動画一覧は全て未視聴の状態となります。 なお、リニューアル前に当コースを修了している方は、コース修了済のステータスに変更は発生いたしません。

会員限定
MECE ~抜け漏れなく分解・構造化して考える~
MECEとは、ある物事を「モレなくダブりなく」切り分けた状態のことです。例えば年代別など、全ての人がその切り分けのどこかに属するようにします。MECEは論理思考の基本で、物事を分解し、構造化する際に役立つ考え方です。 例えば、状況を調べて問題箇所を特定する必要がある場合に、いくつかのポイントに分解して考えることが重要になります。その際に、モレやダブリなく分解することができれば、分析や問題解決の効率性が高まります。 ロジックツリーやマトリックス、あるいはその他のフレームワークなどにも応用できる基本となるコンセプトであるMECEを理解しましょう。 ※2018年2月15日にコース内容を一部リニューアルいたしました。 リニューアルに伴い、コース動画一覧は全て未視聴の状態となります。 なお、リニューアル前に当コースを修了している方は、コース修了済のステータスに変更は発生いたしません。

会員限定
ロジックツリー ~物事を把握する「分解」の考え方~
ロジック・ツリーとは、モレなくダブりなく(MECE)を意識して上位概念を下位の概念に分解していく際に用いられる思考ツールです。 問題解決で、本質的な問題がどこにあるのかを絞り込む場面や本質的な課題に対して解決策を考える場面で活用できます。 ※2020年3月30日、動画内のビジュアル、表現を一部リニューアルしました。 理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
リーダーシップとマネジメントの違い ~違いと使い方を理解する~
リーダーシップとマネジメントの違いとは、主にそれぞれ異なる特性と役割にあります。リーダーシップは人と組織を動かし変革を推し進める機能、マネジメントは定められた戦略やルールに基づき効率的に組織を運営する機能とそれぞれ定義されています。このコースでは、リーダーシップとマネジメントの違いについて詳しく学んでいきます。2つの違いと意味を理解し、日頃の業務やコミュニケーションに役立てていきましょう。 ☆関連情報 フレームワークでニュースを読み解く、こちらの記事もぜひご覧ください。 「吉本興業のこれからに必要なのはどっち?リーダーシップ、それともマネジメント?」 https://globis.jp/article/7224 「日本電産の永守氏にみる有事のリーダーシップ」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58614190Y0A420C2X12000/?n_cid=DSPRM5277

会員限定
因果関係 ~原因と結果の関連を理解する~
因果関係とは、あるものごとが「原因」と「結果」の関係でつながっていることです。「因果関係」という言葉は様々な場面で使われますが、ビジネスにおいても、因果関係の把握は問題解決などの場面でとても重要な思考技術の一つです。 因果関係を把握し、因果関係を明らかにすることのメリットやコツを身につけましょう。
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
100+人の振り返り
taku5181
その他
常に変化し続けることが重要とわかった。
確かにコダックが倒産し、富士フィルムが成長したのが最たる例と思う。
また、感知する能力、長期的な目線で予測することが大事と感じた。
tomo-tom
営業
良く言われていることの紹介だったが、復習になった。
sphsph
メーカー技術・研究・開発
納得は出来ましたが、今の自分に何ができるか?
チャレンジしにくいというと逃げているだけかも知れませんが、難しいです。
根本の考え方に立ち返って、深く、広く考えます。
ozawa_h
IT・WEB・エンジニア
GLOBISではまだポジショニングのコースが多くあり、ケイパビリティやダイナミックケイパビリティについては少ないです。
今の時代に生き残るためにもこららについてもう少し勉強する必要があると感じました。
yuji-fukuniwa
人事・労務・法務
最も変化に対応した種が生き残るは名言ですね。
koyahiro
経営・経営企画
組織が大きい場合、変化速度が加速しないこと気にかけていたが、他社事例から参考になるポイントを踏まえ検討していきたい。
tanesannta
営業
変革に激しい現代においては、企業も人も、その変化を察知し、把握して、それに打併せr手変容を遂げることが不可欠。ダイナミックケイパビリティそのものだと感じました。
kfujimu_0630
マーケティング
ダイナミックケイパビリティのことがよく分かりました。富士フィルムはフィルム技術を活かして、化粧品事業で成功したことで有名ですね。自社の強みを活かして、他事業にシフトしていくことは、これからの経営で必須だと思いました。まさに経営は変化対応ですね。ありがとうございました。
bun0717
営業
日本企業が変化に対応できず苦労している中で、どうしたら社内にダイナミックケイパビリティの意識を取り入れることができるのか?具体的事例を聞きたかった
a_7636
人事・労務・法務
お話の中で出てきた「アンゾフのマトリクス」のコースをご参考までに。
②は今のままの自分でよいのだろうか?のヒントになる分析方法です。
①アンゾフのマトリクス ~製品と市場から成長戦略を考える~
【経営戦略】【初級】0:07:19
②自分の成長に不安を抱いたときは「アンゾフの成長マトリクス」で考えよう/
みんなの相談室Premium
【自己啓発】【知見録 Premium】
ruimasiko
その他
生き残る為に、何をしていくのか。
面白いですが、難しいですね。
chease
クリエイティブ
進化しようと思うと、嫌いな業務から逃げず、
自分に負けないという気持ちが湧いてきます。
zummy_0617
金融・不動産 関連職
初めてダイナミックパビリテイを聴きました。
・感性 ・変容力
VUCAに適応したことを自己変革に持っていけるか、
従業員の課題に重くのしかかるのではないかと感じています。時代背景に沿って柔軟性に動いていきたいです。
tetsu-mitsu
営業
自社の置かれている状況も、現状のままでは会社存続出来ない事は明らかです。しかし、コモディティ化した能力しか無く、自社の強みを見いだせずにいます。更に学びを深めないといけないと思います。
yas_fourier
マーケティング
変化に対応する者が勝ち残る、という考えをもとに、現状維持でなく、進化し続ける策を考えていきます。
kiso_2115
コンサルタント
外部環境の変化から新しい現実を感知し、変容に繋げることができる仮説を検討すること。
takumi_1453
経営・経営企画
フジフィルムさんの例でいえばどのくらいトップが決断が必要だったか、組織がトップ決断にむけて内発的に取り組んだ事はあったのか、など生々しい話も聞きたいですね。
tak_en
メーカー技術・研究・開発
提唱者の言葉に、ぐさっときました。だからこそ、変革を推進していく、継続していく必要があると、メンバーに周知していきます。
footmark4
営業
環境変化に応じて経営資源を再構築して自己を変革する。今の仕事内容について顧客、社内の環境を分析してもう一度見つめなおしてみようと思う。
makoto03
経営・経営企画
オーディナリーケイパビリティ、すなわちオペレーショナルエクセレンスでは生き残れないことがわかりました。また、今までは新規事業とは既存事業とはかけ離れたものを構築するものだと考えていましたが、既存技術の転用によるものだと考えを新たにしました。
自身の企業でも効率化とともに時代に合わせた自己変革能力を高めなければ確実に衰退するため、新規事業を考える際に参考にしたいと思います。
vegitaberu
人事・労務・法務
「ダイナミックケイパビリティ」を持つことによって、イノベーションよりも効率性を優先する企業に勝つことができる。
先が見えないVUCAの時代においては、状況に合わせて、機敏に、自己の中から、変わっていける企業が、変わらない企業に勝っていく。
この2点を理解し、そこから、「ダイナミックケイパビリティ」の重要性を理解できたと思います。
taikou
営業
当社も前処理薬品メーカーだが、
それだけでは今後生き残っていけないと感じている化学薬品メーカーの強みを生かして、
前処理薬品以外の分野にも活路を見出す必要はあると考える。
d-mat28
マーケティング
変革をしていく能力が、これからの予測不能な世の中にはより必要になってくる
yuko_ewalu
営業
自社の潜在的価値は何か?
その価値を時代の変化に合わせてどのように転用していくのか?
自社を見つめなおすきっかけになりました。
hatayuz
メディカル 関連職
外部環境を考えてポジショニングにこだわるだけでなく、自社の持っている価値を最大限に生かすことが、ダイナミック・ケイパビリティだと理解しました。
これが、SWOT分析が役立つ理由でもあるのだと思いました。
mskamakura
その他
先日、ビジネスワールドサテライトで、アパレルの会社が昨今の円安と原材料費高騰により、商品の値段が高くなり、顧客離れが進んでしまい、このままでは会社存続が難しくなるため、地元の特産である干芋を、倉庫を利用して製造したら、思いのほか好調な売れ行きで、輸出するまでになったと放送していた。社員はアパレルの会社なのに農作業を行うことに抵抗があったが、今は売れ行き好調でそのことが社員を一つにまとめて、厳しい環境変化を乗り越えられると言っていたが…まさに「ダイナミックケイパビリティ」だと感じた。時代の激変に合わせて、社員が本業以外の戦略に打って出たとき、どれだけついてきてくれるかが成功するか否かの分かれ目だと実感した。
koji_wada
マーケティング
ダイナミックケイパビリティは、現代に重要な視点だと思いました。事例なども鑑みると、大切なのは変化することではなく、変化に「適応」することだと感じました。検知できても、補足し、変容することはとても難しいが、意識していきたい。
tan_tan_
クリエイティブ
変化に対応する企業が生き残る時代にあたって、ダイナミックな変化を許容・推奨する企業風土の醸成が何よりも大切だと感じた。
ya_sawai
経理・財務
富士フィルムの例など各社が持っている優れた技術を現在の事業ポートフォリオで活かすだけではなく、新ビジネスに転換し、広げる柔軟性をもったチャレンジ無くして成長がない事実を理解できました。
iwamon98
人事・労務・法務
経営的視点を持ち自身の業務でも実践できると思った。
cs1960
販売・サービス・事務
富士フイルムの事例を聞いて、コアの技術の転用によって、特にイメージング事業の成長は目を見張るものがあります。この事は今後この路線を踏襲して進めて行けば良いのか、又はそこから派生した新技術の種に着目し、新たな事業にチャレンジすれば良いのか、さらに学習していきたい。
tobeeroo
マーケティング
自社の強みを見つめ直すことが、まず重要な事だと理解した。
その上で、外部環境に柔軟に対応し、自社を変革し続けていかないと、VUCAといわれる時代、企業成長はおろか、企業存続も危ぶまれるのだと、実感できた。
sai-3448
人事・労務・法務
今回学んだことを参考にしたいと思います。
ymhr
メーカー技術・研究・開発
生き残るためには変化が最も重要ということがよくわかった。まだ若手の今だからこそ感じられる視点もあると感じた。
ysblue41
金融・不動産 関連職
何となく聞いた事のある事例であるが、アメリカではコダックが倒産した一方、GAFAに代表される新たな大企業を生み出している。日本ではユニクロ、ソフトバンク、楽天などが挙げられるが、規模は比べるべくもない。新事業が立ち上がらない限り厳しいと、考えているので、既存企業の生まれ変わりに成功するのは、かなり稀なのではないかと考えている。新事業を立ち上げる時に、自分の強みを活かして、環境の変化に対応するといった視点を持つこと。これがせいぜいのところではないだろうか?富士フィルム以外の成功例を聞いたことがない。
masato0609
人事・労務・法務
こういう変化に対応して生き残った(成長した)企業の事例が紹介されるたびに、口を揃えて出てくるコメントは「メーカーの事例ばかりで、自社の業態の事例がなく参考にしにくい」である。それこそ、「自社の業態」に囚われ、変化を厭う姿勢の現れではないかと日々感じる。大切なことは自社事業とその戦略を因数分解し、どの部分をどう変えれば変革が起きるのか(=事例の中で活かせる箇所はないか)を考えることと思う。ダイナミックケイパビリティは、自社の強みを別の方向に向けることで、変革を起こすことである。紹介されている事例そのものではなく、そのプロセスと、自社(自組織)の中身に徹底的に目を向けることが重要と学んだ。
akira258
IT・WEB・エンジニア
成功体験にとらわれず、常に変化していく事が大事と分かった。
kuro-787
営業
環境変化に応じ、常に変革していかないと生き残っていけない。会社もそうであるが自分自身の考え方も同様である。
uhhu
専門職
日々、様々な事に対応する事が多くそれが重要であるとは漠然と認識していたが、生き残るのは変化に対応した種という名言を学び、改めて現代社会の厳しさを実感した。自己変革を恐れず、VUCA時代に対応したい。
luft_kato
営業
時代や世界の流れに対応し変化し続ける力、改めて大切だと思った。
変化していく様は、自社の社員にも影響し、先陣を切って挑戦することをみせることができ、たとえそれが失敗したとしても反省や立ち直り方までみせられるので、会社にはどんどん新しいことに手を出してみてほしいと思う。
shige010107
経営・経営企画
常に変化し続けることが重要とわかった。
mk-tkezawa
営業
最も変化に対応した種が生き残るは名言ですね。
yokok167
メーカー技術・研究・開発
プロジェクト業務でも顧客が求めていることは何であるのか理解することがスムーズ進行に繋がる。内部の担当者間の協力できる体制を整えることが重要。
ruru_ruly
経理・財務
変化への適応能力が最強論に勇気をもらえた
yutahayasaka
その他
富士フィルムとコダックの例が分かり易かった。
VUCAの時代なので、Dianmic Capabilityが重要ということか。
satoshi_201709
コンサルタント
ケイパビリティの話しは、囚人のジレンマや両利きの経営に関する考えと似た部分があると持った。
taisuke1212
営業
常に環境変化に目を光らせることがまず大事。(感知)
それに対して柔軟に変化することができる組織運営にすることが大事かつ一番難しいと感じた。
企業風土から活発な人材交流や挑戦を奨励する文化、権限移譲がしやすい組織にしておく必要があると思う。
noguchihiroyuki
金融・不動産 関連職
ビジネスモデルが強いほど、変えることが難しいことは日々の業務でも感じています。なかなか良いイメージが浮かびません。
m-masa-2311
その他
カメラのフィルムがデジタル化によって生き残った企業とそうでない企業の説明がわかりやすかった。
自分の身近所にも色々注視して考えて行きたいと思った
kenya_ishii
メーカー技術・研究・開発
今まさに必要な能力である。これを実践するためにはその基盤となる組織文化や風土の醸成も必要であろう
naoto_yamakami
資材・購買・物流
<<ダイナミックケイパビリティ>>
「環境や状況が激しく変化する中で
企業がその変化に対応して
自己を変革する能力」
~戦略としてのダイナミックケイパビリティ~
ポジショニング派
⇒市場での立場(ポジショニング)が重要
ケイパビリティ派
⇒自社の経営資源(ケイパビリティ)が重要
・優れた人材
・独自の技術
・ノウハウ
naokiyamahara
専門職
生き残るために何をしなければならないの考えなければならないと感じました。
コダックと富士フイルムの例はすごく象徴的でわかりやすかったです。
bonjours
金融・不動産 関連職
企業が生き残るためには、変化に対応することが不可欠と強く感じているので、ダイナミックケーパビリティーという言葉が好きです。ただ、どのように自分の属する部門がそのような能力をつけるのかは、別途学びたいと思っています。
h3110
営業
強いものでもなく、知的でもなく、生き残るのは変化に適応できたものというのは言葉でいうのは易し、行うは難しだと本当に思います。
y-shiraki
販売・サービス・事務
変化についていけていないメンバーがこのままでは衰退する一方。なんとか変化を受け入れるメンタルを強化していきたい。
an038789
その他
何ができるのか、を見つけ出すのが難しい。どんな考え方をしているのかを知りたい
wantsuai
建設・土木 関連職
メディアを変容させて浸透させられたと言うのは興味が湧く
pertama
営業
富士フイルムの例はとてもわかり易かった。生き残るには欠かせない考え方だと思います。
h_h--
マーケティング
生き残るために何をしなければならないの考えなければならないと感じました。
コダックと富士フイルムの例はすごく象徴的でわかりやすかったです。
yoshi-koyama
営業
仕事、私生活、趣味や物事の価値観など、あらゆる面において変化することを前提とし、常に意識することができると感じます。大きな仕事やプロジェクトだとハードルが高く、トライしにくいので、まずルーティンワークにおいて事務処理、日々の連絡業務を変革していけると感じられました。
redcomet
IT・WEB・エンジニア
組織再編などの身近での大きな変化の際にも適用できるのではないかと考えた。
kawaihrm
人事・労務・法務
ダイナミックケイパビリティのことを知ることが今後の戦略に行かれると感じました
monpipu1587
販売・サービス・事務
組織やチームのケイパビリティを把握することで、メンバーの強みを効果的に活用し、チーム全体のパフォーマンスを向上させることができると考えます。
どのメンバーがどの分野で高いケイパビリティを持っているかを理解することで、適切な役割分担やプロジェクトのアサインが可能になります。
活用例: プロジェクトを進める際に、チームメンバーの専門スキルや得意分野を活かして役割を割り振ることで、効率的なプロジェクト運営が可能になり、成果を最大化できます。
masato-kato
IT・WEB・エンジニア
変化に対応する力は日に日に必要であると感じており、その知識や能力を得ようと持ってきた。ダイナミックケイパビリティという言葉は今回初めて知ったが、まさに当てはまる内容だった。3つの能力、感知、補足、変容を得るための考え方を学ぼうと思う。
y_takano
販売・サービス・事務
普段環境変や競合の変化がどう影響するか、意識はしているものの今回のカリキュラムで再度認識しました。
今抱えている事業について、もう一度業務の棚卸しを行い、中長期の計画に反映、今できることから始めようと思いました。
kawakamimasa
専門職
変化することが大事であること。
しかし、継続することは難しいと思います。
gandai
専門職
非常に参考になりました。
なんとか生き残りたいと思います。
toshi2024
クリエイティブ
自社のコアとなるデザインという能力を狭義にとらえ、かたくなに守るだけではなく、社会に目を向け、視点を変えてみてみると、建築だけでなく、様々な分野に応用できる思考パターンだということがわかる。
kochin66
経営・経営企画
自社のケイパビリティの分析が一番難しい気がします
ik_hrs
営業
変化に対応できることが生き残れるということはビジネスの世界でも同じことであり、富士フィルムの事例も参考になった。
sayaendou100
専門職
VUCAのなかでは既存の事業だけでは倒産する可能性があることを学んだ。
いかに時代にあった変化をすることができるかが今後の課題である。
okamotoyutaka
メーカー技術・研究・開発
変化に対応することは重要だと思っていましたが、ここまで分かりやすく言語化されると明確にわかった気になりました。
通常の能力は模倣されやすいとありました。逆にいえば、他社の良いところは簡単にまねできるということで、その辺勉強したく思います。
そして、変革し続ける能力が変化した環境に正しく適合するように努めたいと思います。
但し、変えることによって、自分のメリットがなくなることがないよう、守るべきことと、変えるべきことは、慎重に考えたいと思います。
suga-naoki
その他
ダイナミックケイパビリティの重要性は理解しましたが、個々に落とし込む際に具体的に何を実践したらよいのかイメージがつきませんでした
kurume_50
販売・サービス・事務
変化への対応とは昔から言われている経営戦略ですが、自社においてどのように変化を感じ事業変革に活かしていくのか考えてみたい。
fukuitoshifumi
その他
VUCAの環境の中,企業が存続するための「ダイナミックケイパブリティ」について,アナログからデジタルに移行する流れの中で富士フィルムがせざるを得ずに変化したことが詳細は不明だがイメージできた。ニコンやキャノン,他の業種はどうしたのか興味が湧きました。一方,「餅は餅屋」事業の主軸を変えすぎて失敗するといったことも聞かされます。我が社はどうなるかの不安もあります。
01sato
経営・経営企画
日常生活のあらゆるところに変革の種は潜んでいる、
仕事と日常生活を切り分けるのではなく、生活の中で仕事をしていくという感性で生きていくと、我々のダイナミックケーパビリディも高まるのではないか。
ya710su
販売・サービス・事務
改めて,強いものや知的なものでなく、生き残るのは変化に適応できたものという言葉を聞いた。
今,我々の業界も真っ只中でもがいているようなものだ。
kyo1227
営業
富士フイルムの例はとてもわかり易かった。生き残るには欠かせない考え方だと思います。
oka-hiro
その他
変化に適応できるようにアンテナを高く持っていきます。
cyari_yama
経営・経営企画
現状のビジネスモデルの生産性向上に取り組むのは重要であるが、その一方で、成長し続ける企業を志向するのであれば、現状の自社ビジネスモデルに新たな視点を付加し、全く新しい市場の開拓に取り組むことも重要である。経営企画部長として、リノベーションとイノベーションの両立を意識した経営方針の発信を意識したい。
sinobu
マーケティング
ダイナミックケイパビリティ大事
nsi-tag
IT・WEB・エンジニア
変化を察知して、自社も変化していくという心構えが大事
shinnosuke-a
マーケティング
生き残るのは、最も強い種ではなく、最も賢い種ではなく、変化に対応した種である。
この生物がたどった道を企業に置き換えて考えることでダイナミックケイパビリティを理解する事ができました。
kazu_osk
経営・経営企画
帰ることを恐れず変わることも、日常の1部と思える位の認識が必要と感じた
everest
営業
変化を前向きに捉え自らの強みを活かして柔軟に対応し続ける力として仕事に活かしたい。
nk_55
マーケティング
大きな転換をすることの必要性と、業務効率化・スリム化をし続けることだけが必ずしも正解ではないということは、通常業務に当たる際にも考えとして持っておく必要があると思いました。
starpearl
専門職
過去の体験に固執せず、現状に見合ったアプローチをするにはどうすべきか、常にアップデートしていく大切さを改めて実感した。
そのためには、アンテナを張り、学ぶことも、相手の意見を取り入れ、柔軟さを持ちたい。
jwjwjwjw
人事・労務・法務
変化なくして成長なし。
少しでもプラスアルファができないか検討した上で諸事情に対応するように心掛けている。
yukiokano0000
マーケティング
環境変化にはAIに頼れば問題ないと感じた
moco1719
営業
年功序列の強い会社組織において、組織の成り立ちを変革する事は容易ではないが、「人」を生かす方法に関してはより変化を追求する事で、”人材”が活躍できる場所を提供する事はできるのではないかと考える。
この変化を忘れると組織の発展は完全に止まってしまい、最悪の場合として倒産という事になると思われる。
日本の最年長企業である金剛組は、どのようにして1000年以上も時代の変化に対応してきたのかを知りたいと思った。
yukois
営業
変化することは怖いことではあるが重要だとわかった。
9047889
経理・財務
家庭でも活用できると思います。家族全員がそれぞれ自己変革を行っていくことは、家族としてより一層質の高い
生活を送ることにつながると思います。
子どもであれば、勉強や友達との関係の向上。親であれば、子供の手本となり、会社での地位も上がり収入も上がるのではないでしょうか。
machida_keigo
クリエイティブ
ダイナミックケイパビリティを実践できるような企業をめざしたいと思います。
qinoue
営業
今まで培った情報、技術等を基に変革する勇気を持ち前向きに取込事をしていきたいと思います。
kaori-g
人事・労務・法務
会社もそうだが、個人においても応用できる。既存事業(主力)は自身のキャリアの中核として、手堅く運用しつつ、次なる(まだ見えない)変化に備えて、アンテナを高くし、感知した変化の自分への影響を明確にし、それらをベースに自分のリソースを外部調達(人脈)・内部育成(リスキリング)することで、自身が生き残る可能性を高めることができる。
ange104
営業
言葉では、変化することを言うのは簡単であるが、実践することは、難しいこと、どう実践してきたのか、別の回で説明してほしい。
haya-88
その他
ダイナミックケイパビリティは当社の変革には必要な概念
tanakasana
専門職
ダイナミックケイパビリティ
cuizhi_pan
人事・労務・法務
製品・産業の将来性を考慮する必要がある
yuppi_san
経営・経営企画
VUCAの時代を生き抜くために必要な考え方であり、当社の経営にも取り入れていく必要があると思いました。