
0:59:48
割引情報をチェック!

AI BUSINESS SHIFT 第8回 機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第8回です。 第8回「機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル」では、AIが営業現場にどのような変化をもたらしているのか、営業担当者・営業マネージャー・組織としての役割や戦略が、AIによってどう進化していくのかを、営業プロセスの分解や実際の現場事例を通じて学びます。 ■こんな方におすすめ ・AIを活用した営業活動の最新動向や現場のリアルを知りたい方 ・営業現場の変化に直面している営業マネージャー・現場リーダーの方 ・AI時代における営業戦略や営業マネジメントのあり方を学びたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年2月制作)
会員限定

マネジャーのための仕事の任せ方
「仕事を任せると失敗が怖い」「自分でやった方が早い」マネージャーとしてメンバーやチームの力を引き出しながら成果を上げるには、どのように仕事を任せていけば良いのでしょうか? 変化の激しい時代において、マネージャーとして成果を上げ続けるためには、メンバーの個性や特性を理解し、それに合わせた効果的な任せ方を身につけることが重要です。このコースでは、ソーシャルスタイル理論を活用してメンバーごとに最適なアプローチを学びます。「任せる力」を高めることで、チーム全体の成長を促進し、自身のリーダーシップを発揮できるようになっていきます。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2024年12月制作)
会員限定

AI時代の個人力
AIが仕事や社会の前提を変え続ける今、最も求められるのは「他者に代替されない個としての力」“個人力”です。 本コースでは、澤円氏の著書『個人力』をもとに、AI時代をしなやかに生き抜くための「前向きな自己中戦略」を学びます。 テーマは、「Being(ありたい自分)」を中心に据え、自ら考え(Think)、変化し(Transform)、協働する(Collaborate)ことで、自分らしい価値を発揮していくこと。 リスキリングやAI活用が叫ばれる今こそ、スキルより先に“自分の軸”を問うことが重要です。 あなたは何を大切にし、どんな未来を描きたいのか? このコースは、あなたが“ありたい自分”として生き、キャリアをデザインしていくための思考と行動のガイドになります。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年11月制作)
会員限定
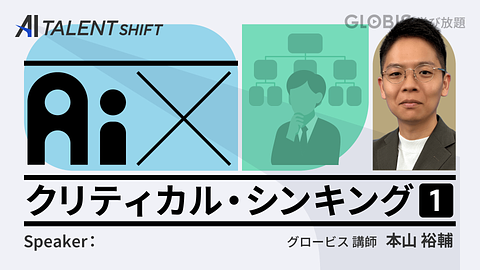
【AI×クリティカル・シンキング】①イシューと枠組みでプロンプトを磨く
生成AIから期待する回答を引き出せず、試行錯誤を重ねていませんか。 本コースでは、生成AI活用の質を高める鍵として、クリティカル・シンキングの視点からイシュー設定と枠組みを押さえる重要性を解説します。 目的に直結する問いの立て方や、プロンプトに落とし込む際の実践ポイントを具体例とともに学ぶことで、AIをより思考のパートナーとして活用できるようになります。 生成AIを業務で使い始めた方から、活用を一段深めたい方まで、再現性あるプロンプト設計を身につけたい方におすすめの内容です。 さらに学びを深めたい方は、こちらも合わせてご覧ください。 【AI×クリティカル・シンキング】②AIの弱点との向き合い方 https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/cdfe41e3/learn/steps/62198 ※本コースは、AI時代のビジネススキルを学ぶ「AIタレントシフト」シリーズの一環として提供しています。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
会員限定

リーダーの挑戦⑤ 藤田晋氏(サイバーエージェント代表取締役)
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第5回目のゲストは、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋氏。起業の理由、経営をどうやって学んだか、アメーバブログ・ABEMAの立ち上げ、経営チームづくりについてなど聞いていきます。(肩書きは2020年12月11日撮影当時のもの) 藤田 晋 サイバーエージェント 代表取締役 堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
会員限定

ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 前編 なぜ眠れないのか?~
「仕事が終わらないから睡眠時間を少し削ろう…」「業務時間中なかなか集中できない…」「毎日朝起きるのがつらい…」。 あなたはこのような経験をしたことはありませんか? 仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削りがちなのが「睡眠」時間。 実は今、日本社会は世界と比較して「最も眠らない国」だということもわかってきています。 慢性的な睡眠不足は、心身の健康に悪影響なだけでなく、仕事のパフォーマンスにも当然大きな影響を与え、社会全体の経済損失につながります。 このコースでは、基本的な睡眠リテラシーを学んだ後の「問題解決編」として、「なぜ多くのビジネスパーソンは眠れないのか?」について解説していきます。 ▼本コースで学べる主な内容 ・そもそも眠れないことは何が問題なのか? ・眠れなくなってしまう原因とは? 睡眠不足の原因は認知機能の問題にありました。 自身の睡眠不足に対し、正しく「気づき・理解し・行動を変える」第一歩を踏み出しましょう。 ▼関連コース ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~リテラシー編~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/24575c03/learn/steps/53129 ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 後編 どうしたら眠れるのか?~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/4ba981e9/learn/steps/62042 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

大阿闍梨 塩沼亮潤が死の手前で見つけた「生き方」
あすか会議2018 第4部分科会B-1「極限の世界で見つけた人生の歩み方」 (2018年7月7日開催/国立京都国際会館) 1300年間で2人目となる大峯千日回峰行満行を果たした塩沼亮潤大阿闍梨。48キロの山道を1日16時間掛けて歩き、それを千日間に亘って続ける過酷な行の中で、どのような悟りを得たのか。そして、9日間、断食・断水・不眠・不臥を続ける四無行満行という極限の世界で何を見つけたのか。塩沼氏が「創造と変革の志士」へ贈る「人生の歩み方」とは。(肩書きは2018年7月7日登壇当時のもの) 塩沼 亮潤 慈眼寺 住職
無料
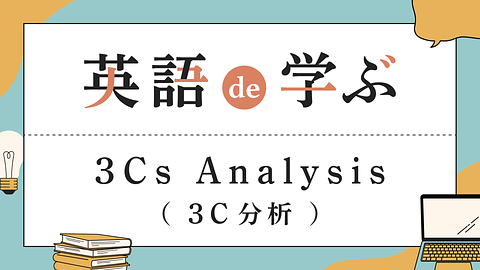
英語 de 学ぶ!3Cs Analysis(3C分析)
このコースでは、グロービス学び放題の英語版である『GLOBIS Unlimited』のコースの中から、ビジネスで役立つ頻出の英語表現をピックアップしています。英語ネイティブの方が実際に見ているコースなので、リアルなビジネス英語の表現を学ぶことができます。 今回のコースは「3Cs Analysis(3C分析)」です。一緒に『英語で』ビジネス知識を学んでいきましょう! ▼今回扱ったUnlimitedコース続きは下記からご覧いただけます 3Cs Analysis https://unlimited.globis.co.jp/en/courses/da5ca962/learn/steps/36362 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
コメント5999件
y1854
そもそも、個々のメンバーが高いモチベーションや問題意識を持っていなければ、激動期に議論をしたり衝突したりすることも出来ない。
この考え方は、ある程度レベルの高い集団にしか通用しないのではないか?
自組織で活かすのは難しいように思う。
yama45
集団とチームの違いを意識したことはなかったので、今後、この2つの言葉は明確に区別して使おうと思った。
ruru_91437303
言っていることはもっともだとは思うが、リーダーがそうやって前向きに考えていても実際の部下がそこまで仕事に対してアグレッシブに望む姿勢ではなく、対立を起こし和を乱す程の存在ではないにしても、言われたことを無難にこなせばいいや程度にしか捉えていないタイプの場合、言うは易く行うは難し…な話だと思う。
saik
会社(一般社会)には激動期の議論・衝突をネガティブにとらえて避けようとする人たち(含リーダー)が少なからずいるので、そこをどう越えるかが課題です。
hiroki1980
衝突は必要な事、メンバーが去る事もある。このような事は知らないとアタフタしていたと思います。
k_shishikura
チームとして纏まる事が必要と分かってはいても、集団に飲まれてるのが現状。
皆が納得出来る目標を見出して、また激動期を恐れず前に進みたい。
同じ会社の仲間として、同じ方向性で仕事が出来るよう、私自身もマネジメントを頑張ってみます。
ashrhryk
激動期と単純な諍いの差は何か。
tarimo
様々な段階があるなかで特に激動期にチームをいかにまとめることができるかどうかが良いチーム作りへのキーポイントになると思った。
wkiymbk
集団の発展段階(タックマンモデル)を学ぶことができました。
激動期(Storming)の上手な対応方法を詳しく知りたいと思いました。
nico0113
集団とチームの違い、言葉ではわかっていてもつい集団になりがちな為、意識的に行動することが大切と感じました。
iseki1234
集団の発展段階理解しました。
kameco
目標の明確化が大切で必要だと思いました。
s_s___
現実は、意見が異なる人は排除されるので、極力意見は言わずイエスマンに徹し責任を逃れるのが、自分がハブられたり自分の邪魔されず能力を発揮できる場合が多いので、それが問題だ。
形成期のまま個々で頑張るところから進展しないし、何かするにもだいたい経験や実績があり失敗しない同じ人が担当になり、視野が異なる意見や新人は除外していないか。
本当は、他人と協力し関わりながらやるより、自分で完結したい人が結構いるのは認めるべき。だから難しい。
takuma_8659
チームの形成から発展、解散までどんなフェーズがあるのか体系的に理解できました。
また、衝突を恐れない、というのは確かにチームビルディングを行う上で重要ですが、反面個が強い人財の集まりだと、衝突後収束が難しく、分散してしまうこともあるかと思います。
将来マネージャーのポストに着くことを想定するとここに大きな課題が生まれるのでは、と感じました。
学びを深めながら自分なりの解決策を持てればと思います。
ricohiroto
目標、ゴールの共有の大切さを改めて認識しました。実現期を経て、終了期について、そのようなチームビルディングを心がけようと思いました。
sue_0120
チームを組んで仕事することで、その成果大きくするには、チームマネジメントが重要で、集団の特徴と発展段階に応じて、リーダーがメンバーへ適切な働きかけを行うことで、集団はチームとして機能することを改めて学習した。
noyo1
チームの目標を基にグループの目標に落とし込み、それらを各リーダーが理解して実現する統制がとれた形に対して、横のつながりをプラスすることが重要。その際は、FtFでグループの目標に対しての進捗状況や困り事を素直に話せる場をつくることもチームリーダーの役割だと考えている。
y2001210m
集団をチームにすることにおいてプロセスがあることを学びました。チームとしてまとまるには時間もかかるかもしれませんが、プロセスを意識して取り組んでいきたいと思います。
yuji_371002
多様性を大切にすること、対立を恐れないこと、去る者がいても良いこと、など参考になった
mskz33182
チームを構築していく中で、各ステージがあることを意識したことはなかった。
fujiwara1226
衝突期を恐れず、コミュニケーションを取っていきたい
gantetsu
相互責任を持ってもらうためにも、まずは明確なチームの目標設定を行うようにしたい。
as95
リーダーとして、課員に自由と権限を与えないとチームが機能しない事を再認識する事が出来た。
saito-yoshitaka
集団でのメリットを最大限活かす事が大事。去るメンバーが出てきても仕方ない。
kys_igarashi
理想は分かるが実態に沿わない説明もあったと感じる。そもそもメンバーの持つ資質を見極めることが大事では。
richie_miyazawa
「誰をバスに乗せるか」チームを組成する上でまず重要なこと、「多様であること」が肝要であることを再認識した。
かつ、メンバーが腹落ちするまで、衝突を恐れず議論を行うことの意義を同様に再確認できた。
今後のチーム組成時に意識したい。
jt007
チームをマネージメントするときに、チームの目標を明確にすることは大切だと思いました。
crystalucas1110
まだまだ私の部署はチームになりきれていない。メンバー間の衝突を避けているのかも知れない。やるべきことが明確になりました。
tomo-shimi
チームとして発展する際、激動期を迎えることは必須であることが分かった。
しかし、激動期は声の大きい人、自分の意見を強く推し進めようとする人がいると、内気な人は何も意見を言えず、最終的に何も考えない、当事者意識の欠けた集団になる傾向がある。
この場合、リーダーのマネジメント能力が重要となってくるが、リーダー自体が内気だとチームとして存続が難しいと感じた。
himawarin
ちょうど自分のチームが激動期にいると感じました。よいチームを作るうえでは必要な過程ということだったので安心しましたが、一方で、自分の所属するチームのメンバーはプライドが高くて主張を曲げない可能性もあり、去る場所もないので、このままずっと対立状態の可能性もありそう。現実的には一筋縄ではいかないと思いました。
t-k-u
集団やチームに参画し自身とその集団やチームがどの時期にいるのか。自分自身での判断材料として集団の発展段階(タックマンモデル)
をキーワードに理解することができると思いました。
とあるプロジェクトに参画した→目標設定→役割分担→達成といった一時的な集団形成にも考え方の理解ができ
議論している時には、自分自身でも「あー、今は、集団発展の激動期にいるんだな。議論を重ね、お互いの理解を深めよう!」という考えに至れると思いました。
kimikimi50
目標をメンバーに繰り返し伝えて、チームにします
osawam
目標の明確化が重要であると理解できた。
dorubitch
【チーム作りで役に立てる】
・事前準備
チーム作りのメンバー編成。
これまでのキャリアや仕事の取り組み方、長所短所を明確化する。メンバーの特性にばらつきが生まれないようにメンバーを選抜する。
・タックマンモデルに基づいてチーム作りを行う。
①形成期
→議論を促す。自らファシリテーションを取って、目標をメンバーに共有する。その上でメンバーの意見を聞き、役割分担、チームの目標のすり合わせを行う。
※この際に1on1を実施、各個人の目標を設定する。
②激動期→仕事の役割や判断基準でメンバーの衝突が起きた際にチームMTGを実施する。
(チーム目標の修正や判断基準、役割分担のすり合わせを行う。この時に各個人の長所短所を踏まえて、役割分担の変更も実施する。)
③規範形成期→チームの目標、判断基準、役割分担が固まったタイミングで模造紙などで可視化する。
④実現期→進捗を管理し、目標達成に向けたスケジュールを調整する。さらに1on1MTGを実施し、各個人の経験学習を支援することでメンバーの課題を明確にし、成長の手助けを行う。
⑤終了期→目標について達成し、チームで振り返りを行う。また個々人に対して1on1MTGを実施し、個人の目標や経験に対する振り返りをし、次のプロジェクトに活かせるように評価する。
nara_keita
激動期、規範形成期、実現期というそれぞれの段階を意識し、チームへの対応を取るという観点は非常に興味深いものでした。チームを作るとすぐに、継続的な成果を出したいと期待してしまいますが、「激動期」や「規範形成期」というステップが強いチームを作るという事が分かりました。
恐れずに、この2つのステップを誘導していきたいと考えました。
joga
今、新しい業務を行う方向に進んでいる。ルールも確立されていないために現業のMGRたちとも個別に議論しながら課の方針を確立していこうとしている。
まさに,今は激動期だと思う。
funao2727
「リーダーの資質はますます重要になります」というのが抜けている
hasehiro0116
メンバー毎の役割を理解させる上で、年間を通してどのようなチームにしていきたいかを指し示すことが期初に伝えられる。
inada-makoto
新しく編成されたチームに入るのと、既存のチームに入るのは考え方が変わってきます
どちらでも共通するのはチームのメンバーの長所・短所を補えるようなポジションに就かせることです
buchi529
現在できて年月の浅い部に所属しているので、その中で今後業務の幅を広げていくうえで参考になると感じている。
現状、上長の個で部が成立している感覚があるが、ある程度今後メンバー増えた際のことや、人事異動などにも備える意味で、集団の発展段階を参考にし、規範やルールなど、体系的に整備していく必要があると思った。
shuji_ics
激動期から規範創成期への移行がかなり難しい。お互いの意見を出し合える環境となっても、そこから自律的に相互互換しあえる集団になるのは並大抵ではない。営業部としてイベントを企画した際に、モチベーションの違いによる偏りがどうしても出てしまう。コミュニケーションをとる努力はしていても、それぞれのプライドや仕事量の違いにより、同じ熱量では仕事を進められない。まずは意見を出し合う事が他人の批判ではなく、自分の足りない部分を発表する場として機能することを目指したいと思います。
hirossii
自社において激動期での葛藤を超える部分が、社風でもあるのだが言いたいことをしっかり言い合えないことで壁になっている。
それは経営者である自分自身が生み出していると一つ認識している。
人種の壁もあるのかと考えたが、今回の学びでは多様性があることも大切とあった。その部分は興味深かった。人種もあるが理念、ビジョンに対する考え方、仕事スタイルにおいても人それぞれ違う。理念、ビジョンに共感できないスタッフにやきもきする部分もあったが、そこはチームとして関わっていくことで、そのスタッフの特性が光り出すことで自分自身の貢献、そして人からの貢献によって、変革していくのではないかと考えた。
今の会社の方針からで部、課の方針をチャンクダウンして明確化していくことから始めたい。その中で激動期に入った時に自社の人に対する暖かい組織が輝いてくるのではないか。
やる気のある子から辞めていく。そのような現象がここ数年続いていた。それは明確な目標があったとしても落とし込めておらず、その子のキャリアパスに繋がっていないからだと認識した。今は経営者である自分自身が応急措置的に、そこに入って行っているが、その子たちが自社で自分の生きる道を見つけ花開くことで、また会社が変わっていくという希望も感じた。
退職者が出ると一人ひとりの負担がまた増える。でも、必要な人材が先に辞めていく現状を考えると、葛藤を恐れずに激動期を乗り越えることを進めていくことを決意する。
er-suzuki2
人数が多いほどに意思疎通や協働は非常に難しい。一人ひとりに寄りそうと前に進まない問題が多々あり、また、そもそものケイパビリティ不足にも関わらず人脈や温情で配属・採用された人材をどう扱うかなど難しい。研修の中での立て付けは理解するが、現場ではさまざまな問題があり、型通りにはいかないということを経営は理解してほしい
blue_t_ree
意見の相違や対立が表面化するのは役割や目標を確認する段階の形成期ではないでしょうか。
nikonnikon
多様性のあるメンバー構成では、意見の対立が起きることが自然です。意見の対立が起きないようにするでのはなく、起きたことでチームが更に発展するチャンスであると捉えたいと思います。
d-tomi
集団の発展段階を学んだことで、業務では新しいプロジェクトチームが混乱期にあるときに、意見の対立を成長のプロセスと捉え、冷静に調整できると感じました。
日常生活でも、地域活動や家族内での役割分担が固まる過程を理解し、相手の立場を尊重しながら円滑に関係を築くことに活かせると思います
kamiya_youhei
多様性のあるメンバー構成が大事であることは、多角的な視点を得たり、新たな仕事のやり方を生み出すことに優位であることは、経験的に理解できる。リーダーだけが多様性を大事にするのではなく、チームメンバーも多様性を求める風土をチーム内に作ることが、リーダー大事なことだと思う。
m_tera
チームメンバーも互いの相乗効果を出すことに責任があることがわかりました。
個人の業務をこなしているだけでは求められることに対しては不十分であると認識しました。
12dc19hxs
チームを構成するメンバーの仕事に対する意識や取り組み姿勢が大きく影響すると思います。
自分だけが良ければよい、他人に興味が無い、For the Team の考え方が無い社員が多すぎる上、結果、数字しか興味のない管理者、経営者が多い会社の為、既に終わっていると思っています。
kunimako
衝突をなるべく避けるようなチーム形成をしていました。議論を交わし衝突が生まれるのは必要な事だと学びました
nomura2510276
チームと集団中々難しい
youko15
課としてチームになっていても部としてチームになっていない場合が多いのではないかと思う。
240497
各担当者の業務内容の理解向上のため、センター内会議等を通じて、共有を図る
t-wat78
まずは目標を設定すること。そして、納得してもらい、課員達で意見の交換をできるように促していくこと。
ここから始めて意識改革していきたい。
yoshiharu_baba
リーダーがチームの目標を設定しメンバーに周知することを再徹底したい。チーム編成は時間とともに変化してきているため同じ認識になっていない可能性もあるため
kinchan0726
メンバー自分自身の仕事の責任をチームの活動を最大化するための「相互責任」との両方を負うように機能させる支援に取り組む。
先ずは多様性の違いを活かすダイバーシティ&インクルージョンも視野に入れ、積極的に取り組む。
激動期におけるメンバー同士の衝突や、チームのビジョンや目標に賛同しないメンバーの脱退も恐れないで、
最終的にはチームで成果を出す、という強い意志を持ってやりきる。
sr-mandarin
チームリーダーとして組織を率いて行こうと思う。
sasamiiiii
チームとなっていくための目標は具体的に納得できるものであることが必要なのかなと思った
takuma_seraku
おもしろいね。いろいろと。
sachi_0819
自分の考えを正とし、人の意見を参考にしない人が多いので、何度も話し合いをし、それぞれの立ち位置を理解する事から始める。
ishikawa_ics
今回の動画内容に当てはめると、自身の率いるチームはチームではなくまだ「集団」であると思った。個々人の能力は高く、個人で抱える仕事自体はうまく処理できているが、チームとして機能しているかと考えると疑問が残る。激動期を迎えることも難しそうだと思うので、まずメンバーそれぞれに対して目標や意識の共有からやっていきたいと思う
tomo1216
チームとしての目標を共有し、各個人のスキルの合わせたタスクを設定することで、最大の成果を発揮できるよう、チームの指揮を取れるよう日々研鑽する。
ngjn2
集団の発展段階を体系的に理解できたため、自身のチームでも実践したい
furaibou
チームとして目標を共有し個々の特性を活かし、協力しあえる環境となるよう働きかけていくようにしていきます。
yamaneki
期に応じてマネジメントしてみる
miketty
自身も過去に集団の段階に属していたのだと振り返って納得しました。最終的には良いチームになったものも、決して最初から良いチームだったわけではなく、あえて様々な意見が出て衝突が起きたからその形になったのだと。
1972shin
集団とチームの違いは理解できました。
チームの優位性を再認識し、さらに取り組もうと思いました。
fuku_ka
メンバーとの相互関係を見極めながらチーム力をあげていく
toby1967
チームメンバーの構成に多様性が重要ということを認識したので入替等して積極的に変化をさせていきたいし、チームの成長段階を常に見ていきたいと思う。
miuzyasu580109
チームビルディングは難しい。
2対6対2の法則も経験している。
それもリーダーシップの問題なのか❔と頭を抱えてしまう。
s-onoue
段階に踏まえてマネジメントします。まずは目標作りから
ooooosome
チームがどんな状況にあるのかを理解し、チームの段階によって適切なマネジメントをしていく必要があると感じた。
チーム内の衝突はできるだけ避けた方がいいと考えていたが、チームを醸成していく上では必要なステップの一つであると認識した。
t-yui
今は安定した環境にいますが自分が異動などでチームを作る、または変革を起こすなどの役割になったときには大変役に立つ知識だと思いました。特に激動期はチームがまとまるまでの一つの階段だと思えば、個人的な感情を抑えて冷静に見守ることができるのではないかと思います。ありがとうございました。
ryo_tanaka5
チームについて深く考えたことがなかったので、
今の集団をチームに成長させるようにプロセスを見直したい。
youngbook
集団とチームの違いに直面している部署があるので、集団からチームになるべく行動を示してあげたい。
syasaka10
集団をチームにできても異動等でまた一からやる難しさがあると思いました。
ryotaro_f_
集団の発展段階についての内容が非常に学びになった
sh_kawano
チームを段階で言語化するということは新鮮であった。
matsuda_taka
自部門の状態が現時点でどの段階にあるのかを理解し、次の段階に進むために何をしたら良いのかが理解できた。
kotarou-
残念ながら、集団のままでチームにはなっていない。
個人の成績にフォーカスされるので、自分自身の仕事にのみ責任を負っている。
チームの活動になれるような改革が必要。
kenta-takamiya
現在チームがどのような状況にあるのか、どのようなチームにしていくことが目標達成やメンバーの目標達成につながるのかよく考えていきたい
masasama14
作っては終わるようなチームを作ったことはないが、今後プロジェクトチーム等を作るときは、チームは変化・成長していくものとして理解しておく。
tomikichi9
チームと集団の違いがよくわかった。
チームがうまく機能しない際、マネジメント側の責任が問われることが多いが、メンバー間の相互理解や協力をうまく引き出すことが大切だとわかった。
ishishiinoshi
自分たちのチームはまだまだ”集団”なのだと認識することができた。
激動期を経ないと規範形成期や実現期は訪れないことは理解できるが、
激動期で声の大きなメンバだけで議論が進んでしまうと
良い方向には進まないと考えている。
ここのコントロールがリーダーやマネージャーの力量だと感じた。
tnomoto
現在の若いチームの変遷の過程を学ぶことができる。
keisuke_toyota
衝突は恐れない。それを乗り越えてチームとしての成果が出せる。
norigoma
まず 形成期(Forming) では、新しいメンバーが加わった際や新しい業務を立ち上げる際が典型です。例えば、新任のメンバーに広宣費ルールやJV精算の流れを説明しても、最初は発言も少なく、まだ役割や立ち位置を探っている段階だと感じます。この時期は、私自身が丁寧に業務の背景や狙いを伝え、安心して質問できる雰囲気を作るようにしています。
次に 激動期(Storming) では、役割分担や進め方を巡って意見がぶつかることがあります。例えば、広宣費の按分方法をどうするか、TLシステムの入力ルールをどこまで厳格に運用するか、といった場面でメンバー間の主張が対立することもあります。私はこの段階を「避けるもの」ではなく、あえて意見をぶつけ合うことで本音を引き出し、方向性を整理する機会と考えています。
その後 規範形成期(Norming) に入ると、次第に「こういうときはこう共有する」という暗黙のルールが定着していきます。部下が強みを発揮しながら互いにフォローする動きが出てきました。課会でも以前より活発に意見が出るようになってきています。
最後に 終了期(Adjourning) は、特定のプロジェクトや提案が完結したときに訪れます。例えば、販売苦戦物件一覧を整理して専務提案を終えたあとや、価格決定稟議に関する臨時対応が一段落したときです。この時期には、やりきった成果を振り返り、「次に活かせる教訓は何か」をチーム内で共有することを意識しています。
morihiro0718
現在のチームの状態を把握して、その状態において、メンバーのマネジメントを考えていく必要がある。
現在、4チームのマネジメントをしているが、チームによって実現期や激動期もあるため、全体としてのマネジメントとの整合性が難しい場合もある。チームに応じたマネジメントを実践していくことを学んだ。
sakaida_n
チームになっていくまでの過程を知ることができて良かった。
kawauchit
チームには段階があることを知った。今すぐうまくいかないと言って悲観することはないと感じた。
hara-ka
形成段階において対応を変える意識が必要だとかんじた。
beginner2025
各フェーズにおける対応を加味して行動したい
mami-hatanaka
規範形成期(Norming)は、チームの規範づくりや役割分担の認識合わせ、課題の話し合いなどを通じて、メンバーが協力し合える状態になっている段階
tk8897
リーダーとなり、当初示した目標やビジョンがあったが、メンバーの入れ替えや外部環境の変化によっては、随時示し続け、共通認識を常に維持する必要があることが大事と感じた。それがあって初めて次の段階に進む下地となる。
aya_t0_mi
「去る者がいても良い」というのをネガティブに捉えがちだけれど、一概にはそう言えないなと気づきがありました。
tsuyoshiito
チームの発展段階によって注意する点が異なることが分かったので、その点を考慮し、今後のチーム育成に活かしていきたい。
11702007ohta
リーダーが目標を明確にし、メンバーに周知・理解してもらい、各々が目標達成できるように、自己解決できるように促し、また不足部分はサポートする事が重要である。業務上についての議論は多いに重要であり一時的な衝突はあってもその後の相互理解で解決できる環境を整え、それぞれの特性をいかしチームに纏めるのも重要だと思いました。
konbu0000
どうしてもチーム内で波風立てないようにすることを念頭に置きがちだが、
そういう時期を経て、チームと成長できるのだと思った。
tarin
集団とチームの違いを知りました。チームを作るには自分やメンバーの意見を聞き、業務を進めてくうえで意識していきたい。
j-otsuka
チームの発展段階について学び、今後のチーム作りにおいて段階に応じた必要な対応を理解することができました。