
無料
ビジネスの全体像ってどうなってるの?
ビジネスを学ぶとはどういうことか、学びの全体像を解説します。 「全社の戦略って何で知る必要があるの?」「自分は会計や財務とは無縁なんだけど…」などと思われている方も、全体像を知ることでビジネスを学ぶモチベーションアップにつながったり、実務で他部門の視点を想像しやすくなって仕事が楽しく、効率的に進められるようになるかもしれません。 学び始め、あるいは何を学ぶべきか迷った際のチュートリアル動画として、ぜひご活用ください。
割引情報をチェック!
すべての動画をフルで見よう!
初回登録なら7日間無料! いつでも解約OK
いますぐ無料体験へ
・チームマネジメントに携わっている
・もしくは携わりたい方
・仕事の効率を上げたいと考えている方
比較優位の法則とは、「自分が得意なことに集中し、苦手なことはそれを得意とする人に任せた方が全体の効率が増す」という考え方です。元は貿易論における各国の役割分担を考える際に用いられたものですが、効率性が求められる昨今のビジネスや職場においても活用できる考え方です。具体的な活用方法や留意点を、事例とともに学びましょう。

無料
ビジネスの全体像ってどうなってるの?
ビジネスを学ぶとはどういうことか、学びの全体像を解説します。 「全社の戦略って何で知る必要があるの?」「自分は会計や財務とは無縁なんだけど…」などと思われている方も、全体像を知ることでビジネスを学ぶモチベーションアップにつながったり、実務で他部門の視点を想像しやすくなって仕事が楽しく、効率的に進められるようになるかもしれません。 学び始め、あるいは何を学ぶべきか迷った際のチュートリアル動画として、ぜひご活用ください。

会員限定
ルールのすり抜け ~より楽な方法を選ぶ人間の性質を知り、活かす
ルールのすり抜けとは、「ルール本来の目的や意図に沿った行動ではなく、都合の良い行動をとって成果を出そうとする人間の性質」のことを指します。他方でこれが業界ルールを変えるきっかけとなることもあります。よくある事例を通して、ルールのすり抜けが生じる背景を理解し、効果的なルールの策定と運用方法について学んでいきましょう。

会員限定
セグメンテーション・ターゲティング ~標的市場を絞り込み見極める~
昨今、市場の成熟化に伴い、顧客ニーズが細分化され多様化しており、そうしたニーズすべてに応えることは現実的ではなくなっています。 セグメンテーション・ターゲティングは、標的市場の絞り込みや、自社の強みが活きそうな市場の見極め、限られた資源の分散度合いの検討などの場面に用いることができます。 これにより企業は費用対効果高く市場にアプローチし、キャッシュを生み出すことができます。

会員限定
フォースフィールド分析 ~人々の心に作用している見えない力を可視化する~
フォースフィールド分析とは、人々の心に働く、推進力と抵抗力を分析する手法です。 推進力とは前に進めようとする力であり、抵抗力とはそれを妨げる力です。これらは人々の心に作用している見えない力ですが、この分析を使えば、プロジェクトや計画がうまくいっていない場合などに、その原因を推進力と抵抗力に分けて捉え可視化することができます。 フォースフィールド分析によって、「心に働いている力」を可視化し、チームを前に進めていきましょう。
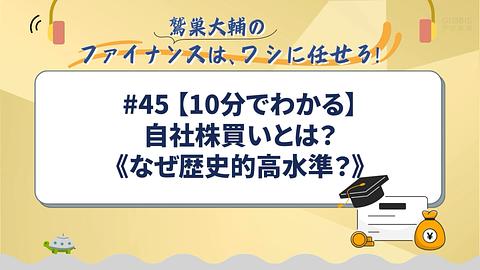
01月27日まで無料
【10分でわかる】自社株買いとは?《なぜ歴史的高水準?》/鷲巣大輔の「ファイナンスは、ワシに任せろ!」
多くのビジネスパーソンが苦手意識を持っているが、今さら聞けないと思っているファイナンス知識を簡単に楽しく学べるコース。グロービス経営大学院でファイナンスクラスの講師を務める“ワッシー先生”こと、鷲巣大輔氏が解説します。本コースは日本最大のビジネススクール グロービス経営大学院による、ビジネスパーソンが予測不能な時代であっても活躍のチャンスを掴み続けるヒントをお伝えするVoicyチャンネルからの転載コンテンツです。 Voicyチャンネルはこちら https://voicy.jp/channel/880 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年01月公開)

無料
みんなの学習図鑑 ~新人育成・オンボーディング編~
グロ放題をうまく活用したいと思ってはいるけれど、他の人がどう学んでいるのか気になりませんか? このシリーズは、ユーザーのみなさんの“超リアル”なグロ放題の活用法をまとめた学習図鑑です。 シナリオ作成も撮影も、実際のユーザーさんご自身に行っていただきました。 ぜひ自分に合った学習スタイルを見つけて、グロ放題ライフを楽しんでください!応援しています! ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)

無料
みんなの学習図鑑 ~グロ放題に聞いてみよう!編~
グロ放題をうまく活用したいと思ってはいるけれど、他の人がどう学んでいるのか気になりませんか? このシリーズは、ユーザーのみなさんの“超リアル”なグロ放題の活用法をまとめた学習図鑑です。 シナリオ作成も撮影も、実際のユーザーさんご自身に行っていただきました。 ぜひ自分に合った学習スタイルを見つけて、グロ放題ライフを楽しんでください!応援しています! ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
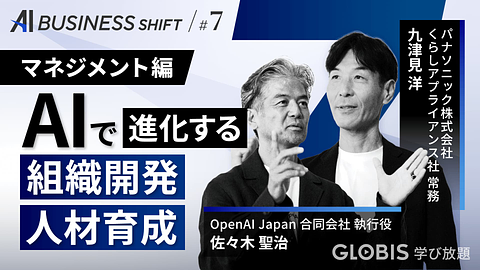
01月27日まで無料
AI BUSINESS SHIFT 第7回 マネジメント編:AIで進化する組織開発・人材育成
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第7回です。 第7回「AIで進化する組織開発・人材育成」では、AIは人や組織にどのような影響を与えるのか、人や組織はAIと共にどのように進化していくべきかについて学びます。 ■こんな方におすすめ ・AI時代の組織開発や人材育成のポイントを学びたい方 ・組織開発や人材育成を担う人事担当者や現場リーダーの方 ・OpenAIやパナソニックHDの取り組みを参考にしたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)

会員限定
ロジックツリー ~物事を把握する「分解」の考え方~
ロジック・ツリーとは、モレなくダブりなく(MECE)を意識して上位概念を下位の概念に分解していく際に用いられる思考ツールです。 問題解決で、本質的な問題がどこにあるのかを絞り込む場面や本質的な課題に対して解決策を考える場面で活用できます。 ※2020年3月30日、動画内のビジュアル、表現を一部リニューアルしました。 理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
MECE ~抜け漏れなく分解・構造化して考える~
MECEとは、ある物事を「モレなくダブりなく」切り分けた状態のことです。例えば年代別など、全ての人がその切り分けのどこかに属するようにします。MECEは論理思考の基本で、物事を分解し、構造化する際に役立つ考え方です。 例えば、状況を調べて問題箇所を特定する必要がある場合に、いくつかのポイントに分解して考えることが重要になります。その際に、モレやダブリなく分解することができれば、分析や問題解決の効率性が高まります。 ロジックツリーやマトリックス、あるいはその他のフレームワークなどにも応用できる基本となるコンセプトであるMECEを理解しましょう。 ※2018年2月15日にコース内容を一部リニューアルいたしました。 リニューアルに伴い、コース動画一覧は全て未視聴の状態となります。 なお、リニューアル前に当コースを修了している方は、コース修了済のステータスに変更は発生いたしません。

会員限定
貸借対照表 ~企業の財務活動と投資活動を読み解く~
財務諸表の要の1つである貸借対照表(B/S)は、ある時点(決算期末時点)での企業の資産内容を表します。継続的な経済活動を行っている企業の一瞬の姿をとらえたスナップ写真ともいえる貸借対照表を理解し、企業の財務活動と投資活動の結果を読み解く力を身につけましょう。 ☆関連情報 フレームワークでニュースを読み解く、日経電子版の記事もぜひご覧ください。 「米SPAC上場ブーム、引き金はコロナ禍の失業対策」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC27E130X20C21A4000000/?n_cid=DSPRM5277

会員限定
リーダーシップとマネジメントの違い ~違いと使い方を理解する~
リーダーシップとマネジメントの違いとは、主にそれぞれ異なる特性と役割にあります。リーダーシップは人と組織を動かし変革を推し進める機能、マネジメントは定められた戦略やルールに基づき効率的に組織を運営する機能とそれぞれ定義されています。このコースでは、リーダーシップとマネジメントの違いについて詳しく学んでいきます。2つの違いと意味を理解し、日頃の業務やコミュニケーションに役立てていきましょう。 ☆関連情報 フレームワークでニュースを読み解く、こちらの記事もぜひご覧ください。 「吉本興業のこれからに必要なのはどっち?リーダーシップ、それともマネジメント?」 https://globis.jp/article/7224 「日本電産の永守氏にみる有事のリーダーシップ」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58614190Y0A420C2X12000/?n_cid=DSPRM5277

会員限定
クリティカル・シンキング(論理思考編)
業種、職種、役職を問わずビジネスパーソンが業務のスピードとクオリティを効率よく高めるために必要不可欠な論理思考力。 論理思考のベースとなる考え方を学び、実務で陥りやすい注意点を理解することで、実践で活用する能力を養います。 論理思考の基本を身につけ、コミュニケーションや業務の進行に役立てましょう。 論理思考を初めて学ぶ方は、以下の関連コースを事前に視聴することをお薦めします。 ・論理思考で仕事の壁を乗り越える5つのポイント ・MECE ・ロジックツリー ・ピラミッド構造 ・演繹的/帰納的思考 ・イシューと枠組み ※2019年10月31日、動画内のビジュアルを一部リニューアルしました。 内容に変更はなく、理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
ロジックツリー ~物事を把握する「分解」の考え方~
ロジック・ツリーとは、モレなくダブりなく(MECE)を意識して上位概念を下位の概念に分解していく際に用いられる思考ツールです。 問題解決で、本質的な問題がどこにあるのかを絞り込む場面や本質的な課題に対して解決策を考える場面で活用できます。 ※2020年3月30日、動画内のビジュアル、表現を一部リニューアルしました。 理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
論理思考で仕事の壁を乗り越える5つのポイント
伝えたいことがうまく相手に伝わらない。仕事がなかなかスムーズに進まない。 仕事をしていると、そんな場面に直面することもあるのではないでしょうか。 そんな方に役に立つのが「論理思考」です。 物事を論理的に考えられるようになると、仕事の効率が格段にアップします。 このコースでは、論理思考のコツを5つに絞って説明していきます。 ビジネスパーソンにとって必須のスキルである「論理思考」をいち早く身につけましょう。 「クリティカル・シンキング」をまだ見ていない方にもお勧めのコースです。

会員限定
MECE ~抜け漏れなく分解・構造化して考える~
MECEとは、ある物事を「モレなくダブりなく」切り分けた状態のことです。例えば年代別など、全ての人がその切り分けのどこかに属するようにします。MECEは論理思考の基本で、物事を分解し、構造化する際に役立つ考え方です。 例えば、状況を調べて問題箇所を特定する必要がある場合に、いくつかのポイントに分解して考えることが重要になります。その際に、モレやダブリなく分解することができれば、分析や問題解決の効率性が高まります。 ロジックツリーやマトリックス、あるいはその他のフレームワークなどにも応用できる基本となるコンセプトであるMECEを理解しましょう。 ※2018年2月15日にコース内容を一部リニューアルいたしました。 リニューアルに伴い、コース動画一覧は全て未視聴の状態となります。 なお、リニューアル前に当コースを修了している方は、コース修了済のステータスに変更は発生いたしません。

会員限定
MECE ~抜け漏れなく分解・構造化して考える~
MECEとは、ある物事を「モレなくダブりなく」切り分けた状態のことです。例えば年代別など、全ての人がその切り分けのどこかに属するようにします。MECEは論理思考の基本で、物事を分解し、構造化する際に役立つ考え方です。 例えば、状況を調べて問題箇所を特定する必要がある場合に、いくつかのポイントに分解して考えることが重要になります。その際に、モレやダブリなく分解することができれば、分析や問題解決の効率性が高まります。 ロジックツリーやマトリックス、あるいはその他のフレームワークなどにも応用できる基本となるコンセプトであるMECEを理解しましょう。 ※2018年2月15日にコース内容を一部リニューアルいたしました。 リニューアルに伴い、コース動画一覧は全て未視聴の状態となります。 なお、リニューアル前に当コースを修了している方は、コース修了済のステータスに変更は発生いたしません。

会員限定
ロジックツリー ~物事を把握する「分解」の考え方~
ロジック・ツリーとは、モレなくダブりなく(MECE)を意識して上位概念を下位の概念に分解していく際に用いられる思考ツールです。 問題解決で、本質的な問題がどこにあるのかを絞り込む場面や本質的な課題に対して解決策を考える場面で活用できます。 ※2020年3月30日、動画内のビジュアル、表現を一部リニューアルしました。 理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
リーダーシップとマネジメントの違い ~違いと使い方を理解する~
リーダーシップとマネジメントの違いとは、主にそれぞれ異なる特性と役割にあります。リーダーシップは人と組織を動かし変革を推し進める機能、マネジメントは定められた戦略やルールに基づき効率的に組織を運営する機能とそれぞれ定義されています。このコースでは、リーダーシップとマネジメントの違いについて詳しく学んでいきます。2つの違いと意味を理解し、日頃の業務やコミュニケーションに役立てていきましょう。 ☆関連情報 フレームワークでニュースを読み解く、こちらの記事もぜひご覧ください。 「吉本興業のこれからに必要なのはどっち?リーダーシップ、それともマネジメント?」 https://globis.jp/article/7224 「日本電産の永守氏にみる有事のリーダーシップ」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58614190Y0A420C2X12000/?n_cid=DSPRM5277

会員限定
因果関係 ~原因と結果の関連を理解する~
因果関係とは、あるものごとが「原因」と「結果」の関係でつながっていることです。「因果関係」という言葉は様々な場面で使われますが、ビジネスにおいても、因果関係の把握は問題解決などの場面でとても重要な思考技術の一つです。 因果関係を把握し、因果関係を明らかにすることのメリットやコツを身につけましょう。
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
100+人の振り返り
a_7636
人事・労務・法務
比較優位の法則は、業務の俗人化と隣り合わせだと思いました。
中長期的にみた「効率化」を意識したいです。
このコースを見て、強味/弱みに関するコースを思い出しました。
最近一気に増えた【自己啓発】【知見録 Premium】の中でもイチオシなコースです(特に①)。
是非ご覧ください。
①強み/弱み どちらを伸ばすべき?/耳で効く!ビジネスサプリ ビジネスクリニック
【自己啓発】【知見録 Premium】0:05:21
https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/b77f6c20/
②『苦しかったときの話をしようか』/耳で効く!ビジネスサプリ ペライチ書評
【自己啓発】【知見録 Premium】0:05:19
https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/e1110a8d
test_
メーカー技術・研究・開発
比較優位というと、先進国が発展途上国との関係性を固定化するために持ち出した考え方、というイメージが強い。講義でもあったが、関係を固定化がされないように十分に考慮すべきだろう。
ao10
その他
チームの中で、より得意分野を任せ、苦手分野はそれを得意とする人に任せる。
しかし、そればかりでは仕事が限定的になり人材が育たない、仕事に偏りが出る為注意が必要。
shigeto-
その他
マルチスキルの考え方としてマネージメントしいていたが、時には比較優位の考え方も取り入れマネージメントに活かす。
yusam
コンサルタント
理屈は分かるが、仕事がかたよることは避けたいという心理がはたらきそう。
keiko_279
販売・サービス・事務
効率と教育のバランスを見ながら対応するのが良いと考えた。
chiisai-kiba
人事・労務・法務
比較優位というと、業務分担といった一人ずつの「人」を基準に考えがちであるが、チーム全体、あるいはメーカーであれば製造製品全体の経営資源をどのように割り振るか、といった高い視座から考えることで、新たな展開が見えてくる場合があると考えています。
今回の題材も、商品A,Bとありますが、客先がAもBも欲しいというのであれば、これはセットでの販売が必要であり、比較優位で解決できる問題ではなくなってきます。この場合は例えば ”販売企画”担当と”販売実務”担当に分けることで、だれもが一定以上の販売できるような仕掛けを作ることができるようになります。売上の大きな人にそのノウハウを共有し、全体レベルを上げることが本来は必要なプロセスかもしれません。
riken
人事・労務・法務
業務の進め方
だfじゃljふぁ
kz_nkjm
金融・不動産 関連職
効率的な業務の固定化やアウトソーシングは、かえって社員の成長を阻害し、また転職市場に吸い取られてしまう。
そもそも社員の能力や器量を計ったうえで入社させたのだから、優位性で仕事を振って効率を図るのは無責任だと思う。
yuji-fukuniwa
人事・労務・法務
個人の力を最大化するために苦手なことはやらずに得意ことを行った方が本人及び全体としてみても生産性が上がると感じます。
今後、組織のタレントマネジメントで活用していきたい重要項目の一つです。
ozawa_h
IT・WEB・エンジニア
アウトソーシングする場合の留意点として、本当にその仕事が必要なのかです。他GLOBISコースでも取り上げられていましたが、先ずは不要な仕事を減らす必要があります。特に問題の根本的な対策を取れば不要になる仕事を先ず整理します。
比較優位の法則に従って作業を行うもう一つ留意点があります。他メンバー作業の最低限レベルのスキルがあることです。最低レベルのスキルがなくて学習する意欲もないと後から直すことになり反対に費用と時間が掛かるようになります。
GLOBISの他コースでも取り上げられているように学習する組織を作ることが大事です。
e-b-i-h-a-r-a
IT・WEB・エンジニア
プロジェクトの体制づくりに活かせる考え方だと思う。
日頃から周りのスキル状況をヒアリングしておくことが大事だと思う。
あとは、やはり攻める分野を定めないと得意なものが活かせる場所がなかなかこない可能性がある。
0402_nyy
IT・WEB・エンジニア
得意不得意は生産性においてありうることです。得意分野は、より活かしてさらに生産性を上げるようにが重要
fhz_0111
営業
部内業務の割り振り
sssss2
メーカー技術・研究・開発
後進を育てることや自身の深い理解のためには比較優位の逆をすることが大事。目的や期間を考える。
現在のアウトソーシングもこの比較優位をもとに考えられたのかなと思った
i_sao
営業
メンバーの組み合わせの工夫。ベテラン社員の活用。
anshin_master
営業
比較優位のメリットと若手育成のバランスが大事。また短期的には合理的でも幅広い知識がつくことによる中長期的なメリットの比較してはどうなんだろか?
75475
メーカー技術・研究・開発
業務効率化のヒントになる
aaaaafafa
販売・サービス・事務
比較対象のアウトプットはどのようにして図るのが良いか、時間当たりで表せない部分は無視するのが良いのか、ここがわからないと現実的でない部分もあるように感じる
yutakabu
販売・サービス・事務
言われていることはご最もだと思いますが、それを判断できる上司がいてこそですね。どうしても仕事ができる人に業務が集中しがちになっています。
allnightjunk
経営・経営企画
業務内容と業務分担の明確化と確認のスキルの再確認
0210
その他
業務で活用するためには、個々のメンバーがより価値を出せることに時間を使うことを意識しつつ、後進の育成とのバランスをとることが重要である。
mao-joan
経営・経営企画
比較優位の考え方も取り入れてみたい。
sphsph
メーカー技術・研究・開発
課題は長期目線の話しですね。
臨機応変に。
k_fukushima1971
専門職
チームとしてのアウトプットを最大化する為の方策として活用していきたい。その為にはおそらく担当者毎のスキルマップや業務スピードの可視化が必要になってくるだろう。
一方で、中期的視野に立った人材育成計画も並行して行っていく必要もあることを理解した。そうでないと会社や組織の中長期的な成長につながらない。
soji2015
営業
チームとして一つの目標達成に挑むような状況の時にいつでも活用することができる考え方だと思う。その判断が必要になった時に迷うことのないよう、自分自身の得意は何かを常に意識しながら日常のあらゆることに向き合う必要があると思う。
ar87531
販売・サービス・事務
比較優位の法則で仕事を分担しても、中長期的な人材育成を忘れないことが必要。
moco1719
営業
短期的な視野で見れば効果は高いと思うため、まずは部下の特性把握を目的として個別懇談を行う。
sadaosadao
経営・経営企画
自分が管理職になった時に、この法則を活用して、業務分担を行いたいと思います。
mikamikazunori
その他
工程の高齢化に伴い簡単な作業についてはアウトソーシングを活用するようにしていく。
yyacupun
人事・労務・法務
チームのスタッフの得意な事を確認して
業務の分担を図る
kfujimu_0630
マーケティング
比較優位の法則は生産性を上げるのにとても大事だと思いました。きちんと定量化して、優位な仕事を判断するのがポイントですね。人の成長も考えながら、うまく仕事の割り振りができればと思いました。ありがとうございました。
33tiger
人事・労務・法務
現状の採用・育成チームの業務分担を効率化できる余地がある
teruhiko800
営業
概念としてはシンプルで分かりやすいがそれだけでは単純に決まらないなとの思った。
決断時の1つの考えかではある。
tomotanino
その他
派遣社員さんと社員の業務分担について改めて考えるきっかけになった。特に定量的な評価は必要
masahiro_kai
IT・WEB・エンジニア
今の利益を追求する分にはよいかもしれないが、
育成面だったり、何を成果にすべきかを念頭において考えるべき内容と理解した。
vegitaberu
人事・労務・法務
この法則に即して、業務分担をしたいと思いますが、業務を平等に分けるとか、これまでの思い入れとか、効率以外の観点から、なかなかできないことが多いと感じています。どのように、納得してもらうかが、課題だと思っています。
hybrid
クリエイティブ
役割分担を明確化して力を発揮するスタッフは多いです。ただそれだけでいいという惰性も生み出す懸念が付きまといます。
そういった意味では時間がかかっても新しいことに挑戦するという行動も意識していただくようマネジメントをする必要がありますね。
cocona_33
資材・購買・物流
自分だけで苦手なことを克服、カバーしようとしていたが、自分は得意なことに集中し、苦手なことはそれが得意なメンバーに任せることで結果としてチームの総生産性を高められると分かった。メンバーに新しい仕事を渡せるようにまずは自身の基礎をしっかり固める。
koichi-k
営業
後輩への仕事の振り方に活かす。
hiroaki_hongo
営業
なんでも自分でやったほうが早いなりがちだが、限られたリソースなので、得意な物にシフトすることを意識したい。
ikegaya8803
経営・経営企画
貿易論より発症の比較優位則は知らず知らず活用しがちですが留意点に注視したい(後継課題等)。
y-kunihiro
その他
見積作成依頼は速くできる人にまかせることにする。
tomi0822
営業
今後の作業割当にいかします。
yosshi--
営業
効率性・チームの士気・育成の観点を持って比較優位の法則を活用していきたいと思います。
takayuki_sato
営業
貿易や世界経済などのイメージがあったが、得意なことに集中し、全体効率を上げるという汎用的な原則ということがわかり、日常の業務に活用できるし、チームワークとしては常に意識したほうが良いと学びました。
gouda0922
経営・経営企画
得意な仕事に集中させることが結果的な優位性を理解しました
lrg_mp
その他
現状、職場では比較優位の法則のような考え方は用いられておらず、全員同じことを行っていますので、より適材適所の色合いをつけたかたちで配置できるとよいと思いました。
reikou
IT・WEB・エンジニア
自分が得意なことだけやると、苦手なことはいつになっても苦手になる。得意な分野のプロになりながら、苦手分野も克服する必要がある。
ot-take
メーカー技術・研究・開発
得意に集中する、短期的には良いと思いました。
ただ、長期的には属人化や交流の低下や人によってはモチベ低下(マンネリ)になるため、注意が必要と思いました。
私も近々異動があり、異動先は第3希望でした。
第一新しいこと、第二今と同じ、第三過去と同じで、1と3は近い部署でした。
30前半ではあるが、年齢的にも得意なこと・できることに集中しろとの人事の意図なのかと思ったので、改めてこれからのキャリアを考えたいと思いました。
s_atmimi
メーカー技術・研究・開発
どういう考え方にすると、効率があげられるか、そこは理解できた。
また留意点でも語られているが、固定の役割分担が続くと、後進が育たない懸念があることも考えて、いくことも必要である。
touto
営業
私の部署では1人の営業がそれぞれ色々なスキルを高めて顧客と仕入先の間に立って数字の取れる営業マンになってもらう方式をとっているので活用が難しいと思った。
チームでのプロジェクトの役割分担としては使えると思う。
maki4878
その他
以前先輩に
「仕事内容は立場で変わっていかないとね」と言われたことがある。
復習問題にもあったように、自分の得意な事に専念するために後輩に他の仕事を渡さないといけないと思う。
bad
建設・土木 関連職
比較優位の法則により、生産性向上を図られるように職場で生かしたい
go2-2023
営業
マネジメントのひとつの運営手段
t-ishiza
販売・サービス・事務
自分が普段思って行動している事なので、間違っていない事が分かって少し自信がつきました。
14001
資材・購買・物流
多数の仕事を分類し、分担してチームで行っていくことが重要だと思いました。学生の時は得意な科目は午前中に勉強して、苦手な科目は午後に勉強していました。
mae09
その他
得意・効率の良さにも着目して業務の棚卸をする。
担当業務の中で後輩に依頼するもの・自分がするものを決定する際に活用する。
100take
メーカー技術・研究・開発
比較優位の考え方は理解できた。長期スパンの人材育成を考慮すると、どこまで実施すべきか難しいと感じた。
hdfxsts04
メーカー技術・研究・開発
業務分担に役立ちそう
masamunecat
専門職
比較優位の考え方は重要だが、苦手なものをやらない言い訳にならないように注意しないといけない。例えば事業を作り上げる際に、アイディや交渉条件は得意なので、そこにリソースを傾注するが、実現するにあたっての業務要件や設計、システム化は苦手だから他の誰かに投げる、知らないふりを行為(ビジネスにおける上流しかやらない行為)は、比較優位の観点で見ると一定評価されるべきだが、あと工程の人達の苦労やそもそも事業自体が作り上げられないリスクがあることから、全体から見ると比較優位になっていない。
対象業務の形態や対象者の年齢、ポジションによって、使い分ける必要があると考える。
jun_sumi_2023
メーカー技術・研究・開発
自分がより成果を上げられる業務を優先しつつ、後輩の育成を行っていく。時間はかかっても、全体最適を考えて業務を割り振ることが大切。
kikicosmos
人事・労務・法務
得意なことばかりしていたら成長がないこと、その人がいなくなったら困るので、ケースバイケースだと思った。個人的には、得意なこと、専門性を活かして組織に貢献したい。
kankita
営業
PM業務とOE業務を見直してみる
mamisan
専門職
後進を育てるためにどう任せればいいのか少し理解できました
gosimakeizou
営業
得意なことに特化できるのは、ストレスも減り
社員の満足度も上がると思います。
watanabenobu
営業
当面比較優位の仕事に取り組むべきだか、後進育成のために任せることも必要。
ksk_aiko
販売・サービス・事務
ヒトもカネも時間も限られている状況で、不平不満を言っても何も前に進まないと考えさせられました。比較優位の法則の観点から考え、全体効率・生産性を上げる方法を作り出していこうと思いました。
platon
メーカー技術・研究・開発
ジョブ型思考の考え方か
sakakibara_
マーケティング
得意なことに集中し苦手なことは得意な誰かに任せることで、全体の効率を良くすることに活用できる。
sakiyam2
IT・WEB・エンジニア
日頃から適用していると役割が固定されてしまうことが懸念されるが、非常に合理的な考え方のため、いざというときの役割分担の際に、説得力のあるアサインをすることができると思った
rikuema-mama
金融・不動産 関連職
資料作成や事務作業は得意な人に任せ、その他人は顧客対応(受架電業務)に特化する
andy-21
営業
得意な業務への専念、ただし専門家にしてしまうことは後身が育たないということには留意する必要がある.
yuyu356
メーカー技術・研究・開発
自分の会社では人手不足や会社の規模の小ささのため得意なことに特化して業務を行うことはできていないと思う。
規模の小さい会社でもどうすれば比較優位の法則を用いて業務ができるか考えようと思いました。
keisuke930111
IT・WEB・エンジニア
比較優位を使うにあたっては、自分の得意な仕事と苦手な仕事を分析しておくことが大事だと思いました。
hikoaz
人事・労務・法務
スタッフの業務状況をよく観察し、効率の高い業務、悪い業務を上司として把握する。全体最適の視点で、最終的に育成と売上の両面がカバーできるようにしたい。
yoshihide-s
その他
改めて言葉にして整理されると納得感が出る。
izapon1976
その他
比較優位の法則は、有用だとは思うが、バランスをとって用いようと感じた。
alpina_b3s
販売・サービス・事務
まとめ
①比較優位の法則は、個々の得意分野の任せることで、チームの効率的な生産性を上げることに適しています。
②ただし、人材育成の為には個々の役割分担を変えていく必要があること。
jinao
マーケティング
個人的には比較優位の法則に従って、業務を遂行していくことの方が効率的だと考えるが、最近はリスキリングなどの言葉も盛んに使われ、自分が苦手だと考えているものや、携わってこなかったものに挑戦し成長することが大事だという風潮もある。どちらがより将来的に選択される方法なのか知りたい。
anzeneisei
その他
生産数のノルマがあればそれの達成は必須。但し、数量を計画する際はNG品発生する考慮も必要。
x0888
メーカー技術・研究・開発
作業色の強い業務は、初めてのメンバーにも振っていく。
hirotana13
メディカル 関連職
使い方にコツはあるが、全体の生産性を上げらためには必要な方法ではある。
導入時の注意とが必要とはおもった。
manabiho
建設・土木 関連職
比較優位の法則という考え方が、貿易関連に由来する考え方ということをはじめて知りました。
全体の生産性を向上できるよう、自分の部署にも活用していきたいと思います。
suzuki12345678
メーカー技術・研究・開発
複数の業務を並行して行うより、得意分野に特化することで全体効率が高まる。
redpine
IT・WEB・エンジニア
所属組織においても特定メンバーに業務が集中する傾向が見られる。集中することが仕方がないと思う組織文化・社風もある。まずは、その点においての改善が必要。トップダウンでの意識づけを継続的に行う必要があると考える。
jun_iwashita_46
メーカー技術・研究・開発
単純作業であれば、比較優位の法則で効率UPできるが、時間に対し常に同じアウトプットができないような想像的な仕事もあるのでバランスが大事だと思います。ただ、できる人に仕事が集中するようなマネジメントは避けていきたいと思います。
tokai-teio
その他
比較優位で効率があがるのはわかるが、比較優位に固執してしまわないよう考慮していきたい
sou_kake
営業
それぞれ部下にも得意不得意があるので、得意分野を持つ部下には力を発揮できる役割を与えて生産性を高める。
debora
クリエイティブ
比較優位の法則はいつも念頭におきながら采配をしているもののノウハウの共有化には課題を持つので今後も工夫しきたあ
chain
販売・サービス・事務
影山さんの業務範囲を考える。
得意なものはわからないが、苦手なものが作業系であること、スケジュール管理であることは明らかなので、これらを他の人に回す?
it_tm
IT・WEB・エンジニア
後進育成を阻害しないシチュエーション、例えば短期的に成果を求められるPJなどで活用したい。
最も得意とする業務・分野を個人ごとに予め把握しておく必要がある。
yujihoshi
経営・経営企画
商談においてセリングが得意でもクロージングが苦手で勝率が上がらない場合がある。だはクロージングは得意な人にやらせればいいとアドバイスもらったこともあるが、お客様にとって担当が変わることへの抵抗感や何よりセリングしたスタックのプライドも考えながらサポートしたい
shimoosako
人事・労務・法務
仕事が出来る人に仕事が集中しがち。自分がやってしまった方が早く完成する。などの考えにより後任の教育が遅れているのが現状の為、比較優位の法則を取り入れ改善したいです。
muramatsu-a
人事・労務・法務
自分がやった方が早いという業務も、自信がより効率の良い業務に集中し、そちらは他に任せる事で、全体の生産性が高まる。
nk1225tk
営業
優秀な社員に仕事が片寄る事で生産性が落ちたり、結果ESやCSが下がることもある。
得意分野を任せ、それ以外の分野が得意な社員に任せるよう分担することで生産性があがり、特定の社員に仕事が片寄らないようバランスをとる。
uta0612
人事・労務・法務
比較優位の法則をうまく取り入れたいと思いますが、「苦手なことは人に任せたらいい」とう考え方が、啓発すべきこと(苦手なこと)を完全に避けるようにならないよう、上手く伝えていかないといけないと思いました。
summner
金融・不動産 関連職
当チームの業務が拡大し、複数の業務を行っていかなけらばならない状況にある。シフト勤務で対応しているため全員同じ業務を行うようにしているが限界を感じている。比較優位の法則に則り、業務分担の検討を行っていきたい。
ab0110
専門職
忙しいときの対応は得意なもの、通常のときはトレーニングを兼ねてなれない仕事をやる。
mie_uchida
メーカー技術・研究・開発
文書作成が不得意なメンバーが多い。文書の定型化および文書作成の専任化を進めるとよい。