昨年12月発売の『ベンチャーキャピタルの実務』から「プロローグ Section6 VCのバリューチェーン」を紹介します。
ベンチャーキャピタル(VC)の仕事と言えば、投資先の発掘、投資、経営支援、エグジット(株式売却)といった流れを思いうかべる人が多いかもしれません。事実、ベンチャーキャピタリストはこれらの業務に多くの時間を割き、価値創出を行います。これらがVCの主活動と言ってもいいかもしれません。
しかし、VCの活動はそれだけではありません。ファンドの運営やファンドレイズ(LPからの資金集め)、ファンドマネジメントといった支援的な業務もVCが円滑にファンドを運営するうえで重要になります。特に海外の機関投資家などから資金を調達している場合は英語での詳細なレポートやコミュニケーションが必要になるなど、こうした支援活動の重要性は増していきます。
一般に若手のキャピタリストは上記の主活動にフォーカスしますが、パートナーをはじめとする幹部は、支援活動も含めたバリューチェーン全体に責任を負います。特にファンドレイズの力、すなわち資金調達の力は、VCの経営陣の力量や過去のトラックレコード(実績)をそのまま反映します。
主活動と支援活動が好循環を描きながら運営され、また属人的なやり方に頼るのではなく、バリューチェーンの各活動においてさまざまなノウハウが蓄積されているのが良いVCなのです。
(このシリーズは、グロービス経営大学院で教科書や副読本として使われている書籍から、東洋経済新報社のご厚意により、厳選した項目を抜粋・転載するワンポイント学びコーナーです)
VCのバリューチェーン
VCの業務はそれぞれのファンドもしくはベンチャーキャピタリストによる多様性が大きく体系化が難しいが、全体像を俯瞰すると下図のように整理される。

本書では、ソーシング(投資先発掘)、デューデリジェンス(DD:投資先の価値及びリスク評価)、経営支援、エグジットというVCの主要な投資活動のみならず、資金を集めファンドを組成するファンドレイズ、持続可能なファンド組織の維持に必要で競争優位の源泉にもなりうるファンド管理、VC組織体制や戦略設計も含めた全体的なファンドマネジメントというバリューチェーンの各活動を章立てとし、詳しく内容を解説していく。ここでは、概要のみ紹介する。
ソーシング
投資先候補を発掘し、投資検討に進めるための活動。ファンド組織としての活動や評判、キャピタリスト個人の活動(起業家や他のステークホルダーとの日々のネットワーキング)の双方が主たるドライバーとなる。
投資検討・デューデリジェンス(DD)
ソーシングした投資候補先の成長仮説の構築・検討と、それに基づく出資意思決定を行う。起業家とのディスカッションに基づき、事業面のみならず組織面や財務面に関して、将来の変化を見据えた仮説を構築し、投資委員会で議論する。その後、起業家との投資条件についての合意を経て、投資の意思決定・実行に至る。投資決定の後に、外部専門家を活用して技術や会計・法務のDDを実施する場合もある。
特に直近では、世界的な知的財産やデータの取り扱いへの意識の高まりを背景に、スタートアップ企業への投資であっても、ソフトウェアのソースコードのレビューや、セキュリティの脆弱性診断が行われることもある。
経営支援
独立系を中心に投資後の「ハンズオン」支援を掲げるVCが多い。ハンズオンには体系立った明確な定義はなく、取締役会や経営会議におけるアドバイスやその仕組み作り、営業協力、キーマンとなる役職員の採用支援など、活動内容は多岐にわたる。
近年では資金の出し手及び資金量の増加に伴い、スタートアップに対する投資家間の競争が過熱する中で、起業家やスタートアップに対してVCの魅力を訴求する差別化ポイントの1つになっている。
エグジット
VCファンドがその持ち分を売却するイベント。事業が順調に成長したポジティブなケースにおいては、証券市場に上場したり、他の企業に買収されることによりVCファンドにリターンをもたらす。
他方で、成長が停滞し事業継続が困難な場合や、資金調達がうまくいかずにキャッシュフローが尽きる場合、ファンドの満期が近づいた場合などには、取得コストを割る形でのM&Aや部分譲渡、経営者への持分譲渡、起業家との合意に基づく会社の清算により投資を終了することもある。
ファンド管理
投資先への連絡や事務管理、LPへの定例報告や出資を要請するキャピタルコール、投資先持分の時価評価を含むファンド監査、関係省庁への対応、GP内の管理業務など多岐にわたる。
VCファンドにおいては、投資期間中のファンド、育成中のファンド、回収期間のファンドが併存するなど、複数のファンドが同時並行的に動いている時期が存在するため、結果的に投資先の累計社数が多くなり、煩雑なオペレーションが発生する。人員規模が大きくないファンドの中には、当該業務の一部もしくは全部を専門事業者にアウトソースするところもある。
ファンドレイズ
ファンドの組成業務とIR(インベスター・リレーションズ)活動。 LPに出資金を募り、ファンドの建付けを検討・組成する。
原則として現行ファンドの投資期間中は利益相反するファンドを新規に設立できず、一定金額の組入れ(投資実行)を経てから後続ファンドの組成が可能になる。投資期間を5年とするファンドが一般的だが、’近年では5年以内に新規の投資組入れが完了し、約3年に1度のペースで後続ファンドを組成するケースが増えている。
また、ファンドの存続期間中は定期的にLPへの報告や承認取得などのコミュニケーションを実施する。バイアウトファンドでは専任の担当者を置くケースが多い一方で、現在の国内VCにおいては投資担当者が兼ねる場合が多い。
ファンドマネジメント
GPは各投資先への投資意思決定だけではなく、ファンド全体でパフォーマンスを創出するため、投資戦略を策定し、投資委員会における意思決定を通じてステージのバランス、投資タイミング、投資金額を分散させて、規律をもってポートフォリオを管理する必要がある。
さらに、投資担当者の採用・評価・育成を通じたチーム作り、GPとしての独自の競争優位性の構築も重要な仕事の1つである。
著・編集:グロービス・キャピタル・パートナーズ (著), 福島 智史 (編集) 発行日:2022/11/25 価格:3,740円 発行元:東洋経済新報社


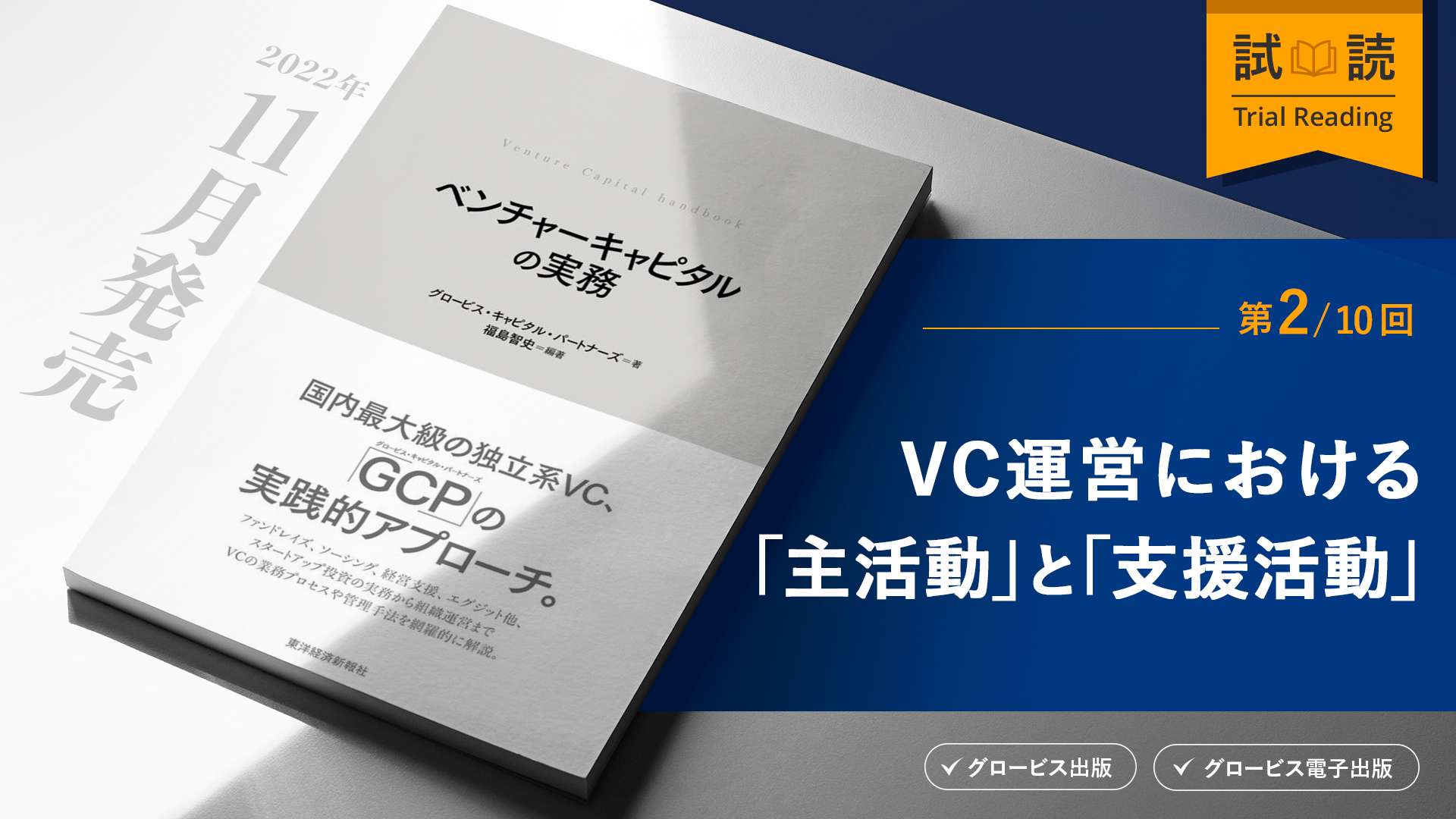










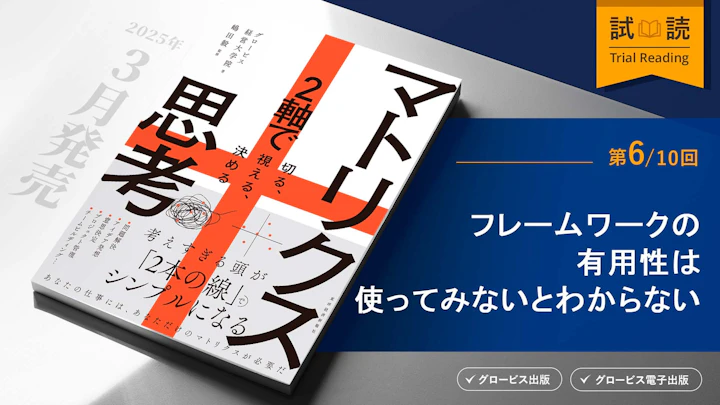
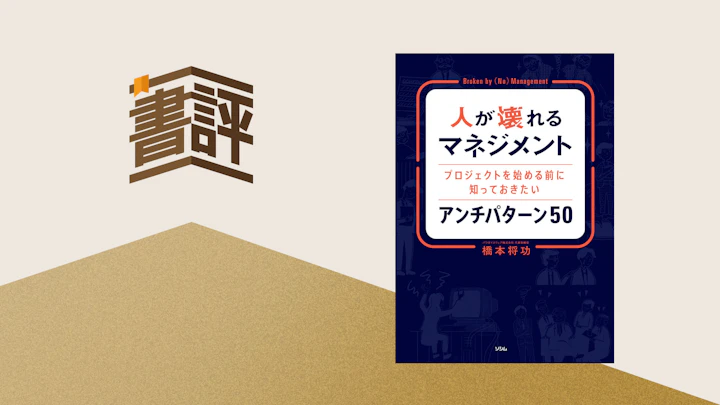



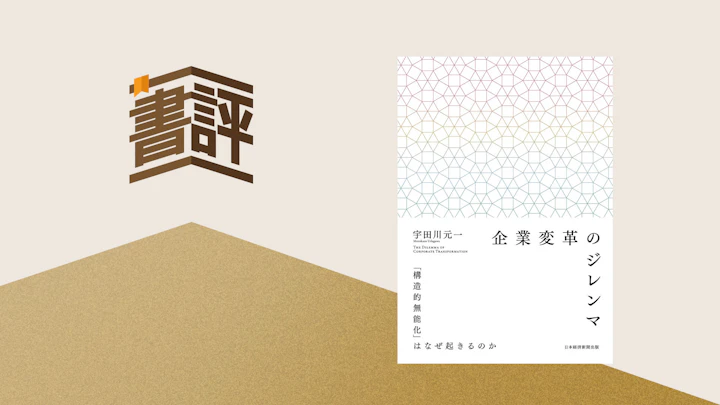
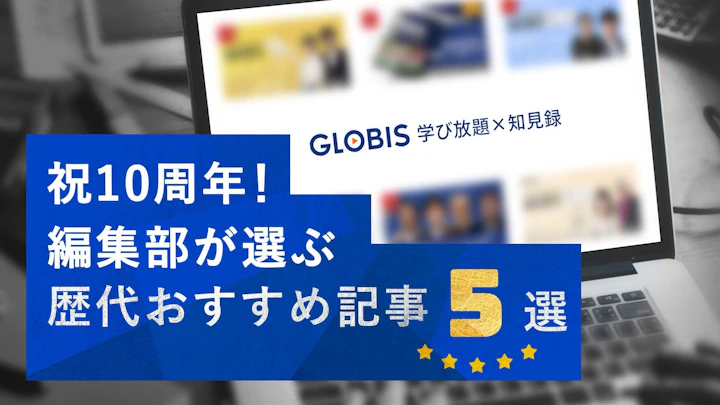






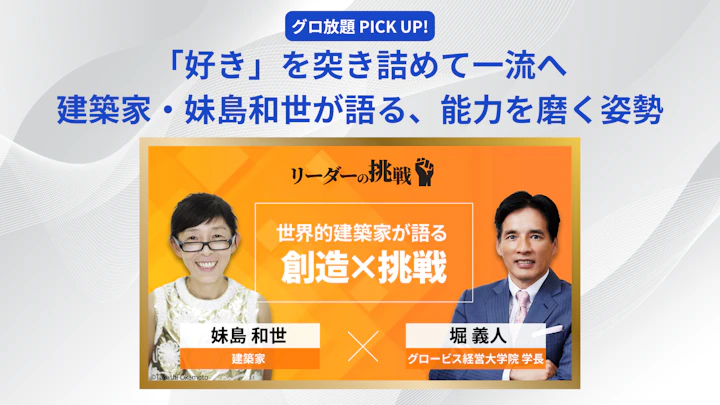
.png?fm=webp&fit=clip&w=720)






