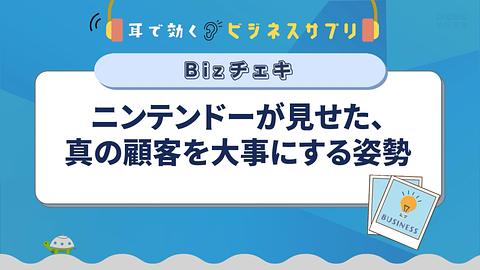SECIモデルとは
SECIモデル(セキモデル)とは、一橋大学の野中郁次郎教授が提唱した、 知識創造活動のメカニズムを説明する理論的な枠組みです。
このモデルでは、個人が持つ「暗黙知」(経験や勘で身につけた言葉にしにくい知識)が、 組織全体で共有できる「形式知」(明文化された知識)に変わっていく過程を、 4つのステップで整理しています。
SECIという名前は、Socialization(共同化)、Externalization(表出化)、 Combination(連結化)、Internalization(内面化)の頭文字から来ており、 この4つのプロセスを循環することで、組織全体の知識創造力が高まるとされています。
なぜSECIモデルが重要なのか - 組織の競争力を左右する知識活用の鍵
現代のビジネス環境では、物理的な資産よりも「知識」や「ノウハウ」といった 無形の資産が企業の競争優位性を決める重要な要素となっています。
しかし、多くの組織では個人が持つ貴重な経験や知見が属人的なものにとどまり、 組織全体で活かしきれていないという課題があります。
①個人の暗黙知を組織の財産に変換できる
SECIモデルが重要な理由の一つは、個人の頭の中にある貴重な知識を、 組織全体で活用できる形に変えることができる点です。
熟練した営業担当者が持つ「なんとなく分かる」顧客の心理や、 ベテラン技術者の「勘」に頼った問題解決方法など、これまで個人に依存していた知識を、 組織の共有財産として蓄積し、活用することが可能になります。
②継続的なイノベーションの土台を築ける
また、SECIモデルは単なる知識の共有にとどまらず、 新しい知識を創造し続ける仕組みを提供してくれます。
既存の知識を組み合わせることで新たなアイデアが生まれ、 それがまた個人のノウハウとして蓄積されるという好循環を作ることで、 組織の継続的な成長とイノベーション創出につながるのです。
SECIモデルの詳しい解説 - 知識が生まれ変わる4つのステップ
SECIモデルの核心は、暗黙知と形式知が相互に変換されながら、 組織全体の知識レベルが向上していくプロセスにあります。
この変換プロセスは、まるでらせん階段を上るように、 4つのステップを循環しながら発展していきます。
①共同化(Socialization)- 経験を共有して暗黙知を伝える
共同化とは、個人が持つ暗黙知を、直接的な体験や観察を通じて 他の人に伝えるプロセスです。
例えば、熟練した職人が弟子に技術を教える際、 言葉では説明しにくい「コツ」や「感覚」を、 実際に一緒に作業することで伝えていく過程がこれにあたります。
現代の企業でも、先輩が新人に業務を教える際の「同行営業」や、 ベテラン社員による「メンタリング」なども共同化の一種といえるでしょう。
②表出化(Externalization)- 暗黙知を言葉や図で表現する
表出化は、これまで言葉にできなかった暗黙知を、 文章や図表、マニュアルなどの形で明文化するプロセスです。
この段階では、「なんとなく分かっている」ことを 「誰でも理解できる形」に変換することが重要になります。
例えば、優秀な営業担当者が持つ「お客様との関係構築のコツ」を 具体的な行動指針として文書化したり、 熟練技術者の問題解決方法をフローチャートにまとめたりする活動がこれにあたります。
③連結化(Combination)- 明文化された知識を組み合わせる
連結化では、既に形式化された複数の知識を組み合わせたり、 整理し直したりすることで、新しい知識体系を作り出します。
異なる部門のマニュアルを統合して新しい業務手順書を作ったり、 複数のプロジェクトで得られた教訓を総合して、 より効果的な手法を開発したりする活動がこのプロセスです。
現在では、ITシステムやデータベースを活用して 大量の情報を効率的に組み合わせることも可能になっており、 AIを用いた知識の自動統合なども連結化の発展形として注目されています。
④内面化(Internalization)- 新しい知識を自分のものにする
内面化は、組織で共有されている形式知を、 個人が実際に使いこなせるスキルや経験として身につけるプロセスです。
マニュアルを読んだり研修を受けたりするだけでなく、 実際の業務で活用することで、その知識が個人の暗黙知として定着していきます。
この段階で新たに蓄積された暗黙知は、次の共同化のサイクルで さらに発展した形で他の人に伝えられることになり、 組織全体の知識創造の螺旋が続いていくのです。
SECIモデルを実務で活かす方法 - 知識創造を促進する具体的なアプローチ
SECIモデルを実際の組織運営に活用するためには、 各プロセスが自然に起こるような環境づくりと仕組み作りが欠かせません。
理論を理解するだけでなく、具体的な施策として実行することで、 組織の知識創造力を大幅に向上させることができます。
①知識共有を促進する「場」を意識的に作る
SECIモデルを効果的に機能させるためには、 知識の共有や創造が自然に起こる「場」を意識的に設計することが重要です。
物理的な場としては、オープンなコミュニケーションスペースの設置や、 部門を越えた交流を促進するカフェエリアの設置などが効果的です。
制度的な場としては、定期的な事例共有会の開催、 異業種交流やプロジェクト横断的なワークショップの実施、 失敗事例も含めた学習機会の提供などが挙げられます。
また、心理的な場として、失敗を恐れずにチャレンジできる風土の醸成や、 知識共有を評価する人事制度の導入も重要な要素となります。
②各プロセスに応じたツールとシステムを整備する
現代では、ITツールを活用することで SECIモデルの各プロセスをより効率的に支援できます。
共同化では、ビデオ会議システムやバーチャルワークスペースを活用して、 物理的に離れた場所にいても経験共有ができる環境を整備できます。
表出化では、ナレッジベースシステムやWikiツールを導入して、 個人の知識を簡単に文書化・共有できる仕組みを作ることが有効です。
連結化では、AIを活用した情報分析ツールや、 異なるデータベースを横断検索できるシステムの導入が効果を発揮します。
内面化では、eラーニングシステムやシミュレーションツールを活用して、 実践的な学習機会を提供することができます。
重要なのは、技術ありきではなく、組織の文化や業務特性に合わせて 適切なツールを選択し、人とテクノロジーが調和した環境を作ることです。
野中郁次郎教授が提唱したSECIモデルは、 単なる知識管理の手法を超えて、組織が持続的に成長し、 イノベーションを創出し続けるための基盤となる重要な概念なのです。



















.png?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)