 『グロービスMBAファイナンス』の第11章から「コーポレートガバナンス」を紹介します。
『グロービスMBAファイナンス』の第11章から「コーポレートガバナンス」を紹介します。
コーポレートガバナンスはこの十数年、常に重要な論点でした。その背景には、「もの言う株主」に代表される株主の力が強まったことがあります。すでに過半数の株式を外国人投資家が保有している企業も少なくありません。また、企業の不祥事や許容範囲外の下方修正が突如表面化して株価が下がり、株主が大きな損失を被るという事態も多数起こったことが、コーポレートガバナンスへの意識をさらに強くしました。一方で、株主重視の経営が本当に正しいのかは現段階ではまだ分かりません。何事も行き過ぎればデメリットの方が大きくなるのは明白です。しかし、株主を喜ばせる経営を行うには、従業員を喜ばせ、さらには顧客を喜ばせることが必要です。適切にガバナンスが働き長期的に企業価値を高めようとする企業は、結局、多くのステークホルダーに幸福をもたらす可能性が高いのです。
(このシリーズは、グロービス経営大学院で教科書や副読本として使われている書籍から、ダイヤモンド社のご厚意により、厳選した項目を抜粋・転載するワンポイント学びコーナーです)
コーポレートガバナンス(企業統治)
経営のチェック&バランスの課題は、一般的にはコーポレートガバナンス(企業統治)と呼ばれている。コーポレートガバナンスとは、「企業は誰のものかを明確にし、所有者の意思、権利、および利益を企業の経営に反映させる手続きとシステム」のことである。経営に対するチェック&バランスのメカニズムが働かないと、経営者は容易に専制君主となってしまい、その結果、業績が停滞する、という問題意識がその背景にある。
世界的にコーポレートガバナンスが注目されるようになった背景には、2つの潮流がある。
一つは、経済のグローバル化である。機関投資家はリスクの地理的分散を図るために国内市場の枠を超えて魅力的な投資機会を追求するようになる。効果的な投資を追求する投資家は、財務報告(ディスクロージャー)と株主利益の取り扱いについて高度かつ統一的な基準を企業の取締役会に求めるようになる。一方、企業側もグローバルに事業を展開するために、国際資本市場で資金を調達する必要に迫られるようになる。
そのため、世界の投資家を説得する必要が生じ、コーポレートガバナンスの高度な基準を採用することが不可避となってきたのである。
もう一つの潮流は、機関投資家の巨大化である。高齢化の進展とともに年金ファンドが世界的に拡大し、それを運用する機関投資家の持ち株比率が高水準になった。例えば、年金ファンドを中心とした機関投資家は、すでにアメリカの大企業の50%を超える株式を持つようになっている。その結果、投資先企業の経営に不満があれば株式を売ればよい、という伝統的なアプローチ(ウォールストリートルールと呼ばれている)が通用しなくなってきた。つまり、機関投資家の持ち株がそこまで巨額になると、経営を信頼できなくなったとしても簡単に株式を売却できないようになったのである。
そこで、機関投資家は株主としての影響力を行使して、企業にパフォーマンスの改善を要求するようになってきた。つまり、株を売れないのなら面倒を見ざるをえないということである。
このような潮流を背景として、アメリカでは1990年代前半に業績の上がらないGMやIBMなどでCEOの解任劇が起こった。株主の代表である取締役が取締役会で業績を好転できない経営者を解任するのは、代表として当然の行動である。また、機関投資家の代理人とも言える証券アナリストとのミーティングは、アメリカ企業のCEOの仕事の中でも重要視されるようになった。
事業の将来性についてアナリストを説得しきれなかった会社の株価は、市場で厳しい評価を受けることになる。それは、株価に連動した経営陣の報酬に対して打撃となる。さらに、企業価値を極大化できない凡庸な経営を続けていると、敵対的買収の標的にされるようになる。そうなると、経営陣も解任されることになる。
アメリカではこのような形でコーポレートガバナンスが機能していると見なされていた。しかし、2001年から立て続けに起こったエンロンやワールドコムの巨大倒産事件によって、コーポレートガバナンスのメカニズムの信頼性に対して疑問符が付けられることになった。その結果、2002年に企業の内部統制を規定したSOX法が制定され、コーポレートガバナンスの改革が行われることになったのだ。
日本のコーポレートガバナンス
日本のコーポレートガバナンスについては、ハーバード・ビジネススクールのマイケル・ジェンセンが興味深い指摘を行っている。高度成長期においては設備投資のための資金調達ができるかどうかが日本企業にとって大きな課題だった。その資金を提供したのは銀行だったので、銀行の力は強かった。資金が使われる事業計画に対するチェックを行うのはもちろんのこと、業績が悪化すると銀行は経営者の更迭を迫ったり、行内の人材を経営陣に送り込んで建て直しを図ったりした。
このように高度成長期は銀行が日本企業の経営のガバナンスの役割を担っていたことになる。経営のチェック&バランスが有効に働いたから高度成長が維持できたというわけだ。
その後、力を付けてきた企業は銀行に頼らなくても資金調達ができるようになった。それとともに銀行のガバナンス機能も低下した。また、この間に株式の持ち合いが進んだので、株主によるガバナンスもうまく働かなくなってしまった。こうして1980年代に入ってから日本のコーポレートガバナンスは根本的な脆弱性を抱えるようになった。日本企業の経営のチェック&バランスが機能不全に陥っていることを見抜いたジェンセンは、1980年代後半の絶頂期の日本企業に対して、早晩没落するであろう、という予言をした。
残念ながらこの予言は的中することになる。バブルが崩壊するまでは持続的な株価の上昇が潜在的な問題を覆い隠していたが、バブルの崩壊によって日本企業の構造的な弱点が一気に露呈するようになった。そのため、不採算事業や余剰人員を抱えながらも、経営体質を積極的に変革しようとした日本企業は少数派にとどまった。こうして日本は失われた10年を迎えることになったのだ。
株主重視の経営の背景
株主によるコーポレートガバナンスと言うと、「それは株主のことしか考えない特殊なアメリカ的経営だ。日本の経営はそんなに単純なものではなく、従業員に対する雇用責任、顧客に対する供給責任、下請けの保護責任など、総合的な観点から経営を捉えなければならないのだ」という意見が出てくる。
このような見解の中には、アメリカというユニークな文化においてこそ株主重視の経営が成り立つのであって、それとは異なる文化を持つ日本では株主重視の経営は成り立たない、という認識も見られる。この点について考えてみよう。
実を言うと、アメリカももともとは株主重視の経営ではなかったのである。例えば、1950年代のアメリカを代表する経営者たったGEのラルフ・コーディナーは、「経営者は、株主、顧客、従業員、供給業者、そして工場のあるコミュニティの利害を最もよい形で均衡させるように企業を経営する責任がある」と主張していた。これはまさに日本流である。
ところが、このような考え方は歴史の試練に耐えることができなかった。なぜならば、「最もよい均衡とは何か」ということを定義できなかったからである。
株主や従業員といった立場の異なるステークホルダー(利害関係者)同士の利害が完全に一致することは通常はありえない。例えば、工場の海外移転は競争力を向上するため株主と顧客にとってはプラスだが、従業員とコミュニティにとってはマイナスとなる。競争力が万全ではない事業からの撤退は株主にとってはプラスでも、従業員と下請け、場合によっては顧客にとってもマイナスである。野心的な投資は従業員に夢を与えるが、株主にとっては必要以上のリスク負担となるかもしれない。
このように、必ずしも利害が一致しないすべてのステークホルダーに対して責任を負うということは、結局のところ、誰に対しても責任を負わないということになる。その結果、1950年代型の経営者は業績を持続的に向上させることができなかった。最終的に1980年代に入ってから増加し始めた敵対的買収が1950年代の考え方を粉砕したのだった。その結果、経営者の株主に対する責任が前面に押し出されてきたのである。

日本ではアメリカ流の株主重視の経営に対して否定的な意見も多いが、以上のような経緯があることは認識しておく必要があるだろう。
(本項担当執筆者: グロービス・エグゼクティブ・スクール講師 山本和隆)






























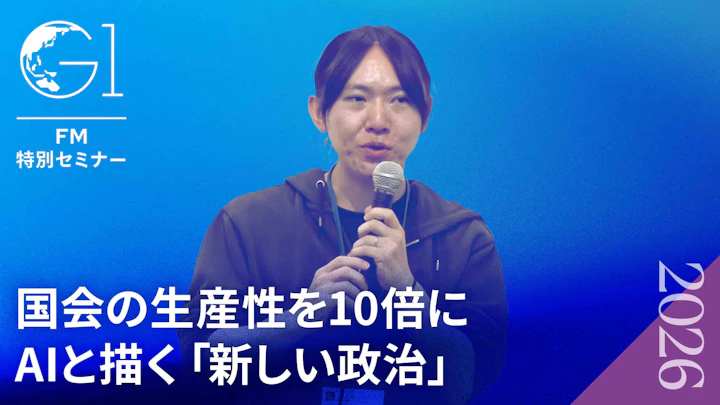



.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
