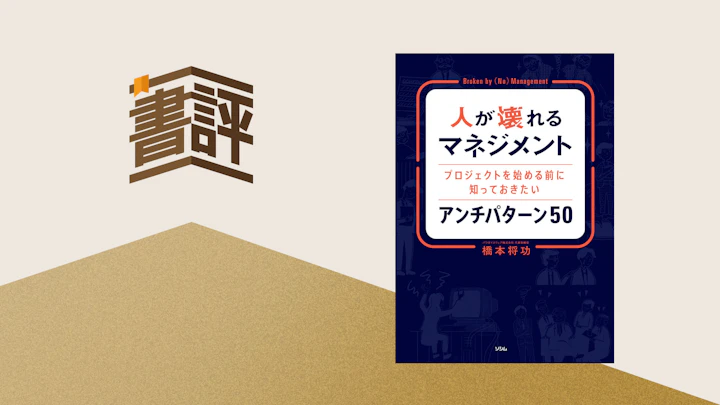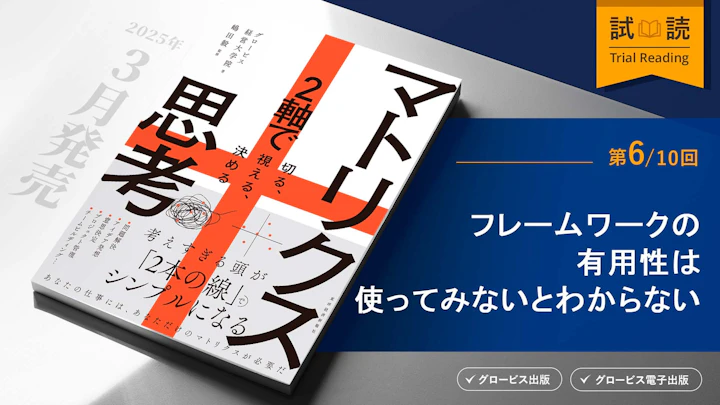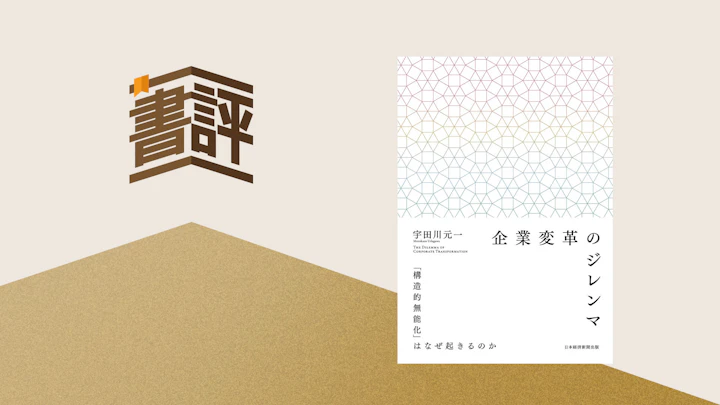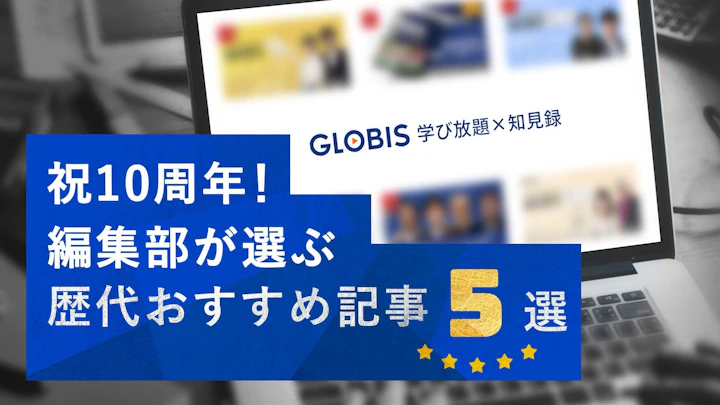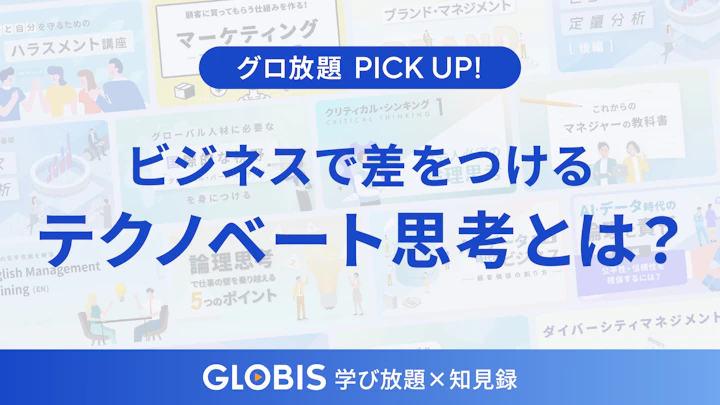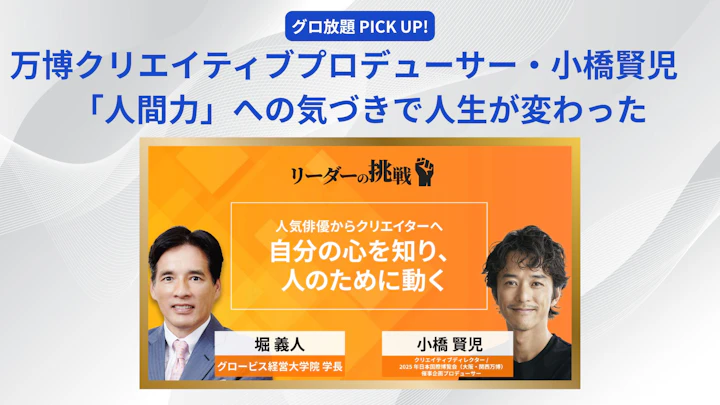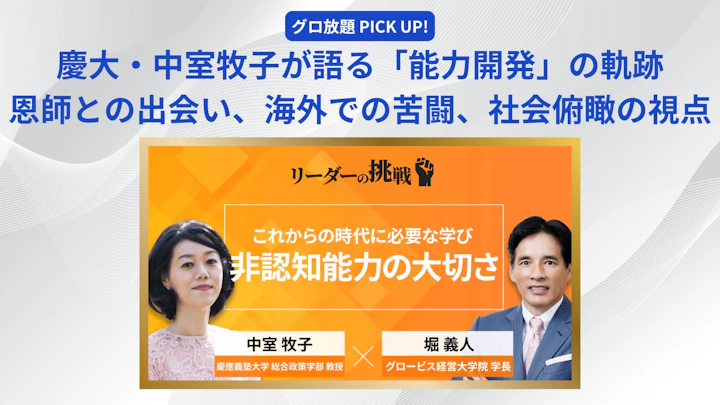『グロービスMBA組織と人材マネジメント』の第4章から「報酬決定要因」を紹介します。
経営者の立場に立てば、「従業員の何に対して報奨(特に基本給)を与えるのか」は極めて重要な問題です。日本ではかつて年功序列的な給与体系をとる企業がかなりの比率を占めましたが、「勤続年数」に対して報酬を与えることを続けていては、人員が多い層がシニア層になった途端に人件費負担が重くのしかかることになってしまいます。近年ではさすがに極端な年功序列は消え始めていますが、それでもいまだに日本の報酬システムは年功を加味した「職能給」的発想が根強く残っています。これはアメリカなどで用いられている「職務給」とは異なる発想です。ボーナスや昇進・昇格については成果主義がずいぶん浸透してきましたが、職能給で言うところの「職能資格等級」が本当にその人間の能力を反映しているかと言えば疑問もあります。グローバル化が進む中で、どのように報奨システムが進化していくかは興味深いところです。
(このシリーズは、グロービス経営大学院で教科書や副読本として使われている書籍から、ダイヤモンド社のご厚意により、厳選した項目を抜粋・転載するワンポイント学びコーナーです)
報酬決定要因
報酬決定要因は、個々の企業もさることながら、国によっても大きな差がある。ここでは、アメリカと日本の伝統的な報酬決定要因について見ていこう。
アメリカでの報酬決定要因
アメリカでは、職務を詳細に分析・記述した職務評価に基づいて、細かな等級と給与レンジを設定するのが主流であった。これは「職務給制度」と呼ばれるもので、1960年代に広く普及した。
当時、公民権運動とそれに対応した法整備が進み、人種、性別、年齢による、報酬を含んだあらゆる雇用差別が禁じられた。それ以降、実際に被雇用者からの訴訟によりダメージを受ける企業も多くなっていった。社員からの訴訟のリスクに対して敏感なアメリカ企業にとって、客観性・説明性が高く、しかも属人的要素を排した職務評価手法と職務給制度は適合性が高かった。加えて、当時は人材流動化が進展しており、この制度を用いれば、職務サイズ(職務評価により判定される、職務の相対的な価値尺)を外部の報酬相場との比較尺度としても使用できた。
しかし、この職務給制度では次第に以下のような問題点が表出するに至った。
・職務等級に対する固執
・業績に対する無関心
・不必要な社内政治、権力争い
・チームワークの阻害
・OJTによる能力開発の阻害
職務サイズのみが報酬の決定要因とされたため、社員は自分の職務サイズを大きくしたり、より大きな職務サイズのポストに就いたりすることを目指すようになった。そのための手段としてしばしば取られたのは、職務において能力を発揮し高い成果を上げることではなく、組織階層の上位者に政治的に取り入ることだった。また、職務が細かく規定されたので、「自分の職務記述書に書かれていないことはやらない」という態度が生じるようになった。その結果、組織の官僚化や硬直化が起こり、チームワークが生まれず組織目標の達成が阻害されるといった弊害が生じた。さらに等級が細かく分けられたため、社員の能力開発の手法として配置転換を使うことが困難になった。
このような弊害を取り除くため、1980年代以降アメリカ企業の間では、目標管理による実績主義の採用や、「ブロードバンティング」などが進展した。ブロードバンティングとは、3つから4つの職務等級を1つのバンドとしてくくり、そのバンドのなかでの異動であれば等級見直しを行わないとするものである(バンドのなかでは報酬を変動させる)。
日本での報酬決定要因
これに対して日本企業では、学歴、年齢・入社年次、あるいは経験によって積み上がる「職能資格等級」など、属人的要素が給与を決定し、内部一貫性(内部公平性)を検討する際の尺度になっていた。このうち経験によって積み上がる「職能資格」は、必ずしも担当する職務と結びつくものではなく、同一資格であっても、実際に担当している職務サイズが相当異なる場合も多かった。たとえば、資格は同じ「参事」であっても、課長もいれば、課長補佐の場合もある、などである。それでも、同一資格であれば給与は基本的に同額だった。等級内の昇給額により差をつけ管理する仕組み(号俸)はあるが、それほど大きな差がつくものではなかった。
また、「職能資格等級」は会社ごとに独自に設定されるもので、他企業の別の資格等級と直接比較することはできず、したがって給与の外部比較の尺度としても直接使用することはできない。このため外部と給与を比較する際には、たとえば「高卒技能職、35歳、勤続17年、扶養家族・配偶者1人子供2人」といった具合に担当する仕事とは関係しない、きわめて属人的な要素のみで給与の外部競争力を検証していた。しかし、このような手法では、昨今の、変化が速く激しい経営環境を乗り切れない。
そこで取り入れられるようになってきたのが、役割/職務に基づいた報酬制度である。多くの企業が、これをベースとしながら、成果に応じたインセンティブを併用するかたちをとっている。
(本項担当執筆者: グロービス経営大学院教授 佐藤剛)
次回は、『グロービスMBA組織と人材マネジメント』から「人材育成」を紹介します。