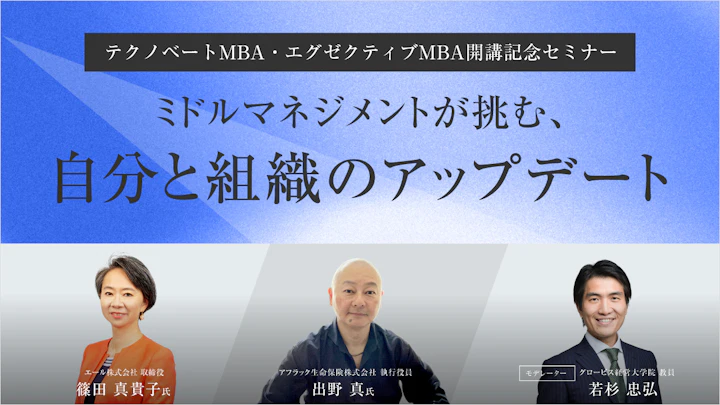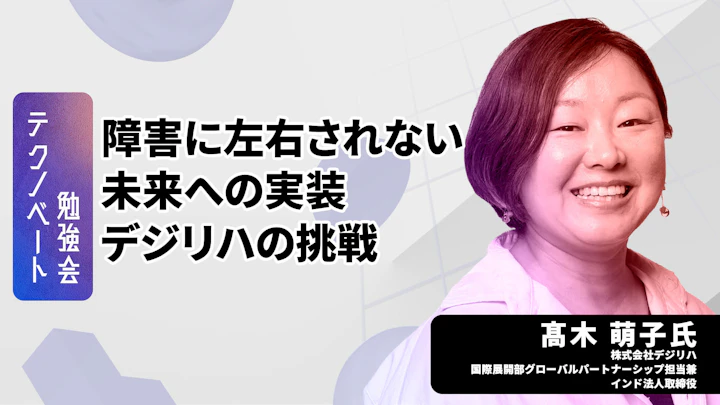「MBAシリーズ」のプロデューサーにしてグロービス経営大学院の人気講師・嶋田毅が創造と変革の志士たちに送る読書ガイド「シマダ文庫」。今回は前作『プリオン説はほんとうか?』で一躍、脚光を浴びた分子生物学者・福岡伸一氏の著作『生物と無生物のあいだ』(講談社)を取り上げる。
これまで小欄では、最近のベストセラーではなく、過去の名著を紹介してきた。ベストセラーの書評はここで書くまでもなく、巷で触れる機会も多いと考えるからだ。とは言え、やはり面白い本に出会うとそれを紹介したくなるものである。ということで今回は、最近いろいろな方面で好評を博しているベストセラー『生物と無生物のあいだ』について書いてみたい。著者は青山学院大学理工学部の福岡伸一教授。ロックフェラー研究所やハーバード大学で研究歴を積んだ分子生物学者だ。『プリオン説はほんとうか?』で2006年度の講談社出版文化賞を受賞し、第1回の科学ジャーナリスト賞にも選ばれている。
企業経営にも相通じるドミナント・ネガティブ現象

"最初に個人的な話で恐縮ではあるが、私は学生時代、生化学を専攻していた。今となっては昔話なのだが、当時は20種類のアミノ酸の化学式や、DNAの構造なども全部書くことができた(本当に!)。タンパク質の構造式を見て、「このあたりは疎水性のアミノ酸が多いから、たぶん折りたたまれるときには分子の内部に来るのではないか」などという議論をしていた。もともと書店で本書を手に取った動機もそんなところにある。若き日を思い出させてくれる本は、それだけで楽しく、メンタルヘルスにも良いということを再確認した。
本書を今回ここで取り上げたもう一つの理由は、「ドミナント・ネガティブ」という生命現象(本書の後半で紹介される重要な概念である)に、企業経営と相通じるものを感じたからだ。「ドミナント・ネガティブ」とは、ある遺伝子の機能を「完全に」つぶしてしまった場合には生物個体に異常は見られないのに、その遺伝子の機能を「中途半端に」つぶした場合には生物の個体に異常が見られるという現象だ。あたかも、中途半端に業績を上げていることが、かえって企業の危機感を麻痺させ、組織にダメージを与えてしまうような現象である。こうした現象があるからこそ、生物学も経営学も面白い。
さて、本書の前半部分は、過去の分子生物学発展の歴史を、人物や出来事にフォーカスしながらドキュメンタリー風に紹介している。教科書に出てくるような科学者の人間的な部分に触れ、読者の興味を引く手法自体は決して珍しくはないのだが、ミステリー風に読者に謎をかけながら次の章につないだり、急に場面展開して人物や風景の描写に入って緩急をつけたりする文章技術は、この手の啓蒙書としては秀逸で、非常に参考になる。日ごろ生物学や分子生物学にそれほど興味をもっていない人間をも惹きつけるであろう構成の巧みさなども、現在、文章を仕事の一部としている人間として、ぜひ盗みたい技と感じた。なお、格調高目の文体やレトリックを評価する書評も多い。しかし、好き嫌いの問題であることを承知で書くと、やや懲りすぎの印象があり、もう少し平易に書いてもいいように感じる。何しろ、扱っている内容自体は、決して簡単ではないテーマなのだから。
さて、後半になるといよいよタイトルにもある「生物とは何か」というテーマに関して、著者自身の研究を交えながらの謎解きが始まる。仮説を立て、実験でそれを検証もしくは棄却し、また新しい仮説を立てる――先端の研究内容の面白さもさることながら、サイエンスという知的作業の現場感が目に浮かぶように伝わってくる。同時に、研究室間の論文先乗り競争や、時として起こる不正や過ちの様子なども描かれており、サイエンスが、ビジネスにおける企画立案などと同様、知的作業であると同時に極めて人間的、属人的な営みであることも強く感じられる。このあたりを自然に描き出している点が、多くの科学啓蒙書と本書の違いの一つであろう。肝心の「生物が何か」という点に関する著者の考え方――先述した「ドミナント・ネガティブ」に関する解釈もこれに関連する――はここには書かないが、ご興味ある方はぜひ一読されるといいだろう。"