本連載「ストーリーで学ぶ経営戦略シリーズ」では様々な立場の現場のマネジャーのストーリーを基点に、古今東西の優れた戦略論から彼・彼女らの仕事をより良くするヒントが得られるかを具体的に考えていきます。
ストーリー概要:
大手焼肉チェーン「ぎゅうにく亭」を運営するナショナルフードの月例業績ミーティングは紛糾していた。この月例ミーティングでは各店舗の業績をレビューするとともに今後の具体的な方針を議論することが慣例となっている。
ぎゅうにく亭の昨今の業績は決して芳しいものではなかった。業界全体では2000年代初頭に発生したBSE(牛海綿状脳症)問題に始まり、至近では東日本大震災の影響、更に生肉の集団食中毒問題などにより、一層の客離れが進んでいた。結果として焼肉業界の市場規模は毎年マイナス成長という厳しい市場環境に陥っていた。そして、消費者の低価格ニーズの高まりに合わせるように、ローカルチェーンや個人経営の焼肉店は率先して低価格化の傾向を見せていた。
そのような市場環境や競合との戦いの結果として、業界最大手であるぎゅうにく亭の各店舗の業績もあおりを大きく受けていた。競争の激しい店舗は売上が半減するような業績に陥ることもあった。
「うちはどうやって差別化していくべきなんだ?」
エリアマネジャーや経営企画担当が集まってのミーディングはいつになく白熱した。今期、自分の担当エリア店舗の業績が最下位になりそうな津田は、白熱する議論を上の空で聞きながら、自分のエリアにおける戦いについて思いを巡らせていた。
「うちのエリアの焼肉店の競合は、競合大手チェーンの『一番苑』、ローカルチェーンの『焼肉sizzle』、そして個人経営の店舗がいくつか。中でも一番苑は、売上の悪い既存のブランドを新たに出した低価格ブランドに入れ替えていて、それにかなり押されているという情報も入ってきている。さて、どうやって戦うべきものか・・・」
経営企画担当のリーダーは、「ポジショニングマップ」というツールを活用して、自分たちの立ち位置をどこにおくのか、ということを議論しているようだ。「たとえば、食べごたえ、という軸と、安心・安全という軸で整理すると、うちは競合に対してまだ差別化できるんじゃないか。低価格化の勝負に乗るのではなく、たとえばお肉の厚さを競合より2mm厚くして食べごたえを感じてもらう、ということで戦うことは十分可能だと思う。また、大手のメリットを生かして独自の安心・安全基準を打ちだして訴求する、ということもできるだろう」などと言って十字の2軸の右上に自社のブランド名を書き込んだりしている。
しかし書くそばから、「まあそれもありだとは思いますが、やっぱりこの時代、価格を訴求すべきじゃないですか。うちは業界1位であるからまだ体力はあるし、うちも価格競争に対して本気になれば、競合は間違いなくついてこられなくなると思いますけど」「いや、それよりも、新商品開発のスピードで差別化すべきじゃないですか。新メニューの投入が競合に比較して遅すぎるので、一度来たお客さまも飽きて来なくなっちゃうんと思うんですよね」など、先に書かれた2軸には含まれない訴求ポイントが出てきている。
議論は白熱していたが、津田はどれも差別化にはならないだろう、と直観的に感じていた。その時に津田はふと思った。差別化、差別化ってみんな簡単に口にするけれど、そもそも差別化とは何だろう?セオリーってあるんだろうか・・・?
理論の概説:差別化
今回は「差別化」、もしくは「差異化」という言葉を取り上げたいと思います。皆さんも何気なくこれらの言葉を使ってはいないでしょうか。
「この商品の差別化のポイントは何だ?」「自社の製品の売れ行きが落ちてきたのは、十分に差別化が図られていないからではないか?」といったように、差別化という言葉が日常化しており、それがゆえに言葉の意味自体を深く考えることもなくなっていると思います。
なぜ差別化という言葉が当たり前のように使われるようになってきたのか。その背景にはいくつかの要因があるように思います。まず、そもそも日本市場が全体的に頭打ち、成熟化傾向を迎えており、この中で成長するには競合と同じことをやっていては勝ち目がない、ということです。つまり、昔のような横並び意識から脱却し、何か少しでも競合と違うことをしなくてはならない、という思い(焦り)があるということでしょう。そして、もう一つは中国を代表とするアジア諸国に価格競争力で太刀打ちが出来ず、必然的に何らかの付加価値をつけたプレミアムポジションでの差別化が戦略の大前提になりつつある、ということです。
これらの要素が相まって、我々が戦略を考える上で、差別化という概念は必要不可欠、もしくは今更そんなことを語るまでもない、という状況になっているのではないかと思います。しかし、この差別化という言葉の意味やセオリーを皆さんはどこまで熟知して使っているでしょうか。私が企業の現場やビジネススクールでの議論を聞く限りにおいては、その原理原則、留意点などを理解して語っている方はそれほど多くありません。したがって、今回はこの差別化という言葉を丁寧に考えていきたいと思います。
まず頭に入れておきたいのは、差別化を考えるには「ステップを踏んで考える必要性がある」ということです。具体的には、まずは顧客ニーズを見定めること、そして競合を特定し、顧客ニーズと競合を睨みながらポジショニングを決めること。そして最後に、そのポジショニングの賞味期限を理解することになります(下の図)。

以下、具体的にそれぞれのステップでの留意ポイントなどにつき見ていきましょう。
1. 顧客ニーズを見定める
差別化の大原則は、単に「競合と差がある」ということではなく、「顧客にとって意味のある部分において差がある」ということです。そんなこと当たり前じゃないか、という人も多いかもしれませんが、実際のところ、顧客ニーズをおろそかにした差別化はいたる所で見受けられます。
特に、限定された市場で競合との熾烈なシェア争いを繰り広げている業界などはその傾向が強く見受けられます。一例として、キリンビールの荒蒔康一郎社長(当時)が2002年に語った内容を引用します。
「たとえば、新製品の売り出し方です。他社がキャンペーンをやれば当社もやる、ビール券つきの商品を売り出せば、当社も売り出すというように、必死になって売る条件を他社に揃えていました。2年前くらいに、アサヒさんが感謝キャンペーンというのをやった。一瞬のうちに我々もやると発表したんですよね。そしてやった。それなりの効果はあったのですが、大きなトレンドは生み出せませんでした。莫大な費用がかかる割には、失ったものの方が多かったと思います。」「『お客様本意』という言葉は前からあるんです。(中略)しかし、知らず知らずの間に、少しずつ経営の優先順位がずれてしまったんですね。お客様は何を求めているか、我々は何をすべきかについて、鈍感になっていたのは、間違いない。(中略)アサヒに抜かれて2位になったのを機に、自分の考え方をもう1回、机の中から出して、見直そう、と。キリンはお客様にどのように見られているのか。会社の発信する声は響いているか。またこれらのことは上っ面だけではないか。全部、検証したい。」(「編集長インタビュー荒蒔康一郎氏[キリンビール社長]競争相手に煽られるな」『日経ビジネス』2002年6月24日号)
この荒蒔氏の発言からも見てとれるように、ビール業界のような限られたパイを奪い合う業界は、顧客ニーズを理解するというステップを通り越して、競合ばかりを意識して考えてしまう、という傾向に陥りやすいのではないかと思います。
しかし、「じゃあ、顧客のニーズを考えた上で差別化すればいいんだろう」と簡単に言えるほど、物事はシンプルではありません。ニーズを特定する上でもいくつかの壁は存在します。
まず、顧客自身が必ずしもニーズを知っているわけではない、ということです。目の前に商品があって初めて「こういうものが欲しかった」ということに気付くことは多いでしょう。もしくは、使いこなすことによって初めて自分のニーズが開拓されていく、という商品もあるはずです。たとえば、iPhone発売前に、iPhoneが持ち得る全ての機能に対するニーズを自己認識していた消費者は極めて稀でしょう。多くの消費者は、iPhoneという商品を購入し、アプリを入れるなど使いこなしていくうちに、自分自身が潜在的に持っていたニーズに気付いていったはずです。
また、ニーズというのはiPhoneの事例のように「製品」に対するニーズもあれば、購入時における「サービス」に対するニーズも、「価格」や「ブランドイメージ」に対するニーズもあり、それがごちゃっとまとまった形で「ニーズ」という複雑なものを形成している、という事実があります(伊丹敬之氏は、自著『経営戦略の論理』において、このことを「ニーズの束」と呼び、ニーズというものが様々な要素で構成される塊でありその本質を捉える事の難しさを表現しています)。
ニーズは、同じ顧客の中でも時間や使用場面によって変化する、ということもあるでしょう。たとえば、レンタカーに対するニーズは、同じ顧客であっても、旅行の際とマイカーが故障した時とでは異なるはずです。
それ以外にも、ニーズを認識していたとしても顧客側がそれを表に出したがらないこともあります。たとえば、自動車に対するニーズの中には、他者に対する自己顕示欲を満たす、ということを考える顧客も少なからず存在しますが、それは顧客から積極的に表だって語られることはありません。
つまり、これらのことから言えるのは、ニーズの特定というのは極めて難易度の高い作業になる、ということです。そう考えてみると、こういった抽象的な作業を避けて、より具体的に見えている競合に対する「切った張った」の戦い方を考えたくなる気持ちもよく分かります。しかし、どれだけ難しくても、基本は顧客を丁寧にセグメント化し、自分たちがターゲットとする顧客を見定めること、そして、その顧客のニーズが何でありどう変化しているのか、ということを現場に入り込みながら試行錯誤して突きとめていくという王道以外に道はありません。
「差別化」という言葉に引っ張られて、目に映りやすい競合の動きばかりに目を奪われ、顧客ニーズ不在型の差別化に走ってしまうことは、先述の荒蒔氏の言葉を借りれば結局のところ「失うものの方が多い」のです(ちなみに、マーケティングの大家であるフィリップ・コトラーは、『マーケティング・マネジメント』において、この顧客ニーズ不在型の差別化について、「競合他社志向の企業」と呼び、この手の企業の課題は、「企業が受け身になり過ぎることである。首尾一貫した顧客志向の戦略を立てて実行するのではなく、競合他社の動きをもとに自社の動きを決定してしまう。それは本来の目標へ向かう動きとは言えない。(中略)明らかに、顧客志向の企業の方が新たな機会を発見し、長期にわたって利益をもたらす戦略を設定することが出来る」と述べています)。

2. 競合を特定する
顧客ニーズを見定めたら、次に考えるべきポイントは、競合を特定する、ということです。つまり、差別化の対象となる競合相手自体を的確に捉える、ということです。もちろん、「うちの競合はA社とB社とC社だ」と明確に意識しているケースは多いでしょう。そして、それらの企業は間違いなく競合なのだと思います。しかし、果たして競合はそこ「だけ」なのでしょうか?
たとえば地域の学習塾の競合はどこでしょうか。同じ地域にある学習塾は間違いなく競合でしょう。しかし、それだけではありません。「子供たちの放課後の限られた時間の使い方を争う」という見方をすれば、サッカーやピアノなどの習い事も競合になります。もしくは、同じ学習という土俵の中でも、“赤ペン先生”のような通信教育、iPadを活用した自己学習ツールといった新たなテクノロジーなども競合になるでしょう。「自分が教えるので十分」と親が思っていれば、潜在顧客と目される親自身も競合になります。つまり、我々が日常的に競合という枠で考えている以上に、競合は多いのです。
しかし、ここで言いたいのは、潜在的な競合も含めて全てを差別化の対象として考えなくてはならない、ということではありません。当然そんなことをしていたら、差別化のフォーカスポイントはぶれ、商品やサービスのエッジは鈍ります。
そうではなく、まず競合を特定する上で大事なことは、「まさか」の死角をなくす、ということです。凝り固まった業界概念で物事を見ると、このような潜在的な競合の脅威を見逃します。特に「業界内ランキング」が長らく経営の重要な指標であり続けるような固定化された業界であれば尚更です。その手の業界に属している企業は、狭い業界定義に基づく差別化を必死に行い、そして潜在的競合に足元をすくわれ、やがてはもろく崩れていくことになるでしょう。したがって、まずは5つの力(Five forces)で言うところの「代替品の脅威」も含めて競合を広く視野に入れること、そして、その中から自分たちが当面の競合となりうる企業を意図的に定める、ということを意識する必要があるのです。
3. ポジショニングを決める
顧客ニーズおよび競合の存在を踏まえたら、次は自らの立ち位置(=ポジショニング)を決めていきます。ポジショニングのセオリーは非常に深いのですが、ここではそのポイントのみを簡潔に説明しておきます。
ポジショニングとは、顧客に対して自社の商品やサービスの違いを明確に認識させていくことを目的にし、以下の図のように2軸を使って競合との比較における自社の立ち位置を示します。
ゲーム業界におけるポジショニングマップ事例

ではこの2軸はどう決めるべきなのでしょうか。大きく分けると3つのポイントが考えられます。
まず、その軸が「顧客にとって意味のあることなのか」、ということ。これは冒頭「1.顧客ニーズを見定める」で述べたことと同根ですが、ポジショニングマップを作るが目的化し、肝心の「顧客は誰なのか」「そのニーズは何なのか」という観点を看過しないよう留意しましょう。繰り返しになりますが、ここをしっかり押さえておくことが大前提となります。
そこで改めて認識しておきたいのが、顧客が何の価値に重きを置いているか、ということです。我々は無意識のうちに商品そのものの価値ありきで、そこをポジショニングのポイントに考えがちですが、果たして本当にその視野だけでよいのでしょうか。製品そのものが重要な場合も当然ありますが、意思決定現場での営業担当者との会話が重要な場合もありますし、それを販売している場所や立地が何よりも重要な場合もあります。コトラーは「マーケティング・マネジメント」において、その差別化の源泉を「製品」「サービス」「スタッフ」「チャネル」「イメージ」という5つに区分して整理しており(下の図を参照)、顧客ニーズを捉えるときの視野の広がりの重要さを示しています。

ポジショニングの軸を考える上での2点目のポイントは、「競合との差が分かりやすいか」ということです。これには2つの側面があります。
1つは軸を定義する言葉がぱっと見て感覚的に分かる表現となっているかどうか、見る人によって解釈の違いを生じるものとなってしまってはいないか、ということです。たとえば、洗濯機において「使いやすさ」という言葉を軸に据えたとしましょう。確かに使いやすさは顧客にとって大事なことではあるものの、「何をもって使いやすいというか」が定まらないとマップ自体の意味が伝わりません。ここは、言葉の意味するところをより丁寧に的確に表現する必要があります。
もう1つは競合との差に距離感があるか、ということです。軸は明確にもかかわらず、結果的に自社と近いポジションに複数の競合がまとまって表現されてしまうものは、「競合と大差ない」ということであり、よい軸であるとは言えません。
つまり、ここでしっかり意識してほしいのは、「顧客に正しく伝わってこその差別化である」ということです。伝え方自体はそれだけで非常に深い世界なのでここでは割愛しますが、現場で散見されるのが、ポジショニングのコンセプトが曖昧過ぎるために末端に正しく浸透せず、顧客に伝わらないままに終わってしまう、ということです。差別化のポイントを伝えていくのは、多くの場合は現場の末端です。CMなどのマスプロモーションだけでポジショニングが正しく顧客に伝わる、というビジネスはほとんどありません。結局は営業現場で1つひとつのコミュニケーションを通じて顧客に価値訴求をして初めて売れるのです。ということは、ここで言う「競合との差の分かりやすさ」ということは、顧客への分かりやすさであることの大前提として、「社内に浸透しやすいか」、ということが何より重要になるのです。特に昨今はソーシャルネットワークサービス(SNS)などを通じた双方向性コミュニケーションによって、顧客との理解を深めていくことが多くなってきています。一部の限られた人間による一発のコミュニケーションでは伝わりません。「このポジショニングを顧客に正しく伝えるためには、営業現場ではどんなコミュニケーションが必要になるだろうか」というような現場視点を持ち合わせて、設計をすることが必要になってくるのです。
3点目は、「企業活動における全体的な整合性が取れているか」、ということです。これは、1つには、過去の他商品やブランドイメージとの整合性があるか、という観点があります。突飛なポジショニングマップを描くことは可能ですが、それが過去の製品や他の製品などと明らかに異なる場合、顧客側が混乱を起こす可能性があります。
そして、もう1つの側面は、本当にそのポジショニングマップを実現できる組織なのか、体現できる社員が揃っているのか、ということです。ポジショニングマップはお遊びのお絵描きではありません。実行を伴って初めてその差別化は実現するものです。プレミアムブランドイメージを打ち出した製品においては、全ての社員がそのポジショニングイメージを体現する行動が求められます。安さを差別化の軸にするのであれば、高次元でのコスト意識を組織全体で持って活動しなければならないでしょう。日々の顧客との接点、社長から末端の社員まで一人一人が発信するメッセージ、そういったものも含めて、ポジショニングマップは現実のものになっていきます。ここが伴わないポジショニングマップは、むしろブランドイメージを毀損させるだけの可能性があります。
たとえば、流行のファッションをいち早く店頭で販売する、という「スピード感」を差別化の軸に据えるZARAというブランドがあります。1品1品で見れば決して真似できないことはないのですが、トータルで見れば他のブランドはそれを真似することは極めて困難です。なぜならば、それを実現するためには、デザインの意思決定のプロセスから製造、発送、店頭販売に至るまで、スピードという差別化の軸に向けて一貫した仕組みや社員の意識が徹底されているからです。部分的には真似が出来たとしても、商品全体のスピード感については、取引先も含めたサプライチェーン全体を巻き込んだビジネス全体としての意思決定やコミットメントが求められるため、生半可な物真似では追随できないのです。裏を返せば、このようなレベルの整合性を実現できた企業だけが、真の差別化を実現できるのです。
ここまで見てきたポジショニングマップの軸の設定のポイント3つを以下に図としてもまとめましたので参考にしてください。


4. 賞味期限を踏まえた次の施策を考える
ポジショニングマップができたからと言って、すぐにその実行をすればいいわけではありません。もう1ステップ考えなくてはならないことがあります。
それは再び競合の存在です。この差別化に対して、競合も指をくわえて待っているはずはありません。もしユニークで素晴らしい差別化戦略を取ってきた企業が出てきたら、それに対する対抗手段、つまりいかに模倣し、その差別化を無力化するかを考えるはずです。更には、差別化要因を模倣するだけでなく、その上で新たな差別化を加えて逆転を図るような「差別化返し」のような事例も少ないわけではありません。永遠に差別化された商品、サービスというのはなく、いずれかのうちに賞味期限は尽きるのです。したがって、賞味期限を把握しつつも、最終的には「真似をされる」という前提で、二の矢、三の矢の差別化の施策を素早く打ち出せる体制を作っておく、つまり「賞味期限を踏まえた次の施策を考え」ておく必要があります。
では、どうやって賞味期限の本質的な長さを読み解くのでしょうか。それは、ポジショニングマップの3つの軸の確実性によります。つまり、「顧客のニーズそのものが変化しやすい業界」「異業種からの新規参入などがあり競合そのものが特定しにくい業界」、競合の変化スピードが速い業界」「自社の全体感の範囲が見えず整合性が取りにくい企業」「組織の流動性が高い企業」・・・そういった条件が背景にあるポジショニングマップであれば、賞味期限は短いと考えた方がよいでしょう(下の図を参照)。

たとえば、ポジショニングマップの事例でも紹介した任天堂のWiiという商品を考えてみましょう。Wiiが「手軽に(=感覚的に)」「みんなで」遊べるという新たな差別化の軸を持ったゲーム機器を出したのは記憶に新しいところです。一時期は、「ゲームの競争の軸を全く変えたイノベーティブな商品だ」と至るところで称賛されていました。しかし、たとえそんな素晴らしい商品であっても、このWiiの賞味期限もそう長くはありませんでした。結果的には、異業種であるスマートフォンの出現によりソーシャルゲームが普及し、新たな競合がマップ上に現れ、「手軽に」「みんなで」という軸が相対的にかなり劣位に置かれてしまったためです。
Wiiの賞味期限は、ゲーム業界の競合の捉えにくさによって起因したものと考えられますが、このように3つの軸のいずれかが不確実性が高いかどうかによって、賞味期限の長さは決まってきます。どんなに差別性が高い商品、サービスを出したところで、それで勝負がつくわけではありません。必ずその先があるのです。したがって、賞味期限の長さを見極めた上で、次の打ち手を備える、ということが差別化を考える最後のステップになる、ということを心得ておくべきでしょう。
解説:津田さんはどうすべきか?
では津田さん、およびミーティング参加のメンバーが考えるべきことを整理してみましょう。
まずこの議論では差別化の軸、つまりステップ3のポジショニングマップのあり方が議論の焦点になっていますが、本来であればもう少し丁寧にステップ1の顧客ニーズ、およびステップ2の競合についての議論をしておきたいところです。
おそらく参加メンバーにとっては「顧客ニーズや競合なんて日頃から意識しているからこんなところで議論する必要はない」と考えているかもしれません。しかし本当でしょうか?本文にも記載した通り、ニーズ特定には固有の難しさがあります。それに加えて、特に今回のケースのような業界上位の企業は顧客層が必然的に広くなるので、そもそも「顧客って誰ですか?」「競合ってどこですか?」というシンプルな問いにも答えにくい、という背景もあります。
もちろん、答えにくい=考えなくてもいい、というわけではありませんから、時間をかけて顧客ニーズや競合に対する仮説を持つ必要があるのは言うまでもありません。ただ、今回のケースもそうですが、その固有の難しさと「自分たちは分かっているつもり」という感情が相まって、現場ではこのステップは往々にしてスキップされてしまいます。
さらに言うならば、特に今回のシチュエーションでは様々な外部環境要因によって外食、そして焼肉に対するニーズ自体も、そして顧客の中でのニーズを叶える選択肢(=競合認識)も大きく変化している可能性もあります。食べごたえを追求したところに反応する顧客はどれくらいいるのでしょうか?安心・安全ということに目新しさを感じて選んでくれる顧客は一体誰でしょう?全く意味のないところで競合と差を出しても仕方ないのです。だからこそ、遠回りかもしれませんが、差別化の軸を議論する前に顧客や競合についてはしっかりと議論しておくべきでしょう。
そして、今回のケースでしっかり考えておいてほしいのは、最後のステップ、つまり賞味期限を踏まえた次の備えについてです。今回案としてあがった施策もそうですが、アイディアとして賞味期限の長いもの(つまり、消費者ニーズにミートし、競合が真似できないもの)はまず出てこないでしょう。だからこそ、その健全な認識を持ちつつ、今回の差別化の施策は何があるのか?今出来ることはそれが全てなのか?それらの施策は、それぞれ誰が責任を持ってやり、誰がどのタイミングで評価を行うのか。仮に成果に至らなかった場合、その一手先はどんなオプションが考えられるのか、ということを具体的に考えなくてはならないのです。大きな戦略の方向性まで見据えて考えるべし、というとこの手のミーティングでは思考停止してしまいかねませんが、少なくともこのような数カ月先レベルの具体的なアクションまで見据えた議論はこの場でしておくべきだと考えます。
ミドルリーダーへの示唆
最後に差別化ということを考える上で、ミドルリーダーが意識すべきポイントを3点ほど整理をしてみました。
まず何よりも大事なことは、自社の強み、自社の歴史、そして大事にしてきたこと、そんなことに対する理解を徹底的に深める、ということです。上記にて差別化のポイントと賞味期限の話をしました。でも冷静に考えてみてください。我々の周りで消費者ニーズが明確であり、不変であると言い切れる業界、もしくは競合が固定的であり新たな参入はないと言い切れる業界はあるでしょうか?日本を離れた名も知らないグローバル企業が競合にならないと言い切れる業界は果たしてどれくらいあるのでしょうか?
結局のところ、顧客や競合に関するポイントは、究極的には予測のつかないものです。その上で、更に自社に対する理解も覚束ないようであれば、差別化なんて考えようがないのです。だからこそ、自分たちに対する足元はしっかり固めることが優先課題になるのです。逆説的ですが、差別化要素は、競合がどうかというよりも、自分たちしか語れない過去や自分たちがなりたい姿、ビジョンに宿るものです。それを見失った瞬間に、差別化を考えているつもりが、気付くと競合と全く同じ戦いをしている「同質化」に陥ることになります。差別化を考えるのであれば、まずは自分たちの理解を徹底的に深めるというところから始めるべき、というのはそんな背景があります。
もう1つは、「劣っていること」は敢えて無視する、もしくはそれを逆手に取る、というマインドを持つということです。競合を特定しポジショニングを考える際に、競合と比較して劣後するポイントが目に見えてくると、無意識に追いつきたくなる心境に陥ります。しかし、本質的な問いは、限られた自社のリソースをどこに振り向けるか、ということです。例えば、ハーバードで教鞭を執る人気経済学者ヤンミ・ムンは、自著『ビジネスで一番、大切なこと消費者のこころを学ぶ授業』において、「真の差別化は、均整のとれた状態から生じるものではない。むしろ、偏りから生まれる」と言っています。
また、何かサービスなり特徴を競合に付加して差別化を図る「プラスの差別化」ではなく、敢えて余分なもの削ぎ落して勝負する「マイナスの差別化」によって成功する事例も増えてきています。(たとえば、洗髪やひげそりをなくしたQBハウス、法人融資をなくしたセブン銀行、組立サービスをなくしたイケアなどはその代表事例です。)大事なことは、競合がやっているからうちも負けずとサービスを加えていこう、ということではなく、顧客が本質的に求めていることは何か、そして競合と対比して見えてくる自社のユニークさは何か、ということを発想の原点に置くべき、ということです。
その上で、最後にミドルリーダーに敢えて申し上げたいのは、差別化に対する過大な「幻想」を抱くことはやめましょう、ということです。先程の顧客や競合に関する不確実さにもつながることですが、本当に意図をして差別化が長期的に持続できる可能性は極めて低いのが現実です。もちろん、アップルやサウスウエスト航空など極めて素晴らしい差別化を実現した事例はあります。これらの商品やサービスを、人々は「差別化」という言葉を超えて「イノベーション」と呼び、至るところで事例研究がなされています。しかし、実際の統計上においては、このようにイノベーティブであり、「持続的な競争優位」を実現する企業は、すべてのうちの2~5%に過ぎない、というリサーチ結果が発表されています。それくらい難しいことなのです。
ではどうすればいいのしょうか。もちろん、その数%を狙って、イノベーションを起こそう、というのも1つでしょう。ここにはいろいろなセオリーはあり、それを否定するものではありませんし、成功した暁には華々しく取り上げられるでしょう。ただ、そのような大逆転の戦いも、実際にはその裏側では死屍累々の世界です。華々しい成功の美談から学べることはそれほど多くありません。
むしろ、我々ミドルリーダーにとって大切なことは、結局は賞味期限の長続きするイノベーションなんてほとんどない、という覚悟の下、自分たちが差別化になりうると信じる軸をスピーディーに投じ続けて、そしてPDCAを早く回して環境に柔軟に対応していくしかない、ということではないでしょうか。もちろん、その過程において、そのたびごとの仮説は必要です。顧客ニーズは何か?競合はどこにいる?どうポジションを取るべきか?そんな議論の下、自分たちが差別化を発揮できる軸を磨いていく。その結果として、その企業ならではの軸やストーリーが徐々に仕上がっていく、というのが現実的な姿のはずです。
そして、ここで大事なことは「徹底」というキーワードです。多くの企業が、差別化の軸を考えるものの実行局面でうまくいかず、そして途中でその路線を変更し、結局競合の戦いにすり寄る形でお互いが集まってきます。大事なことは、どれくらい自分たちが信じる仮説を徹底的にやり遂げるか、であり、最終的にはその現場での細かな意思決定の積み重ねこそが息の長い差別化につながるのではないでしょうか。特に我々ミドルリーダーが華々しい一発逆転のホームラン(=イノベーション)を狙えることは稀です。むしろ、ヒットでいいからそのヒットをスピーディーに打ち続ける、という気概を持って差別化を考え、磨き続けていく、ということが現場での現実解ではないかと思う次第です。
■参考文献:
経営戦略の論理 〈第4版〉―ダイナミック適合と不均衡ダイナミズム
コトラーのマーケティング・マネジメント -ミレニアム版
世界の経営学者はいま何を考えているのか――知られざるビジネスの知のフロンティア
ビジネスで一番、大切なこと 消費者のこころを学ぶ授業
なぜ、あの会社は儲かるのか? ビジネスモデル編
■連載一覧はこちら
#ストーリーで学ぶ経営戦略シリーズ
















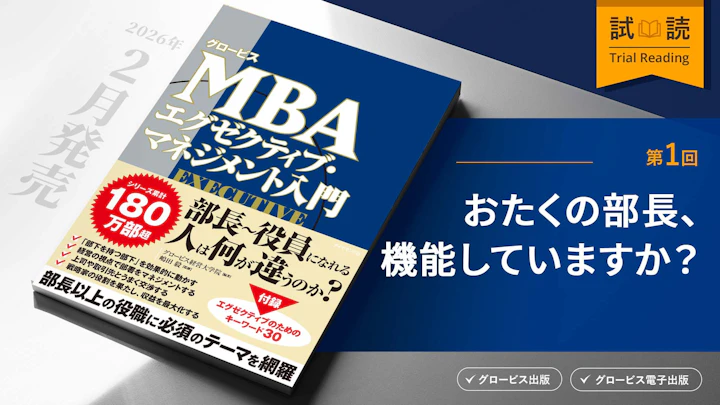






















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
