本連載「ストーリーで学ぶ経営戦略シリーズ」では様々な立場の現場のマネジャーのストーリーを基点に、古今東西の優れた戦略論から彼・彼女らの仕事をより良くするヒントが得られるかを具体的に考えていきます。
ストーリー概要:
インド法人に着任した浜村は、顧客開拓に向けた今後の営業攻勢のシナリオを練っていた。
浜村は大手損害保険会社アジア海上に勤務する10年目社員である。入社時、仙台支社の配属となった浜村は、その後も広島、熊本をローテーションの一環でまわり、地域営業を担当してきた。
浜村の受け持ちは主に、ディーラーや代理店に対する自動車保険や火災保険の営業。この営業の肝は何といっても相手の懐にいかに入り込むか、ということに尽きる。商品や条件面では競合と比較してほとんど差別化要素はないため、勝負のポイントはいかに顧客から気に入ってもらうか、ということにあった。
そのために浜村は、顧客の元に足繁く通うのはもちろんのこと、朝礼に同席参加したり、週末はゴルフ接待を行ったり、といったように、顧客との関係深化のためにあらゆる打ち手を計画的に進めていた。その結果として、浜村への担当顧客の評価は高く、過半とアジア海上の商品を優先的に販売してもらえる関係性を構築していた。
浜村が意識していたことは丁寧なPDCAサイクルを回すことであった。まずは計画段階で、どの顧客をターゲットにどれくらいの売上をあげるのか、どういう商品を薦めるのか、ということを具体的に練り込んでいった。「計画は勝負の8割を決める」というのが浜村の持論であった。その上で実行に入るのだが、予め決めた顧客には必ず決まった頻度で訪問することとし、新規顧客からたとえ厳しい扱いを受けてもとにかくやり続ける、ということを信条としていた。そして、四半期ごとに自身の業績を上長に報告し、次の動きをどうするかを具体的に考える、ということを確実に行っていた。浜村のこうした動きは部下からも上長からも高く評価され、配属された先々で「浜村のPDCAを見習え」ということが言われるようになった。
そんな中で、浜村のキャリアに転機が訪れた。インドに立ち上げられた新しい子会社への異動が決まったのである。浜村は帰国子女であり、英語には自信があったため、キャリア面談の際にも英語を使う業務の希望を出していた。アジア海上のグローバル化が急展開となる中で、現場からの評価も高く、英語が使える浜村に白羽の矢が立つのは自然な流れだった。浜村はインド法人における営業担当部長として、顧客開拓を進めるとともに、商品開発についても関与するように言われた。
これは浜村にとって大きなチャレンジであった。同じ営業であり、かつ得意の英語が使えるとはいえ、異国の地で顧客開拓をしていくことは骨が折れることだろうと思っていた。また、今までは担当してなかった商品開発も担当する、ということで、業務的には大きな飛躍も求められる。しかし、そうは言いつつも、浜村には少なからず自信があった。自分には10年かけて築き上げてきた営業の“型”というものがある。これはどこにでも通用するはずだ、という思いがその背景にはあった。
実際にインドに着任後、浜村は早速計画作りに取りかかった。「こういう時は一にも二にも計画が命だ。ここを中途半端にするとPDCAサイクルが回せない・・・」。浜村は、事前に集めてもらった市場リサーチの結果を多面的に分析しながら、どのような顧客をターゲットにして、どのような商品をどれくらい売るのか、という具体的な検討にじっくり時間をかけた。データを深く洞察し、その結果を分かりやすく資料に落とし込むことに関して自信のあった浜村ではあったが、さすがに新しい市場ということもあり、インパクトのある戦略プランを構築するには多くの時間を必要とした。しかし、本社にある海外企画部にもたびたび電話会議で協力をもらいながら、浜村は大きな戦略プランとともに、具体的な1年分の営業計画の数字を積み上げていった。
「これで大丈夫だ。こういう動きをすれば本社にも報告できる数字が出来るはずだ」。着任してから一人、難しい顔でオフィスにこもる時間が長かった浜村にようやく明るい表情が戻った。浜村はプランを説明するために急いで現地の営業担当リーダー陣を招集した。リーダー陣は、着任してからあまり表に出てこない浜村が一体何をやっていたのか訝っていたのであるが、その資料の出来栄えに総じて驚いた顔をしていた。「ここまで精緻な計画は見たことがありません・・・」。そのあっけにとられる表情を見ながら、浜村はちょっとした既視感を覚えていた。「過去に、新しい支店に就任した時も、こんな驚きの表情で見られたよな」。
現地営業リーダー陣とのミーティングもそろそろ終わり時間に近づいていた。浜村はリーダー陣の表情を見ながら、「あとは現場を彼らに任せて、自分自身は新商品開発の勉強に専念しよう」と思っていた。ミーティングの最後に浜村は、「ここまでがPDCAサイクルのPの部分だ。さて、これからはDに移るぞ。気合を入れていこう!」と高らかに宣言した。
理論の概説:PDCA
今回は、浜村さんが言っている「PDCA」という言葉にフォーカスし、考えを深めていきましょう。
PDCAサイクルは、「トヨタ生産方式(TPS、Toyota Production System」の創始者である大野耐一氏が始めた問題解決プロセスをベースに、エドワード・デミング氏が体系化して整理したものだと言われています。今やPDCAサイクルという言葉は経営の世界に閉じた用語というよりは、むしろ日常あらゆる場面で使われる言葉になってきています。
PDCAは、ご承知のとおり、Plan-Do-Check-Actの4つのステップの頭文字をつなげたものになります(下の図を参照)。

当然ながら、この4ステップを一通り行ったら終わり、というわけではなく、最後のActを次のPlanにつなげ、1周ごとにサイクルを向上させて、継続的に業務改善することが重要となります。ここから語られる示唆は、以下のようなポイントが代表的です。
・ 実行(Do)に至る前に、しっかり目標(Plan)を具体的かつ明確にすること。
・ 実行(Do)の後は、評価(Check)によって振り返りを行うこと。
・ 改善(Act)を最後に行うことにより、改善を確実に行い、新たな計画(Plan)に確実につなげること
このあたりまでは、日々の活動から皆さん、よくお分かりのところでしょう。このような個人レベルにおいてPDCAをいかに効果的に回していくのか、ということは、多くの書籍でも語られていますので、敢えてここでは触れません。
今回お伝えしたいのは、PDCAを経営レベルに引き上げたとき、つまり「組織」としてこのPDCAを実践しようとした時に直面する多くの課題についてです。実際、経営レベルでPDCAが効果的に回せている事例はそれほど多くはありません。ここは実はあまり語られていないことでもあるので、このコラムで深めていきたいと思います。
経営現場におけるPDCAの実際
では、経営現場においてPDCAが回せていないケースというと、具体的にどのようなものが挙げられるでしょうか。
【パターン1:スピード感のないPDCA】
まずは、PDCAはよく考えられ丁寧に実践されているものの、スピード感がない、というパターンが散見されます。日本企業がグローバルの競合にスピードで負ける、ということがよく語られますが、まさにそのケースです。
これはなぜ起きるのでしょうか。まず理解しておきたいのは、PDCAの速度は相対的なものでしかないということです。その企業はずっと同じスピードでPDCAサイクルを回していたとしても、競合がそれ以上のスピードで回し始めれば「遅い」ということになりますし、また顧客がよりスピーディーな行動を求めれば、その瞬間に今までのスピードでは「遅い」ということになるのです。つまり、PDCAに求められるスピード感というのは絶対的なものはなく、そのビジネス環境に依存するのです。
ちょっと極端な例ですが、自動車市場での変化を見てみましょう。テスラモーターズに代表されるような電気自動車メーカーは、20世紀の自動車業界を支配した「ビッグ・スリー」との対比で「スモール・ハンドレッド」と呼ばれています。その名の通り、小さなベンチャー企業がどんどん参入して新たな商品を投入してきています。
たとえばテスラモーターは、会社設立からわずか5年後の2008年前半に1000万円のスポーツカー「ロードスター」を発売し、注目を集めました。小さな組織であることを生かして意思決定を素早くし、外部の力を使いながら、既存の業界では考えられないようなスピードでPDCAを回しているのです。元グーグル日本支社長だった辻野晃一郎氏は、テスラのことを「自動車メーカーという枠組みで見るのではなく、シリコンバレーのIT企業として見なくてはダメだ」と仰っています。スピードが全てであるIT業界のプレイヤーと、大きなヒエラルキーの中で重たく長いPDCAサイクルを回している既存の自動車業界とのスピードの差は歴然としています。これが「相対化」の恐ろしいところです。
では、なぜ環境に合わせてスピードを変えることが出来ないのでしょうか。それにはいくつかの要因がありますが、もっとも大きいのは、個々のメンバーの過去の成功体験によるものです。つまり、「ビジネスというものはこの程度までじっくり練らないとうまくいかない」、という程度感覚を体が覚えてしまっているのです。ですから、それ以下に下げるということが、本能的に難しい。頭で分かっていても、体がついていかないのです。こんなことが、PDCAのスピード感が一向に速くならない背景にあります。

【パターン2:接続感のないPDCA】
次のパターンは、PDCAの相互の接続感がなく、P・D・C・Aがそれぞれ個別に独立してしまっているものです。このパターンは、たとえば典型的には、本質的な目的意識がないままに、現場でひたすら実行(Do)を「やらされている」、といった現象として表れます。つまり、当初立てた目標が実行面まで理解、共有されていないのです。
そのことは、
・ やること(Do)そのものが目的化してしまい、何のためにやっているのかを誰も理解できていない。結果として現場のモチベーションはあがらない。
・ 他方で業績評価(Check)として数値管理はなされ、それに伴いインセンティブがついてくるために、手段を選ばずに実行が行われる。
・ 振り返りや改善(Act)については、そもそも目標が共有されていないために、「なぜその数値が達成できなかったのか」という側面だけに注目が集まり、本来の目的に照らし合わせた改善が行われない。自己満足や部分最適の改善行為が横行する。
といったことにつながり、形ばかりで意味のないPDCAが遂行されることになります。
では、なぜそういうことになってしまうのでしょうか。そこには組織的な分断による血流不全が背景にあります。
つまり、本社や経営企画、はたまたある特定の人物が戦略を考え、それを実行するのは別法人や別組織、といったパターンになると、組織間でうまく情報流通や感情の共有が行われなくなり、結果的にはPDCAがバラバラになってしまうことが多くなります。
さらにその背景にあるのは、責任意識の希薄化です。計画を立てた組織や人物が実行面まで責任を持たない、もしくは持てないケースは実は結構あります。たとえば、立てた計画の結果が出るのが数年後、というような事業であり、ローテーションで担当が交代するような組織の場合、一人の人が結果責任の意識を持ちにくくなります。
そうなると、PとDの間に乖離が生まれ、現場を理解しないまま計画作成がなされ、そして被害者意識を持った現場が計画を理解せぬまま実行していく、ということが横行する結果になります。P・D・C・A間に接続感が生じない背景には、こんなことがあります。

【パターン3:Plan偏重のPDCA】
典型的なパターンの3つ目は、Plan偏重のPDCAです。PDCAのサイクルは同じであっても、その中の時間配分においてPlanの比率が高いケースです。
よく見られるのが、予算策定や戦略策定に長時間、多くのメンバーが関わる事例です。予算策定までに下手をすると半年くらいの時間をかけ議論し、そして気付くとまたすぐに翌年度の予算策定に入っている、というようなケースが該当します。
このスケジュール感でPDCAを回そうとすると、当然、CheckやActはほとんど機能しません。結果が出る前に計画を練らなくてはならないからです。
このパターンの怖いところは、計画者側が強い思い込みを持ち始める、ということです。ここまで考えたのだからこういう結果でなくてはならない、必ずこうなるはずだ、という過度な期待値が発生することになります。そうなると、当然Checkの段階においても、出てきた結果を客観視することが出来なくなり、「自分が見たい情報だけを見る」ということや、「自分が解釈したい方向に解釈する」というような行為を誘発します。

こうしたことが、結果的に環境変化の認知の遅さにつながり、柔軟性の欠ける経営に結びついていってしまうのです。
解説:ミドルリーダーへの示唆
では、こんな現状を踏まえて、経営の現場において、より実効性のあるPDCAにしていくために、ミドルリーダーは何を心がけるべきなのでしょうか。
まず逆説的ですが、「PDCAの型ありきで考えない」ということが言えます。上記3つの症状の全ての背景にあるのは、「PDCAかくあるべし」というマインドセットが固定化してしまっていることです。しかし、PDCAというのは、当然ながら業界によって異なります。
たとえば、数年単位で計画を立てて様々な企業を巻き込みながら緻密に進めなくてはならないようなプラント・プロジェクト事業におけるPDCAと、携帯電話のアプリケーション開発のような事業におけるPDCAでは、それぞれスピード感、重点を置くべきところなどが全く異なります。前者の事業であれば、限定された発注先のニーズをどうやって満たし、そして顔の見えている具体的な競合相手数社に対してどういう優位性を打ち出していくのか、ということを念頭に、入念に計画を練ることが重要になります。この手のビジネスの怖いところは、万が一失敗した時に、後戻りできないことです。したがって、多少スピード感を犠牲にしても、緻密に入念にPlanをしっかり立てた方がいいのです。他方、後者のアプリ事業の事例でいえば、計画も重要ですが、まずは試してみて(Do)、そこから結果(Check)を読み取りどう素早く軌道修正(Act)していくのかの勝負になります。業界の変化のスピードが速く、先読みがしにくい業界であればある程、実行(Do)以降の後工程に比重が移ってきます。
つまりは、業界環境をどう捉えてPDCAを設計するのか、ということが重要になるのです。
加えてどのようなビジネスにおいても深く留意すべき点は、「業界環境は変化する」ということです。先の自動車業界の事例でも書いたとおり、「今まで競合だと思っていなかったようなプレイヤーが業界に入り込んで、業界環境を大きく変える」ということはよくあることです。また、顧客が変わればその期待値も変化します。今まで日本の顧客を相手にしていた企業が、中国に進出した際、現地の顧客側のスピード感にまったくついていけずに右往左往する、ということもよく耳にします。
そして、概して、どの業界においてもスピードは速まってきています。異業種から違うルールを持ちこんで参入してくる競合、トップダウン型のガバナンスで迅速に意思決定をしてくる競合、そして急激な内需の高まりを背景に爆発的な拡大や変化を見せる新興諸国のニーズ。これらのことは、全てPDCAのスピードを速める方向に変化を促します。
だからこそ、我々ミドルリーダーは、「現行のPDCAサイクルありき」で考えず、外部の競争環境に注意を払いながら、絶えずゼロリセットであるべきPDCAサイクルを考えなくてはならないのです。
PDCAサイクルの発展版「LAMDAサイクル」
その時、ミドルリーダーが心がけるべきことは何でしょうか。
ここで、PDCAサイクルの「発展版」として、LAMDAサイクルという概念を紹介したいと思います。このサイクルは、MITにてトヨタ製品開発を参考に「リーン生産方式」を体系化したアレン・ウォード博士によって開発されたものです。
LAMDA(Look-Ask-Model-Discuss-Act)サイクル

このサイクルにおいて伝えていることは、まず現場を見て、その真相を問いかけることにより、背後に潜むメカニズムを理解するということ。そして、理解したことをシンプルにモデル化(試作品や見本、グラフ、報告書など具体的に目に見える形に変換)して表現し、その“叩き台”をベースに議論を始め、意思決定を行う、ということです。言っていることは極めてPDCAに似ていますが、このサイクルにPDCAサイクルのスピードを速めるヒントが隠されています。
LAMDAサイクルとPDCAサイクルの比較を端的に言うと、以下のポイントに集約できます。
・ 机上で考える前に現場に赴いて「現地現物」を確認すること
・ 一人で考えるのではなく、他者との「双方向コミュニケーション」を通じて問題の所在を明確にすること
・ 抽象的に考えるのではなく、無理矢理でもいいのでサービスや商品を具体的な「プロトタイプ化」すること
・ その具体的なプロトタイプに対する他者(含む顧客)からの「フィードバックを吸収」し、知恵として取り込むこと
つまり、PDCAの裏側に「現地現物」「双方向コミュニケーション」「プロトタイプ化」「フィードバックの吸収」という4つの行動原則をセットで持つことが、現場のミドルリーダーにとってより効果的なPDCAの実現につながると言えるでしょう。

浜村さんはどうすべきか?
では、そんなポイントを踏まえつつ、冒頭の浜村さんのストーリーに立ち戻ってみましょう。彼の課題は何だったのでしょうか。
まず、浜村さんの無意識に陥ってしまっている症状は、過去の成功体験によって培われた「PDCAかくあるべし」というマインドセットが根強く残っていることです。しかし、本文でも記載した通り、PDCAは業界環境によって大きく変わるのです。たとえば、浜村さんが過去にいた国内地域営業はどちらかというと競争が緩やかな中で、農耕的に計画に基づいて実践を重ねて収益を上げていくことが重要なポイントでした。不測の事態も起きにくく、実践を重ねていき、そこで1年単位でじわじわ溜まったノウハウをもとに改善を重ねていくことが結果につながったのです。
しかし、今回の配属先は、環境変化が激しく、不測の事態が急に起きる職場です。インドと日本の市場は大きく異なります。平均年齢も異なれば、規制も違う。市場の拡大スピードも、そして保険に対するニーズも全く違うでしょう。こういう市場においては、まずはいかにPDCAサイクルを短くスピーディーに回すか、ということを考えなくてはなりません。
そこで求められるのが、先ほどの4つの行動原則です。浜村さんの取っていた行動の多くは、この原則に反していたことに気付きます。具体的には、現場を十分に見ていないこと。双方向のコミュニケーションもせずに自分だけで考えていること。そして、プランに時間をかけ、スモールスタートによってフィードバックを得ながら改善する、という意識に欠けていること、などがあげられます。これら全ては、日本での成功体験によって見えなくなっていることなのだと思われます。
裏を返せば、もし浜村さんが日本市場での成功体験を忘れて、新たな行動原理を確実に行うことが出来れば、この新興市場は日本では決して発見できない新しい示唆に満ち溢れている、ということでもあるのです。
日本企業がこれからのグローバル競争において、変化対応スピードに追いついて行けるかどうか、ということについては、全社レベルの大きな戦略の方向性に因る部分ももちろんあるでしょう。しかしながら、それだけではなく、このように浜村さんのような現場ミドルリーダークラスのPDCAの積み重ねの勝負でもあるのです。
浜村さんのみならず、多くのミドルリーダーがその事実に気付き、環境変化を踏まえて行動原則を変えることが出来るのか。その点がこれから問われてくるのでしょう。
激変する環境に即した「PDCAのスピード勝負」の時代
今回はPDCAサイクルという、ある種、使い古された概念について考察を深めてみました。
本文中にも書きましたが、今日の競争環境においては、ほぼ全ての業界において「PDCAのスピード勝負」になってきています。日本が大きく成功したのは、20世紀におけるフルバリューチェーン型工業製品での競争です。そこではリコールなどが起きて損害を被らないように、入念なPlanが練られ、開発から販売、アフターフォローまで足の長いPDCAサイクルの設計が行われていました。しかし、そのモデルは徐々に終焉を迎えつつあります。
昨今のIT、もしくはバリューチェーン特化型の産業では、スモールスタートを切って顧客評価からの学習を重ねながら徐々に完成モデルに近づけていく、というまさに「走りながら考える」というスタイルが定着しています。これこそが21世紀型のPDCAサイクルというのかも知れません。
時代環境は確実に変わってきています。このスピードに乗り遅れないためにも、「ミドルリーダー自身がリスクを取り、走りながらPDCAを回していこう」ということを最後に申し上げておきたいと思います。
■参考文献:
危機を超える経営―不測の事態、激変する市場にどう対応するか
グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた
開発戦略は「意思決定」を遅らせろ! ─トヨタが発想し、HPで導入、ハーレーダビッドソンを伸ばした画期的メソッド「リーン製品開発」
■連載一覧はこちら
#ストーリーで学ぶ経営戦略シリーズ
















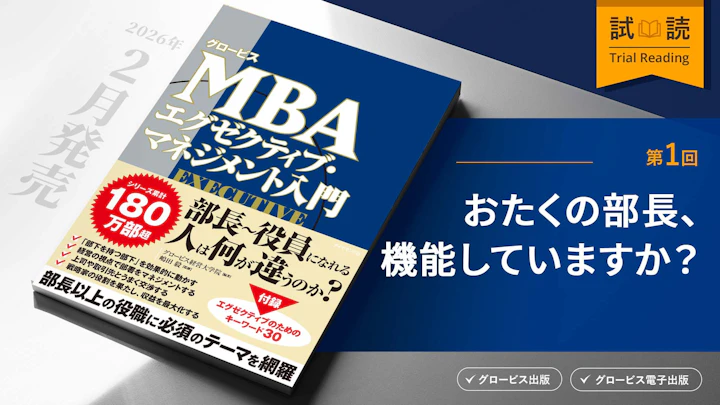






















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
