
会員限定
世代間のコミュニケーションで迷う時は、Z世代の価値観を理解するよう努めよう/みんなの相談室Premium
日常にある身近な疑問を、ビジネス知識を使って解決する「みんなの相談室Premium」。 今回寄せられたのは、「ミドル層はハラスメントを恐れてコミュニケーションがとりづらくなり、一方でコミュニケーションを欲している若年層は物足りなさを感じている、という意見を社内で耳にしました。職場の交流を増やし、活性化させるためにはどのようにしたら良いでしょうか。」というお悩み。1996年から2015年に生まれたZ世代の価値観は、これまでの世代の価値観と全く異なるとグロービス経営大学院教員・高岡明日香が説明し、その「Z世代の価値観を理解する」ために必要なポイントを解説します。(肩書きは2022年6月24日撮影当時のもの) 高岡 明日香 グロービス経営大学院 教員 名越 涼 アナウンサー





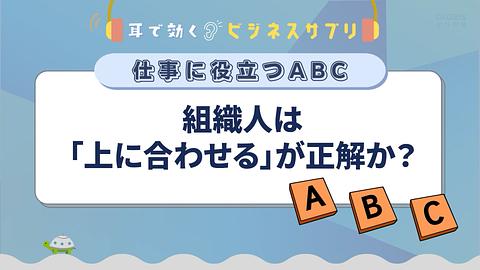
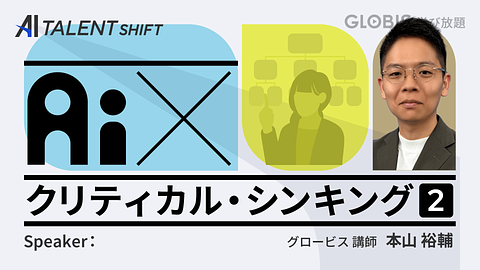
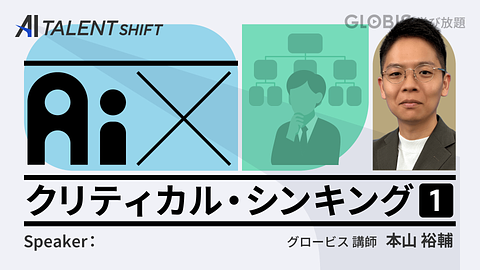









より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
54人の振り返り
y_cerezo
専門職
おっさんは年齢的なものでなく立ち振舞い。
masa_isikawa
販売・サービス・事務
年長だからと言って、上から目線の態度はとらない。
fujino_0920
販売・サービス・事務
どこの会社でも年長者が威張る、偉いといった風潮を誰かが壊していく必要があると感じました。
wata_hiroyuki
メーカー技術・研究・開発
大人同士である事を考えれば、本質的な問いかけも、年齢関係無く要求されて良く、誰が言っているかでは無く、何を言っているかが大事であり、問題点は解決のための代案とセットで話す様な議論の作法としたい。若手が、おじさんがでは無く、個々の意見について、立場や年齢関係無く、公平に全方向から評価しながら議論する仕組みが必要である。時代に追いつけない事も、未熟である事も区別なく評価される事のメリット・デメリットも考えたい。
ozawa_h
IT・WEB・エンジニア
社会が変化して今までの方法では競争力が無いにも関わらず新しいことを勉強しないで言うだけで実行しない人はどこでもいると思う。
人は楽が出来る方に進むため、そのような人がいると他の人も真似をして職場及び会社はダメになる。
しかし、人は人で自分は自分なのでそのような人に対して文句を言う時間があるならば自分のキャリアを優先して自分の実績を作ることにする。
kfujimu_0630
マーケティング
提案なき批判は私も嫌いです。オッサンですがオッサンにならないように気をつけたいと強く思いました。ありがとうございました。
yo_ma
販売・サービス・事務
おっさん社会で日本沈没!!
makoto112
営業
私を含め、年長者にも、今までと違う別の方法で、社会や組織に貢献する方法を学ばなければならない。
mimimi1030
メーカー技術・研究・開発
自分でいつでも違う道を選べる力をつけておく。
肝に銘じます。
mo_0ika
営業
オッサンを定義してくれてありがとう。年長者は尊重すべきという幻想はすて、間違っていることは指摘できる自分になりたいです。
th15470
IT・WEB・エンジニア
この4つのパターンがよく分かるなぁと思いました。自分も気を付けようと思いました。
0402_nyy
IT・WEB・エンジニア
古い価値感
過去の成功
年功序列
よそ者
自己主張を大事にする。
若手に支援を投げかける
rashimaru
その他
女性もおっさん化する
a_2024
販売・サービス・事務
自分もオッサン化してる部分があるかもしれないので気を付けようと思った
chengyi0102
営業
提案無き批判をしない、ダサいオッサンにならない そうゆうオッサンとは距離を置くようにして自己研鑽して行きたい。
tsubamoto_
営業
とかくおっさんが不要という風潮があるが、おっさんが言う事全てが悪いとは思われたくない
若者ばかりの会社もどうかと思う。
年長=エライ という考えは捨て去り、組織に役立つ人材は年齢関係なく使う組織を作りあげたいものである。
axtyu
IT・WEB・エンジニア
劣化するオッサンとならないよう、過去のやり方に固執せず、新しいやり方でも良い案があれば、積極的に受け入れていく
htnakaga
メーカー技術・研究・開発
うん きをつけます おっさんにならないよに!!
taka5megu6
メーカー技術・研究・開発
つくづく、このように言われるような「おっさん」にはなりたくない。メンバーのためになるよう経験をもとに今の状況に合わせた考えができるような「おっさん」になります
skoike777
経理・財務
年齢とともに自然とおっさん化しやすいことに留意して日々過ごしたい
dia44
メーカー技術・研究・開発
提案なき批判は私も嫌いです。オッサンですがオッサンにならないように気をつけたいと強く思いました。ありがとうございました。
hirokitokiwa
営業
き批判をしてくる人がもう嫌いで嫌いで仕方ないです ただただ会議で腕を組んでふんぞり返って提案なき批判を繰り返す まあもしかするとこれ良い面もあるかもしれませんけど基本的にはこういう人は嫌だなぁと そんな気持ちで日々悶々としておりましたそんな最中であった本を今日はご紹介します 本のタイトルは劣化するおっさん社会の処方箋 まあこれまず何より重要なのがおっさんの定義ですよね これは次の4つの特徴のいずれ
yuuki-i
人事・労務・法務
良いオッサンになれるようにがんばります。考え方、やり方は人それぞれ、柔軟的になろうと思いました。
a-psychopath
マーケティング
当然ながらおっさんであることが悪いわけではないが、おっさんを言い訳にしているおっさんは悪いおっさんだと思う。
everest
営業
年齢に関係なく多様な価値観を受け入れる組織づくりとなり健全な対話を促す行動ができるようになると感じた。
matt_chan
IT・WEB・エンジニア
油断しているとオッサン化すると思いました。
ak15
メーカー技術・研究・開発
おっさんが上に立つと仕事が進みにくくなります。おっさんを進化させてつい夢中になると視界が狭くなりがちなところに気づきを与えて、進路の可能性はたくさんあることを教えてくれたらいいなと思いました。
脱おっさんして若者と競うよりは。。。
ichigo_mikan_55
経理・財務
私もオッサンであることに気がついた。臨機応変に対応していこうと思いました。
moririn-yukirin
専門職
自分の周りにたくさんの劣化するおっさんが居る。例えば不機嫌であることを態度に示す「おっさん」、そのおっさんを年下だからと機嫌を取るような行動をとる「おっさん」、年下は敬語を使うべきだと思っている「おっさん」。様々な「おっさん」がいて、その「おっさん」が上司になると、どんどん上司に忖度する「おっさん」が増える。社会の劣化がどんどん促進される。
そういう私も、年上の無能な「おっさん」に気を使うシーンは多い。その様な年上を敬う文化は認めつつ、一方で、若者に育て、そして若者から学ぶ謙虚な姿勢をもって予測できない変化の起こる今の時代をドライブしていこうと思う。
two-tani
その他
批判しかしないオッサンは男だけとは限らない。
古い慣習にとらわれないよう気をつけたい。
yamadaippei
メーカー技術・研究・開発
役立った
hibizenshin
営業
レッテル貼り、言葉の暴力は恐ろしいことがよくわかりました。この題名の「おっさん」部分が「若者」だったり「おばさん」だったりしたらどうでしょうか?おそらく各所から批判を受けるでしょうね。
普通に成功体験に凝り固まった頭の固い人だと売れない題名というのはわかりますけどね。
dai8azusa
その他
オッサンの役割が代わった、
sphsph
メーカー技術・研究・開発
面白い考え方と思いました。
まさに自分は?
forhappy
経理・財務
「おっさん」の定義が面白い。自分がならない戒めとしたい。
hideakiusuda
メーカー技術・研究・開発
提案なき批判をしないように気を付けます
m102201
人事・労務・法務
年長者に対する対応の変化が実用であり、年長者もそれを理解し、受け入れ、対応していく必要を感じた。
3tomy
資材・購買・物流
オッサン年代のオバサンが聞きました。
分かる!わかりすぎます。
”オッサン”に変わる代名詞にすれば、もっと年齢に関係なく食いつきそうです。
sho23915
経理・財務
..........
500nozomi
その他
まずは自分自身をよく省みる
koji_0036
メーカー技術・研究・開発
古い価値観を棄てる。
年功序列の禁止。
組織をダメにする。
shin_pei
その他
時代に沿って考え方や価値観も変化するので柔軟に対応しなければならないが、年長者の方は価値観が進化してないので、そこに対してどう促していくかが大切だと思います。
kazuyoshi0624
販売・サービス・事務
これも、時代の流れですね。
naokiyamahara
専門職
昔の功績を自信満々に語っている方が年長者に多いです。過去の成功は今の失敗という言葉を思い出しました。
h_szk
IT・WEB・エンジニア
「オッサンの定義付け」として4つあげておりましたが、聞いていて違和感を感じました。
まず、オッサンと言う言葉を使って一括りにすると誤解を生むのではないでしょうか。
オジさん世代のみならず、若い世代にも言えると仰っていたかと思います。それを「オッサン」という言葉を使って一括りにしているのは聞き手の受けを狙っているように聞こえます。きっとそうなのでしょうけれども、一括りにせず、4つの定義をそのまま語れば良いのでは?と感じました。
「オッサン」としたのはマーケティングを意識されたのでしょうか。
yasso
販売・サービス・事務
我が社にも、提案なき批判をするメンバーがいます。自分自身もそうならないように、自己研鑽に励みます。年長者や偉い人の言葉を鵜呑みにせず、意思を持って、行動や指示をしていきます。
t-k001133
販売・サービス・事務
自己に照らし合わせおっさんの定義を考えてみると、凝り固まった、価値観や上司への忖度など当てはまる部分があった。自分いつでも会社を出ても問題ない状態を常にへ考えておく必要があると感じた。
tsuchinaga
営業
若年層の提案や成果物に対し、代替案もなく、ただ批判するだけの上司は日本の社会には不要だと思う。自分が若かったころには、絶対にこのような上司になりたくない!と思っていたが、この立場となって改めて肝に銘じていきたいと感じた。
matsumym
資材・購買・物流
オッサンの定義が、新しい価値観を受け入れられない人、過去の成功体験に固執する人、階層や年功序列意識の強い人、よそものに排他的な人のいずれかに当てはまるというのは興味深かった。
目まぐるしい社会の変化スピードへの適応、情報の普遍化、長寿命によりオッサンであることが許されない社会になってきている。
年長者を尊重すべきとの意識を排除し、若手を支援するリーダーシップが必要とされている。
miroku
資材・購買・物流
提案なき批判はいけません。が,それがオッサンに定義されるのは疑問です。若い世代でも意見を言わない者は大盛いる。若い世代程,選挙には行かない。権利放棄している。
j0333135
その他
おっさんのやる気をいかに出すかが今後の管理者の宿命
sai-3448
人事・労務・法務
一度手に取ってみたいと思います。
morimotoa
営業
あくまでも発言は行動で判断する。年長者であるからは考慮しない。
shikay
メーカー技術・研究・開発
自分の組織は平均年齢が高いが、シニアが活き活き働いているので、接するこちらも楽しい。シニアはシニアなりにぶ厚い経験があるので、自分は興味がある。自分は転職してこの組織にやってきたが、意外にもよそ者の自分が見るよりもずっとこの会社にいる人は課題を感じているようだ。若手からはよく年長者の重箱の隅をつつくような指摘が嫌だという声を聴くし、年長者からは最近の若手は忍耐力がなくて甘えているという声を聴く。若手は若手なりに面白い考えを持っているし、シニアはシニアで面白い経験を持っているので自分は両方の話をもっと聞きたいと思った。この組織はジェネレーションギャップをすごく意識しているが、自分はよそ者に冷たい排他的な感じに課題感を持っている。この講座をきいて、どちらも同じ課題から来ているような気がした。