
02月10日(火)まで無料
0:59:48
割引情報をチェック!

AI BUSINESS SHIFT 第8回 機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第8回です。 第8回「機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル」では、AIが営業現場にどのような変化をもたらしているのか、営業担当者・営業マネージャー・組織としての役割や戦略が、AIによってどう進化していくのかを、営業プロセスの分解や実際の現場事例を通じて学びます。 ■こんな方におすすめ ・AIを活用した営業活動の最新動向や現場のリアルを知りたい方 ・営業現場の変化に直面している営業マネージャー・現場リーダーの方 ・AI時代における営業戦略や営業マネジメントのあり方を学びたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年2月制作)
02月10日(火)まで無料

マネジャーのための仕事の任せ方
「仕事を任せると失敗が怖い」「自分でやった方が早い」マネージャーとしてメンバーやチームの力を引き出しながら成果を上げるには、どのように仕事を任せていけば良いのでしょうか? 変化の激しい時代において、マネージャーとして成果を上げ続けるためには、メンバーの個性や特性を理解し、それに合わせた効果的な任せ方を身につけることが重要です。このコースでは、ソーシャルスタイル理論を活用してメンバーごとに最適なアプローチを学びます。「任せる力」を高めることで、チーム全体の成長を促進し、自身のリーダーシップを発揮できるようになっていきます。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2024年12月制作)
会員限定

AI時代の個人力
AIが仕事や社会の前提を変え続ける今、最も求められるのは「他者に代替されない個としての力」“個人力”です。 本コースでは、澤円氏の著書『個人力』をもとに、AI時代をしなやかに生き抜くための「前向きな自己中戦略」を学びます。 テーマは、「Being(ありたい自分)」を中心に据え、自ら考え(Think)、変化し(Transform)、協働する(Collaborate)ことで、自分らしい価値を発揮していくこと。 リスキリングやAI活用が叫ばれる今こそ、スキルより先に“自分の軸”を問うことが重要です。 あなたは何を大切にし、どんな未来を描きたいのか? このコースは、あなたが“ありたい自分”として生き、キャリアをデザインしていくための思考と行動のガイドになります。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年11月制作)
会員限定
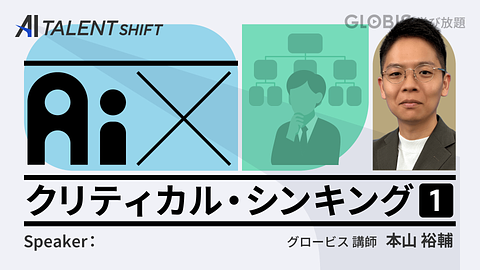
【AI×クリティカル・シンキング】①イシューと枠組みでプロンプトを磨く
生成AIから期待する回答を引き出せず、試行錯誤を重ねていませんか。 本コースでは、生成AI活用の質を高める鍵として、クリティカル・シンキングの視点からイシュー設定と枠組みを押さえる重要性を解説します。 目的に直結する問いの立て方や、プロンプトに落とし込む際の実践ポイントを具体例とともに学ぶことで、AIをより思考のパートナーとして活用できるようになります。 生成AIを業務で使い始めた方から、活用を一段深めたい方まで、再現性あるプロンプト設計を身につけたい方におすすめの内容です。 さらに学びを深めたい方は、こちらも合わせてご覧ください。 【AI×クリティカル・シンキング】②AIの弱点との向き合い方 https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/cdfe41e3/learn/steps/62198 ※本コースは、AI時代のビジネススキルを学ぶ「AIタレントシフト」シリーズの一環として提供しています。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
会員限定

リーダーの挑戦⑤ 藤田晋氏(サイバーエージェント代表取締役)
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第5回目のゲストは、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋氏。起業の理由、経営をどうやって学んだか、アメーバブログ・ABEMAの立ち上げ、経営チームづくりについてなど聞いていきます。(肩書きは2020年12月11日撮影当時のもの) 藤田 晋 サイバーエージェント 代表取締役 堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
会員限定

ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 前編 なぜ眠れないのか?~
「仕事が終わらないから睡眠時間を少し削ろう…」「業務時間中なかなか集中できない…」「毎日朝起きるのがつらい…」。 あなたはこのような経験をしたことはありませんか? 仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削りがちなのが「睡眠」時間。 実は今、日本社会は世界と比較して「最も眠らない国」だということもわかってきています。 慢性的な睡眠不足は、心身の健康に悪影響なだけでなく、仕事のパフォーマンスにも当然大きな影響を与え、社会全体の経済損失につながります。 このコースでは、基本的な睡眠リテラシーを学んだ後の「問題解決編」として、「なぜ多くのビジネスパーソンは眠れないのか?」について解説していきます。 ▼本コースで学べる主な内容 ・そもそも眠れないことは何が問題なのか? ・眠れなくなってしまう原因とは? 睡眠不足の原因は認知機能の問題にありました。 自身の睡眠不足に対し、正しく「気づき・理解し・行動を変える」第一歩を踏み出しましょう。 ▼関連コース ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~リテラシー編~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/24575c03/learn/steps/53129 ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 後編 どうしたら眠れるのか?~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/4ba981e9/learn/steps/62042 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

大阿闍梨 塩沼亮潤が死の手前で見つけた「生き方」
あすか会議2018 第4部分科会B-1「極限の世界で見つけた人生の歩み方」 (2018年7月7日開催/国立京都国際会館) 1300年間で2人目となる大峯千日回峰行満行を果たした塩沼亮潤大阿闍梨。48キロの山道を1日16時間掛けて歩き、それを千日間に亘って続ける過酷な行の中で、どのような悟りを得たのか。そして、9日間、断食・断水・不眠・不臥を続ける四無行満行という極限の世界で何を見つけたのか。塩沼氏が「創造と変革の志士」へ贈る「人生の歩み方」とは。(肩書きは2018年7月7日登壇当時のもの) 塩沼 亮潤 慈眼寺 住職
無料
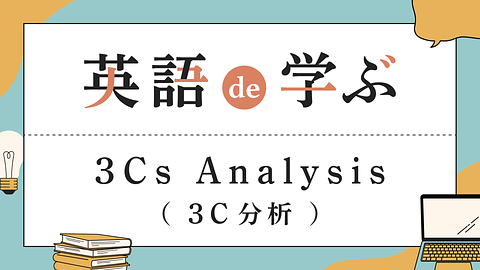
英語 de 学ぶ!3Cs Analysis(3C分析)
このコースでは、グロービス学び放題の英語版である『GLOBIS Unlimited』のコースの中から、ビジネスで役立つ頻出の英語表現をピックアップしています。英語ネイティブの方が実際に見ているコースなので、リアルなビジネス英語の表現を学ぶことができます。 今回のコースは「3Cs Analysis(3C分析)」です。一緒に『英語で』ビジネス知識を学んでいきましょう! ▼今回扱ったUnlimitedコース続きは下記からご覧いただけます 3Cs Analysis https://unlimited.globis.co.jp/en/courses/da5ca962/learn/steps/36362 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
コメント418件
namifour
リーダーシップのタイプについて改めてどのようなリーダーシップを適用していくか、再確認した。
また、表彰などの外発的動機付けに取り掛かりやすいが、内発的な動機を積極的に引き出していきたい。
yasu-okazaki
リーダーシップはサーバント型が合っていると思う。良くコミュニケーションを取り、目標共有、権限の付与、チームでの貢献を目指す。モチベーションを高めるような、プレゼンやチャレンジャブルな仕事を与えてフォローをしていく。
kk1911
チームの状態が時を経るごとに変わっていくのは実体験からも納得できる。しかしながら動乱期を抜けるのは大変エネルギーのいることで、往々にしてプロジェクトの期限までその状態が続くこともある。
その場合の対処方法をもう少し具体的に知りたい。
daisukehan
プロジェクトを遂行する際に自分の役割、求められるスキルに迷うことが多い。緊急性が低く、重要度が高いプロジェクトはサーバント型リーダーシップが発揮できれば成果が得やすくなることが学べた。
ozawa_h
チームのモチベーションなどの詳細についてはGLOBISの他ビデオでも説明されていました。
asatani
DX推進のプロジェクトでアドバイザーの立場にあります。
内発的モチベーションの向上を重視し、メンバーへの声掛け等を通じて業務改革の達成感や自己の成長感を持ってもらえるよう努力したい。
masashi_miura
チーム/プロジェクト編成やメンバの育成・モチベーション向上手法の参考となった。
atuya
指示命令型は、昭和初期なイメージ、サーバント型は令和なやり方なのかな
mori-za
10月に異動となり新たな職場で組織職をするので、チームパフォーマンスを早く発揮できるようコミュニケーションに力をいれていきます
maedakazu
自身のマネジメントスタイルをいままで意識しておらず、教育を受けてサーバント型にあてはまると感じた。
奉仕するスタイルであるが、メンバ主導になりすぎて、リーダの存在が消えないようにはしたい
emico_co
プロジェクトリードをする上での立ち上がりを推進していく上でとても重要な要素だと感じました。またコンフリクトや衝突が起こってはダメという認識でしたが、そういうことも乗り越えることが大事であると理解できたのが大きかったです。
tae-sugawara
日々の業務おいて、少なからず個々の業務の偏りがみられるため、その改善に活用できると思います。
ken1123
モチベーション作りには十分活かせそう。
natsumi2022
プロジェクトマネジメントのリーダーシップの発揮方法についていくつかあることがわかりました。チームメンバーや状況に応じて、自らの振る舞いの適切な関わり方があると理解しました。一方で、自分の個性としてどれが得意・不得意などあると感じました。教科書通りに対応することが最も適するかもしれませんが、うまくいかないときは自分の得意な対応方法の中でどのようにカバーするかをプランBとして考える必要もあると理解しました。
20221122
少しずつ意識付け、を心掛けしたい
stani
これを参考にしチームパフォーマンスを向上したい。
007mine
PMの業務遂行には、目的、目標の共有、役割の明確化、チームとして活動するなど、各自のモチベーションを上げる必要が有る。
sakiyam2
サーバント型の運営をやってみたいと思っているが、スキルを持ったメンバーを集められることはほとんどなく、結局集権型の無理矢理カリスマ型で自分自身が疲弊してしまうことが多い。
miemie2020
チームのパフォーマンスが低めなので、対話をしながら、各メンバーがどのようにしたら、パフォーマンスが高く維持できるかを確認します。
tomona06
モチベーションを保つ方法は外発的動機と内発的動機があり、内発的動機付けの方が長持ちする
chang_shin
最後にあったように、メンバーが内発的にモチベーションを上げて行動できるように持って行くことを目指したい。具体的な行動がなかなか思いつきませんが…。
inokoko
モチベーションを高めるのはほんとに難しい。
k_yuna
大変勉強になりました。
karikomi-1011
大変お世話になっております。
jktaisuje
メンバーの性格や役割によっては、自身のマネジメントスタイルを変える必要がありますね。メンバーが何に対してモチベーションを発揮するのか、どんな仕事のスタイルならパワーが出しやすいのかなどを見極め、支援するのもマネジメントの重要な役割だと思います。
そのためにも、メンバーとのコミュニケーションを積極的に取り、人となりを把握する事も重要だと思いました。
keiichi_1123
発言するメンバーがいつも限られているなども課題を抱えているため、メンバーに対する目標の動機づけから始める必要があると思った。
意見を言うことが損という発言もあるため、見直しが必要だと感じているが、まだ具体的な進め方が維持できていない。一番初期の段階か安定期か、いまいち現状も分析できていない。
nyx
本項目をうけて、サーバント型リーダシップをとるためには、どうしたらいいかをもっと学びたいと思いました。
noriko_chita
自分自身は分権型・サーバント型で進めていることが多いと感じたが(集まるPJメンバーの立場専門分野が自分と異なることが多い),PJ対応の期間やメンバーによっては集権型にも使い分けることが必要かと思った.
kawai_ryouta
自分の性格も含めてこれまでのプロジェクトを振り返ると、マネジメントはサーバント型だったと思うが、現在のプロジェクトではメンバーも十分な知識を持たない業務のPJなので、どういった進め方が良いのかを考えてみるいい機会になった。
moveon-s
自分自身は気持ちが弱く、メンタルに注意必要だと認識しました。
mayutaro
モチベーション維持をさせるために外発的な動機付けを多く使用してきたが、内発的な動機付けも必要であるという部分が印象深かった。
kita_furukawa
モチベーションは、個人およびチームともに非常に必要なこと
持続するように大切にしていきたい
umebryo
プロジェクトを進めるには、マネジメント活動、リーダーシップ活動とともにチームを育成していくことが重要と感じた。
westin4324
プロジェクトの立ち上げで集権型、分権型を決めるとあったが、状況により変化すると考える。トラブル発生時には集権型を発動するケースがある。
チーム育成においては、目的・目標の共有と権限付与が大切と理解した。PMが指導するというよりメンバー各自が自身と他社の役割を理解し責任を果たすためのスキル獲得と準備を行うことが、チームとしての成果につながると考える。
sugima
チームの成長過程が成立、動乱、安定、遂行の4段階あり、動乱から安定への移行を迅速に行い
その後のモチベーション維持が重要だとわかった。
モチベーション維持にはボーナスやインセンティブを有効に活用したいと思う。
noriaki_08
多用な業務を行っていく必要があるが、これにチームを形成して取り組む必要性がましているこの頃です。これを的確に行う上で、そのチームの形成から実際に成果を生むようなチームにして実績を上げていく上で、段階があり、各々の時期に適切、必要な視点が提供され、有用なノウハウを気づきを与えてもらったと思う。特に、チームとして業務を進める上で必須のマネージメントとリーダーシップについていくつかのVariation選択肢があり、業務の内容、特性、チーム大きさによりこれを使い分ける視点は、柔軟に成果を上げていく上で有用だったと思うし、チームとしての育成と各人の育成、インセンティヴの用意、選択潮も活用していくことになると思う。総じて業務の対応力、必要な管理、マネージメントの能力があがると思われ、感謝している。
mekaboo
チームが遂行期に入ったとしても、ついてこられないメンバーがいる。
いかに救済するかどうかが問題。
451u
チームメンバーが快適に作業ができるよう、方針は定めつつ、自発的に行動できるようにするのが大切だとわかりました。
tdi-ihara
チームの偏りを念頭に置いて配置していますが、うまくいかないことが多くあります。配置変へなどでモチベーションが上がる下がるがあることも事実でこの中で学んだことを少しでも活かせるよう頑張っていきます
ka110
チームの成熟度によってパフォーマンスが変わるのは理解できる。
私は社外の人間を使うことがほとんどで部分的に社内の人間を使う。
効率重視で進めてきたが、これは集権型といわれるものだと初めて知った。
任せられるリソースがあれば、もっと楽ができるのだろうと思った。
aya_anne
他人のモチベーションを上げることは、片手間で出来る事でもなく、
決まったやり方があるわけではないので難しいと感じた
bobby2490
チームの問題は人の問題が本当に多くある意味一番難しい領域だと感じます。
理想は全員が内発的なモチベーションで活動し生産性が最大化できている状態だが、完ぺきなプロジェクトはほぼ無いとも思う。
特にサーバント型リーダーシップでは「人たらし力」が結構重要かなと思う。
hr-sakai
プロジェクトを成功させるためにもチームのモチベーションを上げて結束することが重要だ。
ma-my
内発的な動機を如何に高められることが組織を安定航行に持っていくポイントであることをしれたので日々注意をして接する必要がある。
ore-ore
チームの成立期、動乱期、安定期、遂行期のどの段階にあるかを見極め、なるべく早く遂行期にもっていく必要があると思いました。
matsuyuki1210
内発的なモチベーションを、もってもららう
ryuji_kawano
プロジェクトの人間関係も、人である以上、学生の部活動での人間関係と変わらないと感じた。
koki_dayo
チームの成長としては個人それぞれにしっかりと役割と責任を与えることが大切だと思った。分散型のほうが良いと個人的に思ったがそのためには個人がある程度の知識と能力を持っていることが条件だと感じた。
kousei_yano
リーダーが指示する方針よりメンバーが自発的な姿勢でプロジェクトに参加するほうがチームとして成長できると個人的には思っています。
yuya_yamada0618
目的、役割を明確にし、メンバーに浸透させ動乱期を早期に乗り越え、スピーディーにプロジェクトを軌道に乗せたい。
sugitaka-jp
メンバーをモチベートし早期にチームを安定期、遂行期に移行するための施策が重要。そのためにはプロジェクトの重要性、メンバーの役割の重要性などのコミュニケーションとメンバーへの目配り気配りが重要
kata8909636
チームは、一人一人個性を持った人格の集まりであり、マネジメントとしてチームの発展段階に合わせたフォローが必要なことを理解しました
mochi_uj
チーム育成には、目的と目標の共有、メンバーへ役割と責任を付与する、チームで成果を出すことの意識づけが大切である。
nigu
・プロジェクトチームを広義的には部、課という「組織」、また「業務単位」に置き換えて考えることができる。
mokkun52
パフォーマンスの最大化を意識し、チームの活かし方を探る習慣つげをする。
madadi
These are very important steps and measures for a successful project managment.
kkkkssss
プロジェクトの運営において、集権型か分権型かということは非常に重要な要素であり、各メンバーの権限と責任がどのように付与されかによってチームパーフォーマンスが大きく影響を受けることが理解出来ました。
koichirou_k
いかに動乱期を短くして、早く遂行期に入るか、学んだことを活かしていきたい。
norihito
内発的な動機づけのコツを知りたいと思った。
また、プロジェクトメンバーと、プロジェクトマネジメントオフィスの両面がプロジェクトを遂行していく意志を持つことが大切だと思った。
ryusho1118
様々なプロジェクトに参加しているが、個人の育成に注力しがちで、チームの育成が後手に回るケースが多い。今回の研修を踏まえて、改めてチームの育成にも目をむけたいと思った。
shigeru----
プロジェクトのマネジメントは、メンバーの成育度合いの把握に大きく依存しているように実感しています。メンバーがリーダー、フォロアー両方とも適切に担務できるほど、経験やスキルがあるような場合であれば、サーバント型のリーダーシップが適切でしょう。しかし、メンバーの経験が浅く視座が低い、プロジェクト活動の全体観をとらえて自身がとるべき行動を客観的に判断できないような場合は、教示型のリーダーシップで組織運営する方が、組織成果を得られると考えています。
プロジェクト管理は、組織メンバーならびに組織自体の成長度合いに応じて、リーダーシップのスタイル(SL理論では教示型、説得型、参加型、委任型が示されている)を使い分けることが肝要と実感しています。
ta-mo-
プロジェクトを成功させるためには、チームのパフォーマンスが重要となる。パフォーマンスを上げると陸は2つ。マネジメントとリーダーシップである。マネジメントには集権型、分権型があり、リーダーシップには、指示命令型、カリスマ型、サーバント型がある。プロジェクトでは、メンバー、内容、納期等に合わせ、どのパターンで行くか、検討が必要。
yoshiki2355
モチベーションのコントロールも意識していきたい
ibe_takeshi
チームの成長のためにまずはメンバーの成長は必要であり、それが一番難しいと実感している
個性が違うため、各人に対して接し方を変えることがいいのかがわからなくなる
t-isaka1983
チームリーダーをしてもモチベーション管理は普段意識していないので意識しようと思った
gobau
プロジェクトマネージャーには高いヒューマンスキルが求められる。マネジメントにおいてもリーダーシップにおいても時と場合による使い分けを行う必要もあり、バランス感覚が求められる。得手不得手もあるだろうが、考え方や手法を認識しておくことが大事だと理解した。
sugi_asa
プロジェクトを成功させるために、スキルアップを図りたいと思います。
vegitaberu
プロジェクトマネジメントにあたり、自分がどういう成果を出すかということを目的を置くのではなく、メンバーにどういう成果を上げさせられるかを一番に考えるべきだということを再認識しました。
それに気づいて以来、サーバントリーダーシップに関心を持っています。メンバーが、100%以上の力を発揮し、それらを無駄なく、協働させることで、最高のアウトプットが出るということを強く意識したいと思います。
noritsuu
動乱期ではプロジェクトマネージャーが各一人一人の意見を真摯に受け止めて最終的にまとめていくことが重要
taku_asa
メンバーの育成をプロジェクト内で完結できるならよいが、別部署と絡む場合は難しい。プロセスオーナーはそこも加味したうえでプロジェクトを発足させる必要がある
tom-_-
メンバー育成によりチームパフォーマンスの向上につなげていきたい。
daiyuta
チームの成長の4段階については参考になった。いかに動乱期を短くできるか、いかに早く遂行期にしていけるかが、プロジェクトマネージャーとして必要な事だと学びました。メンバーの性格や経験や知識によるところがあるので、焦らずチームパフォーマンスを磨いていきたい。
toshi-iwai
成立期→動乱期→安定期→遂行期の各ポジションでのリーダーシップが違うことが理解できた。復習したいと思います。
hs_1031
リーダーシップには様々な型があり、それをメンバーと共有して、どの型でプロジェクトを進めるか合意形成してプロジェクトスタートするのがよいと理解した。ベンダーとしては、顧客からカリスマ型リーダーシップを要求されることが多いが、顧客含めてキックオフ時に型を共有するのがよいと感じた。
yuji_fujii
現状、動乱期から安定期に向かっている途中と感じる。外発的な取り組みは難しいので…内発的な取り組むで何とか動乱期を短く切り抜けていきたい。
luckyjene
チームメンバーによく話しかけ課題や問題に陥っていないかなど考え行動しているつもりですが、自立的な働きかけも必要と思いとで、そのはざまで悩んでしまうこともありますが、とりあえずはチームの成果を優先に考えフォローしていくことがよいと判断しました
kazuma_yasuda
目的を共有すること、チーム力を高めることをメンバーに働き掛けることで実施していこうと思いました。
nobuhiko7
リーダーシップ活動にも使いどころによって適した方法があり、昨今もてはやされているサーバント型が万能ではないことが分かった。
goma515330
外発的な動機付けと内発的の動機付けにおいて、外発的な動機付けが無い場合に内発的な動機付けだけでモチベーションを維持できるのか?
10512
チームの成長の4段階では、いかに動乱期を短くし、いかに早く遂行期にしていけるかが重要であると理解しました。
suwa_nobuo
自職場ではサーバント型の体制で個々人の自律とチームとして成果を出す行動を目指している。中には前を向けないメンバーもおり、離れた発言で
チームに悪い影響を与えている。
改めて、目的の共有と役割、働き方について一歩踏み出せる環境を話し合っていきたい
ryoca
定義については再確認する機会になりました
potupen
チーム内をよく観察することの大切さを学んだ。モチベーション管理は日頃からのコミュニケーションを通してできるようにしようと思う
akaba2024
マネージメント活動において、能力などが近い人間で構成されている場合、サーバント型は、メンバーの主体性や自律性が高まりチームの全体的に生産性も高くなりそうだと感じた。
kymyhy
良く理解できた
チームの組成
daikidasu
チームの状況を確認しながら、形成などの段階から知って対策したいです
nakashi49
組織力向上には、各メンバの内発的な動機付けによるモチベーション向上が不可欠であることがよく理解できた。
プロジェクトマネージャーのあるべき姿とは、まさに山本五十六の格言「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば人は動かじ。 話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば人は育たず。」の通りなのだと思う。
言うは易し行うは難し、ではあるが、本研修で学んだ内容を活用し、実務に反映させて行きたい。
ponpon__
繰り返し行う、キーワードだったと思います。またチームのxx期によっても適切な行動があるということ。それはわかっても、どれぐらいその期間にいることが適正なんだろう、という疑問もありました。
tonyst
チームビルディングは非常に重要ですが難しく、動乱期をどのように収めるかは各チームメンバーによっても異なります。そんな中で内的なモチベーションと外的なモチベーションがあることを改めて確認できました。特には内的モチベーションを上げる方法を探していきたいと思います
kenji-masuda
プロジェクト・マネジメントにおけるマネジメント活動とリーダーシップ活動の重要性は痛感している。
これまで集権型のマネジメント活動が多かったが、負荷の集中やテーラリングやリスク選好に関してリソース不足によるスケジュール遅れなども発生した。今後は分散型による担当業務毎のマネジメント活動も視野に入れ、体制構築を検討したい。
リーダーシップ活動についても、これまで指示命令型やカリスマ型の活動であったが、サーバント型も取り入れたい。ただし、メンバーの経験が浅いため、経験者のプロジェクト・タスク内容を共有化する等の準備が必要と考えている。
また、チームでの成果を効率よく発揮すべく、動乱期のコンフリクトに早期に対処することに留意したい。
k_yashi515
チームマネジメントに非常に悩んでいるので、大変参考になった。
toshikazu_st
成長の4段階のうち、いかに動乱期を短くするかが重要だと思ったが動乱期をそもそも生じさせないようにすることが最も重要だと感じた。
yfujioka
サーバント型リーダーシップでは意思決定プロセスの迅速化・効率化が重要。
yuki_nagato
マネジメント活動、リーダーシップ活動とともにチームを育成していくことが重要
yu_kawa
チームメンバーへの育成にはいろいろな手法があることを学びましたが、メンバーのモチベーションを内部的に維持するように指導、気づかせるキッカケをあたえる事が重要と感じました。
mipok
チームプロジェクトとして高い成果をあげるためには一人一人の能力の向上も必要だし、何より動機付けも必要で、一人ずつ細かくマネジメントし、総合力に結び付けることが重要。常に考えながら進めていくことが大切だと思う。
tf078
リーダーとしては分散型を志向したいと思いますが、そのために必要な類型的なパターンを意識して、コミュニケーションしていきたいです。
user2698
プロジェクトを進めていくためには、メンバーに目的と役割、それを達成することでどういうメリットがあるかを共有することがモチベーション維持に大切と思いました。
tkawa_0977
自チームはサーヴァント型を使用していますが、枠割、立ち位置が曖昧になっているためサイド振る舞いを検討したいと思います。
kaishingo
業務での活用は日頃の意識を変えることから始めたい。