
無料
【耳で復習】学んでみたけど? ~機長症候群~
この動画は音声のみでお楽しみいただけるコンテンツです。 フレームワークの「機長症候群」。学んでみたけど、実際仕事でどう使うの…? そんなあなたのモヤモヤに共感したグロービススタッフが、自分の経験も踏まえて語ってみました。 音声だけなので、「ながら」復習にぜひご活用ください! 出演:グロービススタッフ 小林 舞良、本山 裕輔
割引情報をチェック!
すべての動画をフルで見よう!
初回登録なら7日間無料! いつでも解約OK
いますぐ無料体験へ
・自身の意見を持っていてもリーダーとうまく議論ができないと思っている方
・自身の経験や能力、自分の意見に自信を持っているリーダー
リーダーが優秀であるからこそ、メンバーは議論や反論をやめてしまうことがあります。その結果、組織にとって好ましくない状態に陥ってしまうことがあります。
本コースでは、メンバーとリーダーがどの様な点に注意する必要があるのかを紹介します。

無料
【耳で復習】学んでみたけど? ~機長症候群~
この動画は音声のみでお楽しみいただけるコンテンツです。 フレームワークの「機長症候群」。学んでみたけど、実際仕事でどう使うの…? そんなあなたのモヤモヤに共感したグロービススタッフが、自分の経験も踏まえて語ってみました。 音声だけなので、「ながら」復習にぜひご活用ください! 出演:グロービススタッフ 小林 舞良、本山 裕輔

会員限定
集団浅慮(グループシンク) ~集団での合意形成の留意点~
集団浅慮(グループシンク)とは、集団の圧力によって、その集団の考えが適切かどうかの判断能力が損なわれることと、その結果、不合理あるいは危険な意思決定が容認されることを指す言葉です。アメリカの社会心理学者アーヴィング・ジャニスによって提唱されました。 「3人寄れば文殊の知恵」と言われるように、集合知により、自分一人では思いつかなかったような結論にたどり着き、そのダイナミズムに興奮した経験がある方も多いでしょう。一方で、集団で議論したがゆえに、不合理な意思決定に陥ることも少なくありません。 本コースでは、集団での合意形成において陥りがちな状況を知り、適切に判断・決定を行うための仕組みや対策を学びます。

会員限定
論理思考で仕事の壁を乗り越える5つのポイント
伝えたいことがうまく相手に伝わらない。仕事がなかなかスムーズに進まない。 仕事をしていると、そんな場面に直面することもあるのではないでしょうか。 そんな方に役に立つのが「論理思考」です。 物事を論理的に考えられるようになると、仕事の効率が格段にアップします。 このコースでは、論理思考のコツを5つに絞って説明していきます。 ビジネスパーソンにとって必須のスキルである「論理思考」をいち早く身につけましょう。 「クリティカル・シンキング」をまだ見ていない方にもお勧めのコースです。

会員限定
ジャムの法則 ~意思決定の背景にある心理を学ぶ~
ジャムの法則(Jam study)とは、選択肢が多すぎると選択に手間暇がかかってしまい、選択肢が少ない場合よりも購買の意思決定が難しくなる法則を指します。購買に至る割合も減少します。1995年にコロンビア大学に所属するシーナ・アイエンガー教授がジャムを使った購買実験から導いたため、「アイエンガーの法則」と呼ばれることもあります。 顧客ニーズが多様になっていく昨今、キャンペーンやプロモーション企画において、商品数は多くしたほうがよいでしょうか。それとも、ある程度絞ったほうがよいのでしょうか。また、交渉では争点が多い場合と、最低限必要なものに絞る場合とでは、どちらがよいでしょうか。 本コースでは、顧客の購買意思決定や交渉時など、人間が選択する際の背景にある心理を学んでいきます。

無料
ブロックチェーンが生み出す未来~國光宏尚×平将明×内藤裕紀×瀧口友里奈
G1サミット2023 第4部分科会T「ブロックチェーンが生み出す未来~」 (2023年3月18日開催/北海道ルスツリゾート) 2021年以降突如として大きな注目を集めたWeb3だが、その本質は15年ほど前に誕生したブロックチェーンの技術だ。固有の価値をブロックチェーン技術で証明するNFTや、分散型自律組織/DAOといったテクノロジーはこれからいかなるサービスを生み出していくのか。ブロックチェーンというテクノロジーによっていかなる世界が拓けるのか、その実態を探る。(肩書きは2023年3月18日登壇当時のもの) 國光 宏尚 株式会社フィナンシェ 代表取締役 CEO 平 将明 衆議院議員 自由民主党広報本部長代理 兼 web3プロジェクトチーム座長・AIの進化と実装に関するプロジェクトチーム座長・衆議院原子力問題調査特別委員会筆頭理事/自由民主党東京都支部連合会政調会長 内藤 裕紀 株式会社ドリコム 代表取締役社長 瀧口 友里奈 株式会社セント・フォース 経済キャスター/東京大学工学部アドバイザリーボード/SBI新生銀行 社外取締役 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年1月公開)

会員限定
マンガで学ぶAI入門⑥メール・ブログ作成
メールやブログの文章作成に時間がかかりすぎて、困っていませんか?ChatGPTやGeminiを活用すれば、効率的かつ丁寧な文章が短時間で完成します。「初手AI」がポイントです!文章作成に苦手意識がある方、AIを業務に取り入れたいすべてのビジネスパーソンにおすすめです。 ▼関連コース GPT-5 働き方を変革するAI活用講座① https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/d8d3f379/ GPT-5 働き方を変革するAI活用講座② https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/c36ffd56/ Gemini AIでブログ記事を書こう https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/125d199b/ Gemini AIでランディングページを作ろう https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/ee916b22/ ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
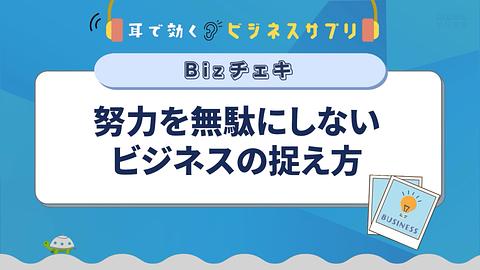
会員限定
努力を無駄にしないビジネスの捉え方/耳で効く!ビジネスサプリ Bizチェキ
1日5分で気軽に耳だけで聴いて学べる「耳で効く!ビジネスサプリ」。 Bizチェキのコーナーでは、好きなものにビジネスの視点で焦点を当ててお伝えします。本コースは日本最大のビジネススクール グロービス経営大学院による、ビジネスパーソンが予測不能な時代であっても活躍のチャンスを掴み続けるヒントをお伝えするVoicyチャンネルからの転載コンテンツです。意識しておくべきビジネススキルやキーワード、今後の時代のキャリアの考え方などを、1日5分で気軽に聴いて学べます。 Voicyチャンネルはこちら https://voicy.jp/channel/880 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月公開)

無料
グローバル展開を目指す経営戦略~アジアに攻め込むプロダクト戦略・GTM戦略・組織戦略とは~鈴木隆宏×十河宏輔×松本恭攝
G1ベンチャー2023 第3部分科会O「グローバル展開を目指す経営戦略~アジアに攻め込むプロダクト戦略・GTM戦略・組戦略とは~」鈴木隆宏×十河宏輔×松本恭攝 (2023年6月11日/グロービス経営大学院 東京校) グローバル市場への進出成功の要諦とは何か。異なる文化、異なる市場環境に対応するためには、高度な経営戦略が求められる。プロダクト戦略、市場進出戦略、組織戦略、それぞれにおけるベストプラクティスとは。アジア市場に焦点を当て、グローバル展開を目指す成功の鍵となる要素を深堀りする。(肩書きは2023年6月11日登壇当時のもの) 鈴木 隆宏 Genesia Ventures,Inc. General Partner 十河 宏輔 AnyMind Group株式会社 代表取締役CEO 松本 恭攝 ジョーシス株式会社 代表取締役社長 ラクスル株式会社 創業者会長 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月公開)

会員限定
ロジックツリー ~物事を把握する「分解」の考え方~
ロジック・ツリーとは、モレなくダブりなく(MECE)を意識して上位概念を下位の概念に分解していく際に用いられる思考ツールです。 問題解決で、本質的な問題がどこにあるのかを絞り込む場面や本質的な課題に対して解決策を考える場面で活用できます。 ※2020年3月30日、動画内のビジュアル、表現を一部リニューアルしました。 理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
MECE ~抜け漏れなく分解・構造化して考える~
MECEとは、ある物事を「モレなくダブりなく」切り分けた状態のことです。例えば年代別など、全ての人がその切り分けのどこかに属するようにします。MECEは論理思考の基本で、物事を分解し、構造化する際に役立つ考え方です。 例えば、状況を調べて問題箇所を特定する必要がある場合に、いくつかのポイントに分解して考えることが重要になります。その際に、モレやダブリなく分解することができれば、分析や問題解決の効率性が高まります。 ロジックツリーやマトリックス、あるいはその他のフレームワークなどにも応用できる基本となるコンセプトであるMECEを理解しましょう。 ※2018年2月15日にコース内容を一部リニューアルいたしました。 リニューアルに伴い、コース動画一覧は全て未視聴の状態となります。 なお、リニューアル前に当コースを修了している方は、コース修了済のステータスに変更は発生いたしません。

会員限定
貸借対照表 ~企業の財務活動と投資活動を読み解く~
財務諸表の要の1つである貸借対照表(B/S)は、ある時点(決算期末時点)での企業の資産内容を表します。継続的な経済活動を行っている企業の一瞬の姿をとらえたスナップ写真ともいえる貸借対照表を理解し、企業の財務活動と投資活動の結果を読み解く力を身につけましょう。 ☆関連情報 フレームワークでニュースを読み解く、日経電子版の記事もぜひご覧ください。 「米SPAC上場ブーム、引き金はコロナ禍の失業対策」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC27E130X20C21A4000000/?n_cid=DSPRM5277

会員限定
リーダーシップとマネジメントの違い ~違いと使い方を理解する~
リーダーシップとマネジメントの違いとは、主にそれぞれ異なる特性と役割にあります。リーダーシップは人と組織を動かし変革を推し進める機能、マネジメントは定められた戦略やルールに基づき効率的に組織を運営する機能とそれぞれ定義されています。このコースでは、リーダーシップとマネジメントの違いについて詳しく学んでいきます。2つの違いと意味を理解し、日頃の業務やコミュニケーションに役立てていきましょう。 ☆関連情報 フレームワークでニュースを読み解く、こちらの記事もぜひご覧ください。 「吉本興業のこれからに必要なのはどっち?リーダーシップ、それともマネジメント?」 https://globis.jp/article/7224 「日本電産の永守氏にみる有事のリーダーシップ」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58614190Y0A420C2X12000/?n_cid=DSPRM5277

会員限定
クリティカル・シンキング(論理思考編)
業種、職種、役職を問わずビジネスパーソンが業務のスピードとクオリティを効率よく高めるために必要不可欠な論理思考力。 論理思考のベースとなる考え方を学び、実務で陥りやすい注意点を理解することで、実践で活用する能力を養います。 論理思考の基本を身につけ、コミュニケーションや業務の進行に役立てましょう。 論理思考を初めて学ぶ方は、以下の関連コースを事前に視聴することをお薦めします。 ・論理思考で仕事の壁を乗り越える5つのポイント ・MECE ・ロジックツリー ・ピラミッド構造 ・演繹的/帰納的思考 ・イシューと枠組み ※2019年10月31日、動画内のビジュアルを一部リニューアルしました。 内容に変更はなく、理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
ロジックツリー ~物事を把握する「分解」の考え方~
ロジック・ツリーとは、モレなくダブりなく(MECE)を意識して上位概念を下位の概念に分解していく際に用いられる思考ツールです。 問題解決で、本質的な問題がどこにあるのかを絞り込む場面や本質的な課題に対して解決策を考える場面で活用できます。 ※2020年3月30日、動画内のビジュアル、表現を一部リニューアルしました。 理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
論理思考で仕事の壁を乗り越える5つのポイント
伝えたいことがうまく相手に伝わらない。仕事がなかなかスムーズに進まない。 仕事をしていると、そんな場面に直面することもあるのではないでしょうか。 そんな方に役に立つのが「論理思考」です。 物事を論理的に考えられるようになると、仕事の効率が格段にアップします。 このコースでは、論理思考のコツを5つに絞って説明していきます。 ビジネスパーソンにとって必須のスキルである「論理思考」をいち早く身につけましょう。 「クリティカル・シンキング」をまだ見ていない方にもお勧めのコースです。

会員限定
MECE ~抜け漏れなく分解・構造化して考える~
MECEとは、ある物事を「モレなくダブりなく」切り分けた状態のことです。例えば年代別など、全ての人がその切り分けのどこかに属するようにします。MECEは論理思考の基本で、物事を分解し、構造化する際に役立つ考え方です。 例えば、状況を調べて問題箇所を特定する必要がある場合に、いくつかのポイントに分解して考えることが重要になります。その際に、モレやダブリなく分解することができれば、分析や問題解決の効率性が高まります。 ロジックツリーやマトリックス、あるいはその他のフレームワークなどにも応用できる基本となるコンセプトであるMECEを理解しましょう。 ※2018年2月15日にコース内容を一部リニューアルいたしました。 リニューアルに伴い、コース動画一覧は全て未視聴の状態となります。 なお、リニューアル前に当コースを修了している方は、コース修了済のステータスに変更は発生いたしません。

会員限定
MECE ~抜け漏れなく分解・構造化して考える~
MECEとは、ある物事を「モレなくダブりなく」切り分けた状態のことです。例えば年代別など、全ての人がその切り分けのどこかに属するようにします。MECEは論理思考の基本で、物事を分解し、構造化する際に役立つ考え方です。 例えば、状況を調べて問題箇所を特定する必要がある場合に、いくつかのポイントに分解して考えることが重要になります。その際に、モレやダブリなく分解することができれば、分析や問題解決の効率性が高まります。 ロジックツリーやマトリックス、あるいはその他のフレームワークなどにも応用できる基本となるコンセプトであるMECEを理解しましょう。 ※2018年2月15日にコース内容を一部リニューアルいたしました。 リニューアルに伴い、コース動画一覧は全て未視聴の状態となります。 なお、リニューアル前に当コースを修了している方は、コース修了済のステータスに変更は発生いたしません。

会員限定
ロジックツリー ~物事を把握する「分解」の考え方~
ロジック・ツリーとは、モレなくダブりなく(MECE)を意識して上位概念を下位の概念に分解していく際に用いられる思考ツールです。 問題解決で、本質的な問題がどこにあるのかを絞り込む場面や本質的な課題に対して解決策を考える場面で活用できます。 ※2020年3月30日、動画内のビジュアル、表現を一部リニューアルしました。 理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
リーダーシップとマネジメントの違い ~違いと使い方を理解する~
リーダーシップとマネジメントの違いとは、主にそれぞれ異なる特性と役割にあります。リーダーシップは人と組織を動かし変革を推し進める機能、マネジメントは定められた戦略やルールに基づき効率的に組織を運営する機能とそれぞれ定義されています。このコースでは、リーダーシップとマネジメントの違いについて詳しく学んでいきます。2つの違いと意味を理解し、日頃の業務やコミュニケーションに役立てていきましょう。 ☆関連情報 フレームワークでニュースを読み解く、こちらの記事もぜひご覧ください。 「吉本興業のこれからに必要なのはどっち?リーダーシップ、それともマネジメント?」 https://globis.jp/article/7224 「日本電産の永守氏にみる有事のリーダーシップ」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58614190Y0A420C2X12000/?n_cid=DSPRM5277

会員限定
因果関係 ~原因と結果の関連を理解する~
因果関係とは、あるものごとが「原因」と「結果」の関係でつながっていることです。「因果関係」という言葉は様々な場面で使われますが、ビジネスにおいても、因果関係の把握は問題解決などの場面でとても重要な思考技術の一つです。 因果関係を把握し、因果関係を明らかにすることのメリットやコツを身につけましょう。
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
100+人の振り返り
matsudatt
メーカー技術・研究・開発
会議を進めるには、少し離れた立場の人を混ぜると、圧力が弱まり、みんなが意見を述べるきっかけを作り易いです。
den_ver1797
マーケティング
この状況は、リーダー以外のメンバーにとっては楽な状況でもあるので、いかに自分事とらえて取り組んでもらえるかも考える必要がある。
chikada
メーカー技術・研究・開発
「リーダーなら常にベターな選択ができている」と思いこまずに話を聞き、意見を言わなければならない。かといって、リーダーの意見の粗探しになってもいけない。あくまで対等の立場で議論をすること。
zon_21sotsu
クリエイティブ
会社でもボランティアや課外活動でもコミュニティの中で活動をしてる人は全てこの事実を認識しておくべきだと感じました。優秀な人にすべてを任せるのではなく、自分も恐れずに自分の意見を積極的に発言してみんなで作っていく姿勢を大事にしたいです。
hiro_yoshioka
メーカー技術・研究・開発
わからないことは、聞こう。
hashimoto_y
専門職
意見が異なるけど言うのやめとこうかなぁと遠慮してしまう・されてしまうことは確かにある。
メンバー全員が意見を言える環境を作ることが大切だし、自身も言うべきことは言う勇気を持つことが大事だと思った。
uhiko
人事・労務・法務
ディスカッションの前に、まずは自分なりの問題意識をしっかりと持って自身の参加意識を高め、リーダーや経験が長いメンバーの意見と異なる場合はしっかりとそれを主張することが重要と感じました。
ban660
メーカー技術・研究・開発
機長症候群は日常業務の中で良く起こることなので、リーダーが行ったことを鵜呑みにせず、メンバーは自分自身でしっかりと検討することが必要。
djmpajmpkm
営業
優秀な人が常に正しい訳では無いということ
takahiro39
メーカー技術・研究・開発
機長症候群とは
優秀なリーダーに反論できず、メンバーが思考停止に落ち至った状態。
対策として、リーダーは自身がメンバーに与える影響を正しく把握し、メンバーは「優秀な人でも間違いを犯すことはある」と理解して議論を恐れないようにすること。
changeupper
販売・サービス・事務
盲目的に従う、は悪。
fujiyoshi1215
販売・サービス・事務
仕事に生かしていきたい
rauna
人事・労務・法務
上に意見する際は、遠慮したり、摩擦が起きないようなコミュニケーションを意識したりするが、事実や論理的に提案を出すフラットさが仕事を適切に進めるには大事だと思った。
20220101
IT・WEB・エンジニア
チーム内で議論する際に、意見や質問が少ないときは機長症候群になっている可能性を疑い、メンバーが発言しやすいような空気作りと傾聴を心がける。
s_s___
メーカー技術・研究・開発
優秀なリーダーではないのに、反論や違う意見はつぶし、形式的な会議で話し合ったことにし、自分は責任をとらないのを、何とかしてほしい。
そっちのほうがよほど問題。
残念ながら機長症候群になりたくても、該当しない。
リーダーが話しやすく意見を聞くし本物の優秀だったり、上記の様な俺様だったり、リーダーに攻撃的に言いたい放題なメンバーばかりでまとまらないことの方が多いかな。
teitosh
人事・労務・法務
これ、自分もやってるなーと、気づきました。
ワタシも間違えるよ、だから何でも言ってね!と話していこう。
kato-hiro
販売・サービス・事務
リーダーが一人で決めるのではなく皆んなの意見を聞いて責任を持つ
mizutashuichi
その他
何が正しいのか?なにが間違っているのか?を考え時には勇気をもって丁寧に議論をしていくことが大切と感じました。
j-munemoto
IT・WEB・エンジニア
力づくで従わせる上司を反面教師にして、自分は部下と目線を合せて円滑な意見交換ができるような組織を目指す
hide-abe
メディカル 関連職
意見を受け入れる、意見の言いやすい環境を整えていきたいです。
mo_
メーカー技術・研究・開発
機長症候群とは初めて聞きましたが、組織にとってあるあるな状況を端的に表した良い表現だと思いました。
kameco
販売・サービス・事務
能力があり、尊敬される機長が欲しいです。
0829koba
マーケティング
リーダーとしての自分の発する言動、行動を今一度見直すところから始まる。
qtkc
メーカー技術・研究・開発
自分が部下の立場ならこれを防ぐ行動は取りやすいが、リーダーの立場ならかなり気をつけないと難しそう
kobu-tama
営業
リーダーは、異なる意見であっても、聞く耳を持つことと、メンバーは、思考を停止せずに、なぜそのような指示を出しているのか?、どうやったら、うまくいくのか?を常に考える必要がある。
その結果、改善点や対案があるようであれば、提案するべきと考える。
saito-yoshitaka
メーカー技術・研究・開発
ピラミッド組織では発生するリスクは高いと考えます。
yoshitake-m
販売・サービス・事務
普段から課内コミュニケーションが必要であり、何でも意見が言い合える、上司に遠慮しない環境が大切
hirakazushi
メーカー技術・研究・開発
メンバーとのコミュニケーションを心掛け、積極的な意見が出るように心がける
mariok
経営・経営企画
意見を出す勇気をもつ。
リーダーは自分の影響力を知る。
他者の意見を否定しない。
test_
メーカー技術・研究・開発
変化が激しく、現場の感覚がより重要なVUCAの時代ではより重要な観点かと思います。
shingo_nishi
営業
優秀なリーダーがいることは素晴らしいが、お互いに盲目にならず、確認しあうことが必要。
kmti
営業
優秀なリーダーでも常に間違いが無いか確認する姿勢が重要ですね。
y-takashima
専門職
社内でも、有りうる事例と思います。
指示された作業だけやっていては、人材も育たず
リーダーの間違いを正すことが出来ません。
haruhiko3
メーカー技術・研究・開発
特に結論ありきではない結論を出すために行っている議論で役に立つと思う
kane21
営業
機長症候群は、どこでも起こりうると思った。しかしこの現象状態を知っているかどうかで意図的に意見を述べたり違う考えもあるのではないかと想像できる思った。
ma2022
営業
・ブレストを取り入れ、全員の意見や考えが出やすい機会や雰囲気をつくりだす
sota0501
営業
自身が上の場合は気をつけ、下の場合は積極的に意見を伝えようと思う。
fuj1mann
IT・WEB・エンジニア
議論の場や意見の発信において、役職に縛られず自らが当事者の意識を持って臨むことが大切な気がします。
k-ta
資材・購買・物流
優秀な人でも間違える可能性があるということを意識したい
mhiropon
メーカー技術・研究・開発
関係性の理解
moritti
販売・サービス・事務
チームとして、業務にあたる必要性を再認した。
takuya_goto
メーカー技術・研究・開発
グループミーティングなどの複数人数での会話の際に周りの人の意見もきちんと聞いてあげるようにする
y98
経理・財務
原理原則に戻り思考する
so_hi
メーカー技術・研究・開発
若手含めた議論の場で、まずは自身のメンバに与える影響や発言の仕方などに心がけてみる
masa4266
販売・サービス・事務
会議、ミーティングで社員からの意見を積極的に聞き出す。
nt369
クリエイティブ
同じ社員同士なので、社内のぶつかりが多少あっても、お客様目線で考えることを忘れないようにしたい。
carateca
販売・サービス・事務
業務の中で、たとえ相手が誰であっても、疑問が生じたら勇気をもって意見を述べる
gyunicerio
マーケティング
機長も間違いはある。自分の知見を磨いていきます。
osk-yamaguchi
その他
リーダーがメンバに与える影響力を正しく把握してもらうことが必要(コミュニケーションする?)
waheianraku
その他
忖度ですね。
yumirin0527
その他
やはり リーダーに分かりやすい可視化やデータの提示が効果的ではないかと思う
nao-s_
メーカー技術・研究・開発
事例では結果が悪かったため気付きを得ていたが、日常ではそうでないことのほうが多く、その成功体験がさらに機長症候群を悪化させていると思われる。どんなに結果が良くても、その過程で思考停止になっていた事実があるならきちんと変えていく取り組みが大切。
satobee
販売・サービス・事務
上司や優秀な同僚に遠慮することなく議論を戦わせる。
gelogelo
メーカー技術・研究・開発
自分なりの学習努力、情報収集の継続。発言に対する批判に真っ向から受け止めてあげられるだけの柔軟性を持っていきたいですね。
takamiyama
経理・財務
間違っていると思ったら、意見すること。
me-rror
経理・財務
後輩がなかなか業務改善について提案をしてくれないので、そもそも現状に異論を唱えるための会議を設けてみるなども考えました。
77na
専門職
より良いチームを作る上で知識として持っておくことは大切なことだと感じた。
momen
営業
疑うこと。意見を出すことをためらわないこと
unagi0141
その他
全体会議では、リーダーに異を唱えづらい可能性が高いため、日々個別にコミュニケーションをとり、部下の意見を汲み取っていきたい。
syamu_hashi
専門職
まさに過去自分に起きていた状況に近い内容だったので、ハッとさせられた。今は脱却していると思っているが、たまに思い返して機長症候群になっていないか自問自答したい。
h_y_70
資材・購買・物流
リーダーは部下が如何に業務がしやすいか
部下がどのような状態にあるかを把握して
色々任せてみてダメな時には
そのダメな理由をアドバイスして
伸ばしていく様にして行ければ良いと感じた
masa_kageyama
販売・サービス・事務
Projectを進めるためだけでなく、若いスタッフの成長のためにも発言を進めて、議論する工夫が必要と感じましたので、さっそく活用したいと思います。
yk_1079
経営・経営企画
部下が思考停止とならないようなコミュニケーションを心掛けたい。
fkmr
IT・WEB・エンジニア
意見を促す、批判を受容する態度を常に見せる。
経歴を持つメンバーに自身の影響力を把握させる。
yimag_1221
営業
客観視!
kazu195
販売・サービス・事務
現在の自分の会社では、あまり活用できない。
反論したところで、部門異動や降格させられるのがオチ。反論しない無能な人間が、愚直に仕事をいしていると評価されたり、派閥みたいなグループにたまたま知り合って気に入られて評価されたりという事が多い会社になってしまった。
なので、自己防衛策として、絶えず数値結果を出して余計な口出しをされても被害を最小限度に抑えるしかない。自分達が守らないと部下に迷惑がかかるので。
shimax
専門職
指示内容よりも意見を充実化させることに注意する
naoyakun
販売・サービス・事務
自分が部下として意見を出すことと、後輩を指導する際に意見を聞くことを意識します。
tomoemasuyama
専門職
部下の意見を全く聞き入れず、こちらが何か議論をしようとしても露骨に嫌な顔をする不誠実な上司のため、おかしいと思っても意見を聞き入れてもらず、プロジェクトが不発したことが何度かある。一人で言えなくてもスタッフ同士の横の繋がりを深く持ち、スタッフみんなで意見をいうような体制にしたい。
takumi0318
営業
自発的に行動してもらうためにやメンバーの成長観点を考えて、楽だから言ってティーチングばかりではなく、コーチングが必要。
yam_
メーカー技術・研究・開発
情報を鵜吞みにせずに、常に何が正しいのか、正しい事はいつも同じではなく、場面において逆転する事も意識しておくと良い。
yaekoo
専門職
通常業務において、メンバーから業務の相談をされた際に、メンバーがどうしたいのかを確認し、機長症候群に陥らせないようにサポートする。
mattari
IT・WEB・エンジニア
自分の意見が他者と異なることを反論ととらえず、議論して理解を深めたいという思いを伝えていく。
ke-ta03
マーケティング
会議の場では必ず疑問点は指摘しあうことを意識することで、機長症候群を防いでいく
kodama77
その他
上司、先輩が説明したことでも盲目的にならずに疑問点等をぶつけてみる。
haraki2018
メーカー技術・研究・開発
プロジェクト運営で各メンバーと議論する際はまず、
・自分たちのチームが前提として受け入れるべきInput
・自分たちのチームでより良いOutputを出すために検討・深化させるべき内容
を明確にする。
その上で自分の意見は根拠を添えて伝え、根拠やロジックの妥当性を各メンバーにもWチェックしてもらうという形で、メンバーの思考停止を防ぎたい。メンバーにも事前に考えさせ、先に発表してもらうのも思考停止防止に有効。
yoshinori358
その他
まさに、今の状態は、機長症候群。
george-y
その他
チーム各自が意思決定フローを常に見直す姿勢をもつ、またその姿勢を基本ルールとして定着させる
takeshitamura
営業
営業
cozy999
建設・土木 関連職
自分の部所でも、議論を大切にして部下の意見を生かしつつ、望む結論にたどり着くようにしていきたい。
shinji_tamate
営業
環境づくりが大切と再認識した。
yumaka
販売・サービス・事務
リーダーの実績を信頼し過ぎるあまり、盲目的に従ってしまうと、リーダーにとってもメンバーにとっても良くない組織になってしまう。フォロワーシップについて学んだ時にも同じようなケースがあった。リーダー側に立つと、メンバーのレベルによってはある程度の導きは必要とされるため、メンバーの自律性を保つ為の線引きが難しいと感じた。いずれにせよコミュニケーションが非常に重要になる。
yuki_nishikawa
営業
不具合対応の判断の際に試行したいと思いました。
selamat
経営・経営企画
思い込みや経験値だけで判断せず部下からも意見がでやすいようこちらから聞いていく。
iwama1138
メーカー技術・研究・開発
ゴール設定は行うが手段提示は極力行わない
tani1205
営業
自身の指示が本当に正しいか、常に確認が必要。
gkw050
営業
うちの課長がとにかくよく仕事ができ、求心力もある人なので、すごいな~と思ってるうちに課題が片付いている。自分で考えることが少なくなった気がするので、気を付けたいと思う
tsuhiko
その他
自分のい意見を言うときはしっかりと事実を確認、調べること
ngsmkzk
その他
責任者として自分がおかれている立場を十分に理解する
haru9000
メーカー技術・研究・開発
かなりよく見かけるし、そのメンバーになった経験もある。前向き、かつ議論は相手を尊重しつつも対等であるという意識を強く持ちたいし、機長症候群の名前を広めたい
t-odajima
営業
意見を言いやすい環境になるよう、部下に弱い部分もさらけ出す。不快に思ったり、言い合いになったりしても、めげずに上司に意見を述べる。
rinsyan
IT・WEB・エンジニア
自分のチームのリーダーに盲目的にならずに、自分の意見を素直に伝える努力をする。
takatada
メーカー技術・研究・開発
一人の有識者の意見を絶対視するのではなく
自由にメンバーの意見をだす環境をつくる
satotaka_com
IT・WEB・エンジニア
傾聴の心で、落ち着いて部下の話を最後まで聞く
oka7712230
営業
今回の内容は、自分自身が、機長にならない事、機長に全て任せない事・自分自身が常に考える事などを学びました。
yasushi1970
販売・サービス・事務
リーダー的社員が意見を出す前に部下の思考力を高めるためのアイデアを出させるミーティングの進行を行うことを心がけたい
k11_t
経理・財務
意見を求められた際は、否定されることを恐れず発言する。
utchi3_3
資材・購買・物流
リーダーに限らず、先輩後輩などの立場により意見の押し付けになっていないか、客観的な視点を意識して議論する必要がある。
yosh_yosh_yosh
メーカー技術・研究・開発
相手の立場も考慮しつつ、議論する姿勢は持ち続けるといった進め方を自分も実践しつつ、若手にも伝承していきたいですね。
mai_marron
販売・サービス・事務
上長の意見についても自分なりの意見を持つよう、調査を行う