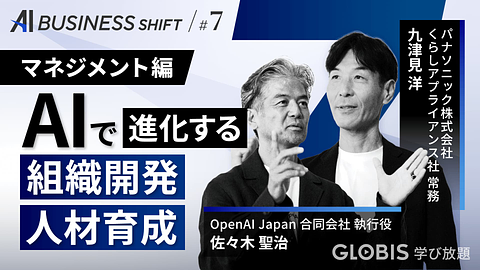
0:53:51
割引情報をチェック!
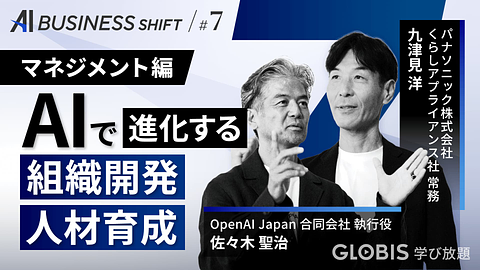
AI BUSINESS SHIFT 第7回 マネジメント編:AIで進化する組織開発・人材育成
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第7回です。 第7回「AIで進化する組織開発・人材育成」では、AIは人や組織にどのような影響を与えるのか、人や組織はAIと共にどのように進化していくべきかについて学びます。 ■こんな方におすすめ ・AI時代の組織開発や人材育成のポイントを学びたい方 ・組織開発や人材育成を担う人事担当者や現場リーダーの方 ・OpenAIやパナソニックHDの取り組みを参考にしたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

マネジャーのための仕事の任せ方
「仕事を任せると失敗が怖い」「自分でやった方が早い」マネージャーとしてメンバーやチームの力を引き出しながら成果を上げるには、どのように仕事を任せていけば良いのでしょうか? 変化の激しい時代において、マネージャーとして成果を上げ続けるためには、メンバーの個性や特性を理解し、それに合わせた効果的な任せ方を身につけることが重要です。このコースでは、ソーシャルスタイル理論を活用してメンバーごとに最適なアプローチを学びます。「任せる力」を高めることで、チーム全体の成長を促進し、自身のリーダーシップを発揮できるようになっていきます。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2024年12月制作)
会員限定

AI時代の個人力
AIが仕事や社会の前提を変え続ける今、最も求められるのは「他者に代替されない個としての力」“個人力”です。 本コースでは、澤円氏の著書『個人力』をもとに、AI時代をしなやかに生き抜くための「前向きな自己中戦略」を学びます。 テーマは、「Being(ありたい自分)」を中心に据え、自ら考え(Think)、変化し(Transform)、協働する(Collaborate)ことで、自分らしい価値を発揮していくこと。 リスキリングやAI活用が叫ばれる今こそ、スキルより先に“自分の軸”を問うことが重要です。 あなたは何を大切にし、どんな未来を描きたいのか? このコースは、あなたが“ありたい自分”として生き、キャリアをデザインしていくための思考と行動のガイドになります。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年11月制作)
会員限定
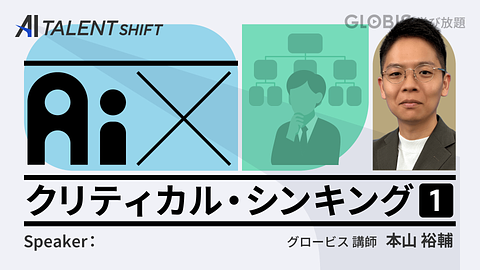
【AI×クリティカル・シンキング】①イシューと枠組みでプロンプトを磨く
生成AIから期待する回答を引き出せず、試行錯誤を重ねていませんか。 本コースでは、生成AI活用の質を高める鍵として、クリティカル・シンキングの視点からイシュー設定と枠組みを押さえる重要性を解説します。 目的に直結する問いの立て方や、プロンプトに落とし込む際の実践ポイントを具体例とともに学ぶことで、AIをより思考のパートナーとして活用できるようになります。 生成AIを業務で使い始めた方から、活用を一段深めたい方まで、再現性あるプロンプト設計を身につけたい方におすすめの内容です。 さらに学びを深めたい方は、こちらも合わせてご覧ください。 【AI×クリティカル・シンキング】②AIの弱点との向き合い方 https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/cdfe41e3/learn/steps/62198 ※本コースは、AI時代のビジネススキルを学ぶ「AIタレントシフト」シリーズの一環として提供しています。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
会員限定

リーダーの挑戦⑤ 藤田晋氏(サイバーエージェント代表取締役)
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第5回目のゲストは、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋氏。起業の理由、経営をどうやって学んだか、アメーバブログ・ABEMAの立ち上げ、経営チームづくりについてなど聞いていきます。(肩書きは2020年12月11日撮影当時のもの) 藤田 晋 サイバーエージェント 代表取締役 堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
会員限定

ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 前編 なぜ眠れないのか?~
「仕事が終わらないから睡眠時間を少し削ろう…」「業務時間中なかなか集中できない…」「毎日朝起きるのがつらい…」。 あなたはこのような経験をしたことはありませんか? 仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削りがちなのが「睡眠」時間。 実は今、日本社会は世界と比較して「最も眠らない国」だということもわかってきています。 慢性的な睡眠不足は、心身の健康に悪影響なだけでなく、仕事のパフォーマンスにも当然大きな影響を与え、社会全体の経済損失につながります。 このコースでは、基本的な睡眠リテラシーを学んだ後の「問題解決編」として、「なぜ多くのビジネスパーソンは眠れないのか?」について解説していきます。 ▼本コースで学べる主な内容 ・そもそも眠れないことは何が問題なのか? ・眠れなくなってしまう原因とは? 睡眠不足の原因は認知機能の問題にありました。 自身の睡眠不足に対し、正しく「気づき・理解し・行動を変える」第一歩を踏み出しましょう。 ▼関連コース ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~リテラシー編~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/24575c03/learn/steps/53129 ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 後編 どうしたら眠れるのか?~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/4ba981e9/learn/steps/62042 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

大阿闍梨 塩沼亮潤が死の手前で見つけた「生き方」
あすか会議2018 第4部分科会B-1「極限の世界で見つけた人生の歩み方」 (2018年7月7日開催/国立京都国際会館) 1300年間で2人目となる大峯千日回峰行満行を果たした塩沼亮潤大阿闍梨。48キロの山道を1日16時間掛けて歩き、それを千日間に亘って続ける過酷な行の中で、どのような悟りを得たのか。そして、9日間、断食・断水・不眠・不臥を続ける四無行満行という極限の世界で何を見つけたのか。塩沼氏が「創造と変革の志士」へ贈る「人生の歩み方」とは。(肩書きは2018年7月7日登壇当時のもの) 塩沼 亮潤 慈眼寺 住職
無料
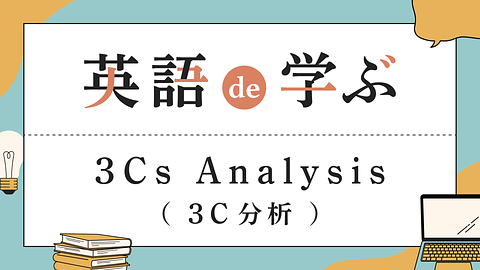
英語 de 学ぶ!3Cs Analysis(3C分析)
このコースでは、グロービス学び放題の英語版である『GLOBIS Unlimited』のコースの中から、ビジネスで役立つ頻出の英語表現をピックアップしています。英語ネイティブの方が実際に見ているコースなので、リアルなビジネス英語の表現を学ぶことができます。 今回のコースは「3Cs Analysis(3C分析)」です。一緒に『英語で』ビジネス知識を学んでいきましょう! ▼今回扱ったUnlimitedコース続きは下記からご覧いただけます 3Cs Analysis https://unlimited.globis.co.jp/en/courses/da5ca962/learn/steps/36362 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
コメント25件
shikay
組織はともかく自分自身の中にも揺らぎを作ることを大切にしている。去年と同じことやっているな とか これ前と同じパターンだな とか 最近マンネリ化してきているな とか そういう自分の感覚を大事にしている。組織に揺らぎが必要なように、自分にも揺らぎは必要だと思う。振り返ってみてみると揺らぎを起点に成長した経験は多い。揺らぎは最初は小さな違和感だった。慣れてくるとこうした違和感は気にしないようにしようと封印に持ち込む気持ちが働く。違和感は日常業務の生産性を下げる。できれば迷いたくないし、矛盾には向き合いたくないし、何かに没頭し、邁進し、今やっていることを信じ続ける事ができたら心穏やかに過ごせると思う。しかし、長い目で見て穏やかな人生は退屈なようにも思ってしまう。自分に揺らぎをあえて持ち込むことは勇気がいることだが、自分は自分のためにたまには揺らぎと接する機会を持ちたい。
morimotoa
揺らぎを意識する。慣れによるブラックボックス化、変化に対応出来なくなる点から。
kubota_k
ゆらぎが必要、ではなく、「適度な」ゆらぎですよね。意図せずともゆらぎは起こっており、その結果どうなったかも大切だと思いました。組織はもちろんのこと、個々人のゆらぎ…問題意識をもつことや何かしらの違和感といった感覚も磨きたい。
yasu-okazaki
目標は毎年変わるし、中期経営計画も外部環境の変化で修正が入る。人の入れ替えも年に数回は発生している。意図せずとも揺らぎは起こっている。
takenokoman3
営業トークは、とくにゆらぎが必要になってくる面があります。毎日ずっと同じトークを話しますから。そこは毎回ゆらぎを意識してやっています。つい成功事例にとらわれやすいですが、マンネリすると熱意が薄れてつたわらないことがあるので、気を付けています。
pontaro-
組織に適度な「刺激」を与えることと捉えます。昨年(今年)うまく行ったからといって、この変化の激しい時代、今年(来年)もうまく行く保証などどこにもないと定義します。現状維持では遅れるばかりなり、という名言もあるように、人や組織の成長を考慮し適度な「ゆらぎ」を持ち込むことは必要でしょう。マンネリ化や思考停止状況は必ずと言っていいほど、何らかの社内問題や対外トラブルを発生させます。
適度な緊張感を持たせること、とも言えるでしょう。注意すべきは「適度な」という内容です。「平凡な」ゆらぎでは活性化しません。「過度な」ゆらぎだと逆効果になります。マネージャーたるものはそこの匙加減(独りよがりの戦略や手法を取らないこと)に留意する必要があります。
akitojo
ゆらぎがストレスに感じていた 大切なことであると知れてよかった
dze07531
揺らぎが大切との考え方は新鮮でした。
okapyonpyon
組織のゆらぎって?どうゆうこと、と思って聞きました。他社への関心もなくなる、剛直な関係の根幹につながる考えだと思いました。
kaz_2021
現在、揺らぎを与える組織変更を行っています。昨年同様が楽ですが、背中を押していただく内容でした。
everest
変化に対応しやすい環境を作りイノベーションやチームの活性化に役立てたい。
kitagawattr
組織に適度なゆらぎが必要なことが勉強になりました。組織の硬直は別に何十年もかかるものではなく、1年であっても生じてくるようなものだと思いました。改善・向上を促すようなゆらぎを意識したいと思います。
akihiro_jinba
ためになるお話でした
takezero1
惰性に流されることなく、確かに適度な刺激は必要であると思います。
tsukamotoya
業務に活かしていくよう努力していきます
ii_y
ゆらぎがストレスに感じていた 大切なことであると知れてよかった
45_shzx
職場は数年に一度組織変更が行われることが多いのですが、実際には誰かが昇格してほかのメンバーは現業のままだったりします。効果が管理職の成長だけにとどまっているのは「ゆらぎの効果」としてはもったいないことなのだと気づきました。
av01211
組織のゆらぎ、初めて聞くことばでした。
t_sugasawa
職場環境への変化に活かしていきたい。
suenaga0013
生産性・競争優位性の維持向上につながることとして、安定を意図的にシステマチックに崩すことも必要
saori_0605
慣れた同じ仕事ばかりしていると視野が狭くなりがちなため、ジョブローテーションを企業文化に根差した上で実施するのであれば効果的かと思いました。まずは、そういった企業文化の構築がないとハレーションにつながるため、基礎固めが必要だか、ゆらぎの必要性については共感できました
3370
公私に関わらず多少のゆらぎ=変化は必要だと思った。当然役割や人は状況によって変わるべきなので活発的なローテーションを検討していきたい。
idetoto
場合によってはスペシャリストが必要な時もあると思います。
okuda06
専門知識、技能をもっていても生かせないのであれば必要ないと思います。会社に貢献できるのに無理強いは本当によくなるのか。
1-100
与えられたリソースを効率的に使って今の成果を出すことに集中しがち(かつそれが評価指標になっている)だが、揺らぎを意図的に仕掛けて人材開発と組織開発をはかっていかないと、成長の持続はないと思う。今所属する組織に決定的に欠けているもの。