
0:59:48
割引情報をチェック!

AI BUSINESS SHIFT 第8回 機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第8回です。 第8回「機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル」では、AIが営業現場にどのような変化をもたらしているのか、営業担当者・営業マネージャー・組織としての役割や戦略が、AIによってどう進化していくのかを、営業プロセスの分解や実際の現場事例を通じて学びます。 ■こんな方におすすめ ・AIを活用した営業活動の最新動向や現場のリアルを知りたい方 ・営業現場の変化に直面している営業マネージャー・現場リーダーの方 ・AI時代における営業戦略や営業マネジメントのあり方を学びたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年2月制作)
会員限定

マネジャーのための仕事の任せ方
「仕事を任せると失敗が怖い」「自分でやった方が早い」マネージャーとしてメンバーやチームの力を引き出しながら成果を上げるには、どのように仕事を任せていけば良いのでしょうか? 変化の激しい時代において、マネージャーとして成果を上げ続けるためには、メンバーの個性や特性を理解し、それに合わせた効果的な任せ方を身につけることが重要です。このコースでは、ソーシャルスタイル理論を活用してメンバーごとに最適なアプローチを学びます。「任せる力」を高めることで、チーム全体の成長を促進し、自身のリーダーシップを発揮できるようになっていきます。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2024年12月制作)
会員限定

AI時代の個人力
AIが仕事や社会の前提を変え続ける今、最も求められるのは「他者に代替されない個としての力」“個人力”です。 本コースでは、澤円氏の著書『個人力』をもとに、AI時代をしなやかに生き抜くための「前向きな自己中戦略」を学びます。 テーマは、「Being(ありたい自分)」を中心に据え、自ら考え(Think)、変化し(Transform)、協働する(Collaborate)ことで、自分らしい価値を発揮していくこと。 リスキリングやAI活用が叫ばれる今こそ、スキルより先に“自分の軸”を問うことが重要です。 あなたは何を大切にし、どんな未来を描きたいのか? このコースは、あなたが“ありたい自分”として生き、キャリアをデザインしていくための思考と行動のガイドになります。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年11月制作)
会員限定
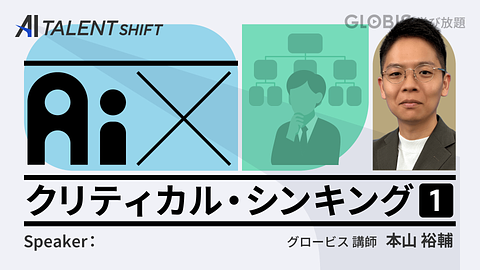
【AI×クリティカル・シンキング】①イシューと枠組みでプロンプトを磨く
生成AIから期待する回答を引き出せず、試行錯誤を重ねていませんか。 本コースでは、生成AI活用の質を高める鍵として、クリティカル・シンキングの視点からイシュー設定と枠組みを押さえる重要性を解説します。 目的に直結する問いの立て方や、プロンプトに落とし込む際の実践ポイントを具体例とともに学ぶことで、AIをより思考のパートナーとして活用できるようになります。 生成AIを業務で使い始めた方から、活用を一段深めたい方まで、再現性あるプロンプト設計を身につけたい方におすすめの内容です。 さらに学びを深めたい方は、こちらも合わせてご覧ください。 【AI×クリティカル・シンキング】②AIの弱点との向き合い方 https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/cdfe41e3/learn/steps/62198 ※本コースは、AI時代のビジネススキルを学ぶ「AIタレントシフト」シリーズの一環として提供しています。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
会員限定

リーダーの挑戦⑤ 藤田晋氏(サイバーエージェント代表取締役)
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第5回目のゲストは、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋氏。起業の理由、経営をどうやって学んだか、アメーバブログ・ABEMAの立ち上げ、経営チームづくりについてなど聞いていきます。(肩書きは2020年12月11日撮影当時のもの) 藤田 晋 サイバーエージェント 代表取締役 堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
会員限定

ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 前編 なぜ眠れないのか?~
「仕事が終わらないから睡眠時間を少し削ろう…」「業務時間中なかなか集中できない…」「毎日朝起きるのがつらい…」。 あなたはこのような経験をしたことはありませんか? 仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削りがちなのが「睡眠」時間。 実は今、日本社会は世界と比較して「最も眠らない国」だということもわかってきています。 慢性的な睡眠不足は、心身の健康に悪影響なだけでなく、仕事のパフォーマンスにも当然大きな影響を与え、社会全体の経済損失につながります。 このコースでは、基本的な睡眠リテラシーを学んだ後の「問題解決編」として、「なぜ多くのビジネスパーソンは眠れないのか?」について解説していきます。 ▼本コースで学べる主な内容 ・そもそも眠れないことは何が問題なのか? ・眠れなくなってしまう原因とは? 睡眠不足の原因は認知機能の問題にありました。 自身の睡眠不足に対し、正しく「気づき・理解し・行動を変える」第一歩を踏み出しましょう。 ▼関連コース ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~リテラシー編~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/24575c03/learn/steps/53129 ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 後編 どうしたら眠れるのか?~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/4ba981e9/learn/steps/62042 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

大阿闍梨 塩沼亮潤が死の手前で見つけた「生き方」
あすか会議2018 第4部分科会B-1「極限の世界で見つけた人生の歩み方」 (2018年7月7日開催/国立京都国際会館) 1300年間で2人目となる大峯千日回峰行満行を果たした塩沼亮潤大阿闍梨。48キロの山道を1日16時間掛けて歩き、それを千日間に亘って続ける過酷な行の中で、どのような悟りを得たのか。そして、9日間、断食・断水・不眠・不臥を続ける四無行満行という極限の世界で何を見つけたのか。塩沼氏が「創造と変革の志士」へ贈る「人生の歩み方」とは。(肩書きは2018年7月7日登壇当時のもの) 塩沼 亮潤 慈眼寺 住職
無料
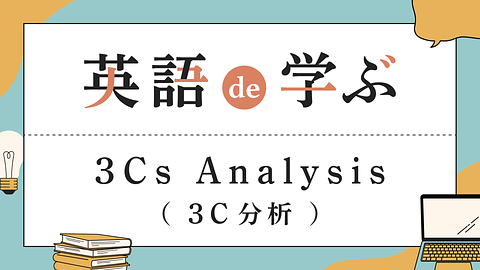
英語 de 学ぶ!3Cs Analysis(3C分析)
このコースでは、グロービス学び放題の英語版である『GLOBIS Unlimited』のコースの中から、ビジネスで役立つ頻出の英語表現をピックアップしています。英語ネイティブの方が実際に見ているコースなので、リアルなビジネス英語の表現を学ぶことができます。 今回のコースは「3Cs Analysis(3C分析)」です。一緒に『英語で』ビジネス知識を学んでいきましょう! ▼今回扱ったUnlimitedコース続きは下記からご覧いただけます 3Cs Analysis https://unlimited.globis.co.jp/en/courses/da5ca962/learn/steps/36362 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
コメント3301件
llasu_ito_0502
C評価というのは、評価面接の際、とても厳しい評価と思います。もし自分なら、一生懸命に働いて、そんな評価ならば、「部署を変えて欲しい」、と言います。
最後の理想的な面接の例は、現実(リアル)には、程遠い様に思います。あんなには、上手く行きません。何か、違う様な、、、
ウチの会社は、いつも上司(面接官)が訳の分からない説明をして来ます。噛み合いません。修羅場です。纏まりません。このコースは、上司(偉い方)が見て、学んで欲しい、と思います。
mille_
ノーサプライズ、たしかに。過去に被評価者として「?!」ってなったことが何度もある。
日々のコミュニケーションなどのプロセスを通じて、納得性のあるフィードバックを行いたい。
sphsph
相手が腹落ちするかどうか?
そのために何をするか、日頃から。
saito-yoshitaka
面談の前から 良好な関係性を構築しておく事が重要だと理解しました。
soga_tomo
部下との面談において、ノーサプライズを意識して、事前に会話を予習しておく。
timpapa
メンバーの成長の為と思い、こうあるべきと言うバイアスが働き、任せたと言っておきながら、指示を出している自分にきがつきました。
フィードバックのコツを素直に実践してみようと思います。
maimaimail
部下との関係性を深めることで色々と成り立つのだなと感じた。
一方的に伝えるではなく部下から言葉を引き出すにしても、関係性が希薄だと本音を話してくれないと思う。
tarako12
ティーチング的アプローチとコーチング的アプローチ。重要なことは、事実に基づき説明し相手に納得してもらうことが重要で、メンバーとの良い関係性を築きながら目標達成のために努力していきたいと思います。
yuitoaina
フィードバックは難しいと思っていたので参考になりました。
toyonaka95
フィードバックは受ける側ですが、受け止め方についても勉強になります。
tako923
フィードバックについて突き詰めて考えていくと、目標設定面談の段階が最重要であり、日々の継続的な1on1等による情報収集が大切であると理解しました。
sk_20211018
使えない成功体験を語る 論理的な説明のないまま業務指示をする 部下より優位に立とうとする
これらはやらない様に真摯な言動をしたい。
miromiya
F Bを行う目的は部下の成長を促すために行うということをしっかりと念頭において接していくことが重要だと思いました。
その為にまずは目標設定をしっかりと行う、私は数字だけでなく、その数字を達成する為にはどのようなことが必要で成し遂げたらどのような姿に成長できているかを目標設定の際に握りたいと思いました。
また、目標達成の為に必要な小さな目標設定もいくつか設定し、定期的に達成できているか確認していく、そのような関わり方ができていれば、期末のF Bの際にサプライズは起きないのではないかと思いました。
F Bの際は自身で気づきや学びを話してもらう、そして、リスペクトしながら一緒に学んだ気づきを踏まえて来期の目標を考えていくことが重要だと感じました。
上記の点を意識しながら業務に励んでいきます。
kfujimu_0630
メンバーへのフィードバックは非常に重要だと実感しています。よくない評価を付けざるを得ない場合も、成長を促せるように、前向きにフィードバックしてあげたいですね。個人的には、ティーチングが苦手なので、意識してフィードバックするようにします。ありがとうございました。
nozom-t
非常にためになった。理解しやすく的確に論点がまとまっており、素晴らしい講座であった。
t-notchy
サプライズをなくすために、期初から期末に向けてのプロセスが大事。評価面談では、TeachingとCoachingを明確に分けて行うべし。
moto5686
ノーサプライズは、参考にします。前むきな話しをするには、重要と感じました。
spro
期中のフィードバックを増やすようにする。1no1をはじめるための傾聴訓練など準備をする
部下に考え言語化させるようにコーチングのところを身につける
shusuke-yamada
他者を驚かすことに脅すことや、押し付けやはねつけることをしないことが大事といえます。
評価については、納得できるまたは正当性があれば、まとまりますが、対立してしまうと、キャリアアップ制度を使ってでも、部署を変えることや転職することを考えます。
本当に、退職のきっかけになったら話になりませんので、言い方やフィードバックの方法は大事であるといえます。
occha
メンバーの目標設定、モチベーション維持について勉強になりました
tw-143
評価で、今まで強制的に決められて合意した数字で設けられていたが、チームやどういうふうにやっていくか協力していくか考えて行かないと駄目と思いました。
yoshimj9
フィードバックの仕方について、具体的でわかりやすかったです。早速、実践していきたいと思います。
dotn
評価面談は非常にセンシティブです。
普段からの良好な関係は必要ですが、友達のようにふるまうと差が産まれてしまう可能性がある等変なバイアスがかかる可能性があります。距離感も大事だと思いました。
masnaka0
12月の賞与前に部下へのフィードバックの機会があるので、事前に準備して臨みたい
toshiemon
日頃のコミュニケーションを円滑にしておくことが一番重要と思います。自己評価が自分に厳しい人、自分に甘い人と性格はそれぞれですが一番厄介なのは被害者意識が強く、自己顕示欲の強い性格の人です。異動させないと職場が崩壊するかハラスメント問題児となります。
seiji-nakamura
日々の情報収集を習慣化して、毎朝の声掛け、コーチング的アプローチが出来るよう、信頼関係を高め、フィードバックを行いたいです。
tappy_
部下からの相談の時に「傾聴」を意識し、自身の過去の成功体験や、結果への焦りに惑わされない様、部下の価値観を受け入れ自己決定させられるコーチングを行っていく。
waruton-208
普段の自分の職場に置き換えて考えてますと傾聴が出来ていないことに気づきました。自身のプロジェクトリーダーとしての立場に余裕がないことも要因だと思います。後輩とはひとりひとりしっかり向き合いたいと思います。
mxlily
今後、評価をつける立場になるため視聴しましたが、とても勉強になりました。特に、自身も平均より低い評価を付けられた場合、フィードバックに納得がいかなかったことがあるため、そういった場合の伝え方を知ることができたのが良かったです。
show0914
ダメ出ししてから、可哀想だから無理矢理に良いところを述べてました。
まさに悪い事例です。
今回学んだことを実践するようにします。
ozawa_h
フィードバックするする側としてもそれなりの知識が必要なことを理解しました。ただ自分の思いでフィードバックをしていると部下が転職するようになるように思えました。
to-ymj
メンバーへの適切なフィードバックが組織としてのパフォーマンスに欠かせないものと改めて感じた。また、その前に組織としてのPDCAを適切に回すことが大前提であり、各人が自律的に動けるような組織としていきたい。
mariko2443
フィードバックを有益なものにするには、伝え方だけでなく、日頃からの関係性も重要だと感じた
ta_hiraoka
フィードバックする上でお互いに納得できる形で話し合うことの大切さを感じた
mctn-11_19
日頃のコミュニケーションが最も大切
mura49ers
何事も準備が大切。行き当たりばったりでは良いフィードバックができないことがよく分かりました。準備をしっかり行い「ノーサプライス」なフィードバックを目指します。
nagai_globis
FBの準備項目として明確な内容でしたので、早速明日のFBで実践します。
tada05
1on1 を相互が有効な場に変えること
a_kakigi
直属の部下はまだいないが、一緒に働くメンバーのサポートやモチベーション維持の点で活かしていきたい。担当業務の設定、自発的な貢献の推奨など。
kyo1-nishikawa
評価のフィードバックの前にじっくり
話す内容を吟味し、出来るだけ納得感
を与えられるように、注意・工夫をして
いく。
onishi_kengo
今まではフィードバックの準備が十分でなかったと感じました。今後はしっかり準備して臨みたいと思います。
kai-rie
3つのLが参考になりました。
h-watanabebu
腹落ち感が無いと相手は動かない、意識していきたいと思います。
yu_ui
数日後にフィードバック面談を控えており、準備段階でした。上司側から見た相手の改善点を、傷つけないようにどう伝えるかということに囚われていました。
事実としての改善点を明確に伝え、本人が考えどう改善するべきかを言葉で表せるよう、ファシリテートするような感覚で挑みたいと思います。
a-yashiro
ノーサプライズ。普段からフィードバックを行いたい
horiuchi1985
後輩にフィードバックする際、事実を、itseemsで柔らかく伝える。相手の考えも聞き出すよう意識する
kimutaka3
私自身はフィードバックを受ける側ですが、上司の考えや気持ちがわかって参考になりました。
xpk
フィードバックは評価面談その場の技術だけでなく期初目標設定と期中フィードバックも含めたメンバーもモチベーション向上と成長を促すプロセスである。
yumiyumi_i
評価の場面においてティーチングとコーチングを使い分けてアプローチする
kaorin55
評価面談をする際の事前準備の必要性を理解できた
また1on1の重要性も理解できた
hirahira117
フィードバックの本質を理解しました。
yusei0206
日々のコミュニケーションと事実に基づいたフィードバッグが重要だということが分かりました。やはり信頼関係なしでこれは無理だと思います。
mid-54
フィードバックの際には、Specificにというのが一つのカギと感じた。
それがNo Surpriseにもつながり、納得感にもつながると思う。まずはこれをしっかりと意識するようにしたい。
fanatic
評価方法の軸を統一するためにも、評価者及び被評価者に、この内容を情報共有するところから始めたいと思った。
norigoma
私は事前に部下の実績データを整理し、評価項目ごとに具体例を添えて面談に臨みます。面談では、まず「この期間で特に成果があった点」を数値と事例でフィードバックし、次に「目標との差があった部分」について原因を一緒に分析したいと思います。その上で、次期の成果評価基準を示し、「この目標はこういう理由で設定している」「ここを改善すれば達成に近づく」という背景を丁寧に説明し、最後に、部下一人ひとりの担当業務に落とし込み、「どの行動をいつまでに実施するか」を具体的に合意し、面談後すぐに動ける状態にさせたいです。こうすることで、評価が単なる結果報告ではなく、次期の行動計画につながる場になるよう意識していきたいです。
aksan
評価の透明性と納得性を高めていくために必要なのプロセツだと思います。
日頃から信頼関係を築くためには評価者が評価対象者に寄り添って行く必要があるようです。
評価内容で納得したことがありまないので評価者の学習をしていく必要性を感じました。
test_
改めて、フィードバックの難しさを考えさせられた。
・相対評価がゆえに、相手だけできまるべきものではなく、他者のはたらきによって、評価が変わらざるを得ないこと。
・評価ということを一年中意識できていないので、時として自分自身の発言との矛盾がでてきてしまうこと。
・すべての部下と信頼性を築くというのは非常に難しいこと。
ぱっと思いつくものでもこれだけ。
それでも誠実に相手の人生を左右することなので一所懸命に評価はするのですが、、、。
kumon65138
自分自身が評価される側の時は評価をあまり意識していなかったので、メンバーの評価についてもあまり深く考えない時期がありましたが、説明の中にもあったように、昨今の風潮として評価に拘るメンバーが増えてきているように感じます。客観性と合意が大切であると感じます。そのためには目標設定の段階から共感ができていること、適度な期待感を持った目標設定などがキーワードになってくると思います。
あとはプロセスをしっかりと掴んでいることも重要な要素と考えます。
user1683
ノーサプライズ的発言が無い様に注意しフィードバック、面談を行う重要性を感じました。
また、目標設定を選んだその人の考え、取り組み方なども本人の口から聞いて進捗の確認を行っていきたいと感じました。
osk-tyamamot
フィードバック及び目標設定の際に、面談を順序だてて進め、当人が納得し、モチベーションアップに繋がるように活用できると思います。
te_yamagu
厳しい評価を伝えなければならない時の自身の臨み方、相手が腑に落ちる説明を心掛けるよう注意します。
tomita_hideo
一方通行ではなく部下に考えさせるようにする必要がる
kunihayashi
成長が期待できる若手社員へのフィードバックにおいては有効と思うが、年長者で成長する気のない社員に対して有効なフィードバックには効果があるかどうか疑問。残り3年程度の年長社員の成長を期待してよいものかどうかわからない。
kazuyoko
1on1の効果的な活用に活かしたい。PDCAを定めたらいかに達成するかに重きを置いており、柔軟なヒアリングが欠けていたと反省しています。
kosakakosaka
コミュニケーションを増やしていきたいと思います。
3194
普段からの関係性の構築はもとより、傾聴と共感、自覚を促しながらの指導や相互のリスペクトが大切だと再認識しました。
017017
指導するときはシンプルに伝え,相手に決めさせることを促せるような指導を意識していきたい
y_ohnuki
今まで目標設定は、予算の達成や単純に人事考課のためのものであると考えていましたが、今回の受講により、今後の発展やより良い環境を目指すために、とても重要であり、それを自ら見直し、外部と共有することで、更なる飛躍へ繋げられると理解出来ました。
marky16
部下の成長を促すためにどういった指摘・評価が良いかよく考えるようにします。
nagaoki
多忙を理由にしてはいけませんが、期中の1on1が実施できていない時は毎日の各人との小対話を意識して実践しています。
普段からの会話で情報交換をしながら信頼関係を築き、引き続きノーサプライズな考課面談を実施できるよう心がけます。
cokita
普段から1 on 1 で進捗状況の確認や部下が困っていることを共有しておけば、最終的な人事評価でサプライズが発生することもないと理解しました。一方的な評価ではなく、具体的な行動や結果をもとに、あの時どうすればよかったか共に振り返りができると納得感も上がると思います。
iimumuoni
評価フィードバックを上手に活用することが重要であると、繰り返し伝えられてきましたが、十分なパフォーマンスマネジメントが行えなければ、相手の成長にもつながらないことがわかりましたし、説明責任というマネジャー本来の活動にならないと理解しました。そのためメンバーの学習経験を十分に引き出し、柔軟に思考し受容と共感をもって活動したいと考えております。また常に相手への尊敬の念を忘れないよう取り組みます。
ozaki_taro
部下の働きに感謝すること、部下の成長を信頼するためには管理職は人間的な成長が必要であり、日本の歴史の中で卓越したリーダーとして名を遺した上杉鷹山、二宮尊徳、西郷隆盛なだが持っていた徳目に近いものだと感じた。
リーダー自身が他責の段階であるとミスを弱い立場の部下に背負わせるようなことしかできない。
まずは、リーダー自身が責任を負うこと、失敗の原因は自身にあり、その原因とリカバリーを考えておく必要がある。
非常に負荷が大きい仕事であるため、日々の部下の働きの観察でルーティン化、システム化を可能な限り行っておく。
一番大切なことはリーダーの人間的な成長であるため、まずは、南洲翁遺訓を読み直します。
miyaketa
FB面談に入る前の準備が大切であること、あらためて認識しました。低評価を伝えた際の反応には個人差があります。図らずもサプライズになってしまった時の説明のロジックも大切だと思います。そんな学びが映像にありました。
bata-masa0205
活用するには最低限の人間関係が必要。会話が重要と考えます
yamabe_masahiro
業務で活用するためには、部下との信頼関係を醸成することが大事だと考えます。
masaki_vivi
サプライズなしの相手の納得感が大事と感じた
takamotoosamu
普段からコミュニケーションを頻繁に取ることでフィードバック時にも大きな考えの違いが起こらず相手の考えや行動が理解でき良いフィードバックが出来る。良い傾聴と相手の思いを思いをリスペクトする。
kitao1234
進捗が確認できなければ自分でやるしかないと思ってしまう。
tsaeki2390
部下との信頼関係、コミュニケーションの重要性、定期的なONE ON ONEミーティングの実施など再認識しました。
dondoko2320
これまで何人かの部下に対してフィードバックを行ってきたが、今回学んだようなことを意識していなかったことを自覚した。
user3103
評価面談の前に 日常よくコミニュケーションを取って、方向性が良いかの共通認識を持ってないと、いきなりフィードバック面談で話をしてもうまくいかないと思います。
dkozuma
フィードバックでは何を伝えるか、どう伝えるかをシミュレーションする必要があると感じた。一方的に悪い部分を伝えるのではなく、自分から振りかえられるようように話すこと、そして相手の話を傾聴することが、良いフィードバック、関係性に繋がると理解した。
yasuhiko_ueno
メンバーの評価は特に難しくセンシティブなので、このような形で学習できる教材がある事がありがたい。
メンバーへのフィードバックについて、具体的に気をつけるべきノウハウが記載されていたので、テキストで座右に置きたいと思った。おすすめの書籍等があれば教えてほしい。
shimaba
フィードバックはすり合わせた目標設定に対して自分の評価だけでなく、他人がどう評価しているかを考えるという観点で非常に重要と考えます。
nobuyukikaneko
部下の成長の為、君に任せたと言いながら本人に解らない様に自分で実施していた事に反省しています。
nakamurahideki
傾聴は受容と共感、話をする時は相手へのリスペクトを忘れないようにします。
hirachi123
部下のモチベーションを下げることなく、やる気を出させるためには、常に会話を心がけたいと思います。
kongkong
評価結果のフィードバックは、ノーサプライズになるようにする。
khara1902
目標設定に当たっては、部門の句表に照らしながらも、本人の意思を尊重する必要が有る。
期中での状況変化なども気を付けて見ておく必要が有る。そのためにも面談などしっかり行う。
フィードバックにおいては結果をしっかり伝えるとともに、今後にどうつなげるかを本人に考えてもらうようにもっていく。
t-etou
フィードバックの仕方について、具体的でわかりやすかったです。早速、実践していきたいと思います。
masashi-koba
簡単に相手に伝わるように話すことが重要と思いました。
日々のコミュニケーションを図り、相手が納得できるようにハッキリと明確に伝えてあげたい。
yuuki_toyota
フィードバックでは傾聴と納得感が大切だと思いました。事前に説明ポイントを準備することも心がけようと思います。
skamiura
係員の評価はこんなことを言ったらどのような気持ちになるだろうかと考え今まで良いことばかり伝えていたと思います。
今後は事実をはっきりと伝えノーサプライズでお互いに成長するようにいたします。
kotoyoda
フィードバックにおいて伝え方によってポジティブにもネガティブにもなるということが理解できた。ポジティブに持っていうためには普段からのコミュニケーション、進捗状況の把握も非常に重要であると感じた。任せきりにせず、一緒に取り組んでいる状態を生み出せるよう意識していきたい。
user1789
現状のFBシステムで実行してます。
nokuroki
フィードバックの時に結果で悪い面を伝えるだけでなく、どうしてそうなったのか、その経緯等をはっきり伝えて部下のモチベーションを下げないよう、次から頑張れる中身にしてあげたい
yjsgt9715
普段のフィードバックで気を付けている点ではあるものの、改めて自分のやり方が正しいか、どうすればより良くなるかを振り返る良い機会になった。
mshdtks
部下との接し方に参考になりました。
niwasa
目標設定は、押しつけではなく、メンバーの話を傾聴し納得してもらったものとする。その上で結果についてフィードバックをおこないたいと思います。