『シン読解力』 というタイトルを目にしたとき、「国語の読解問題の点数アップを目指す学生や国語教育の在り方などの教育関係者向けの本」と思う方も多いだろう。
ところが実際に読んでみると、入試突破から社会人になってからの資格試験や、時系列グラフの読み取り能力までが広範囲に扱われた一冊だとわかるはずだ。そのため、学生や教育関係者にとどまらず、ビジネスパーソンにもお勧めしたい本である。
人生で長く役立つ「シン読解力」
本書で説明されている「シン読解力」とは、「知識や情報を伝達する目的で書かれた自己完結的な文章」(つまり文学的作品ではなく、教科書や辞書や事典、新聞記事などの記述)を読み解く力を指している。この力は、15歳くらいまでは子どもの成長に伴って自然に伸び、その後はあまり変化せずに頭打ちとなることが多いそうだ。
ただこの力は、ある一定水準以上でないと有名私立大学には合格しにくいというデータがあり、入試の合否の一部にも関わっている。また、免許や資格試験等の合格率にも関わっているという。このシン読解力は、卒業後も長い尾を引く(?)全く侮れないスキルであることが判明したというわけである。
「シン読解力」はビジネスに応用できるか
シン読解力は、もちろんビジネスにおいても活用可能だ。本書ではシン読解力を会社内で計測し、年代別で考察した事例も紹介されている。例えば、年齢が高くなるにしたがってスキルが高い傾向にある会社は、実は若手人材採用があまりうまくいっていない可能性があることが考察されている。逆に年齢が高くなるほどスキルが下がっていっている会社は、もしかすると組織内に「俺の読めるような文章を出せ」的な昭和の雰囲気が生き残っている可能性がある。つまりこのシン読解力は、会社の人事採用戦略や形成される組織文化にも影をおとしていると仮説を立てられるのだ。
組織文化を変革してゆくことは難易度の高い経営課題といわれているが、リーダーシップに関する要因以外を用いて考察された例はあまり多くない。多くの会社が抱えているであろう人事政策上の悩みは、実は年代や組織階層間における「シン読解力の偏り」が隠れた要因の1つとなっていることが考えられる。その場合、処方箋は構成員のスキルアップ(リカレント教育)である可能性も考慮したい。
AIに仕事を実行させるために必要なスキル
昨今発展が著しい生成AIを仕事に活用できるかどうかは、個人の素質によることが多いことも、このシン読解力によって説明できるかもしれない。業務の上でAIを活用するのであれば、実行したい仕事を対話形式であっても言葉で定義しながらAIに渡さないと、望ましいアウトプットは得られない。つまり、AIに仕事を実行させるための基礎は、シン読解力に懸かっているということになりそうだ。
逆説的かもしれないが、AI時代におけるビジネスでは、教科書的な文章を正しく読み解くスキルを身に着けるトレーニングの重要性が以前よりも高まっているのかもしれない。
『シン読解力 学力と人生を決めるもうひとつの読み方』
著:新井 紀子 発行日:2025/2/11 価格:1,980円 発行元:東洋経済新報社
















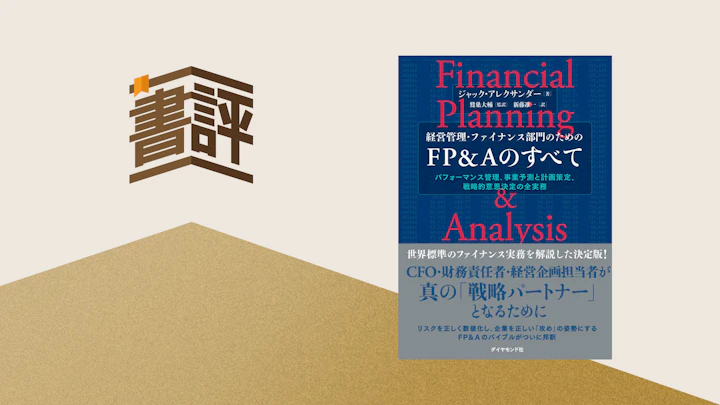


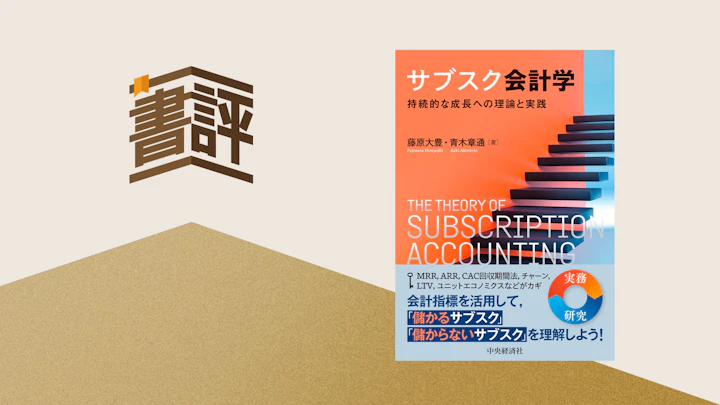












.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


