2020年8月発売の『KPI大全–重要経営指標100の読み方&使い方』から「094 実効税率」を紹介します。
税負担は社会市民である企業の責任とも言えますが、一方で、企業の所有者である株主から見れば、キャッシュの流出=企業価値を損ねるものという見方もできます。つまりステークホルダーによって、その意味が変わってくるということです。東洋経済オンライン2020/02/03の「『税金を多く納めている』TOP100社ランキング」(2018年11月期〜19年10月決算内)によれば、多額の税金を納めている日本企業は概ね30%程度の税負担率(法人税等÷税引前利益)となっていますが、ソフトバンクグループの14.0%や、5大商社の21.1%(単純平均)といった数字も目立ちます。これは投資会社である、あるいはその性格が強いゆえとも言えますが、ソフトバンクグループなどは、かねてから節税を積極的に行っていることが指摘されています。アメリカの巨大IT企業のようにとは言わないまでも、株主がグローバル化するなかで(その一方で、ますます企業の社会貢献が求められる中で)、どういうスタンスで節税をするのかは、これからの企業にとって決して小さな問題ではないのです。
(このシリーズは、グロービス経営大学院で教科書や副読本として使われている書籍から、東洋経済新報社のご厚意により、厳選した項目を抜粋・転載するワンポイント学びコーナーです)
実効税率
最終的に支払った法人税、住民税、事業税が純利益に占める率
KPIの設定例
うちは過度な節税はしないが、アジア展開については税率の低いシンガポールに法人を設立することで、トータルの実効税率20%程度をめどとしよう
数値の取り方/計算式
(法人税+住民税+事業税)÷純利益
主な対象者
経営者、財務責任者
概要
実効税率はファイナンス系のKPIを求めるときにも出てくる非常に重要な数字です。脱税はもちろん違法行為なのでアウトですが、企業としては適度な節税対策を施すことで、政府や当局への税金を減らし、資金提供者への利益を増やすことも昨今はある程度求められるようになっています。この数字が低いことは、節税のうまさや、税率の低い国での活動比率が大きなことを意味します。
KPIの見方
節税に関しては、企業の意識の差が大きく出る部分でもあります。中には「税金を納めるのは公的存在である企業の役目」との考え方の下、節税対策をほとんど行わない企業もあれば、税務や法律のプロを雇って極力租税回避をする企業もあります。社会を重視するのか株主を重視するのか、どちらが良いとは、一概にはいえません。それゆえ、実効税率の高低をどう評価するのかは非常に難しいといえるでしょう。
なお、実効税率はグローバル化という要素でも変わってきます。例えば法人税率が日本より低い国でビジネスを大きく展開すれば、平均としての実効税率は低くなります。日本国内でも企業誘致のために税率を下げている自治体はありますので、そうした地域に進出すると実効税率は変わります。
KPIの使い方
節税にあまり関心のない企業の場合、この数字は最終的に自動的に決まってくるものであるため、目標を設定するということはありません。ここでは、節税に積極的なグローバル企業をイメージして議論します。
そうした企業においてこの数字を意識するのはやはり経営者や財務責任者です。節税につながる投資の減損などは期初に想定することが難しいため、目標の設定は難しいといえますが、それでもある程度のめどは立てることが多いでしょう。例えばフェイスブックなどでは概ね10%程度の実効税率をイメージしているようです。先進国の実効税率は20%台前半といわれますからうまく節税ができているといえるでしょう。特にIT企業の場合は「モノ」を売っているわけではないので、形式上の本社をアイルランドなどの低税率の国に置けば、合法的に実効税率を下げることは比較的容易なのです。「ダブルアイリッシュ・サンドウィッチ」などの節税スキームなどもどんどん開発され、規制がかかりそうになるとまた新しいスキームを作るといったことも行われています。
補足・注意点
特にIT系の企業においては、最近、さすがに低すぎる実効税率や、商売をしている国に税金を払わないことは企業イメージを損なうとして、一時期ほどの節税を控える動きも出ています。例えばアマゾンは2016年までは日本で法人税などを支払っていませんでしたが、2017年からは日本でも税金を払う方が日本での事業を拡大するうえで得策と判断し、数百億円の税金を支払うように方向転換をしました。
関連KPI
税引後利益、WACC














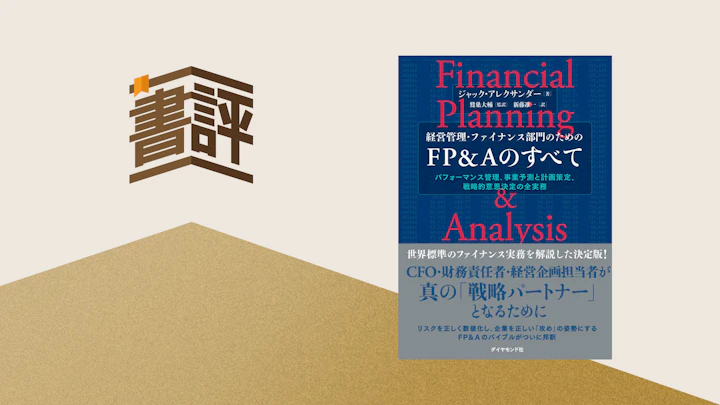


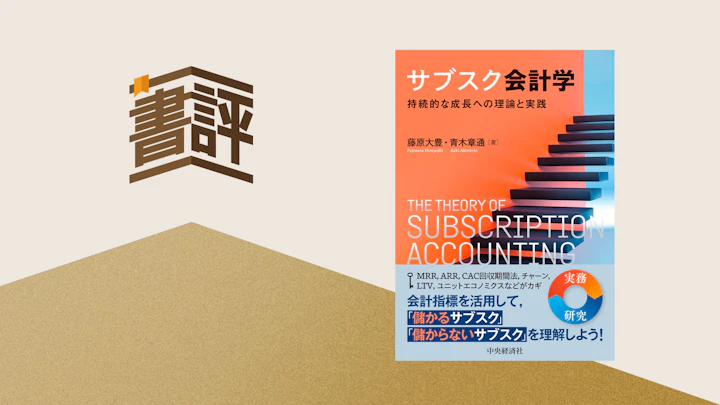













.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


