人と人の関係性の中に生じる「やっかいな問題」への処方箋としての「対話」
正しい知識が実践されない――ビジネスの現場で実務を担う読者の多くは、こんな壁に直面し、なぜこんなことになってしまうのか疑問を持ったことがあるだろう。筆者にとっても、ビジネスや経営の研究・教育に携わる中で、自分ごととして問わずにはいられない。
なぜ、正しい知識が現場で実践できないのか。言い換えれば、なぜ組織の中で"正論"が通用しないのか?その理由を、本書は、現在の経営現場で発生している課題の多くが「適応課題」だからである、と指摘する。
本書では、現場における課題を「技術的問題」と「適応課題」の2つに分けて論じる。現在は、様々な経営知識やビジネスツールが生み出され、それを実現する技術も発達している。それらの知識や技術など、既存の方法で解決できる問題を「技術的問題」と呼ぶ。一方、そのような既存の知識では解決できないのは、人と人、組織と組織の関係性の中で生じる「やっかいな問題」だ。これを「適応課題」と呼ぶ。
この類の問題を解決するには、問題に関係する当事者たちのモノの見方や価値観、習慣などを変えること(=適応)が必要であり、当事者に変化の痛みが伴うため、一筋縄で解決できない。そんな組織の生々しい現実に対して、いくら新しいノウハウや技術を用いたとしても、良い解決にならないことは想像に難くない。そんな適応課題への処方箋として提示されるのが、「対話」だ。
対話とは、単に「向き合ってじっくり話をすること」ではない。本書のいう対話とは「新しい関係性を構築すること」、具体的には、相手の抱える事情や背景に目を向け、その状況を理解した上で自分と共有できるポイントを見つけ出し、これまでとは違う眼差しで相手を認めることだ。
そのプロセスを、「溝に橋を架ける」という行為になぞらえ、
①準備:溝に気づく
②観察:溝の向こうを眺める
③解釈:溝を渡り橋を設計する
④介入:溝に橋を架ける
という4つのプロセスで説明する。これらの4プロセスの詳細は本書に譲り、本稿では、筆者がなぜ、この対話のプロセスの重要性を強調せずにいられないのか、実体験から紹介したい。
相手と向き合うことから逃げて、組織が傷んだ経験
筆者はかつて、NPO法人の経営に関わっていたことがあった。当時は、経営に関わる立場として、精一杯成し遂げたい社会の姿や組織が果たすべきことを描き、それに向けて情熱を持ってアクションし続けていた。しかし、文字通り四六時中、組織のことを考え続けるに従い、だんだんと頭の中には歪な考え方が湧き上がっていた。
「この中で、誰よりも自分こそが一番組織のことを想っている」「そんな自分と違う意見を持つ人がいるとしたら、それは考えが足りない、分かっていないのだ」と。
その結果、意見の異なる人との多くの軋轢が生まれ、組織のために信念を持ち情熱を傾けるほど、仲間として向き合うべき相手の考えを認めることができなくなっていった。相手を信頼して向き合うことができず、あたかも理想を実現するための道具のように見なすようになっていたのだ。
この状況はまさに適応課題そのものだった。当時の自分に、別の意見を持つ相手の文脈を認めようとする心があったら、傷つかずに済んだ人が(自分も含め)たくさんいただろう、と今でも思い返す。
いくらノウハウや技術を駆使しても、組織の中で向き合う相手のことに目を向けないのであれば、それは、一方的な押しつけ(もしくは説教)でしかない。上述の通り、現在は様々な経営ノウハウやツールが生み出され、技術の発達も目覚ましい。それだけに、経営知識を学ぶ人々の中には、それらの知識を身に付けることで、まるで自分が"何者か"になったかのように考えてしまう人もいる(何より、筆者自身もそんな勘違いをしがちな人間だ)。
だからこそ、ビジネスの現場で組織をより良くしようとする読者には、少しでも相手のことについて思いを巡らせることの重要性を知ってほしいと筆者は願ってやまない。
「分かってない」相手の一理を認める
読者の中には、経営知識を学んでそれを活かして組織を変えようとしながらも、思い通りに物事が進まず悶々とした気持ちに駆られる人もいるかもしれない。そんなとき「上司が(あるいは部下が、同僚が)自分のことを分かってくれない」と嘆く前に、その相手の立場や背景にも思いを馳せてみてはいかがだろうか?あなたにとって「分かっていない」と見える、その相手にも背負っている責任があり、成し遂げたい理想があり、そして何より、現状を変えたいという熱い想いがあるかもしれない。
組織の中で、誰も自分の組織を悪くしたいと願う人はいないはずだ。相手には相手にとっての一理がある。それに向き合い、認め、相手と共有できる新しい正論を作り上げていくことが、組織を変えていくことの本質ではないだろうか。
相手の一理を認めるというのは、自分の視点やモノの見方(本書ではこれを「ナラティブ」という)がとても一方的なものでしかなかったと認めることだ。それは、誰にとっても受け入れ難く、痛みを伴い、自分の心がさらされるような怖さがある。それでもなお、自分のモノの見方を見つめ直し、相手との関係を紡ぎ、理想に向けて組織を変えようとする、その行動1つひとつこそが、リーダーシップではないだろうか。本書は、そのリーダーシップの過程を、理論と事例を交えながら描いている。
本書の「おわりに」にも記載されている通り、著者は自らも痛みを抱えながら人間同士の関係性に向き合ってきた経営理論家である。その実体験から導き出した理論は、真に迫るものがある。本書が語るのは、リーダーシップの精神論ではない。同時に、実務と結びつきにくい(悪い意味での)アカデミックな理論でもない。本書が語るのは、骨太な理論に裏打ちされた、組織を変えるため本質と、その実践方法である。
『他者と働く——「わかりあえなさ」から始める組織論』
著:宇田川元一 発行日:2019/10/4 価格:1980円 発行元:NewsPicksパブリッシング


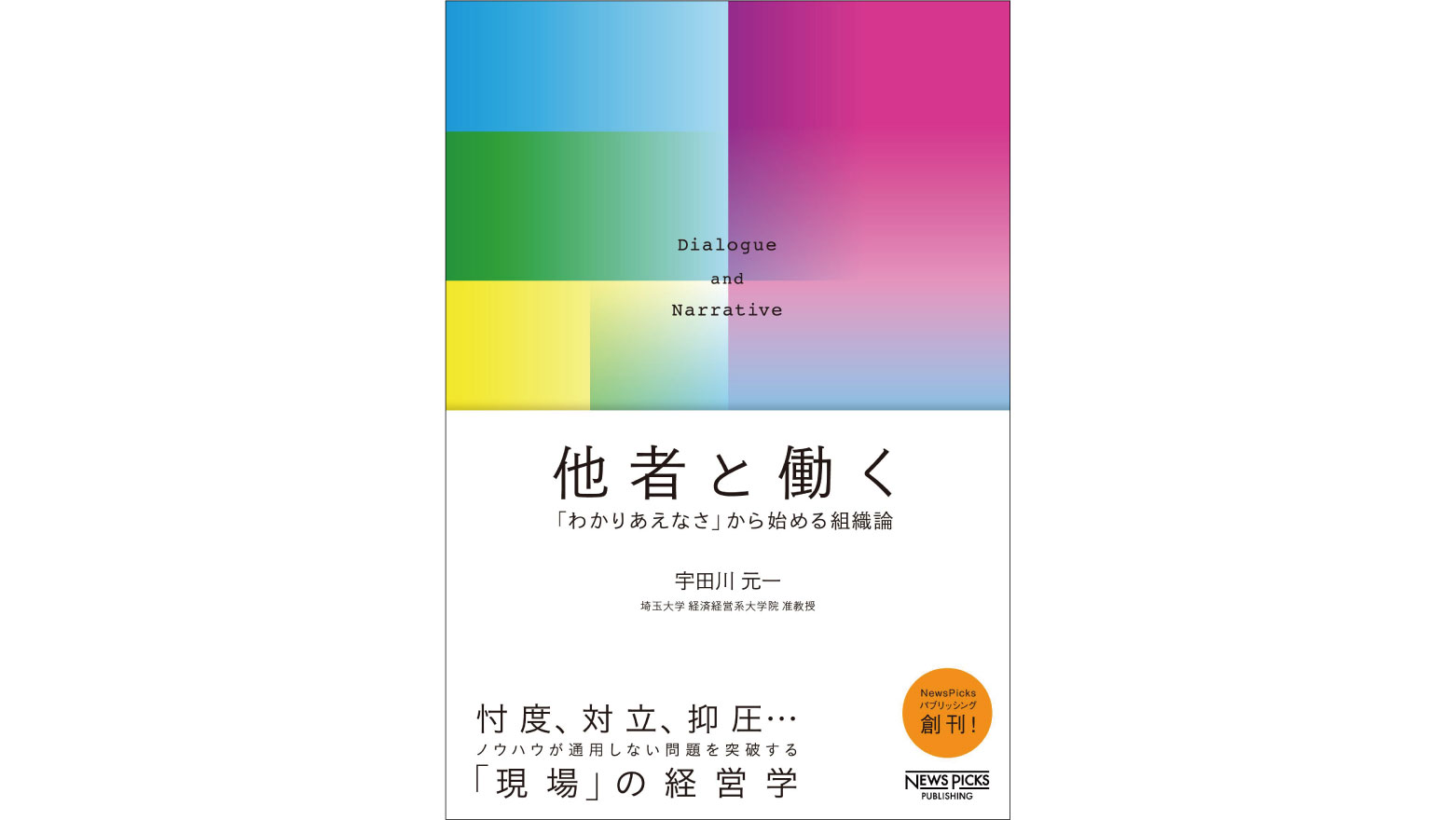


































.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

