 『ビジネス仮説力の磨き方』から「走りながらの検証に向くパターン」を紹介します。
『ビジネス仮説力の磨き方』から「走りながらの検証に向くパターン」を紹介します。
ベンチャー企業、特にIT系のベンチャーでは、「β版」や「MVP(Minimum Viable Product)」あるいは「ピボット」という言葉がよく使われます。これは最初から完成形を目指すのは難しいし、ビジネスで勝つ上で重要なスピードもそいでしまうので、まずは多少完成度が低くても市場に受け入れられるか否かを検証し、必要に応じてバージョンアップさせたり大きな方向転換を図ろうというものです。
この考え方は昨今ではベンチャーのみならず、多くの企業で応用されるようになってきています。それだけスピードが重要になってきたことの証とも言えるでしょう。ただし、実際にテスト的にやってみることは、検証の精度は上がる一方で、リスクも内包します。そうしたリスクも正しく理解した上で、バランスを適切にとりながら仮説検証し、ビジネスを推進することが望まれます。
(このシリーズは、グロービス経営大学院で教科書や副読本として使われている書籍から、ダイヤモンド社のご厚意により、厳選した項目を抜粋・転載するワンポイント学びコーナーです)
◇ ◇ ◇
走りながらの検証に向くパターン
「走りながらの仮説検証」が向く典型的なパターンは、すでにたくさんの商品や店舗を展開している企業が、新たな商品や店舗の企画をするという状況です。
全国的に営業展開をしている消費財メーカーであれば、新商品の発売にあたって、いきなり全国展開をするということはなく、まずは地域や期間を限定して、テストマーケティングを行うことでしょう。それにより、そもそもその商品が受け入れられるかどうかということや、パッケージ、価格帯、プロモーション方法などに関する仮説を検証していくのです。
たとえば、テストマーケティングの結果、20代の女性をメインターゲットにしていたにもかかわらず、30代の女性のほうによく売れたとすれば、
「そもそも、30代に向く商品なのではないか」
「パッケージが20代に向かなかったのではないか」
など、新しい仮説が生まれてきます。そして今度はそれを検証し(パッケージを変えてみるなど)、さらなるアクションにつなげていきます。
なお、こうしたテストマーケティングは、そこで検証された結果が、その時その場所でしか通用しないようでは本来困るのですが、実際には、偏ったサンプルゆえに正しい検証、判断ができないケースは少なくありません。
これを避けるため、テストマーケティングは、「平均的」な地域や顧客層を選ぶことでその普遍性を高めるよう工夫します。たとえば、かつてわが国では、全国発売する商品については、静岡近辺でテストマーケティングするというやり方が好まれました。嗜好や購買力などが平均的であるということに加え、大企業の本社に比較的近い、日中の県外との人口移動が少なく他県からの電波も入リにくい(閉じた「実験系」とみなせる)、などの理由からです。
科学的経営やブランドマネジメントで有名なプロクター&ギャンブル(P&G)はかつて、消臭芳香剤「ファブリーズ」の日本でのテコ入れにあたって、北海道をモデル地域とし(先述の静岡県に近い理由から)、プロモーション手法を練り上げました。その方法論は日本国内はもちろん北米など世界に横展開され、「HOKKAIDO MODEL」と同社内で呼ばれました。
テストマーケティングに限らず、「まずは簡単にテストができる」という状況であるのなら、事前にあれこれ悩むより、まずはテスト的にやってみることをお勧めします(もちろん、事前の仮説検証がまったく必要ではないという意味ではありません。念のため)。
ここで言う「簡単に」とは、企業規模や当事者自らが持つ権限との相対感にもよりますが、おおむね図に示したことを指します。

たとえば、営業担当者であれば、自分なりのセールストークを試してみる、レストランオーナーであれば、「限定発売」として新メニューを試してみる、チェーン店の企画担当者であれば、ある店舗だけ品揃えやレイアウトを変えてみる、などが該当します。本章のケースで、五葉が子連れ客の受け入れをまず別館のみでテストしたのは、その意味で賢明なやり方です。
逆に言えば、大きな金銭的・人的投資が必要で、全社的な影響が大きく、また簡単には中止・変更できない場合などは、走り出す前にしっかり仮説検証の精度を上げておく必要があります。莫大な初期投資を要する製品開発や、巨額の資金を要するM&Aなどはその典型です。
ケースのなかでアイデアとして出されたスパなどは、投資額もさることながら、一度やってしまうと旅館の提供価値に大きな影響を与えますから、事前に慎重な検討が必要です。「一度変えたり止めたりしてしまったら取り戻せないものと、試しにやってみてもいいことを見極める」ことが重要です。
近年では、企業の屋台骨を形成する経営戦略の分野においても、現場に近いところで立案・実験し、臨機応変に修正を試みるという傾向が強くなってきています。
(本項担当執筆者:嶋田毅)
『ビジネス仮説力の磨き方』
グロービス経営大学院/嶋田毅 (著)
1600円(税込1728円)















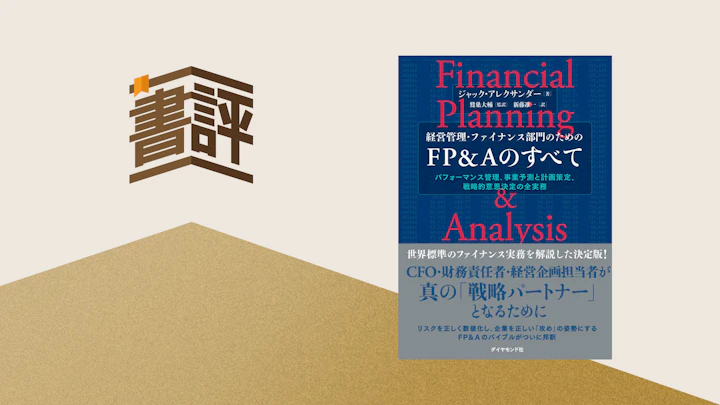


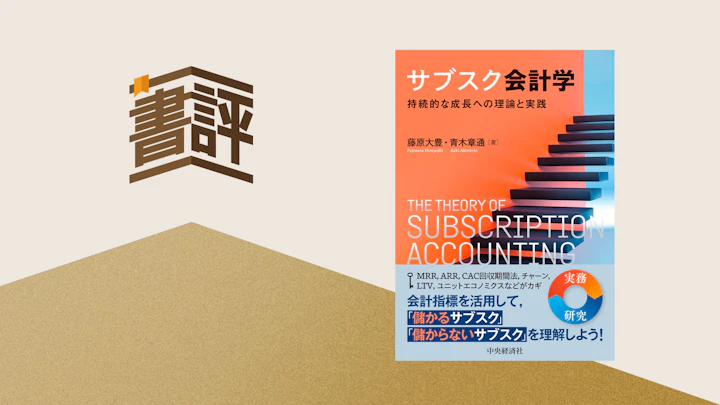














.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)





.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
