 『グロービスMBAで教えている プレゼンの技術』から「聴き手の心をつかむ」を紹介します。
『グロービスMBAで教えている プレゼンの技術』から「聴き手の心をつかむ」を紹介します。
プレゼンテーションに限らず、ビジネスのさまざまな営みは、枠組み(フレームワーク)やプロセスに代表される再現性の高い王道的な方法論だけで完結するものではなく、ちょっとしたコツが効くことも多々あります。あまりにそれに頼り過ぎると危険かもしれませんが、そうした「傾向」を正しく理解し、状況に応じて使うことで、聴き手を自分のプレゼンテーションにより強くひきこむことが可能になるのです。今回紹介したもの以外にも、もっと「泥臭い」ものもあるでしょう。多くのプレゼンテーションに触れることで、そうしたコツを自分なりに見つけ出し、使いこなせるようにすることも、ビジネスパーソンにとって大事な心がけなのです。
(このシリーズは、グロービス経営大学院で教科書や副読本として使われている書籍から、ダイヤモンド社のご厚意により、厳選した項目を抜粋・転載するワンポイント学びコーナーです)
◇ ◇ ◇
聴き手の心をつかむ
前項までで聴き手の関心に沿った話題選びとメッセージ、そしてストーリーラインについて書いてきました。これらはプレゼンテーション全体の構成に関する、いわばマクロレベルの話でしたが、ここからは、もう少しミクロな、本題と直接関係ないスキマの話題や、話の中で使うワンセンテンスレベルの工夫についても述べたいと思います。

1. 自分という存在に共感してもらう
聴き手がアクションを起こす原動力の一つに「共感」があります。では、共感は何から生まれるのでしょうか。話の中身は当然重要ですが、話し手であるあなた自身も負けず劣らず重要です。
話し手の言葉や振る舞いに対して、聴き手が邪推や裏読みをせず、素直に受け止めてくれる状態が理想的と言えるでしょう。このような、お互いが相手のことを信頼し、安心感を抱いている状態のことをラポールと呼びます。話す前に互いのことをあまりよく知らないときは、なるべく早い段階、特に自己紹介や導入のところでラポールを築いておきたいものです。
ポイントは共感ですので、あなたと私は共通した属性を持っている、同じことに興味関心を抱いている、同じことに驚いている、同じことを懐かしんでいる、同じことに感動している……というように、同じ心の動きをする話題を出すことです。
たとえば、「この会場に来る途中、緑のきれいな並木道を通りましてね。もうすぐ夏ですね」とか、「ヤンキースのマー君、また勝ちましたね。すごいですね」といった雑談を混ぜるのには、単に聴き手をリラックスさせるだけでなく、自分と聴き手が同じ反応をしそうな話題を出して「共感」の場を作る目的もあるということは意識しておきましょう。
2. ほどよく権威をアピールする
一般的な傾向として、人は「権威」を認めた人の言うことを受け入れやすくなります。聴き手と自分との関係に照らして分不相応なハッタリはいけませんが、それなりの裏付けのあるときは、自分はこの話題に関して人前で語るだけの権威があるのだと、それとなく示すことを意識しておきましょう。
単に、自己紹介で肩書きや実績に触れるだけとは限りません。説明の中で、自分が経験した事例を紹介したり、著名人や専門家の言葉や体験を引用したりするのも、さりげない権威のアピールになりえます。質問を投げかけながら進めていくというのも、「こちらが話の主導権を握っていますよ」と暗示する効果があります。もっとも、あまり露骨すぎると反感を買う危険もありますので、「ほどよく」やることが肝心です。
3. 不安や迷いを取り除く
メッセージやロジック、ストーリーラインを作るときには、プレゼンの目的に対して聴き手が感じるだろう疑問や反応を想定してきました。現実には、聴き手はそれ以外にもさまざまな心配ごとを持つものです。たとえば、「いつ終わるのかな」「机の上のこの資料は何に使うのかな」といった具合です。
冒頭で全体の概要と時間配分などを予告するのは、聴き手を安心させる効果を狙っています。質問をしたくなったときの対応として質疑応答の時間は取るのか、配布資料に何があるかなどを説明するのも同様です。時間が長いときは、あらかじめいくつかのパートに分けておくのも、聴き手が残り時間を読めるという効果があります。
また、最後の締めの部分で、それまで話した内容を再度まとめたり、何かプレゼン後にして欲しい行動があるときに念押ししたりするのは、聴き手に迷いを残さないという効果を狙っています。
4. 「地雷」を避ける
聴き手の「共感」が重要ということは、言いかえれば「聴き手に共感されないこと」「聴き手の反感を買いそうなこと」はなるべく避けようということです。もちろん、本論部分では多少聴き手の耳の痛いことも言わなくてはいけない場面もあるでしょうが、本筋以外の部分で聴き手の感情を逆なでするようなことは避ける必要があります。
(本項担当執筆者:グロービス・コーポレート・エデュケーション 講師 山臺尚子)
『グロービスMBAで教えている プレゼンの技術』
グロービス経営大学院 (著)
1800円(税込1944円)














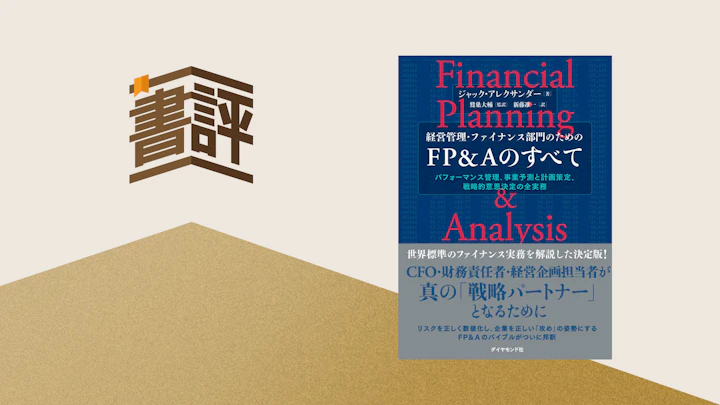


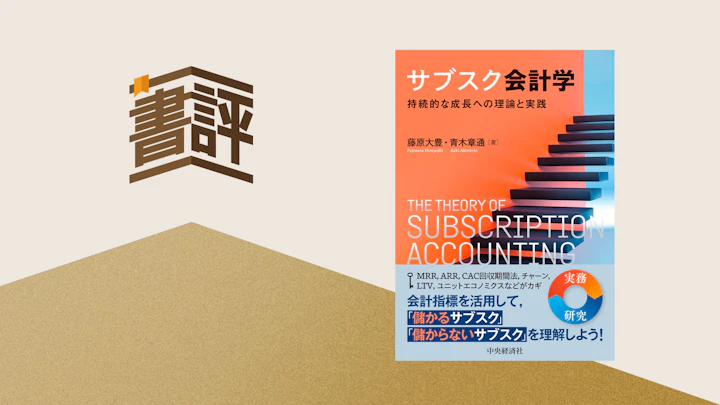
















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




