ビジネススクール経営の一環として、多数のカンファレンスを開催している。東京のメインキャンパスで丸一日でやることもあれば、東京から遠く離れたエキゾチックな町で3日連続で実施することもある。ビジネスに特化することもあるが、多くの場合、もっと広い話題を取り上げている。国際関係、安全保障、政治、経済、文化のほか、スポーツなどを話題にすることもある。
成功の秘訣は、刺激的なディスカッションで聴衆を魅了し、没頭させること。以下に、そのためのシンプルなルールを紹介しよう。
1. セッションテーマ: タイムリーな話題、一流のスピーカー
当然だが、そのカンファレンスにとってタイムリーかつ直結するテーマを選ぶ必要がある。ここはアジアだから、南シナ海――中国が精力的に軍事目的の人工島を作っている――の安全保障のような話題が好例だ。世界的な視点では、世界中の人々に脅威を与えている非国家組織(ISISなど)や、ユーロ圏から離脱することで世界経済を混乱に陥れるかもしれないギリシャを話題にしてもいいだろう。
単にタイムリーなだけでは不十分だ。一流のスピーカーに登壇してもらう必要がある。スピーカーのレベルで妥協するぐらいなら、そのトピック自体を無くした方がいいというのが、僕の厳格なルールだ。
2. オリジナリティが最優先: 他人と違う意見こそ愛される
僕が世界経済フォーラムのダボス会議に参加するようになって、10年以上になる。何度も参加するうちに、人気を集めるスピーカーはいつも、多くの人と異なる意見を持つ人であることに気がついた。直感に反するので最初は信じられないが、いつの間にか引き込まれてしまうのだ!
ダボス会議の常連スピーカーであるウェブ起業家の伊藤穣一氏は、これが非常にうまい。彼自身が生きるパラドックスを語っているようなものなのだ。タフツ大学中退の伊藤氏が、MIT(マサチューセッツ工科大学)でメディアラボの所長になった。そんな彼の口から、オリジナルで刺激的なコンセプトが出てくるのは当然と言えば当然だ。
例えば、伊藤氏が提唱している「B.I.」「A.I.」というコンセプトがある。「Before Internet」(インターネット登場前)と「After Internet」(登場後)を意味するこの言葉は、彼にとっては「B.C.」(紀元前)「A.C.」(紀元後)のようなものだ。また、「antidisciplinary」(脱専門的)と「interdisciplinary」(学際的)の違いも面白い。脱専門的とは、従来の学界的な意味での専門分野の区分けにとらわれない、型破りでハイリスクな課題解決アプローチを意味する。
無難で、ありふれた意見を聞きたくてカンファレンスに参加する人はいない。大胆で刺激的な、新しいアイデアが求められているのだ。だからスピーカーには、聴衆をハッとさせ、魅了する力がなければならない。
3. 多様性こそ人生のスパイス: スピーカーをキュレートせよ
これまで参加したパネルディスカッションのうち、特に素晴らしかったものの1つが、2005年のダボスで行われたものだ。テーマはアフリカ。パネリストはビル・クリントン、ビル・ゲイツ、タボ・ムベキ(当時の南アフリカ大統領)、トニー・ブレア、ボノ、オルシェグン・オバサンジョ(当時のナイジェリア大統領)の6人だった。
確かにパワフルな男性ばかりだが(ダボスはここ数年、ジェンダーのバランスにも積極的になっている)、民族、職業、世代、ライフストーリーなどは、面白いほどに多様だ。特にボノが、「議論のトーン」が気に入らないという理由で話を中断し、不満を述べていたのを鮮明に覚えている。彼は、グループ内で唯一のミュージシャン/活動家であり、異色の存在だった。
議論を活発にするには、異なるバックグラウンドや視点を持つ人たちを集めるのが一番だ。僕は、「思想家」と「実践者」を混ぜることを心掛けている。例えば、学者と実業家といった具合だ。そうすることで、すべての議論がリアルワールドに根差したものになるのだ。
スターの力でダボスと張り合うのは難しいかもしれないが、イベントを主催するなら著名人を何人か呼ぶのはいいことだ。著名人はイベントの吸引力を高め、他の素晴らしいスピーカーを惹きつけることができる。
4. モデレーターは本当に重要: 勢いを弱めるな
優秀なモデレーターとは、優秀な映画編集者のようなものだ。カメラの前に立つスターではないが、スピーカーの間に割って入る決断が、セッションのペースやエネルギー、ひいては成否を左右する。優秀なモデレーターにはさらに、難しい質問を投げかける度胸と、パネリストが言葉を濁して逃げないように食い下がる粘り強さも必要だ。
僕はいつも、特に重要なセッションのモデレーターは、元BBCワールドテレビのジャーナリスト、ニック・ゴーイングに頼んでいる。ニックは、手短な説明をしてディスカッションを進行し、すべてのスピーカー(重要度にかかわらず)を話題から脱線させず、質疑応答では聴衆を巻き込むことに、たぐいまれなる才能を発揮する。その進行は、お見事としかいいようがない。
5. 洞察は意外な場所に隠れている: アイデアを多方面から攻めよ
カンファレンスで、どのセッションが最も重要な洞察をもたらすかは、やってみなければわからない。そこで僕は、メインテーマを多様な角度――文化、政治、技術、経済など――から攻めることで、その可能性を高めるようにしている。
例えば、震災後の日本経済復興をテーマにしたカンファレンスでは、標準的で「真面目な」話題――金融政策、フクシマ後のエネルギー問題など――だけでなく、日本のストリートファッションやスタートアップシーンなどの「軽い」話題も取り上げた。これら2つのセッションは、日本経済を立て直さなければならない若者の回復力、クリエイティビティ、ポジティブシンキングについて、印象的な洞察をもたらした。どこからグッドアイデアが生まれるかはわからない。だから、手あたり次第にやってみればいい。
6. できるだけ身近に: 聴衆との距離をなくせ
ローリングストーンズの演奏を見るならどこがいいだろう。小さなクラブ?それとも5万人収容のスタジアム?これに議論の余地はないだろう。小さなクラブの方が楽しいに決まっている。それは、カンファレンスでも同じだ。スピーカーと聴衆の間には、リラックスした親密な空気がある方が、良い結果につながる。
そのためにも、パネリストの演壇は30cm程度と低めに設定し、座席はそれを取り囲む三日月状に設置している。聴衆にはなるべく前の席に座ってもらえるよう、スタッフが声をかけている。そうすることで、スピーカーと聴衆の間で、ダイレクトなエネルギー交換が生まれるのだ。
以上が、カンファレンスで成功するセッションを作る、僕なりのルールだ。
ほかに考慮すべきことがあったら教えてほしい。僕はいつも、フロアからのフィードバックを歓迎している。
(訳:堀込泰三)


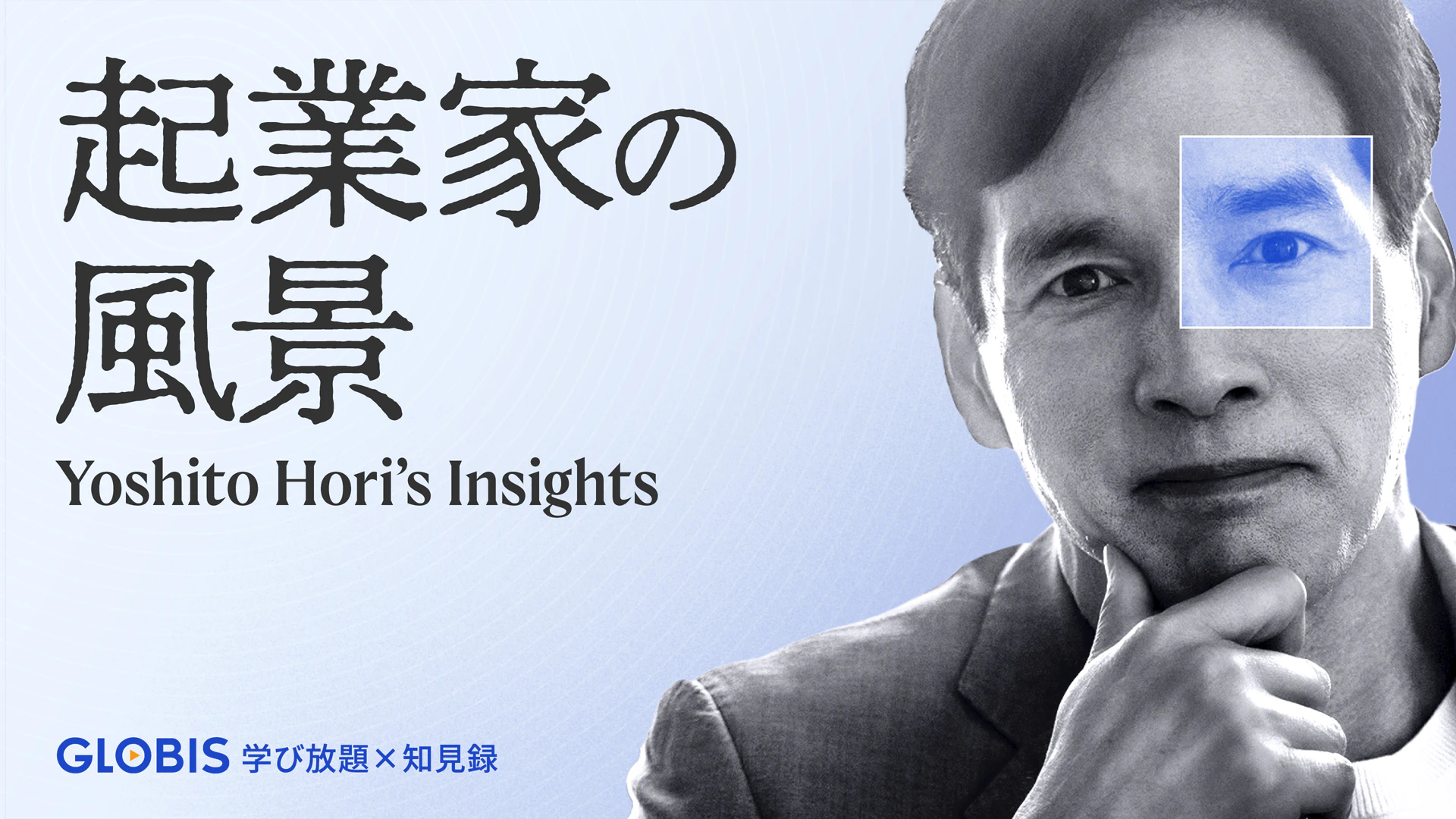
































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
