
会員限定
何かに依存してしまう人は「レジリエンス」を高めて乗り越えよう/みんなの相談室Premium
日常にある身近な疑問を、ビジネス知識を使って解決する「みんなの相談室Premium」。 今回寄せられたのは、「私はついつい、次々とバッグが欲しくなり、買ってしまいます。自分でも良くないと思っているので、何とかやめたいのですが、どうすれば良いでしょうか?」というお悩み。何かがやめられない依存傾向から脱するための方法を「レジリエンス」という言葉を使って、グロービス経営大学院教員・林恭子が解説します。(肩書きは2021年9月14日撮影当時のもの) 林 恭子 グロービス経営大学院 教員 名越 涼 アナウンサー







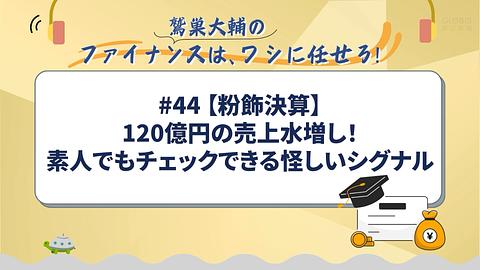
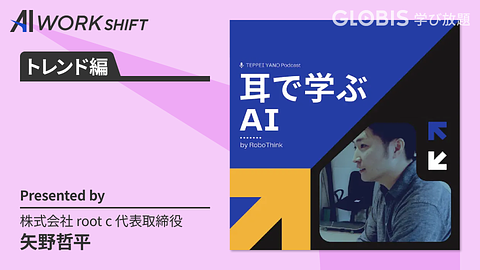








より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
26人の振り返り
h-goto
その他
裸眼思考とレンズ思考について聞きましたが、レンズ思考はよく言われるPDCAに類似した考え方で近視的な見方だとしている、反対に裸眼思考は大局的の見方をしているということでした。課題解決の方法はいろいろと説明されていますが、それを理解した上で、どれを選択するのかが大事に思えました。
khoo
専門職
裸眼思考xレンズ思考
レンズ思考:目的→仮説→検証→決定
裸眼思考:今に集中(表面のみでなく、裏にも注意)→保留(一晩寝かせてからまた考える→思考停止しない)→記憶(もよもやの点、気づき等を記録する)
ik_hrs
営業
ものごとに集中すると、どうしても周りが見えなくなったり、視野が狭くなったりするが、客観的な視点を忘れないようにすることが大事だと思った。
eizan_1000
IT・WEB・エンジニア
「保留」を許す職場でありたいと思います。
yuko-1015
メディカル 関連職
今の状況をしっかりと見つめる
kubota_k
販売・サービス・事務
引き出しの一つとして理解しました。肝要なのはどれを選択するのかと思います。
th0588
その他
裸眼思考を読んでみようと思いました。
watanabe_jiro
マーケティング
裸眼思考。レンズ思考 差があまりないように感じた。ようは自分で判断する選択肢をたくさん持つことが必要と感じた
kawa-yasu
営業
知覚、保留、記憶の流れを意識して裸眼思考の考え方を取り入れて日々活動できればと思いますが少しずつ取り組んでいきたい。
okamei
経理・財務
俯瞰的にものごとをとらえるようにしたい
dia44
メーカー技術・研究・開発
ものごとに集中すると、どうしても周りが見えなくなったり、視野が狭くなったりするが、客観的な視点を忘れないようにすることが大事だと思った。
everest
営業
先入観やバイアスを取り払って物事をありのままに捉え的確な判断と問題解決を行いたい。
kawasemi3
専門職
裸眼思考は今の情報を捉えて(視覚)、いったん保留して、記憶(もやもやなどはメモに残す)
結論を拙速に決めるのではなく、また出した後も問い続ける。
レンズ思考(目的、仮説、検証、採用)と裸眼思考いずれも併用することが大事。
tn_infinity
営業
分かりやすい考え方として、頭を整理できました。
特に、答えを急ぎやすい性分でもあるので、「場合によって保留」(=いったん寝かせる)という観点は非常に響きました。
物事を考えるサイクルの中で、実践してみたい。
shikay
メーカー技術・研究・開発
今目の前の人の語りに集中することは、意識しないとできない。せっかく時間を取ってもらってヒアリングしても「次何を聞こうか?」とか「どうやってまとめようか?」とか結構器用に「聞いているふり」をすることが多い。終わってから文字起こしをするようになって、ようやっと目の前の人の語りに集中するようになった。今は自動で文字起こしできるようになったが、相手が使った言葉をそのまま覚えておこう、後で再現しようとするだけで、よく聞けるようになったと思う。たまには手間をかけて集中したい。自分は文字起こしをして、小さな違和感を漏れなく抽出する癖がある。その時浮かんだ問いはしばらく寝かせてストックしてある。ストックがあまりに多くてさばききれないから、このストックに意味があるのか悩ましかったが、意外に時間がたつとそれらしい答えが作れるものだ。無意識に材料を集めているのかもしれない。しかし放置のまま忘れる場合もあるから、しばらくして改めて今持っている情報で仮でもいいから答えることを心掛けたい。
akihiro_jinba
建設・土木 関連職
ためになるお話でした
morimotoa
営業
バイアスを掛けず物事を見る視点も養う。
se_n
クリエイティブ
裸眼思考とは何かについてもう一段掘り下げて考えてみたい。
tsukamotoya
資材・購買・物流
裸眼思考参考になりました。クリティカルな思考ですね。業務に活かしていくよう努力していきます
kuri109512
建設・土木 関連職
レンズ思考、裸眼思考をうまく使い分けができると良いと思うが中々難しいな。
071029
販売・サービス・事務
2回聞き直しました。
目先の物事への対処だけ考えて進んでいたら、見落としがあったり、一方は良くても一方が悪かったり、物事がうまくいかなかったことあります。
回答を急がず最後まで聞く、最短的確に導くためには情報を広く捉えて見るなど意識していきたいです。
av01211
人事・労務・法務
続けて見てチックみます。
chiikawanousagi
販売・サービス・事務
いまある物事に集中する
sphsph
メーカー技術・研究・開発
事実は何か。
自分に必要な情報をどうやって入手して分析し活かすか?
情報化社会で、アンテナの精度の重要性を感じます。
aaaoo
販売・サービス・事務
今に集中することが大切。日常の会話シーンでも活用していこうと思いました。
rinto289
IT・WEB・エンジニア
どう返事をするか考えて話をあまり聞いていない、という事例にハッとさせられました。
保留する勇気も持ち、ゆとりを持って対応できるよう心がけたいと思いました。