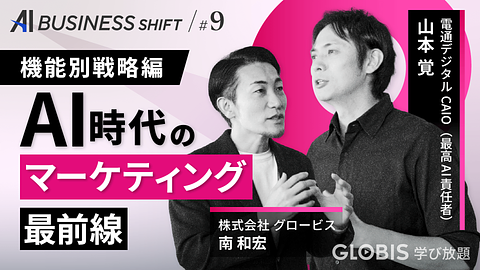
02月28日(土)まで無料
1:05:27
割引情報をチェック!
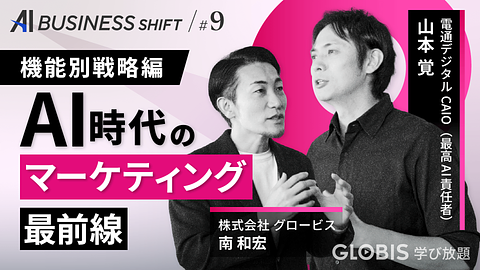
AI BUSINESS SHIFT 第9回 機能別戦略編:AI時代のマーケティング最前線
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第9回です。 第9回「機能別戦略編:AI時代のマーケティング最前線」では、マーケティング担当者が日々の業務の中でAIをどのように活用しているのか、AIの普及によってマーケティングマネージャーの役割や育成・評価の考え方がどう変わるのか、さらに、AI活用を前提としたマーケティング戦略の再設計について掘り下げていきます。 ■こんな方におすすめ ・AIがマーケティング活動に与える影響を知りたい方 ・マーケティング組織を率いるリーダー・マネージャーの方 ・AI時代におけるマーケティング戦略や人材育成のあり方を学びたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年2月制作)
02月28日(土)まで無料

マネジャーのための仕事の任せ方
「仕事を任せると失敗が怖い」「自分でやった方が早い」マネージャーとしてメンバーやチームの力を引き出しながら成果を上げるには、どのように仕事を任せていけば良いのでしょうか? 変化の激しい時代において、マネージャーとして成果を上げ続けるためには、メンバーの個性や特性を理解し、それに合わせた効果的な任せ方を身につけることが重要です。このコースでは、ソーシャルスタイル理論を活用してメンバーごとに最適なアプローチを学びます。「任せる力」を高めることで、チーム全体の成長を促進し、自身のリーダーシップを発揮できるようになっていきます。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2024年12月制作)
会員限定

AI時代の個人力
AIが仕事や社会の前提を変え続ける今、最も求められるのは「他者に代替されない個としての力」“個人力”です。 本コースでは、澤円氏の著書『個人力』をもとに、AI時代をしなやかに生き抜くための「前向きな自己中戦略」を学びます。 テーマは、「Being(ありたい自分)」を中心に据え、自ら考え(Think)、変化し(Transform)、協働する(Collaborate)ことで、自分らしい価値を発揮していくこと。 リスキリングやAI活用が叫ばれる今こそ、スキルより先に“自分の軸”を問うことが重要です。 あなたは何を大切にし、どんな未来を描きたいのか? このコースは、あなたが“ありたい自分”として生き、キャリアをデザインしていくための思考と行動のガイドになります。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年11月制作)
会員限定
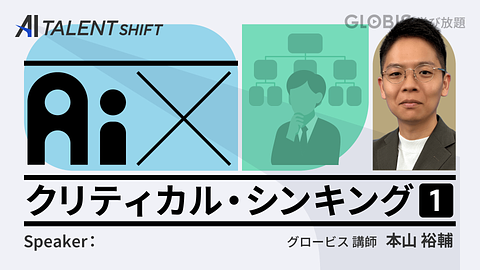
【AI×クリティカル・シンキング】①イシューと枠組みでプロンプトを磨く
生成AIから期待する回答を引き出せず、試行錯誤を重ねていませんか。 本コースでは、生成AI活用の質を高める鍵として、クリティカル・シンキングの視点からイシュー設定と枠組みを押さえる重要性を解説します。 目的に直結する問いの立て方や、プロンプトに落とし込む際の実践ポイントを具体例とともに学ぶことで、AIをより思考のパートナーとして活用できるようになります。 生成AIを業務で使い始めた方から、活用を一段深めたい方まで、再現性あるプロンプト設計を身につけたい方におすすめの内容です。 さらに学びを深めたい方は、こちらも合わせてご覧ください。 【AI×クリティカル・シンキング】②AIの弱点との向き合い方 https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/cdfe41e3/learn/steps/62198 ※本コースは、AI時代のビジネススキルを学ぶ「AIタレントシフト」シリーズの一環として提供しています。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
会員限定

リーダーの挑戦⑤ 藤田晋氏(サイバーエージェント代表取締役)
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第5回目のゲストは、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋氏。起業の理由、経営をどうやって学んだか、アメーバブログ・ABEMAの立ち上げ、経営チームづくりについてなど聞いていきます。(肩書きは2020年12月11日撮影当時のもの) 藤田 晋 サイバーエージェント 代表取締役 堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
会員限定

ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 前編 なぜ眠れないのか?~
「仕事が終わらないから睡眠時間を少し削ろう…」「業務時間中なかなか集中できない…」「毎日朝起きるのがつらい…」。 あなたはこのような経験をしたことはありませんか? 仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削りがちなのが「睡眠」時間。 実は今、日本社会は世界と比較して「最も眠らない国」だということもわかってきています。 慢性的な睡眠不足は、心身の健康に悪影響なだけでなく、仕事のパフォーマンスにも当然大きな影響を与え、社会全体の経済損失につながります。 このコースでは、基本的な睡眠リテラシーを学んだ後の「問題解決編」として、「なぜ多くのビジネスパーソンは眠れないのか?」について解説していきます。 ▼本コースで学べる主な内容 ・そもそも眠れないことは何が問題なのか? ・眠れなくなってしまう原因とは? 睡眠不足の原因は認知機能の問題にありました。 自身の睡眠不足に対し、正しく「気づき・理解し・行動を変える」第一歩を踏み出しましょう。 ▼関連コース ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~リテラシー編~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/24575c03/learn/steps/53129 ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 後編 どうしたら眠れるのか?~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/4ba981e9/learn/steps/62042 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

大阿闍梨 塩沼亮潤が死の手前で見つけた「生き方」
あすか会議2018 第4部分科会B-1「極限の世界で見つけた人生の歩み方」 (2018年7月7日開催/国立京都国際会館) 1300年間で2人目となる大峯千日回峰行満行を果たした塩沼亮潤大阿闍梨。48キロの山道を1日16時間掛けて歩き、それを千日間に亘って続ける過酷な行の中で、どのような悟りを得たのか。そして、9日間、断食・断水・不眠・不臥を続ける四無行満行という極限の世界で何を見つけたのか。塩沼氏が「創造と変革の志士」へ贈る「人生の歩み方」とは。(肩書きは2018年7月7日登壇当時のもの) 塩沼 亮潤 慈眼寺 住職
無料
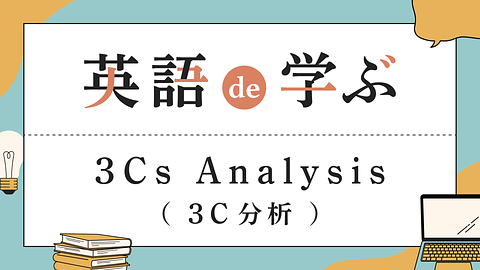
英語 de 学ぶ!3Cs Analysis(3C分析)
このコースでは、グロービス学び放題の英語版である『GLOBIS Unlimited』のコースの中から、ビジネスで役立つ頻出の英語表現をピックアップしています。英語ネイティブの方が実際に見ているコースなので、リアルなビジネス英語の表現を学ぶことができます。 今回のコースは「3Cs Analysis(3C分析)」です。一緒に『英語で』ビジネス知識を学んでいきましょう! ▼今回扱ったUnlimitedコース続きは下記からご覧いただけます 3Cs Analysis https://unlimited.globis.co.jp/en/courses/da5ca962/learn/steps/36362 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
コメント1532件
wkiymbk
「「共同化」とは、経験の共有によって、人から人へと暗黙知を移転すること。「表出化」は、暗黙知を言葉に表現して参加メンバーで共有化すること。「連結化」は、言葉に置き換えられた知を組み合わせたり再配置したりして、新しい知を創造すること。そして「内面化」は、表出化された知や連結化した知を、自らのノウハウあるいはスキルとして体得すること。ナレッジ・マネジメントでは、SECIのプロセスを管理すると同時に、このプロセスが行われる「場」を創造することが重要。」」であることを学びました。
まず、チーム内で場の整備をします。
iijiro
暗黙知を暗黙知のまま共有すると言う考えは新鮮だった。いきなりの文書化は難しく、進める際の参考にしたい。
tetsuyai24
共同化、表出化のプロセスを飛ばして連結化しても有効ではないと再認識しました。
goda12611
自社でも暗黙知の形式知化が標榜されているが、一足飛びに内面化を目指していると分かった。段階と、それに相応しいメンバーの関与が重要と理解した。
yoshi1020
共同化、表出化、連結化、内面化の使い分けは組織において重要だと思いますが、共同化に関してはなかなか難しい。部署毎の見えない壁があるような気がします。
test_
共同化し、表出化すれば、暗黙知が形式知になるかのような説明であったが、実際には難しいように感じた。暗黙知を完全に形式知として、身に付けるのは難しく、表出化するのは、暗黙知の一部分だと考えるから。
暗黙知の一部でも形式知化し、他の形式知との結びつけや経験をへることで、元の暗黙知に近いものが得られるのかもしれない。
tarimo
非常に難しい内容だったが今後のステップとして4分割した内容を業務に役立てたい。
owh_jinji_ex
組織において共同化、表出化、連結化、内面化の使い分けるように、意識的に場を創り上げることが重要である。
ara007
ベテランかいる中で、いかに形式知として共有していくか考えたい
lado
ノウハウの継承は、マニュアルがあればそれでいいのではなく、コミュニケーションも必要と認識した。
piri6
暗黙知である「共同化」からはじまり、形式知である「表出化」「連結化」で共有、創造し、また暗黙知である「内面化」に戻して、自己に戻る一連のプロセスであることを理解した。振り返ると、当職場は、「共同化」の時間は大いにあるが、雑談により、おかしな方向にいってしまう傾向がある。ここを有効に使えると、会議でより有効な「表出化」ができ、更には「連結化」への発展が期待できると思った。
kami5
知識の共有のプロセスについてとても勉強になった。実際の場で活かして、自分のものにしたい。
takesawa
新しい業務を行う際に、マニュアルでは対応出来ない部分があり、創発の場で経験者の方から色々と話を聞く中で自分の中で繋がって来た事がたくさんあった。これが暗黙知の共同化なのだと腹落ちした。
sue_0120
SECIモデルというナレッジ・マネジメントのプロセスを勉強したので、これを理解しながら、今後の教育に活かしていきたい。
uwabami
暗黙知を文書化することばかりに目が向いていたので,創発場の考え方は目からウロコでした.
oy_ko
自分の職場では、暗黙知の共有が弱いと感じた。形式知の量が膨大であることも関係しているかもしれないが、新しい価値の創造やイノベーションのためには、意識を変えてみてもいいのかもしれないと思った。
hasegwa86
自分のもつナレッジを属人化させたまま終わらせるのを防ぐことを考えていたところだったので、ちょうどよいモデルを勉強することができた。実務に役立てていきたい
tomoko_gco
暗黙知の洗い出しや共有には、マニュアルやSOPのフォーマットを作って入れ込めばよいだろうと考えていたが、まずは適した場を設け共同化し、表出化するというステップバイステップの方法があると初めて知った。
moss_green_5
知識の共有について漠然と考えていた。また何か文書やシステムとして作っていけばいいと思っていたが、多くのステップをきちんと踏んで、時間をかけて行う必要があるとわかった。時代の流れはますます早くなっており、時間をかけて知識を共有するのは大変だが、そういう時代だからこそ、きちんと知識を共有できた企業が生き残るのだと思う。知識共有は当社でもよく話題に上るが、今回の学習を今後生かしていきたいと思う。
hiro_yoshioka
なるほど、順番があるのですね。
runnerh
優秀な先輩社員がいなくなったときに組織が困らないように常にSECIモデルを回し続けることが重要だと感じた。
yamada_takuma
日本人の思考特有の,なんでも小難しく形式化し論じるという,悪い部分が出ている考え方と思います。もっと簡単化できる程度の内容と思います。難しいだけで全然頭に入ってこない理論なのですぐに忘れてしまいます。(覚える意味もないと思いますが)
batah
シンプルで普段行ってそうだが、実は出来てなくこれに取り組むことで相当の効果ぎ期待できる気がします。
kodama77
思考力の向上に役立つ。
20090531kk
ベテラン社員と若手社員を一緒にすることで、何でそうするのかという細かいニュアンスをうまく伝えていける。
それが若手社員の実力を引き上げるのに必ず必要。
yatian
今まで分かったようで分かっていなかったSECIモデルが腹落ちしました!
仕事を行う中では、「暗黙知」ばかりです。これを引き継いいで行くことは容易ではありませんが、最初の「共同化」の時間を惜しむことなく、「担当の複数化」から初めて、その後のステップを意識して進めていくことにより、ハードルの高い「知の伝承」をしていきたいと思います。
saito-yoshitaka
暗黙知の形式化は難易度が高いが共有する事で理解できると感じます。
mckusa
暗黙知をナレッジにすることが出来るなんて、大変参考になり、実践してみる。
s_s___
暗黙知とは、その人の努力や経験によって、その人だけが知りえた秘密なので、教えたくない人がほとんどと思う。
(こういうタイプのお客様は、この言葉は禁句とか、これくらいの力でやるとうまく入るなど)
暗黙知をうまくマニュアル化できない事が多く悩む。簡単にマニュアル化できず、相手や状況によって自分で考えろというのは難しいが「カジュアルな服装」「余裕をもってというのは何分か」の様な感じ方基準が難しい。それを常識でしょとか、自分で考えろではマニュアル化できないし、そんな事教えるのバカバカしいと言っては進まない。
piri6
暗黙知に共同化があり、形式知では表出化や連結化があり、そして、そこから暗黙知の内面化となり個人に落としていくというプロセス。形式知の二つは見えていたが、暗黙知についてはなるほど、確かにそうだなぁと経験から落とし込んだ。このプロセスがあることを意識し、メンバー配置することや、計画の評価の時期などを検討したい。
osamukondo
一般的には暗黙知は悪で、属人化を排除するために、マニュアル整備など進めますが、実は暗黙知と形式知は同じレベルで重要で、それを回転させていく運用が必要なのだと改めて実感しています。
sugi2024
SECIモデルについて参考になりました。
fu-ka-
暗黙知は心を開き深いコミュニケーションの下で共有が可能
t-96
暗黙知の教育は難しい
kanai_masa
SECIモデルには4つのプロセスがある
nx-nakamura
OJTの進め方において考え方としては活用できると考えます。
hayatokawamata
とても勉強になりました
mac24-evo
暗黙知をオープンにする風土とそれをどう形式知と組み合わせて情報公開することは結構難しいと感じました。
no-sugawara
「共同化」(Socialization)、「表出化」(Externalization)、「連結化」(Combination)、「内面化」(Internalization)という4つの変換プロセスを経ることで、集団や組織の共有の知識(形式知)となることを理解した。
katoh47
SECIモデルの考えに初めて触れたが、営業ノウハウなどは確かに暗黙知と形式知を組み合わせていかないと新しい知識として生かせないことから、今後のノウハウ共有の再留意して進めていく場期と考えられる。
_yk_
暗黙知と形式知の組合せについて、とても興味深い内容だった。いずれにしても日々のコミュニケーションは不可欠であると感じた
mzk9999
各部署が蓄積している暗黙知を共有する場を創出することを、プロジェクト進行の際に心がける。
iiom
PRにおいても同様のことが言える。
SECIプロセスは活用できそう
masa-32
機会に応じて適切な場を設定し4つのサイクルをまわしていきたい。
by03hiro
建築現場の監理行う上で問題となっている、現場ノウハウの取得において必要となるモデル。
弊社においては①から④の流れは実現できているような気もするが、特に①から②における連動がなされていない気がする。
表出化を行おうとする人が新鮮な現場の暗黙知を持っていない場合が多い(と個人的に感じる)。
もっと現場の最前線にいる人を表出化の場に関わらせるシステム作りが重要だと思う。
nico-nelo
営業が営業以外の時間に割くことが多く、個々人で暗黙知を持っており、血の共有が進んでいない。この部分をDXで解決しようとしている。
sada-k
暗黙知というのはどのような現場にあるものと思うが、非常に重要な知識となっていると思う。この暗黙知をしっかり共有出来る事が組織継承や建設的な組織運営には必要と感じる。
mimi123
ベテランと若手でコンビをくみ、暗黙知の共有から始めると良いことを学習しました
yka50
暗黙知を形式知化することで業務効率化にもつながり、かつ新たな知識の創造にもつながっていくことであると理解致しました。ただ、そのプロセスにおいては、必ず、<場>を設けることが重要であると理解できました。
masaka2-u
マニュアルが全てみたいな風潮があるが、実は「暗黙知」の共有があってこそのマニュアル(形式化)が重要であること、自身の所属部署における「業務共有化」においても実践していきたい。
kei-kawakita
共同化が始まることによって、それぞれの知見に影響が出てくると感じた。
相互に意見を聞き入れ、また発言することで暗黙知は浸透する場になるようなセッションを組み立てる必要性=若手+熟練の交流できる創発場が深耕することで企業の活性化が進むと感じた。
kanokoto
暗黙知、形式知に合わせた場の設定をおこない、知識を共有していきたい。
nexitaro
対話場というのは簡単そうで、その場の形成が難しいと感じた。共同化がしっかり行われていないと、知識の共有は難しく、対話場を設けても会議や打ち合わせのような環境になってしまい、逆効果になるのではと感じたので、場の形成に関してもう少し知識を広げていきたい。
o_k_d
ベテランの匠の技術や技は頭にインプットされ体に染み付いたものである為これまでは見て真似するしかそれを受け継ぐことは難しかったが、ITの活用による形式知化が可能になることで人材育成の場が広がり個人保有されてきた優れたものが財産として永らく社内で受け継がれより磨かれていけるようになることを組織作りにおいて活用する
yasu--ta
サイクリックに進める、何回も回すことが大事
yokouchitakashi
暗黙知を人に引き継ぐのが難しいのは現場作業においても、操配作業においても言えることです。相手の性格や知識によっても教えることや量が変わってしまうため、そのまま自分のやっていることを
伝えることは難しいと感じました。
morita5
SECIモデルがわかりました。
tsuboike
共同化に関しては新人メンバーや中途入社の研修時に意識していきたいと思う。
mondenmonden
属人化されている部分を標準化させるときに活用できると思いました。
kobahiro_1623
オペレーターの平準化が課題であったので、今回のSECIモデルのフローに従い、一度分析する必要があると感じました。
fumitoshi990055
暗黙知を暗黙知のまま共有すると言う考えは新鮮だった。いきなりの文書化は難しく、進める際の参考にしたい。
tomo5963
マニュアル化出来ない内容をSECIを利用して周りに共有し発展させていく
osakedaiski
暗黙知を形式知にするために、対話をする必要があることや、継続して行く必要があることを理解しました。
emewood
マニュアルに依存せず、暗黙知の形式知の共有について、学べた。
hohata
新規事業案の創出において、各部署が保有するナレッジを、形式知化して共有する。
noboru-
暗黙知と形式知にわけて考え現状共有していきたい知をどのように伝達していけばよいのかの参考となった
ya4594
SECIプロセスを回すには、各段階に適した方法が必要である
必要な場の設計を通じて、プロセスが回り続ける仕組みを作るよう心掛ける
tstuomu_ishii
暗黙知は暗黙知だと思う。暗黙知を簡単に共有できた見えるかできるものは、真の暗黙知ではない。
buddyhouse
まさに後輩を育てるにあたって、自分の暗黙知を吸収して欲しいと思っていたところである。そのためにはあまりにも後輩と時間的にも物理的にも共有できる接点がないため、来年の目標としてかがけていきたい。
tac_akiyama
マニュアルや手順書を作成し周知させることは行っているが、文書化できない感性や経験則である暗黙知をどれだけ浸透させられるかは、OJTという形式で実施してきたが、暗黙知、形式知それぞれの知識特性に合った方法で、活用・マネジメントすることが重要であり、場の設計を通じて、プロセスが回り続ける仕組みを作り、感性を活かし、論理を駆使して知識の共有を図っていく。
umeharu
SECIモデルは今まで知らなかったモデルなのでもう少し理解する事が必要と感じた
uno_hiromasa
SECIモデルの知識を、日常業務に活用したい
sk_ks
暗黙知は確かにマニュアル化できない。経験は大切な知識だと思う
yuki_nari
成果にばらつきが生じるのは暗黙知の共有が出来ていない事が原因ではないかと感じた。暗黙知を見える化させ共有する事が必要だと感じた。
izawa-shinken
SECIモデルは知識の共有化を実現するためによいものであると思いました。
今まではまずはマニュアルを作って、共有と考えましたが、最初の行動と最後の行動で暗黙知があることに納得をしました。
baseball_kids
①共同化:暗黙知→暗黙知をつくる:創発場:共通の経験、共同営業など
②表出化:暗黙知→形式知をつくる:対話場:プロジェクトチーム、エキスパート議論
③連結化:形式知→形式知:システム場:社内イントラ、ナレッジデータベース
④内面化:形式知→暗黙知:実践場:実践する
matsukem
知識の共有は課題として取り組んでいるが、その大半は形式知の共有であった
暗黙知の共有を強化していきたい
g911096
共同化、表出化のプロセスを飛ばして連結化しても有効ではないと再認識しました。
n-takemi
暗黙知と形式知を組み合わせて、知識の共有活用を図りたいと思います。
yo-hamabe
現状の業務を暗黙知・形式知に整理をし
組み合わせを考えながら行う
koga-chie
若手育成、新人育成、または、現場から好事例、失敗事例を吸い上げ効率化資源配分を行い、システム化し、実践に移す、その繰り返しを行う流れを暗黙知、形式知というプロセスで構成されている事が理解できました。組織レベル、現場レベルでも行えることも理解できました
nishi02
暗黙知の共有はどの場面(現場・事務)でも課題である
システムによる共同化をから推し進めると本質をも失うことがあるのではないだとうか?
連結についても何を選定するかで大きく成果はかわるのではと考える
koba0705
社内間で持ち寄ることでの、共同化は組織の仕組みに組み込むことが必要であり
会社として発信することが、継続的で有効な場として生み出されると思う。
haluhiko
自分の課題として、暗黙知を後輩へ伝える事が難しいと感じています。
rose24
経験者と若手が一緒に経験することで、暗黙知が共有されることがわかった。
konno_toya
今後の業務で活かせるようにしたいと考えております。
manaboo111
ナレッジマネジメントがうまくいかない際、SECIモデルのどのプロセスに問題があるか特定する事が大事だと思った。
問題のあるプロセスにおける具体的な取り組みを観察する事で、適切な打ち手を検討できると感じる。
macmacmosmos
SECIモデルの循環を意識して取り入れている工場の生産現場は、新たな付加価値を生み出す製品が誕生しやすいかもしれない。
y-okuyama
すぐにマニュアルの作成、文書化が社内で指示されるが、それ以前に暗黙知の共有が非常に大切であることを学ぶことができて良かった。
ishino_takashi
暗黙知と形式知のバランスが重要
950056
SECIモデルについて学んだ。普段、まったく意識していない考え方で、どのように活用すべきか、まだ完全には理解できなかった。
takamoto-
先ずは誰だどのような知識を持っているのか、不足しているのかを把握しないといけない。
yas_5953
このようなモデルは初めて知ったので新鮮だったが、よくよく考えてみたら普通にやっていることのように思えた。
kosuke_kawakita
なかなかシステムチックにここまでやるのは難しい(時間がすごくかかる)と思いました。
hidetoshi_amano
直接的に活用する場面はないが検討する
nx-watanabe
それぞれの場を用いた目的・取り組みを活かせる職場環境・対人関係を築き、自分に限らず同僚も同じく習得した知見の共有・スキルの向上に繋がる行動を日々心がけていきたい。
fuji124
暗黙知 と 形式知の対比は勉強になった。
eiichi_ikeda
暗黙知を得ることが組織の力量につながってくると思うので、形式知についてはマニュアルの作成を工夫して分かりやすいものとしていき、チーム内では暗黙知の伝承により力を入れていくことが必要。
masasi0226
感覚的な暗黙知と、実態ベースの形式知をどのように広めて円滑なマネジメントをするかの手法となり、特に人に伝えにくい暗黙知をどのように広めていくかに特化しているものであると認識しました。
daisuke_someya
様々な業務おいて暗黙知は必ず存在しているものなので、当社でもSECIモデルが活用可能かを検証してみたいと思う。