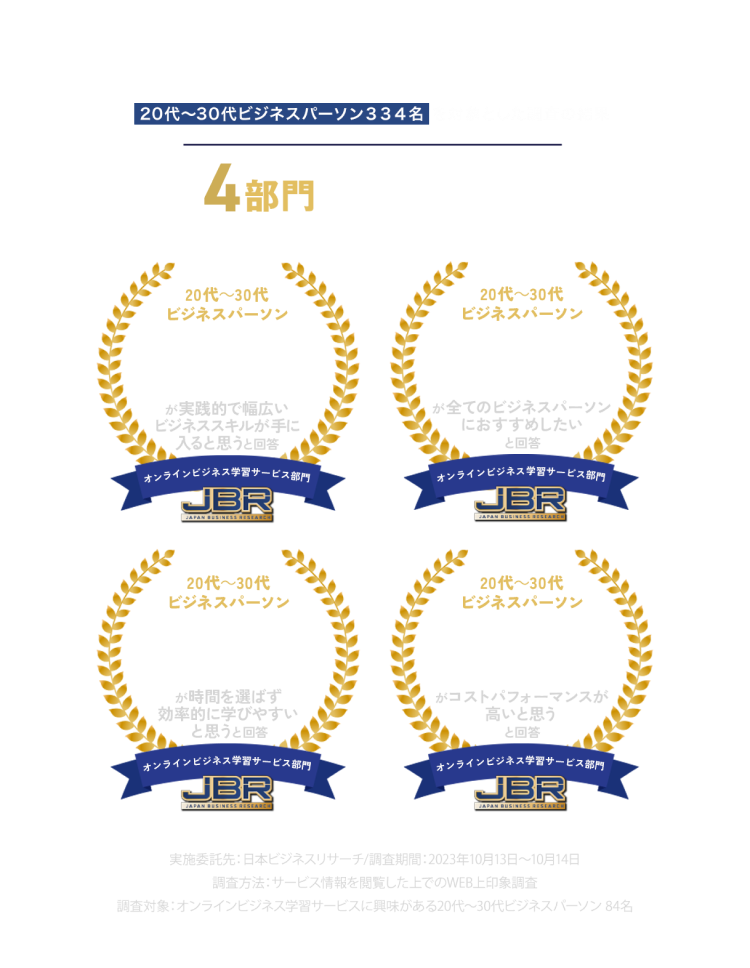タラップに足をかけると、熱気が頭からつま先までを包み込んだ。思ったより、空気が優しい。2005年4月10日、山崎一郎さん(当時39)はインドネシアのスカルノハッタ国際空港に降り立った。これから、インドネシア味の素グループの人事、総務責任者として、組織改革に挑む。上司から与えられた使命は、「グループを、会社として体を成す組織に変えて欲しい」。従業員約2800人、営業拠点は180カ所、大きな土俵を預かる日本人はたった、14人。ここ数日、大きな不安にさいなまれていた。
「労組で組織と人をサポートする裏方役を担ってきた自分にピッタリの職責とは思いましたが、異国の地で、ましてやリーダーとして現地のスタッフを引っ張っていけるのか」
* * *
インドネシアは、味の素にとって因縁の地。あれは2001年。まだ松もとれない1月4日のことだった。
衝撃的なニュースが飛び込んできた。インドネシアで、味の素製品がイスラム教の戒律で禁止されている豚肉成分を使用しているとして、騒ぎになっているらしい。当時のメディア各社は連日、波紋が次々に広がっていく様を大きく報じている。
全製品の回収命令、現地当局による従業員の聴取、工場の操業停止等々、……。最終的には、原料を替え認証を取り直すことで、1ヵ月後に事態は収束した。
アジアは重要な戦略地域。海外食品事業の売上高は全社売上構成比の約10%を超え、その約8割がアジア地域に集中している。1950年代後半からのこの地域への進出により、一気に家庭の調味料として東南アジアで普及が進んだ。一時期は、日本人観光客が街を歩いていると、「AJINOMOTO」と声をかけられるとも言われたほどだ。
豚肉成分騒ぎから数年間は、1000人以上の営業担当者がインドネシア全土をくまなく回り、味の素の製造法を説明、地方の農村での巡回映画会にも出向き、イメージ回復に躍起になった。その結果、「味の素」やインドネシア市場向け風味調味料「MASAKO(MASAK=料理する)」は業績を回復した。
社内のリソースが売上及びイメージ回復へと向けられたため、いくつかの組織構築や人事施策は実施されていたものの、十分ではなかった。業績が回復し、こうした人事、組織の取り組みに地道に取り組める人材が必要とされ、労働組合を経験した山崎さんに、白羽の矢が立った。
健全な組織を目指して

闘いは、社内で起きた不正事件への対応から、始まった。
インドネシアなど途上国では、数多くの企業が現地スタッフの不正に苦しんでいるといわれる。手口は様々。完成品を持ち帰る。領収書を書き換えたり、売上をごまかす。会社の規模が大きく、歴史が長ければ長いほど、監視の網のすき間も、大きくなる。
インドネシア味の素グループもまた、例外ではなかった。山崎さんは、様々な情報や噂、内部告発などから不正の端緒をつかむと、外部の警備会社に内部調査を依頼した。背景や真相が徐々に浮かび上がってくる。10月には、直属の部下である人事部長が不正に関っている可能性があることが分かった。
人事部主催の3日間の幹部研修の後。人事部長をホテルのカフェへ呼び出した。「研修ご苦労さん」と声をかけた後、つたないインドネシア語で、異動の話を切り出した。実質の解雇通告。「全く理解できない」。大声でまくしたてられた。文化の違い、考え方の違いにより、理解しがたい溝を感じたが、何とか通告した。
帰りの車の中。携帯電話で、上司に報告した。「よく頑張ったな。お疲れ様」。人を解雇する経験は日本ではほとんどといっていいほどない。その痛みを知っての、ねぎらいの言葉だった。携帯電話を握り締めながら、涙が溢れてとまらなかった。
最終的には翌年の1月に関係者がはっきりした時点で、複数の従業員に退職してもらう形で、この事件は一応解決した。
当時内部調査を行った警備会社の担当者(46)は言う。「インドネシアだけでなく、多くの途上国で現地スタッフの不正が起きます。背景にあるのは貧困なんです。子供が産まれた、家族が病気になった。目の前に1カ月分の給料の商品が流れている。つい手をだしてしまう。そういうきっかけで始まります。山崎さんもそのことを分かっていたから、辛い決断だったと思います」
マイナスをゼロまで引き上げる

インドネシアに赴任してから1年が過ぎると、ようやく仕事も一巡し、様々な施策を実施する下地が整った。
組織運営の基本的なポリシーを三つ掲げた。
「良い労働環境」
「ルールを整備する」
「公正な評価」
はじめに手をつけたのは、社内規程の整理。外部の信頼できるコンサルタントと連携し、インドネシア国内にある本社、4支店、1工場の間での規程の違いを項目ごとに調べ上げ、運用の違うものを洗い出していった。
驚いた。
医療費の計算方法、早期退職対象の年齢、残業代の計算方法、子供手当ての人数制限、病欠中の賃金支給など、次々と相違点が明らかになっていく。「やはり、ひとつの会社としてはまだまだだな」。違いの一つひとつを一本化したドラフトに揃えていくとともに、様々な情報を本社で管理、コントロールするような仕組みが必要と、強く感じた。
そのひとつが、全従業員データ管理と給与支払をインドネシア本社に集中させる取り組みだ。将来のデータの更新にも役立ち、支店の支払業務も軽減することができる。日本であれば一見シンプルそうな作業だが、インドネシアではまず、従業員に銀行口座を開設させるところから始まる。
元々給与を現金払いしている事業所が多く、ほとんどの従業員は銀行口座を作ったことすらない状況では、号令をかけてみたところで、組織は動かない。趣旨を理解してもらい、浸透させるためには、地道なコミュニケーションの繰り返しが必要となった。
まずは各支社の人事総務担当者を納得させなければ、下に伝わっていかない。日本人であればすぐに理解できる「三つのポリシー」を伝えるにも、工夫をこらし、現地の人が好きなサッカーに例えた。「もし地面がでこぼこだとプレーヤーは気持ちよくプレーができない。ルールがあいまいでは正しい動き、判断はできない、ジャッジが迷っているといい試合はできない」と、ことあるごとに話し続けた。始めは興味なさそうに聞いていたのに、サッカーの例えに変えると、目つきが変わった。
また外部の調査で指摘された“コミュニケーションギャップ”を埋めるための「補助階段作り」にも力を入れた。末端のスタッフからみれば、自分のポジションは雲の上の存在。ましてやインドネシアと日本の文化、価値観、背景の違いを考えれば、こちらの意図は想像を絶する壁に阻まれる。長い歴史の中で始めて、インドネシアスタッフを日本へ“逆駐在”させたり、本社内に数人の日本在住経験者を採用・配置することで、コミュニケーションの“のりしろ”として、活躍してもらった。
全従業員のデータ管理と給与支払いシステムは、2010年4月完全実施を目標に現在そのプロセスを進めており、ルール統一された規定も徐々に浸透している。組織が、少しずつ変わりつつある。「マイナスからゼロにする仕事」と山崎さんは謙遜するが、その目線の先には、キャリアを通じて追い続けてきた、組織と個人の“幸せな関係”が、ある。
モノでなくヒト 生き方を見つけた

平均的な“サラリーマン”からみれば、少し異色の経歴かもしれない。それはずっと自分の中の違和感を大切にしてきた、証でもある。
早稲田大政経学部では、周囲の学生がバブルに浮かれる中、夏休みには、長野・菅平でレタスの収穫のアルバイトで汗を流した。労働して、現場で働いて、結果が収穫になることがとても気持ちが良かった。経済学の著名な教授のゼミに在籍しており、同期が次々と人気の高い金融機関に就職を決める中、「派手なものはどこか違う。生活に身近なビジネスをしたい」と、味の素を選んだのも、自分らしい。
社内では、入社以来5年間外食用営業、その後、本社マーケティング担当として、かまぼこやハムなどに使用する大豆たん白製品、業務用の油脂製品などを担当した。研究、製造、営業までトータルでコーディネートする新製品開発にも取り組んだ。でも、自分が開発した商品が全国的に売れても、不思議と心のそこから喜びを感じない。「このままでいいのか」。自問自答する中で、当時の本社支部長から誘いを受けていた労働組合で、専従組合役員になることを決めたのだった。
他の企業では組合が“出世コース”のこともあると言われるが、味の素の組合には、決してそんな華やかさはない。大部屋にたった2人が、席を構える。
専従の本社支部長としては最長の5年間、社員と組織を裏側から見守った。旭川から1日3本しか電車がないところまで、組合員の家族の葬式に出向く。借金を抱えた組合員と一緒に返済計画を作成し、毎月チェックした。病気を抱える家族がいる組合員の相談に乗ったり、職場での悩みを泣きながらしゃべる組合員の相談相手になったこともある。
従業員の家庭事情に触れるたび、皆、会社では普通の顔をして机に向かっているけれど、様々な背景を抱えながら仕事をしているんだと、痛感した。
「社員を仕事としてサポートしているうちに、この仕事が自分の生き方、価値観とフィットしているなあと感じるようになりました。自分が関心があるのはモノではなくて、ヒトなんだと気づいたんです。人間辛い事があっても、支えあう仲間がいると、また浮上できる。会社って最近はドライなところになりがちだけど、皆が支えあうような組織にしたいですよね」
理想の組織への想いが募ると、それを一つの提案にまとめ上げて、経営陣に納得させるだけのスキルがないことに気づいた。「ふだんは文句ばかり言っているくせに、公式の交渉場所では経営者の方々に全然叶わないなと思いましたね。やっぱり現場を知っているだけじゃだめだと。経営のスキルみたいなものを身につけないと同じ土俵に立てない」
ビジネススクールに通い始めたのはそのころだ。数々のケーススタディーをこなしていくうちに、事実の羅列をグルーピングし、そこから何が言えるのか考える頭の使い方が身についた。
「正直、こんな場所があることに純粋に驚きを感じました。自分は全く武器を持たずに今まで仕事をしていたんだということがよくわかりました。自分に足りないものを痛切に感じているときだったので夜間スクール通いも何とか継続できたんだと思います」
組織と人に対する熱い想いと、経営を俯瞰する眼を養った。インドネシアで組織作りに携わることは、自分の想いを実践の場で生かす、最高の舞台だった。
現地スタッフの自主性を引き出す

組合やビジネススクール、そしてインドネシアでの経験を通して、人と会社の距離感について考え続けた山崎さんには、一つの結論がある。
どこの会社にいってもやっていけるだけのマーケット・バリューを持った人材を育成しながら、その人材をずっと引き留め続ける魅力的な会社であること。二律背反のようだが、両立しないと、強い組織はつくれない。
組織として人を守るのに充分な基盤が整った今、個々の能力を引き出す試みも始まっている。その象徴が、毎週部長クラスを集め行っている「井戸端会議マネジメント」だ。
テーマ、やりたいことを説明したうえで、「私では実現のためのプロセスを作るのは無理があるので、手を貸して欲しい」と意見を求める。そうやってしゃべれる「場作り」をすると、普段めったなことでは自己主張をしない現地スタッフが生き生きと意見を主張し始める。やる気や主体性をうまく引き出せていると、実感する瞬間だ。
最近は、そういった井戸端会議を仕切れる人材の育成にも力を入れている。副社長という立場上、現場のスタッフの育成にまで口を挟むのは若干気が引ける。直に接して自己成長に協力できるのはマネジャークラスまで。その層が仕事のプロセスや意識を変えれば、カスケード式に組織が進化を遂げるきっかけになりえる。
女性の総務部長がいる。とても優秀でヘッドハンティングで引き抜いた人材だが、担当分野のすべての会議に顔を出し、多くの仕事を抱え込んでしまうタイプだった。重要な定期会議の際には、「会議の間は自分の机に座っていること。部下を信じて、彼らが結果を持ってくるまで待ちなさい。方針徹底、報告は会議の前後に時間を取って個別に行うこと。その方が明らかに効率的だし、責任を感じて部下も育つ」と繰り返しアドバイスし、今、ちょっとずつではあるが、彼女もその部下たちも、変わりつつある。
指示待ちの仕事が当たり前のインドネシア人を育成していくには、日本人よりも数倍の時間がかかる。それでも価値観を押し付け、管理することにさほど意味はない。部下と方法についての意見が異なっても、結果にある程度の歩留まりを設けたり、万が一失敗したときのことも考えておけば、ある程度は安心して任せられる。たとえ小さな仕事でも、最初から最後まで自分で仕事をコントロールした経験は、将来にきっと役立つはずだ。
もちろん、仕事の成果に責任を持つ立場として、リスクもある。でも、その後には必ずいいことがあると信じている。現地スタッフの内にある能力を引き出すために、「絶対あきらめない」と自分に言い聞かせている。
「日本人スタッフが具体的な指示を出し続けていたら、何年経っても仕事の幅が広がらない。現地の人が自ら問題を発見して、解決していくようにしないと、この国の競争には勝っていけないんです。それが2800人全員に行き渡るかどうかわかりませんが、今種を蒔かなかったら、10年後も花は咲きませんから」
心の拠り所になる組織を目指して

ただ、心配もある。インドネシアでは優秀な人材はすぐに流出してしまう。手塩にかけて育てた部下が引き抜かれてしまう可能性もある。では、会社と個人のかすがいになるものは何か。制度の透明性や公平性といった基本的なことはもちろん、組織の懐の深さが重要ではないかと、感じている。
山崎さんが、ひそかに楽しみにしている“儀式”がある。
日本人スタッフが帰国するとき。現地スタッフが、当時日米で絶大な人気を誇ったアンディ・ウィリアムスの出演で話題を呼んだ60年代のCMソング「マイファミリー『AJINOMOTO』」を、インドネシア語で歌ってくれるのだ。
「いつでもどこでもわすれないあのころあしたもかわらないマイファミリーあじのもと」
日本ではとうに忘れられ、化石となったCMソングだが、ここではずっと歌い継がれている。肩を組んでにこやかに、そして誇らしそうに合唱するインドネシアスタッフの姿が、どこか懐かしく、ほほえましい。高度成長期、会社は一つの共同体だったことを思い返す。
今、周囲を見渡せば、会社組織は以前と比べドライな場所になりつつあるのかもしれない。でも、同僚が抱える様々な背景を知り、一人の人間として付き合うような、ウェットな関係も必要だと思う。
「仕事がバリバリできる人でも、飲みに行くとポロッと愚痴をこぼしたりする。人間弱くなるときは必ずあります。正直自分も、組合の時はとんがっていて、色々な人に叱られ、支えられて、ここまでやってこられた。少し変わっていたり、異質だったり、弱くなったからといって排除するのではなく、何かあったときには、支えあう組織であってほしい。互いに深く理解しあっている仲間に囲まれた組織こそ、個を幸せにできる“心の拠り所”になるのではないでしょうか」
10年後、インドネシアスタッフはどんな成長を遂げているだろう。この3年間で皆と築いた骨組みの上に、それぞれの従業員が、自分の特徴を生かしたデザインを施し、前を歩いた人がふと振り向くような、思いも寄らない建物に創り上げてくれているといい。
自分が違和感という不確かな綱を手繰り寄せ、居場所を見つけたように、会社という組織に身を預けつつ、なお独自の花を咲かせようとする気概を、と思う。そして、そのときも、「マイファミリー『AJINOMOTO』」を口ずさんでいてほしい。
強い組織を創るため、この国で自分がやるべきことは、まだまだたくさんある。
オリジナルのフレームワークやマトリックス、赴任中にやりたいことなどを書き込んできた小さなメモ帳は、今、63冊目になった。