日本人でありながら名門シカゴ大の社会学科長(20数名の教授陣を率いる)を務める山口一男氏が「ダイバーシティ(多様性)」についてヒントを提示した一冊を取り上げる。「寓話」は社会科学の書籍にとってどのような武器となりうるのだろうか?

今回、本書を紹介しようとした理由は大きく三つある。
第一の理由は、本書が「寓話」という方法論を積極的に採用している点である。書籍の書き手、作り手でもある筆者にとって、寓話の持つ可能性を確認、再発見させられた点で興味深かった。第二の理由は、後半パートの寓話を用いたディスカッションの描写が非常にエキサイティングだった点。そして最後に、「ダイバーシティ(多様性)」というテーマを議論するのに、本書のような形式をとった著者・山口氏の戦略や新鮮さに強く印象を受けた。
さて、本書は「寓話」という表現形式を軸に、大きく二つのパートからなっている。前半のパートは、「六つのボタンのミナとカズの魔法使い」というサブタイトルがついている。まさに寓話そのものがメインであり、主人公であるミナの冒険を通じて、さまざまな社会学的、論理学的テーマ(「囚人のジレンマ」「合成の誤謬」「ベイズの定理」、そして「ダイバーシティ=多様性」など)について気づかされたり、考えさせられる構成になっている。そして長い寓話を読み終わった後に著者の理論的な解説がつく、というスタイルだ。
後半のパートは、「ライオンと鼠」という短い寓話を提示した上で、教授のファシリテーションの下、学生たちがディスカッションをするシーンを実況中継的に描いている。面白いのは、一つの寓話のみをディスカッションするのではなく、日米それぞれのバージョンの「ライオンと鼠」の寓話を紹介し、さらにその差異や共通点から何が見えてくるのか(例:日米の比較文化論など)、その意味合いを学生たちが激しく議論するとスタイルとなっている点だ。
しかも、最後に親切に要点の提示があるわけではない。読者は、その実況中継そのものの中から、さらに言えば、自分自身もその議論に参加したつもりになって、自分なりの発見と思考の整理をしなくてはならない。
グロービスの受講生の方であれば、この方法がケースメソッドに酷似していることがお分かりいただけるだろう。しかも、日米それぞれの寓話について、学生(アメリカ人)と著者(日本人)が、さらに現代風の要素も盛り込んで、新しいバージョンを作り、それを議論するという追加もある。つまり、「ライオンと鼠」という寓話について、合計4つのバージョンが紹介され、聡明な学生の議論の俎上に載るわけだ。面白くないはずがない。
読者に響く本作りに脱帽
さて、著者によれば、前半のパートと後半のパートは相互補完して一つの主張を成す不可分のパートだと言うことであるが、小職の素朴な感想を述べれば、前半の寓話「六つのボタンのミナとカズの魔法使い」は、ビジネスパーソンに対してはやや安易すぎる印象を受けた。大学の学部生などにはちょうどいいのかもしれないが、寓話と呼ぶにはややテーマとの関連性が明確すぎて、それほど強い感激は受けなかったというのが正直なところである(もちろん、これだけの寓話を様々な理論と結びつけながら作るにはかなりの知見や力量を必要とするのは分かるのだが……)。寓話は、あまりにダイレクトすぎると、かえって白々しく感じるという思いを逆に持ってしまった。
さらに言えば、前半パートの「六つのボタンのミナとカズの魔法使い」は、タイトルからも分かるとおり、日本でも有名な「オズの魔法使い」へのオマージュであると思える。「オズの魔法使い」は、単なる面白い物語として読まれることも多いが、その深層には、当時米国で政治問題化し、大統領選挙の争点ともなった「銀貨の自由鋳造」の論争に対する問題提起や揶揄が込められているというのが研究者の定説だ。そのことを知っているだけに、かえって今回の寓話は短絡すぎる印象を持ったのかもしれないということは付記しておく。
後半は一転して、非常に興味深かった。これは小職が、ケースメソッドと言う「議論を軸にした学びの方法論」に日常親しんでおり、考えているからかもしれないが、それを割り引いてもインプレッシブだった。しかも、これが大学院生ではなく、学部生によるディスカッションであるという点は、日米の教育事情やディスカッションに対する慣れの差はあるにせよ、新鮮な驚きである(グロービスの受講生にも、ぜひ心してほしい)。
本パートについては、下手な解説よりも、実際に読んでいただき、議論や対話で学ぶことの意義や効果を実感いただくのがいいように思う。
注目されるのは、著者自身は決して自分の主張や見解を押し付けていないことだ。「ダイバーシティ」という重要なテーマに関する題材と、それを考えるヒントは提供しつつも、そこからどのような結論や示唆を導き出すのかは、基本的に読者に委ねられている。書籍の作りとしては非常に斬新であるが、同業者として、大いに可能性を感じさせられた。
同時に感じたのは、著者の楽観的な姿勢、あるいは人間の可能性というものに関する温かな目線である。近年の社会不安もあって、往々にして社会科学者の論調も悲観的になりがちだ。しかし、本書からは、そうした悲観論は全く感じられない。大きな問題があるのは認めながら、人類には、それを乗り越えるだけの英知があるし、議論や対話がそれを加速するというスタンス(あるいは著者の信念)は、小職も強く共感するところである。
いずれにせよ、「ダイバーシティ」という難しいテーマを、読者に提示しつつ、最小限のヒントでとどめ、あとは読者に考えさせるという方法論は、極めて有効であるし、読者にとっても得るところが大きいのではないかと強く感じた。
最後に付け足しだが、イラスト(挿絵)の凝り具合というか印象も、本書を親しみ易い書籍にしている一要因といえる。様々な意味で、「読者に響く本の作り方」を考えさせられる一冊であった。


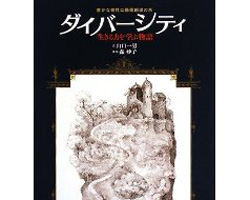














.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

