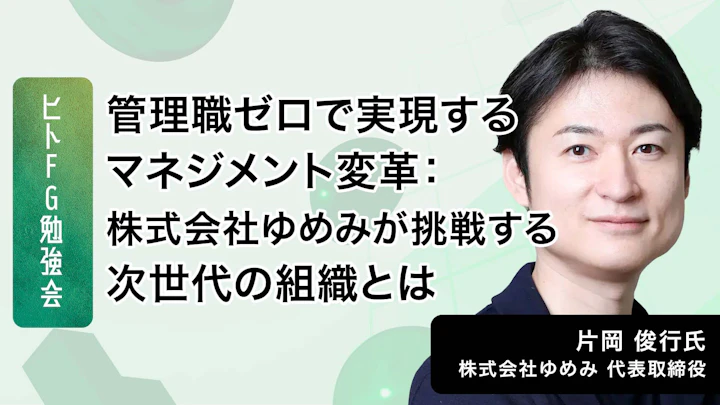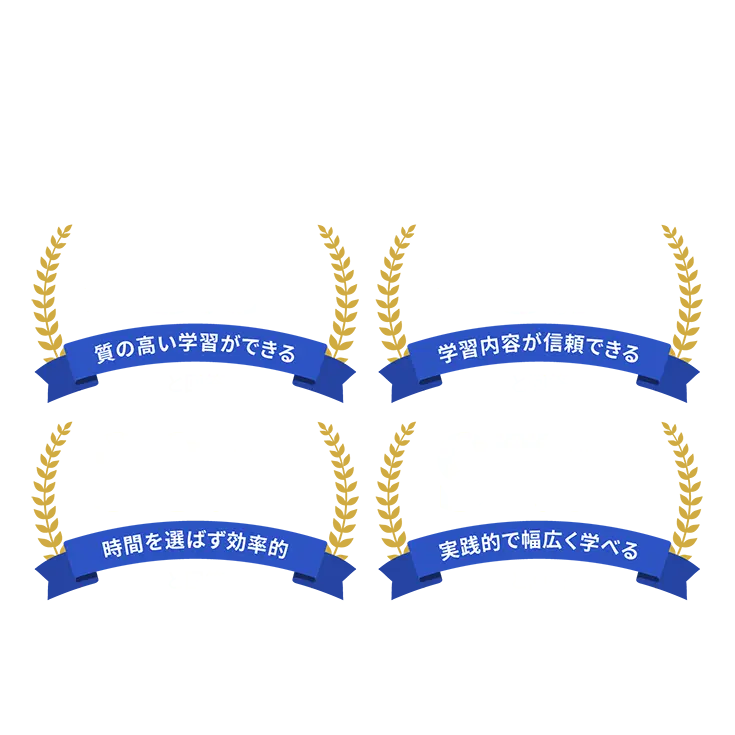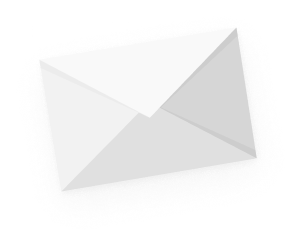前回は、日本GE株式会社の新野昭夫氏には、製造業におけるIoTの導入をテーマに、また、SAPジャパン株式会社の馬場渉氏には、ドイツ発の「インダストリー4.0」の文脈における今日的な産業改革についてお話いただきました。今回は、それらを踏まえて、ローランド・ベルガー代表取締役の長島聡氏が、日本の製造業へのインパクトを俯瞰的に総括します。(第2回/全3回)
第4次産業革命がもたらす製造業の新たな進化形[2]
秋山咲恵氏(以下、敬称略): GEやSAPは、インダストリー4.0へのチャレンジのなかで直面する課題を、どのようにクリアしていらっしゃるのだろう。
新野昭夫氏(以下、敬称略): GEにはもともとトップダウンが非常に強いというカルチャーがあるし、デジタル化もトップダウンではじまった。実際、私自身も日本のお客さまといろいろお話をしていて、IoTのように先々が予測しづらいようなことはトップダウンの力がないと成功しづらいと、肌で感じている。
グローバルで見ても日本の現場には非常に優秀な方たちがいらっしゃる。ただ、その現場からボトムアップで進めようとしたことが、最終的な決済のところでトップダウンの力がないために実現に至らなかったという事例もいくつか見てきた。やはりトップダウンの力は不可欠だ。GEではトップがそうしたメッセージを全社員に繰り返し伝えている。
それともう1つ。GEはデジタル化と同時に「リーン・スタートアップ」の考えかたを取り入れている。また、仕事の進めかたに関しても「ファスト・ワークス」という考えかたをベースにして、お客さまにアプローチしている状態だ。これはシンプルな話だけれども、つまりはお客さま指向でアプローチするということ。そうしてお客さまのニーズやペインポイント(課題)、それらについて一緒に考えながら答えを見つけ出す。とにかくスピード感を持って進めている。完成品ではなく60%の出来でもいいから、プロトタイプの段階でお客さまに提供してダメ出しをしてもらおう、と。
そこでダメ出しがあったからといって失敗というわけじゃない。ピボットということで方針を転換すればいい。そこで学びとともに進めたら、さらにお客さまのニーズへと近づける。そういうことを全社員で徹底的にやっているという部分はGE特有かもしれない。
秋山: 「徹底的に」という部分で、「GEはここまでやっているんだ」といった具体的事例がもしあれば、差し支えない範囲で教えていただけたらと思う。
インダストリー4.0の加速のために、人事評価制度を劇的に変えたGE

新野: まずはトップのCEOからフローダウンしてくるわけだけれども、各レイヤーに対しては今後の方向性に関する周知徹底を繰り返し行う。加えて、全社員に対する教育のプログラムと評価制度…、これが非常に重要だけれども、デジタル化のマインドがないと人事評価にまで影響するという仕組みもつくっている。
以前、GEには「9ブロック」という人事評価制度があった。下から10%の「ボトム10」と言われる人間は去らなければいけないという、ちょっと有名になり過ぎた評価制度だ。我々はそれを一昨年、完全に廃止した。今後は点数をつけず、いろいろな人が評価していく。それも年に1度や2度でなく、適宜、「これは良いね」「これは直したほうがいいね」といったことを互いに言い合うような文化にしていった。そのうえでデジタル化を進めている。
秋山: SAPさんのほうはどうだろう。先ほどのお話からは、かなりトップダウンのキャラクターが強いという印象を受ける。実際のオペレーションやトレーニングとして、「具体的にこういう風にしている」といったお話があればぜひご紹介いただきたい。
イノベーションは、トップダウンでは起こらない
馬場渉氏(以下、敬称略): まず、基本的にイノベーションはトップダウンで起こらないと思っている。「変革やイノベーションを量産する会社になるぞ」ということ自体はトップダウンでやる。ただ、個別のイノベーションに関しては、トップダウンではなかなか…、“なかなか”どころか、トップダウンで生まれると思うほうがおかしいというほど、そのやり方は違うんだと思う。
あと、GEさんの「徹底的」という部分について…、ご自身で言われるのもアレだと思うので、私からも少し補足したい。去年か一昨年か、GEジャパンの熊谷社長や日立製作所の中西会長と、第4次産業革命をテーマにしたパネルでご一緒したことがあって、その控室で面白いお話をした。「GEとSAPにあって日立にないもの」というお話だけれども、日立を「製造業における代表的な日本企業のほとんど」と読み替えていただければと思う。
そこで感じたのは、GEやSAPは働き方や社風、あるいは「ものの捉え方」のトレーニングといったことを徹底している点が、日立または日本企業と違っているという点だ。たとえば、ご自身もアメリカに長くいらして、すごくグローバルな視点をお持ちの中西会長も驚いていたことがある。GEはまさにファスト・ワークスを掲げ、千数百人をシリコンバレーで採用していたわけだ。
で、そこでイメルトCEO以下経営幹部の方々は、Gパンで仕事をしているシリコンバレーの若いお兄ちゃんに「デジタル時代ってこうなんです。これからの経営はですね~」なんて講義を受けていたという。普通に考えたら、「GE…、ですよ?」みたいな。GEのシニア・エグゼクティブがシリコンバレーのお兄ちゃんにこれからの経営論なんていう話を聞いたりする、と。かなり徹底している感じでしょ? トップがそういうことをしている。すごいと思う。
新野: それは事実ですね。
馬場: ですよね。そういうことを日本企業はやらない。トップは知ったつもりになって、「じゃあ、君たち勉強しなさい」なんて言って。でも、そこでトップが本当に心から覚醒して信じ切っているかどうかというのは、人間同士の会話で伝わる。そこで本当に、なんの疑いもなく、「私は第3次産業革命時代の延長上にある戦闘能力にすがる思いはない」と腹を括った経営者がどれほどいるのか。
誰かひとりでもそういうことを感じたのなら、それをまずは直接会話する10人ほどのボードメンバーに話す。それが、次は間接的にしか会話をしないような30人や50人、100人や300人に伝わるわけだ。当然、これは2年や3年かかる。でも、それをやっている会社とやっていない会社では、なんというか、「火が付いているかどうか」という点で違ってくる。
私どものケースで言えばそれはデザインシンキングだった。それを創業者以下、トップダウンで行っていった。ボトムで誰かが突然感じた「これはパラダイムが違うぞ?」ということを共感・共有し、それを全社員に徹底的に叩き込んでいこう、と。そのために当時は7万人の社員全員で「総アントレプレナーシップ計画だ」と。「シリコンバレーの起業家のようなマインドセットを7万人全員が持とう」「もうサラリーマンじゃありません」といったことを教育で実現していった。そこは徹底していた。…で、質問はなんでしたっけ(会場笑)。
秋山:SAPが具体的にどういった感じで進めていったのかな、と。
馬場: 外向けでない社内改革の話でいいですか? 整理すると、まず私どもは創業40年ぐらいの地味なドイツ企業だ。非常に地味で、なんというか、堅く、スローな会社だった。それが、シリコンバレーに対するここ10年ほどの投資でたしかに変わっていった。
では、我々はどのように変わったのか。まあ、ある意味では教科書通りだと思う。先ほど別セッションでコニカミノルタの松崎会長がおっしゃっていた、外側でスカンクワークス的に行っていくという方法だ。ど真ん中のメインストリームは変わらないから外側から」というお話だったけれども、我々もドイツの本体でなくシリコンバレーで行っていった。
そうして我々は社内改革を進め、ある種のメソッドを確立していった。その結果として「“イノベーションのジレンマ”というのは、もはや難病ではなく治る病気なんだ」と。その治し方を、体験談および方法論とともに提供するという、ある種のビジネスモデルを構築したというのが今の状況になる。
ただ、「シリコンバレーで」と言っても、そこが数千人の組織になれば、そこはそこでまた官僚的になる。だからパロアルトという街にあったオフィスからも離れて、そこから車でさらに15分ほど行ったところにある住宅街のロスアルトスでやろう、と。そうして、パロアルトにて自由闊達でやんちゃな、カウチソファーが並ぶ、いかにもスタートアップというようなオフィスをつくった。そんな風にして外側でも進めていくというのは、王道中の王道なんだと思う。
ただ、それによって外側が盛りあがっても、「じゃあ本業は再生したっけ?」という話になる。そこで大企業の場合は失うものがあるわけだ。新しい会社であれば失うものがないから、「No Software!」という感じでドーンと行っていいと思う。けれども我々はそういうわけにいかない。
だから、外のスカンクワークスが成長してイノベーションが起きるわけだけれども、それをどこかのタイミングでぐっと、中の本体側に入れる必要がある。また、それで「本社に吸い込まれたよ」という風にせず、主従を逆転させないといけない。その3ステップだ。ある種のインダストリー4.0的な事業を外でつくった。ただ、7万人の給与を払っているマジョリティは3.0のパラダイムだから、外でつくった事業を中に入れた。で、そこで3.0に吸収されるのでなく、タイミング良く主従逆転させていった。我々に関してはそういう感じだった。
秋山: 他セッションで、事業転換に関連して松崎会長から、「やはり主力事業のど真ん中にいる人には新しいもの、あるいは従来とまったく違うものを生み出すことがなかなかできない」といったお話があった。「だからセンターから外れたところでやらせよう」ということで、イノベーションセンターをサテライトに5ヶ所ほど置いた、と。GEさんにしてもSAPさんにしても、まさにそういうことを実行していらっしゃるわけで、これもひとつのやり方なのだと思う。ただ、「じゃあ、それをやればいいじゃん」というだけでは、なかなか進まないという部分もあると思う。長島さんにはその辺も伺ってみたい。
イノベーションをどう量産できるか。日本企業の課題

長島: 日本企業に関しては、「現場が強く、しっかりとものを考える人が現場にたくさんいる」という風に感じている方が多いと思う。実際、私もいろいろな日本企業の方々とお話をして、そういうことを感じる。ただ、結果を見るとイノベーションは量産できていないわけだ。なぜか。個々人で持っているものがなかなか表に出てこない。すべて個人のなかにある。「職人芸」という言葉が適切かどうか分からないけれども、個人で何ができるか、周囲に見えていない。見えていなければ、それと別の何かの組み合わせでイノベーションが生まれることもない。だから、相当にもったいない状態なのだと思う。
上流部分も含めて、イノベーションの種になることは日本の現場にたくさんあると思う。でも、一方では個々人の視野が狭かったりする。「誰がどんなものを持っているか」「お客さまがどんなことを感じているか」といったことにまで視野が広がっていない。あるいは、他の人のこと、あるいは自身が所属する部署以外のことを知らない。そういう状況のなか、とにかくいま与えられている業務を突き詰めるというようなことになっているのだと思う。
ですので、少し楽観的な言い方だけれども、タレントが揃っている日本企業であれば、個々人が視野を広げて機動力を高めればイノベーション量産もそれほど遠い話ではないのかな、と。デザインシンキングを含めて身に付けなければいけない技術は多い。ただ、量産を目指すという意味では日本も捨てたものではないのかなと思っている。
秋山: ポテンシャルは決して低くないというご指摘だった。逆に考えると、それぞれに歴史や背負ってきたものがある日本企業にとって、今は何が重荷になっているのだろう。
長島: 成功(体験)だと思う。過去、たとえば自動車産業はしっかりとしたピラミッド構造をつくり、それによって与えられた安心・安全という感覚のなか、皆がスピードを持って与えられた役割をやりきっていた。そうして平和で収益の上がる世界があったのだと思う。
でも、今は車で言えばモデルチェンジのサイクルがどんどん早くなってきた。昔はフルモデルチェンジとマイナーチェンジぐらいだったものが、イヤーモデルの投入、さらにはランニングチェンジといったことまではじまってきている。モデルとモデルのあいだで変えなければいけない部分も増えてきて、よりスピーディーな価値の変化が求められている。
そうした状況になって、今申しあげた役割分担がむしろ硬直化して機能しなくなってきている。で、そうなるとSAPさんやGEさんがやっているような、いろいろなものをあらかじめ標準として持っておいて、その組み合わせで物事をつくる必要が出てくる。「ありものの組み合わせでつくる」ということをそれなりに取り入れていかないと、現在のスピードについていけなくなるのではないかと思う。
※この記事は、2016年11月3日にグロービス経営大学院 東京校で行われた、G1経営者会議2016 第4部分化会「第4次産業革命がもたらす製造業の新たな進化形」を元に編集しました