
0:59:48
割引情報をチェック!

AI BUSINESS SHIFT 第8回 機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第8回です。 第8回「機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル」では、AIが営業現場にどのような変化をもたらしているのか、営業担当者・営業マネージャー・組織としての役割や戦略が、AIによってどう進化していくのかを、営業プロセスの分解や実際の現場事例を通じて学びます。 ■こんな方におすすめ ・AIを活用した営業活動の最新動向や現場のリアルを知りたい方 ・営業現場の変化に直面している営業マネージャー・現場リーダーの方 ・AI時代における営業戦略や営業マネジメントのあり方を学びたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年2月制作)
会員限定

マネジャーのための仕事の任せ方
「仕事を任せると失敗が怖い」「自分でやった方が早い」マネージャーとしてメンバーやチームの力を引き出しながら成果を上げるには、どのように仕事を任せていけば良いのでしょうか? 変化の激しい時代において、マネージャーとして成果を上げ続けるためには、メンバーの個性や特性を理解し、それに合わせた効果的な任せ方を身につけることが重要です。このコースでは、ソーシャルスタイル理論を活用してメンバーごとに最適なアプローチを学びます。「任せる力」を高めることで、チーム全体の成長を促進し、自身のリーダーシップを発揮できるようになっていきます。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2024年12月制作)
会員限定

AI時代の個人力
AIが仕事や社会の前提を変え続ける今、最も求められるのは「他者に代替されない個としての力」“個人力”です。 本コースでは、澤円氏の著書『個人力』をもとに、AI時代をしなやかに生き抜くための「前向きな自己中戦略」を学びます。 テーマは、「Being(ありたい自分)」を中心に据え、自ら考え(Think)、変化し(Transform)、協働する(Collaborate)ことで、自分らしい価値を発揮していくこと。 リスキリングやAI活用が叫ばれる今こそ、スキルより先に“自分の軸”を問うことが重要です。 あなたは何を大切にし、どんな未来を描きたいのか? このコースは、あなたが“ありたい自分”として生き、キャリアをデザインしていくための思考と行動のガイドになります。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年11月制作)
会員限定
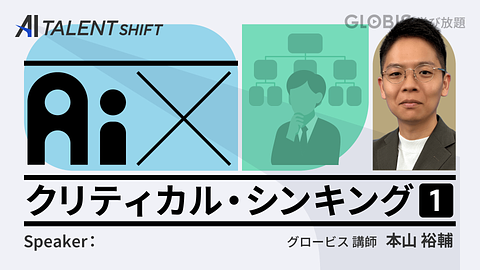
【AI×クリティカル・シンキング】①イシューと枠組みでプロンプトを磨く
生成AIから期待する回答を引き出せず、試行錯誤を重ねていませんか。 本コースでは、生成AI活用の質を高める鍵として、クリティカル・シンキングの視点からイシュー設定と枠組みを押さえる重要性を解説します。 目的に直結する問いの立て方や、プロンプトに落とし込む際の実践ポイントを具体例とともに学ぶことで、AIをより思考のパートナーとして活用できるようになります。 生成AIを業務で使い始めた方から、活用を一段深めたい方まで、再現性あるプロンプト設計を身につけたい方におすすめの内容です。 さらに学びを深めたい方は、こちらも合わせてご覧ください。 【AI×クリティカル・シンキング】②AIの弱点との向き合い方 https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/cdfe41e3/learn/steps/62198 ※本コースは、AI時代のビジネススキルを学ぶ「AIタレントシフト」シリーズの一環として提供しています。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
会員限定

リーダーの挑戦⑤ 藤田晋氏(サイバーエージェント代表取締役)
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第5回目のゲストは、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋氏。起業の理由、経営をどうやって学んだか、アメーバブログ・ABEMAの立ち上げ、経営チームづくりについてなど聞いていきます。(肩書きは2020年12月11日撮影当時のもの) 藤田 晋 サイバーエージェント 代表取締役 堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
会員限定

ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 前編 なぜ眠れないのか?~
「仕事が終わらないから睡眠時間を少し削ろう…」「業務時間中なかなか集中できない…」「毎日朝起きるのがつらい…」。 あなたはこのような経験をしたことはありませんか? 仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削りがちなのが「睡眠」時間。 実は今、日本社会は世界と比較して「最も眠らない国」だということもわかってきています。 慢性的な睡眠不足は、心身の健康に悪影響なだけでなく、仕事のパフォーマンスにも当然大きな影響を与え、社会全体の経済損失につながります。 このコースでは、基本的な睡眠リテラシーを学んだ後の「問題解決編」として、「なぜ多くのビジネスパーソンは眠れないのか?」について解説していきます。 ▼本コースで学べる主な内容 ・そもそも眠れないことは何が問題なのか? ・眠れなくなってしまう原因とは? 睡眠不足の原因は認知機能の問題にありました。 自身の睡眠不足に対し、正しく「気づき・理解し・行動を変える」第一歩を踏み出しましょう。 ▼関連コース ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~リテラシー編~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/24575c03/learn/steps/53129 ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 後編 どうしたら眠れるのか?~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/4ba981e9/learn/steps/62042 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

大阿闍梨 塩沼亮潤が死の手前で見つけた「生き方」
あすか会議2018 第4部分科会B-1「極限の世界で見つけた人生の歩み方」 (2018年7月7日開催/国立京都国際会館) 1300年間で2人目となる大峯千日回峰行満行を果たした塩沼亮潤大阿闍梨。48キロの山道を1日16時間掛けて歩き、それを千日間に亘って続ける過酷な行の中で、どのような悟りを得たのか。そして、9日間、断食・断水・不眠・不臥を続ける四無行満行という極限の世界で何を見つけたのか。塩沼氏が「創造と変革の志士」へ贈る「人生の歩み方」とは。(肩書きは2018年7月7日登壇当時のもの) 塩沼 亮潤 慈眼寺 住職
無料
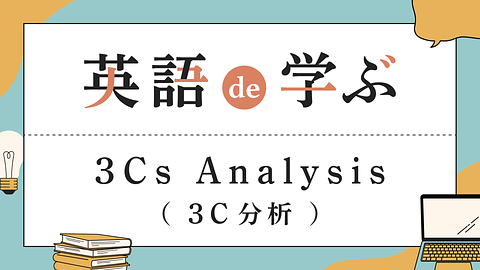
英語 de 学ぶ!3Cs Analysis(3C分析)
このコースでは、グロービス学び放題の英語版である『GLOBIS Unlimited』のコースの中から、ビジネスで役立つ頻出の英語表現をピックアップしています。英語ネイティブの方が実際に見ているコースなので、リアルなビジネス英語の表現を学ぶことができます。 今回のコースは「3Cs Analysis(3C分析)」です。一緒に『英語で』ビジネス知識を学んでいきましょう! ▼今回扱ったUnlimitedコース続きは下記からご覧いただけます 3Cs Analysis https://unlimited.globis.co.jp/en/courses/da5ca962/learn/steps/36362 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
コメント40件
a_7636
法務を10年以上やっている者です。
デザインについては全くの素人です。
私も「いい感じで」「なるはやで」という依頼をしながら、起案したドラフトに「なんか
イメージ違う」と言われると「もっと具体的に例を出してくれないと分からない」と戸惑うし、
逆に微に入り細に入り表現を指定されると「そこは私の経験に任せて欲しい」と思うことも
あります。
その道のプロに任せるところと、自分で判断すべきところは似ているのかもしれません。
共通点に気づけて、今後デザインのお仕事をされている方とのコミュニケーションの仕方を
工夫できるようになれたのは、大きな収穫だと思いました。
hirokiyui
類似事例を集めつつ言語化してイメージを伝える、ただし、一つに決めつけず、複数提示する、デザイナーの考えに配慮する、ということを気を付けたいと思います。
ushi_ff
デザインは人依存性の高い主観的なものというイメージがあったが、論理的に考えることが可能だということに気づけた。
行間、文字の太さが与える影響などを学べたが、他の観点も多数あると思うので別途学んでいきたい。
また、何事もそうだが目的が何か、その目的に対して優れているか否かを論理的に言語化することは重要で、日々の業務で意識していきたい。
masa-ota
デザインは主観的でなく客観的・論理的に考えることが重要
そのためには関係者がデザインというものを学び共有すること、個人としても感性を磨く(興味を持ってデザインを見ること)ことも大切である それにより、より論理的に伝え、判断することができる
suzume114
なんとなくのセンスで決めていた部分や、好き嫌いの判断で決めていたとこがあったが、目的に最適化されているかを考えることによって、本来訴求したいことが伝わるものを選別できることが理解できた。また、発注依頼側もデザインの知識を得ることで、デザイナーとの認識のズレをなくせることがよく理解できた。
syousei
この学習で非常にデザインに興味がわきました。自分が携わるビジネスシーンでも報告資料やプレゼンでデザインセンスが問われます。引き続き学習したい。
ayapen
デザイナーに発注する際に、細かく伝えるべきこと逆にそうすべきでないことがクリアになった
shingo_tokimoto
会社内でのデザイン発注でよくあるシーンがいくつか見受けられました。社内はもちろん、デザイン会社にも伝えたい内容でした。
my-dream
デザインは感ではなく、目的や対象に照らし合わせて、しっかり理由をつけて判断することが大事
t000
発注の際に、具体的過ぎる指示を出してしまいがちだったので目的や印象を伝え、より良いものができるようにしたいなと思いました。
tsukamotoya
業務に活かしていくよう努力していきます
hironorih415
デザイナーとのコミュニケーションを学ぶ事ができた
sept__mers
デザインが苦手で避けてきたのに、女性だからという理由でデザインをやらされる意味がわからなかった。デザインには理由があって、全員が腹落ちするまで、一つの具体的なイメージを追求していくこと、誰がターゲットなのかを明確にすることが大切だと気付いた。
tosan103
日頃何気なく目にしているTVCMや看板、ポスター等が何を伝えたいのか?その先の本質や目標、目的は何かも考え自身の感性を磨きロジカルな思考へ結びつける。
st82201
もう一回学びます。段階が早かった
mdr_
デザインを伝えることも、受ける側もなかなかここは難しい点だったので、ペルソナ設定やターゲットの大事さに気付きました。
yokot3
日々の他部門への業務依頼と同じと認識した
semskkw
デザインには理由がある。
デザインを観察し、言語化するトレーニング、日頃から取り組んでみたいと思いました。
nsi-tag
デザインも論理的に考える必要があるとわかった。主観中心だと、その時のメンバーによって結果も変わってきますね。
tokoko
最終判断をする人にデザインリテラシーを学んでもらうことが難しそうなのが
ネックかと思いました。結局多数決で決めている状況を変えたいと思います。
minoru_okada
デザイン発注のポイントについて理解が深まりました。
デザインには理由がある事を念頭におきたいと考えます。
everest
デザインは感覚でなく判断軸を持つことが重要だと学んだ。
mmotty
自分で普段やっていることが正しかったという認識。
ms09rs
デザインの業務に特化した事案ではなく,他の業務(特に建設関連業務は類似)でも同様に,関係者が1つのイメージを共有することが重要であることを理解した。各立場で所掌すべき役割(依頼内容を具現化できる説明をする側と形にする側)を理解することがプロジェクトを成功させるの必須事項であることを理解した。
jh2026
主観で判断しない!
デザインも理路整然と判断する!
tm16tm
デザインをデザイナーさんにお願いするにあたってのポイントが整理でき、接し方の対応がよく分かりました。
h_yamahi
細かな具体的要求とそうでない部分の使い分けは、なかなか難しい判断だった。
koichi-kun
デザインに関わる側面においては、いずれもターゲットなど論理的に指向していくシーンが多いと感じました。
tmtm33
デザインを発注するうえで、同じリテラシーを持っている人間同士またはある程度デザインに精通している人間同士でないと
主観や見た目でしか判断されないため同じ目線合わせが準備で必要というところは改めて大事だと感じました。
また、デザインといってもシステムのデザインであったりパッケージのデザインなどその用途や業種によってもデザインの伝え方を変えたり
事前準備の内容を変えるなど臨機応変に対応が必要であると思いました。
umejuen
とっても参考になりました。ありがとうございます。
ic434
イメージの言語化は、ビジュアルデザインの世界と同様、製品設計でも使えると感じた。
matsutake-999
デザインの方をお呼びして商品デザイン決定に関わるワーキングを開催する側として、注意すべきポイントをわかりやすくお伝え頂ける内容でした。
t_shibayama
製造職であるが資料など目的に最適かを考えてつくるようこころがけたい
mytricht_13
業務に活かせるよう復習もしておく。
nikoniko_t
デザインを外注、発注することはないが、ボンヤリしたイメージで多人数で話しを進めるのも同じ感じと認識した。参考例を複数用意したうえで関係者の方向性を一致させる必要が重要だと学んだ。発注など外部の専門性の高い人へお願いする場合は、絞り込みすぎない…学ぶました。
t-ohshima1226
デザインって大切と思う気持ちが大切と思う。
miwako_miura
ペルソナを想定し、目的に沿ったデザインを心がける。
k-kuroki
自分の持っているイメージを言語化する力を持つことが大事である感じた。日々、何気ないキャラクターだったり、ロゴであったり視覚に入るものの構成要素を自分の頭で解釈することで、良いトレーニングになるのではないかと感じた。
choppedpork
プレゼンのデザイン。まずはCopilotに指示してアウトプットを見るところからはじめてみたい
sphsph
なるほど、納得します。
とはいうもののまだまだ実践には望めない状況です。
分かったような気にならないように、地道に日々感じられるようにアンテナを研ぎ澄ませます。