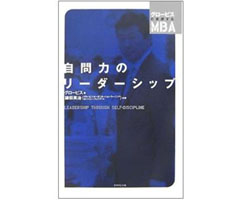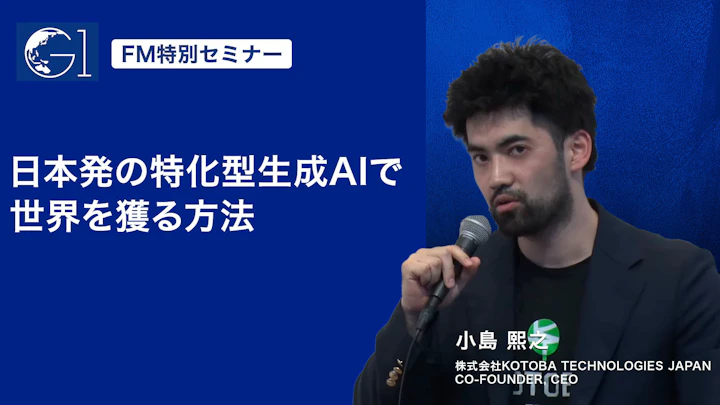TV脚本家による「ドラマ仕立ての物語」と、模擬授業のような「ライブ解説」でリーダーシップを醸成する書籍『自問力のリーダーシップ(グロービスの実感するMBA)』(グロービス・著、鎌田英治・執筆)から、勤め先の倒産という危機に追い込まれたリーダーの苦悩を描いた第5章「リーダーの責任 真の自立に向けて リーダーに求められる気構え、意識、姿勢」の内容を、今回、発行元であるダイヤモンド社のご厚意により、特別に再掲載します。書籍には、このほか様々なシチュエーションの物語と解説を掲載していますので、是非、そちらも手に取ってご覧ください。
(1.Story)経営破綻!高杉部長の起死回生
会社
(株)日本産業銀行
昭和27年、長期資金の安定供給を目的に設立。戦後日本の「産業育成」に大きな役割を担う。独自の「金融債」を発行し、企業の設備投資や地域開発など、長期の融資を専門に行う。一般には「産銀」の愛称で親しまれる。その後、企業の資金需要が低下し、企業そのものの信用力が向上した1980年代以降は、ノンバンクを通じた融資活動や、不動産・流通・建設のいわゆる三業種への融資に傾斜し、膨大な不良債権の山を築く。1998年10月に経営破綻。当時の社員はおよそ4000人。
主人公
高杉 隆太郎(46)
経営破綻時は38歳。妻と一人息子の3人暮らし。札幌市生まれ。北海道大学経済学部卒業後、日本産業銀行に入社。日露戦争の戦費調達に外債を発行、日本の財政政策の基礎を築きながら二・二六事件で殺害された宰相・高橋是清の生き方に感銘。自らも「金融」を通じて社会に貢献したいと銀行への就職を決める。産銀入行後はさまざまな部署と業務を担当し、数多くの先輩・同僚に恵まれる。責任感の強い熱血漢で、部下からついたあだ名は「軍曹」。産銀が経営破綻したときは、関連の信託銀行の営業部長だった。
背景
戦後、重工業への融資を通して日本の経済発展に大きな貢献を果たした産銀だが、他の銀行と同様、バブル期の不動産投資に失敗。1990年代にはその不良債権と系列ノンバンクの負債処理に追われる。98年、浪速銀行との統合に活路を求めるが、経営悪化によって破談。これによって経営破綻に追い込まれ、RCC(預金保険機構)が0円で株式を強制取得し、特別危機管理銀行=国有化となる。
ゆっくりとしたテイクバックから、ドライバーをフルスイングするとボールは低い弾道から一気に加速し、ピンに向かって真っ直ぐに……。
と思った瞬間、途中から急激に右にスライスし、ラフの向こうの崖に消えた。
「オイオイ、いきなりOBかよ」
「練習のしすぎじゃないのか」
「会社もゴルフも、軌道を外れたら仕舞いだぞ」
一瞬、森林と西口が凍りついたような表情で福島をにらんだ。
「え……冗談だよ冗談! そんなにナーバスになるなよ!」
「まったくお前って奴はどうしてそうなんだ」
「昔から無神経すぎるんだ。それでよくカスタマー部長がつとまるな」
「高杉、スマン。別に深い意味はないんだ」
正直、高杉は小さく傷ついたが、笑ってすませた。
年に一回、東京にいる大学の同期が集って楽しむ親睦ゴルフ。
幹事の西口が気を回して、今年は中止にしようかと問い合わせてきたが、高杉はあえて開催を主張した。変な同情はイヤだったし、気晴らしにもなると思った。
産銀の「破綻」が不可避なのは、連日のマスコミ報道で世間に知れ渡っていた。
実際、社内にいても、抗いようのない大きな「うねり」を肌で感じていた。
気がつかない間に、櫛の歯が抜けるように社員は辞めていたし、集まれば必ず口をついて出た上層部批判もめっきり聞かれなくなった。社内に「諦め」が支配し始めていた。
確かに、そんなときにゴルフどころではなく、出がけに妻が「大丈夫なの?」と怪訝な顔をしたのも無理はなかった。スコアでもよければ気晴らしになったが、一番ホールでOBを叩いた動揺が最後まで尾を引いたのか、スコアは散々の出来だった。
「やっぱりゴルフってのはメンタルなスポーツだなあ……」
「ハハ……ま、今日はそういうことにしておこう」
「で、どうなんだ、銀行のほうは?」
ビールで顔を真っ赤にした森林が口を開くと、話題はやはり産銀に集中した。
「どうもこうも……上からの指示が一切なくなった。静かなもんさ」
「不良債権の処理に奔走してるわけか。さしずめ嵐の前の静けさってところだな」
「しかし、もうどうにもならんだろ、ここまで来たら。無駄なあがきだ」
「なんでノンバンクにあそこまで貸し込んだんだ。どう考えても異常としか思えんな」
高杉はいちいち反論する気はなかったが、これまで散々、世間から批判を浴びてきたうえに大学時代の仲間にまで非難がましいことを言われて、さすがに苛立ちを抑えられなかった。
「わかってたさ。飛ばしも何もみんな薄々はわかってたさ。でも、俺たち中間管理職に何ができたって言うんだ。自分の銀行をつぶしたい人間なんて一人もいない!」
「怒るなよ。別にお前を非難しているわけじゃ……」
気まずい雰囲気が流れたが、それをとりなすように西口が高杉にビールをついだ。
「バブルだよ。みんなバブルのせいだ。日本中が儲けの幻想に踊らされた! 俺たちだって似たようなもんじゃないか。俺も森林も福島も……みんな明日はわが身だ」
その西口が再就職の話を持ってきたのは、ゴルフの一週間後だった。
通りを挟んだ喫茶店の窓からは、産銀の豪奢なビルが目の前に見える。
バブル末期、大手町から移転してきたこの本店ビルは、その豪華さと奇抜なデザインで評判を呼んだが、いかにも地に足がつかない不安定なデザインだった。
「聞きしに勝るバブリーさだな。こんな無駄な金を使う余裕があったら……」
「まったくだ。風水的にもどうなんだか」
就職話は、西口が勤める大手物流会社と取引のある金融コンサルタント会社だった。
「そこの専務と仲がよくてな。お前のことを話したらぜひ会ってみたいと……」
「スマンな、いろいろ気を遣わせて」
「早いほうがいいんじゃないのか? お前は義理固い人間だから、抵抗はあるかもしれんが先のない会社にしがみついていても仕方がないだろ。切り替えも大事だぞ」
「わかっているけど、まだそういう気になれないんだ。現実に、部下もいるしな」
「なんだ、沈没船の船長のつもりか?」
「そんなカッコイイ話じゃないさ。ただ踏ん切りがつかないだけなのかもしれん」
「まったく……お前らしいけど、時にはドライに決断することも必要だろ」
「それに……まだ完全に望みがなくなったわけじゃないんだ」
「浪速銀行との経営統合の話か? ありゃ、まとまらないってもっぱらの噂だけど……」
高杉は相変わらず忙しかった。
信用悪化による後ろ向きの仕事がほとんどとはいえ、忙しいことが何よりの救いだった。
働くことが使命感なのか、それとも現実逃避なのか、自分でもよくわからなかった。
表面上はオフィスの雰囲気も普段と変わっていない。なかには事情を知らずに資産運用の相談にやって来る年輩の新規顧客もいて、そのときはさすがに複雑な思いだった。
結局、西口の再就職話は断った。断ったが……その瞬間、ふいに生じた「未練」の感情に高杉は思わず狼狽した。明らかにゆれていた。
外回りから帰ると、部下の山崎と池辺から会議室に呼ばれた。
差し出されたのは辞表だった。
池辺が辞めたがっているのは気づいていたが、山崎はちょっと意外だった。
「いろいろ面倒見てもらった部長には申し訳ないと思いますけど……」
「本来なら辞表は澤井本部長に出すのがスジですが、先週から出社しておられないので」
「もう決めたってことか?」
「え、ええ……」
「再考の余地はまったくないのか?」
「何を再考しろと言うんですか。このまま泥船に乗っていても仕方ないですから」
「産銀は泥船か?」
「そうでしょう。沈むのはもう時間の問題なんですから」
「自分たちが誇りを持って働いてきた銀行を、そんな風に呼ぶのはよせ」
「その銀行に裏切られたんじゃないですか、私たちは!」
「被害者意識しかないのか、お前は? 銀行員としての責任はどうなる」
「責任?」
「俺たちは裏切った側でもあるんだぞ。世間を裏切り、顧客や株主を裏切り、金融機関としての信頼を裏切った……その責任はどうなる?」
「それは上が勝手にやったことじゃないですか」
黙っていた山崎が、救いを求めるような目で言った。
「部長はどうされるつもりなんですか」
「俺は最後まで残る。可能性があるうちは努力しようと思う。銀行マンの責任としてな」
「わかりません、僕には。いったいどんな可能性があるんですか?」
高杉が一瞬、言葉につまると、池辺が呆れたような表情になった。
「部長は根っからの軍曹なんですね。負け戦がわかりきっているのに突撃しろって言うのと同じじゃないですか。いまどき、軍隊なんかついていけません」
「池辺さん、やめてください」
「銀行マンの責任って何です? ここで残れば、そりゃカッコイイかもしれませんけど、じゃあ、部長は私たちの人生に責任を持ってくれるんですか!」
池辺の目には涙があった。高杉はそれ以上、何も言えなかった。
問1 高杉さんの態度をあなたはどう評価しますか。
庭には、妻が丹精した秋バラやコスモスが美しくゆれていた。
三年前にちょっと無理をして購入した自宅は、まだローンの大半が残っていたが、引っ越しを契機に本格的にガーデニングを始めた妻は、いまは庭づくりに夢中になっている。
もともと草花の類には無頓着な高杉も、そんなイキイキとした妻の姿を見るのはやはり嬉しく、四季折々に美しさを変える庭の草花は、いわば家庭の「平和」の象徴だった。
しかし……最近は、ふと不安がよぎる。
この平和を、妻が生きがいを注ぐこの庭や家を……守ってやれるだろうかと。
もともと高杉は、会社の愚痴や心配事を家庭には持ち込まないのが信条で、妻もほとんど聞いてくることがなかったのに、連日のマスコミ報道は、さすがに止めようがない。
産銀と浪速銀行の経営統合が破談に終わったことを伝えるテレビのニュースを、食い入るように見つめていた妻が心配顔で振り返った。
「つまり縁談が壊れたってこと?」
「ああ。世話になった仲人に強引に結婚を勧められたが、花嫁に途方もない借金があることがわかって、花婿がビビり、慌てて断ったという、情けない三文芝居だな」
「どうなるの、花嫁は?」
「借金がある限り、もう縁談は無理だろうな」
「借金はどうにかならないの?」
「残念ながら、もはや、どうにかなるような額じゃない」
深いため息をついた妻が、何を思ったか、つとめて明るい顔で言った。
「いざとなったら、私もパートで働くわよ」
「パート?」
「そう、お隣りの高田さんも、ご主人がリストラにあって、奥さんが先月から駅前のスーパーでパートを始めたの。私もそのくらいだったら……」
自分の仕事が原因で、気苦労をかける妻が不憫(ふびん)だった。
「どんなことになったって、お前と雄一ぐらいは俺が責任持って食べさせる。心配しなくていい!」 それは自分自身に言い聞かせる言葉でもあった。
また新たに三人の辞表を預かった。
二〇人いた部下はついに七人にまで減って、さすがにオフィスにも落魄の感が漂う。
もはや、辞めていく部下を引き止める論理も言葉もなかった。
「部長は私たちの人生に責任を持ってくれるんですか!」
池辺に言われた一言が、いまも臓腑をえぐられるように思い出される。
もとより他人の人生に責任を持つことなど、できようもないこととはわかっていても、辞めていく人間を慰留することさえできない、その最低限のやさしささえ通じない、過酷で非情な現実が、そこにはあった。
その三通の辞表と書類を抱えて、高杉は本店の人事部に向かった。
事務の女性社員も辞めてしまったため、すべて自分でやらなければならない。
手続きを終えて帰ろうとしたとき、奥の机に人事担当取締役の石神の姿が見えた。
高杉にとっては横浜支店時代の直接の上司で、結婚のときの仲人でもあった石神は、裏表のない率直な人柄で、誰よりも尊敬できる上司の一人だった。
久しぶりに見る石神の頭には、驚くほど白いものが増えていた。
「頭だけじゃなくて、最近は不整脈も出てボロボロだ。お前も大変だろう」
「いや、石神さんに比べたら私なんて……会社、どうなりますか?」
「RCCを通じての国有化の道筋はもう固まったようだ。あとはその受け皿のスキームづくりで、ひと月以内には結論は出るだろう」
「そうですか……」
「再就職、動いているのか?」
「いえ、まだ何となく踏ん切りがつかなくて」
「ハハ、お前らしいな。率直に言ってもいいか?」
「ええ」
「どのような体制になろうとも、関連会社や取引先に出向している人間が、銀行本体に帰る席は用意できないだろうな。自分で生きる道を探したほうがいい」
その夜、高杉は珍しく一人で遅くまで飲んだ。
新人時代から通い続けてきた神田の居酒屋のオヤジも、しばらく見ない間に自慢のもみあげにめっきり白いものが増えていたが、陽気な笑顔はそのままだった。
石神の言葉は自分に対する、心情あふれる「リストラ勧告」だったと、高杉は思う。
踏ん切りがつかず、ズルズルと「決断」を先延ばしにしている自分に、厳しい現実を明確に伝えてくれた。……その率直さが、石神ならではのやさしさだった。
「うまい! ここのモツ焼きの味は変わらないなあ」
「世の中ドンドン変わっていくのに、こんなことでいいのかな、なんて思うけどさ」
「それがいいんじゃないか。何でも変わればいいってもんじゃないさ、世の中」
「高杉さんとこ、いろいろ大変みたいだけど、大丈夫なの?」
「大丈夫じゃないよ。今日、ハッキリと引導渡されてきた。来月からは失業保険」
「そうなの。ま、俺なんか女房にしょっちゅう引導渡されてるけどね」
そう言うなり、ビールが目の前にドンと置かれた。
「え……なに?」
「いろいろご苦労さんってことで、俺からのサービス! ねぎらいビールだよ」
「いつからそんな人情サービス始めたんだよ」
「俺もいままでに何軒、店つぶしたことか。でも、まあ、生きてりゃ何とかなるもんよ。人生いろいろあらあな!」
お茶の水駅のホームの上空に、冴え冴えとした満月が出ていた。
最終電車を待ちながら、高杉は不意に悪寒にも似た身震いを覚えた。
銀行がつぶれる、どうすればいい、何に頼ればいい……初めて実感する恐怖だった。
これまで「銀行」という安全で巨大なシェルターに守られてきた、企業人としての自分の人生が、その生活が、まさしく音を立てて瓦解していく実感が襲ってきたのだった。
やはり家は売らなければならない……。
雄一の進学も高校までで諦めなくては……。
そんな絶望の中で、後悔と自己嫌悪が一気に胸に突き上げてきた。
いったい自分の銀行員としての矜持は何だったのか……。
不良債権などの事実を知りながら、上層部批判を繰り返すばかりで、なぜ体を張ってでも体制を変えようとしなかったのか……。
辞めていく人間に、通りいっぺんの「責任感」や、根拠のない「可能性」を語りながら、ズルズルと自分自身の「決断」を先延ばしにしてきたのは、最後になれば誰かが何とかしてくれるかもしれないという、甘えがあったからではないのか……。
骨の髄まで「護送船団方式」に毒されていたのは、実は自分ではなかったのか……。
次々とわき上がってくる思いは酔いのせいばかりでなく、高杉はその息苦しさに、思わずホームのベンチに倒れかかった。石神が口にした「自立」という言葉が、酔った頭の中で何度も浮かんでは消えていった。
日本産業銀行は一九九八年一〇月、経営破綻。そして国有化。
翌一九九九年、譲渡先が決まり、高杉隆太郎はそれを見届けるように銀行を去った。
最後の最後まで踏みとどまったのは、企業の「死に方」を見届けたいという思いとやはり銀行マンとしての使命感だった。
問2 高杉さんの内省・自問をあなたはどのように感じますか。
国有化に伴う不良債権処理で巨額の公的資金が投入されたにもかかわらず、産銀は、その後、「ハゲタカ」の異名で名高い米国の外資系ファンド「ウォルバーグ・グループ」を中核とした投資組合にわずか一〇億円で経営譲渡された。
外資の軍門に下ったとも言える、その再生スキームのあり方については、当時、マスコミを中心に賛否渦巻いたが、とにもかくにも産銀は「自立」への道を歩み始めた。
そして、高杉隆太郎もまた、人生の再生をかけた新しい「自立」の舞台へ……。
「組織にとってリーダーの条件って、何だと思いますか? 宮本さん」
「視野の広さでしょうか。常に全体を見渡すことができる人っていうのか……」
「視野の広さ……なるほど、大事な要素ですねえ。じゃあ、高田さんは?」
「やっぱり人望というか信頼というか……部下がついていくような人じゃないと」
「人望、信頼……大切ですねえ。ドラッカーもリーダーの定義を、フォロアー(つき従う者)のいる人と言っていますが、まさにその通りですね。もう一人、山下さん!」
教室は今日も熱気につつまれていた。
受講生たちの真剣な視線と対峙するとき、ディスカッションで手ごたえのある意見が出てきたとき、高杉は無上の喜びを感じる。やり甲斐と言ってもいいかもしれない。
彼は現在、企業研修やビジネス・スクール事業を運営する「フューチャーズ経営大学院」で教壇に立っている。大企業を中心とした三〇~四〇代のビジネスパーソン、中間管理職を対象にしたリーダーシップ教育が仕事の中心だ。
産銀を退職後、先輩や知人から再就職の誘いはいくつもあったが、銀行に対する失望感は自分でも予想以上に強く、金融関係への再就職はすべて断った。
大企業ではなく、たとえ小さくても自分の力が活かせる職場で働きたい……。
できることなら、「企業倒産」という負の体験も含めて、自分が産銀で経験した一六年間を何か意味のあることに活かしたい、誰かのために役立てたい……。
そんな思いから、ヘッドハンティング会社の知人に紹介された現在の職場に決めた。
当時はまだ社員五〇人ほどの小さな会社だったが、社内には成長力がみなぎっていた。
ここで働きたい、自分もここで成長したい……心からそう思った。
「リーダーになると、どんないいことがあるんでしょうか?」
「どうしても肌の合わない上司がいるんですが、どうしたらいいですか?」
「いまプロジェクトで、ちょっと壁にぶつかっているんですが……」
「先生にとって、銀行の倒産は人生にプラスでしたか、マイナスでしたか?」
受講生たちからぶつけられる率直な疑問や質問は、高杉にとって大きな刺激だった。
真剣に組織に向き合おうとしているビジネスパーソンがこれほどいるとは、正直、思わなかったし、淡々としているように見えて、実は自己実現や自己成長への希求が強いことにも驚かされた。 産銀時代、ともすれば組織に埋没し、ルーティンの仕事に追われるまま、無意識のうちに「寄らば大樹」に陥っていた自分を、大いに恥じた。
それを感じるのは教室だけではない。
入社時もいまも、高杉にとって職場のスタッフのほとんどが年下だ。
銀行時代は、相談したりアドバイスを受けたりするのは上司や先輩がほとんどだっただけに、年長者のいないいまの職場は少々勝手が違った。
自分が手本にならなければと、妙に力んだこともあった。
しかし、年下の人間の礼儀正しさに感心したり、考え方に共感したり、その発想の柔軟さに舌を巻くことは再三だった。学ぶことはどこにでもあった。
以来、大ファンである吉川英治の著作に出てくる「我以外、皆我が師なり」という言葉が自らのモットーとなった。自らを鍛え高めるためには、あらゆることから謙虚に学ぶ姿勢が必要なのだ。
「えー、また海軍ですか!」
「先生、ホント、好きですねえ」
「ちょっとアナクロニズムと違いますか」
高杉がいつものようにホワイトボードにその五カ条を書き始めると、生徒から一斉にヤジが飛ぶ。
戦中、江田島の海軍兵学校の生徒たちが唱えた「五省」だ。
当時のエリートたちが、国のリーダーたらんと理想に燃え、自らを律したその言葉は、時代を超えて現代に通じるものがあると、高杉は思う。
一つ、至誠に悖るなかりしか
一つ、言行に恥ずるなかりしか
一つ、気力に缼くるなかりしか
一つ、努力に憾みなかりしか
一つ、不精に亘るなかりしか
現代のリーダーたちが「五省」によって自らを省みる。
高杉にとっては、それはもちろん自らへの問いかけ、自問でもある。
企業の将来を担う彼らに、自分の経験を伝えたい……。
そして、自分自身も学び続けたい……。
銀行という大きな庇護を抜け出し、高杉の本当の「自立」への道が始まった。
問3 あなた自身のリーダーとしての気構えを言語化してください。
本稿の著作権は著者・グロービスに帰属しています。内容の無断転載、無断コピーなどはおやめください。また、私的利用の範囲を超えるご使用の場合は、グロービスおよび出版社の承諾書と使用料が必要な場合があります。