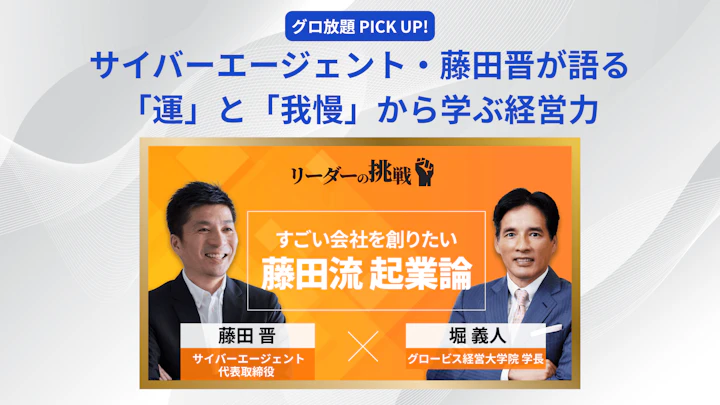日本は英米の猿真似をすべきでない――。日本を愛し、日本型経営のコンセプトをまとめあげた故ジェームス・C・アベグレン氏のメッセージを振り返る。1万冊読破を目標に掲げる田久保善彦による「タクボ文庫」第8回。

ここ1年ほど、グロービス経営大学院大阪校で講師を担当することが多くなっています。昨年は大阪に30泊以上しました。グロービスは名古屋にもキャンパスがあり、よく学生の皆さんから、「東京、大阪、名古屋でクラスの雰囲気とか違うのですか?」と聞かれます。クラス自体はあまり変わりませんが、クラスの後に学生の皆さんと行く懇親会の「濃さ」は地域によってだいぶ違うと思います。おそらく多くのグロービス講師も同意見ではないかと思います。どこがどうという話はここでは避けますね^^。
その懇親会の場で、昨年11月ごろ、「タクボ文庫は新書の紹介が多いですね。たまにはハードカバーも紹介してください」と言われたことがあります。出来るだけ手軽で読み応えのある本を取り上げようと心がけてきましたが、世の中には色々なニーズがあるものです。そこで今回はハードカバーの本2冊をご紹介します。
『新・日本の経営』 ジェームス・C・アベグレン・著 山岡洋一・訳 日本経済新聞社・刊 2004年
グロービス経営大学院が立ち上がったのは2006年の4月でした。その際、名誉学長に就任くださったのが、ジェームス・C・アベグレン先生です。ボストンコンサルティンググループの創設メンバーの一人。日本支社の初代代表を務め、『日本の経営』という著作で日本的経営論をまとめられるなど、様々な分野でご活躍をされた方でした。
先生にはグロービス経営大学院の「日本企業経営」という科目をご担当いただきました。クラスの準備に際しては、グロービス経営研究所の君島朋子さんと一緒にお手伝いをさせていただいたことを、昨日のことのように思い出します。ミーティングの度、優しく丁寧に色々なことを日本語で教えてくださいました。アベグレン先生にほぼ個人指導に近い状態で教えをいただくという貴重な時間でした。非常に印象に残っている先生の教えは次の五つです。
●目先のことを考えずに、20年、30年という長いスパンでものを考えなさい。
●会社という単位でばかりものを見ずに、地域、国、そしてグローバルといったマクロな視点を持ちなさい。
●比較をするときはアメリカとだけ比較してはだめ。欧州と比較することを忘れないようにしなさい。
●アメリカ的であることと、グローバルであることは違うことをしっかり認識しなさい。
●日本はすばらしいものを、たくさん持っているのだから、日本人としてもっと自信と誇りを持ちなさい。
そして、最も感銘を受けたのは80歳を過ぎてなお、新しいことへの興味がつきることなく、「一緒に本を書こう」「論文を書こう」「ケースを作ろう」とおっしゃっていたことです。時おり、「先週の新聞のあの記事は読んだ?」という風に質問され、こちらが困ってしまうこともありました。
そのアベグレン先生は昨年5月に他界されました。本当に残念でなりません。先生の最後の著作、多くの方に読んでいただきたいと強く思い、ご紹介します。山岡さんの翻訳も秀逸だと思います。
この本の中で最も印象に残っているフレーズです。この本を読んで元気づけられる日本人はきっと多いのではないかと思います。是非、オリジナルの『日本の経営』の新刊とあわせてお読みください。
日本の経済と企業は、健全性を維持しようとするのであれば、英米流の制度と価値観の猿真似をするべきではない。そして自国を卑下し否定的にとらえる日本の習慣によって、日本的経営の強みを損なう結果にならないように注意しなければならない。
日本企業は社会組織であり、共同体なのだ。物理的資産や金融資産の集積に過ぎないものではない。
ここ何年かは日本にとって「失われた十年」になり、日本経済は「停滞」しているとする見方が常識になっている。まったくばかげた見方だ。日本経済は停滞するどころか、産業の再構築と再設計をきわめて活発に進めてきた。
『影響力の法則−現代組織を生き抜くバイブル』 アラン・R・コーエン、デビッド・L・ブラッドフォード・著 高嶋成豪、高嶋薫訳 税務経理協会・刊 2007年
ビジネスパーソンが抱える悩みの中で、とりわけ多いのは「コミュニケーション」に関する問題でしょう。怒鳴り散らす上司、言うことを聞いてくれない部下、相性の合わない同僚たちとどう接したらいいのか。日々悩み、試行錯誤されていることと思います。最近ではフラットな組織が増えた結果として、かえって指揮命令系統があいまいになり、様々な課題も発生しているようです。
そこで紹介したいのが、米国のバブソン大学で教鞭をとるアラン・R・コーエン氏の著書。真っ赤な表紙に白い文字が印象的なこの一冊は、米国はもとよりヨーロッパ各国、中国、インド、ロシア、南アフリカなどで幅広く支持されているといいます。
この本のコンセプトは一つ。レシプロシティ(reciprocity、互恵性)です。
「一般的に、誰かのために何かをした場合、相手はこちらに対して恩を感じると考え、また同等の見返りがあると期待する」
それゆえに、
「人を動かすには、相手が求める何かを提供し、こちらのほしいものと価値の交換をする」
このコンセプトを実現するためにすべきことを、短い事例をはさみながら極めてわかりやすく解説してくれます。まずは基本的な法則です。
法則1「味方になると考える」
法則2「目標を明確にする」
法則3「相手の世界を理解する」
法則4「カレンシーを見つける」
法則5「関係に配慮する」
法則6「目的を見失わない」
具体的に何をすべきか、どんなことに気をつけるべきか、など、かなり詳細に書き込まれています。特に「第8章 上司に影響を与える」、「第9章 やっかいな部下を動かす」は実際のビジネスで困ったときにも参考になるはずです。
私個人としては、「なにが人を動かすのか―相手の世界を知る」という章が一番印象深く、注意して生きていきたいと思った箇所を引用します。
相手の世界を理解する際に 注意すべき自作の壁
●あなたの自覚だけ必要な場合
・自分が得たいものにこだわり、相手のニーズを見ていない
・相手の抵抗は組織的な要因のために起きているとは考えず、全て性格のせいだと思い、相手の個性や意図や知性を悪く言う
・相手の世界に馴染みがないので、ヒントが見つけられず、勝手な解釈をする
・相手の言葉、特に懸念に関する言葉に注意深く耳を傾けない
・質問しない
●あなたの態度が問題の場合
・相手が防衛的になったり、怒りそうな責め口調で質問する
・影響力を与えるのが難しい相手を避ける
・たったひとつの情報から結論を導く
・相手の世界を理解して相手を動かそうとせず、相手の世界自体を非難する