初稿執筆日:2014年2月17日
第二稿執筆日:2016年2月10日
小惑星探査機はやぶさが世界で初めて月以外の天体小惑星イトカワの固体表面に着陸してサンプルを採取して地球に帰ってきたのは2010年のことだ。日本の宇宙技術の高さを示すものであり、今後の宇宙工学の発展にも大きく寄与する偉大な成果といえよう。
しかし、はやぶさの成功がクローズアップされる日本の現状は、あまりにも研究に偏っている日本の宇宙政策の姿を現しているとも言えよう。世界の宇宙政策は、もはやビジネスの世界での競争に移っているのだ。
アメリカのSpace Foundation(宇宙財団)が発行する「Space Report」によると、世界の宇宙産業の市場規模(商業ベースと政府の宇宙支出の合計)は、2014年で3300億ドルと巨大で、過去5年で約40%も拡大している。もともと世界の宇宙開発を牽引してきたアメリカ、ヨーロッパ、ロシアは、以前から宇宙の産業化、宇宙ビジネスの展開に力をいれており、今後も世界の宇宙産業の市場規模は拡大していくだろう。
欧米だけではない。中国は、低コストを武器に商業衛星の打上げを進めており、大型衛星の開発・製造技術も保有している。世界のマーケットに進出し、海外への輸出実績もある。
ひるがえって日本はどうか。日本の宇宙機器産業の売上は約2600億円、米国の1/15で、輸出実績は170億円規模に過ぎない。
これは、これまでの日本の宇宙政策に原因がある。日本の宇宙開発は歴史的に宇宙開発事業団(現JAXA)による「研究目的」中心の施策が進められてきた。宇宙ステーション、科学衛星、H2Aロケットなどで技術は高いが産業力の向上をそもそも指向してこなかった。
政府の宇宙予算も、文部科学省によって大学などでの一過性の研究衛星の開発に大半が費やされてきた。そこに産業化、競争力強化という視点はない。技術体系も研究に偏重しているため、高コスト体質や開発期間の長期化など、産業競争力強化に必要な「低コスト、短納期」といった視点が欠けていたのだ。
2008年にようやく宇宙基本法が制定され、研究中心であった宇宙開発を利用ニーズ主導にという政策目的の転換がなされたが、未だ宇宙産業で世界に遅れを取っている現状は変わらない。今こそ、拡大する世界の宇宙市場を日本の高い技術で獲得していく政策に舵を切るべきだ。
1. 宇宙の利用サイドたる防衛・ビジネスが宇宙開発を主導する体制を作れ!
日本の宇宙開発が「研究中心」に偏ってしまった最大の原因は、宇宙分野の最大のユーザーである「防衛(軍事)」を平和利用原則の名の下、宇宙開発から切り離してきたことによるところが大きい。
「100の行動 防衛省編」で提言したように、「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」いわゆる「宇宙条約」により、全世界で宇宙の平和利用が定められている。日本以外の諸外国では、この平和利用原則は「非侵略」と解されている。
一方、日本では、政府答弁において「平和の目的に限り」という文言を、「非侵略」ではなく「非軍事」と解した。その結果、防衛省による衛星等の宇宙施設の利用が原則禁止され、宇宙の最大のユーザーたる防衛分野が宇宙の研究開発を牽引することができず、研究中心の宇宙開発が行われてきてしまった歴史がある。
しかし、宇宙開発は数少ない成長分野の1つである。ユーザーたる防衛分野と民間ビジネスが一体となって宇宙開発を引っ張っていくことが合理的なのは、世界の常識だ。世界各国が宇宙利用を軍事、ビジネスともに積極的に進めている現在、日本だけが固有の宇宙の平和利用原則の解釈で軍事を宇宙から切り離すのはナンセンスだ。
政府は一刻も早く宇宙の平和利用原則の解釈を国際スタンダードの解釈に変更し、さらに、JAXAと防衛省技術研究本部が共同研究を行える体制を作って、限られた予算をユーザーオリエンティッドな宇宙開発に集中投資できる体制を作るべきだ。
政府が利用サイド重視の宇宙開発を牽引し、その宇宙開発の成果を防衛、ビジネスに最大限活用して日本の競争力を高める体制が早期に確立することを望む。
2. 【宇宙技術からのスピンオフ】民間主導の宇宙開発で産業の裾野を広げ、イノベーションを起こせ!
宇宙開発は、常に新技術への挑戦である。宇宙開発によって生まれた技術が宇宙以外の分野のさまざまな場面で活用されるスピンオフの事例は極めて多い。
古くは、たとえば医療機器や照明装置などで使われるレーザー技術はアメリカのアポロ計画で地球と月の距離を測定するために生まれた技術だし、スペースシャトルの宇宙服の技術からは、バスケットボール・シューズが開発された例もある。
火星軟着陸探査機からは自動車のエアバッグが開発されたし、身近なところでは、構造設計技術から、缶チューハイの缶などに使われるダイヤカット缶も生まれている。太陽電池や燃料電池といった技術も宇宙技術からのスピンオフだ。
つまり、宇宙開発は、新産業のイノベーションを起こす宝庫であるといえよう。政府は、日本経済の成長戦略の重要な一部として、宇宙予算を長期にわたって確保すべきだ。かつ、宇宙開発は、民間主導で進め、産業の裾野を広げる努力をしてもらいたい。
下の表は内閣府の資料だが、世界の宇宙開発関連企業をみると、欧米の企業が上位を独占している。日本勢ではわずかに衛星を製造する三菱電機が20位圏内に入るのみだ。後で述べるロケット打ち上げに関しても、国内の開発主体は三菱重工に限られている。さらに懸念されるのは、関連企業の撤退数の多さだ。日本ではこれまで宇宙産業の官需が限定されてきたため、関連企業の撤退が相次ぎ、技術の承継が危ぶまれる事態が続いてきた。欧米では、スペースXなどのベンチャー企業が宇宙開発を担っている例も多い。

政府は、先述のようにJAXAと防衛省技術研究本部の共同開発などによる宇宙開発予算の統合などで、十分な宇宙予算を確保するとともに、民間主導の開発体制を築くことで、宇宙関連産業の育成と、スピンオフによる新産業の創造を早急に取り組む体制をつくるべきだ。
3. 【地球観測衛星】商業・軍事デュアルユースの解放と民間主導の開発を!
日本政府が運用する情報収集衛星は、北朝鮮による弾道ミサイル発射を契機に導入され、昨年レーダー4号機の打ち上げに成功して当初予定から10年遅れてようやく本格運用となった。運用計画の遅れは打ち上げ失敗やレーダー衛星の故障などによるが、本格運用には光学衛星とレーダー衛星各2基の「4基体制」が必要で、2013年にやっと態勢が整った形だ。しかし、同年11月には、2006年に打ち上げた「光学」2号機との通信が途絶えてしまっている。これは衛星の設計寿命の5年をオーバーしているためで、やむを得ない事態だといえる。
いずれにしても、日本の情報収集衛星の現状はお粗末と言えるだろう。
先述の日本固有の「非侵略」宇宙の平和利用原則は、「自衛隊が衛星などを利用する場合、民間で一般的に利用されている技術レベルに限定する」という「一般化原則」に進化し、このため、日本が現在運用している情報収集衛星も衛星の解析能力が民間並みに抑えられているが、運用・開発の遅れのため、地上の物体を識別する能力(解像度)は光学が約60センチ、レーダーが約1メートルに留まっている。その後2015年3月には「光学」5号機が打ち上げられ、過去最高の解像力40センチまで精度を上げたが、それでも、アメリカの民間商業衛星の光学約30センチ、レーダー50センチに劣り、アメリカの偵察衛星の光学10数センチにははるかに及ばない。政府による発注が少なくマーケットが小さいため、開発価格も高騰して国際競争力がない状態だ。
情報収集衛星は、要は宇宙から地球の写真を撮る「リモートセンシング」を行う地球観測衛星の一種だが、地球観測衛星の用途は、軍事目的に限らず、気象観測、防災、災害対策、資源探査、地図作成など幅広い。
日本でも情報収集衛星の他、陸域観測技術衛星「だいち」、静止気象衛星「ひまわり」、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」などが政府によって運用されている。(なお、情報収集衛星はあくまでも非軍事目的であるため、日本では偵察衛星は保有していない)
アメリカでは、偵察衛星技術を民間企業に開放し、政府が民間衛星の画像を長期にわたって購入する契約を結び、かつ、開発費用の支援も行うことで、アメリカの地球観測衛星ビジネスの競争力が強化されている。ヨーロッパでも同様に、官民連携による高解像度の観測衛星の開発・運用が進められている。
日本でも、政府は民間主導の衛星開発・産業競争力強化を図るため、民間の開発支援と、長期の画像購入契約によるマーケットの一定の保障などの形で地球観測衛星分野の産業競争力強化を進めるべきだ。
その際ネックになるのが、日本の官需の小ささになる。このためにも、「非侵略」の宇宙の平和利用原則といった非合理的な解釈を取り払って、情報収集衛星(軍事)とその他の地球観測衛星(非軍事)のデュアルユースを可能にして、地球観測分野の需要をできる限り大きくし、民間への発注増で市場を大きくすべきだ。
4. 【準天頂衛星】7基体制を早期に実現し、ビジネスチャンスの拡大を!
日本は、世界最大のGPS利用国だ。言うまでもなくGPSはアメリカのシステムだが、日本では、GPSの補完を目的として準天頂衛星システムを開発し、2010年9月に1号基を打ち上げている。準天頂衛星の本格運用には4基体制が必要だが、政府の計画では2017年から19年にかけて、その4基体制を整備し、2025年度までに7機体制を目指す計画だ。
準天頂衛星システムは、衛星が日本のほぼ真上を通り、日本上空からオセアニア地方にかけて八の字に回る軌道を持つ。衛星が真上(天頂)に近い位置から測位できるため、山やビルに遮られることが少なく、アメリカのGPSによる即位が10m程度の誤差範囲である精度を1mレベルにまで向上させることができるのだ。
7基体制が整えば、日本だけでなく、アジア・オセアニア地域にもその機能を展開することが可能であり、GPS測位関連のビジネスチャンスが大幅に拡大するはずだ。また、アメリカのGPSシステムに完全に依存しきっている現状から、測位システムの精度向上が可能な準天頂衛星システムで日米協力を進めれば、宇宙分野における外交上/安全保障上の日本のバーゲニングパワーの向上にも寄与する。
ヨーロッパの調査では測位関連ビジネスの市場規模が2025年に56兆円に拡大するとのデータもある。早期に準天頂衛星7基体制を整備し、測位分野での国際競争力を構築すべきだ。
5. 【ロケット】低コスト化で世界のマーケットを獲得せよ!
現在、世界のロケット打上げ実績は、年間平均約70機(そのうち、2/3が政府、1/3は商業用)だが、日本の打上げ実績は世界の4%にすぎず、国際競争力は非常に弱い。世界の商業ロケットマーケットはヨーロッパのアリアンとロシアのプロトンでシェアがほぼ二分されている。
日本の大型主力ロケットであったH-2A/B(エイチツーA/エイチツーB)は、24機中23機成功(成功率95.8%)しているなど、技術水準は世界レベルだが、需要は年間4回程度のJAXAによる国内官需にほぼ限られるため、競争力はない。海外市場に関しては、韓国のコンプサット3を受注した実績があるのみだ。
しかし、最近は日本のロケットにも新たな萌芽が出始めている。2013年に打ち上げに成功した、JAXAの新型ロケット、イプシロンは打ち上げ費用の低コスト化に挑んでいる。量産時の打ち上げ費用は1回30億円を見込んでおり、固体ロケットの先代にあたるM-5(ミューファイブ)は打ち上げ費用が約75億円だったから、半額以下に圧縮したことになる。日本の固体ロケットは、2006年に予算削減のためM-5の開発が停止されて以来止まっていたが、2009年からイプシロンの開発が再開され、開発期間3年という短期間でM-5の性能第一主義を捨てて、低コスト化と打ち上げ作業簡素化に成功した形だ。
さらに、2014年からは、日本の基幹ロケットであるH-2A/Bの後継であるH-3の開発が始まっている。H-3は、打ち上げ能力をこれまでの1.4倍に増やし、大型衛星まで対応能力を高める。打ち上げ間隔も従来の半分の1カ月以下に短縮、価格も半分を目指す計画だ。
イプシロンやH-3の開発が順調に進めば、日本のロケットビジネスの国際競争力は高まるはずだ。今後拡大する世界のロケット市場を獲得するため、低コスト化や打ち上げ間隔短縮など、競争力重視の開発を進めてもらいたい。
6. 官民合同ミッションで世界に日本の宇宙技術を売り込め!
これまで述べてきたように、宇宙のマーケットは、大きく分けて、地球観測衛星、測位衛星、ロケット打ち上げに加えて、通信衛星などの静止衛星がある。通信衛星に関しては、日本にもアジア最大の通信衛星企業であるスカパーJSATがあるが、1990年のいわゆる日米衛星調達合意により、実用分野の衛星は原則として国際入札となったため、通信放送衛星の大部分(17機中16機)は米国企業が受注しているという悔しい状況だ。
今後は、国内宇宙産業の競争力を強化していくほかないが、海外マーケットを獲得していくために、官民合同で海外への宇宙産業の売り込みを進めるべきだ。特に新興国における宇宙産業は大幅に拡大すると予想され、地球観測衛星利用分野では今後10年で4倍に成長すると見込まれている。
政府は、宇宙産業におけるパッケージ型インフラ輸出を促進するため、民間企業とともに世界各国を訪問し、ワークショップの開催等を行う官民合同ミッションの派遣を積極的に行っている。ここ数年で東南アジア、中央アジア、南米、アフリカ諸国にミッションを派遣しており、2011年には日本企業がトルコから通信衛星を受注し、同年、ベトナムに対して地球観測衛星の開発・利用のための円借款の実施が決定されるなど、成果も出ている。大いに評価したい。
これまでは欧米が独占してきた海外市場だが、トップセールスを含めた官民合同での売り込みで、競争力を強化した日本の宇宙産業が海外市場を獲得していくことを大いに期待したい。
この「行動」で見てきた通り、宇宙の「非軍事」原則により、JAXAと防衛省が分断され、しかも事業用途への展開が遅れているのが現状だ。防衛省、JAXAそして民間がオールジャパンで連携することにより、研究中心型の発想から、防衛・事業中心へと発想転換する必要がある。さもないと、日本の宇宙戦略は、米国、EU、ロシア、中国に大きく取り残されることになるであろう。
大いなる夢がある宇宙分野において、日の丸が大きくはためく姿を見たいではないか。そのためにも、今こそ抜本的な発想の転換が必要なのである。


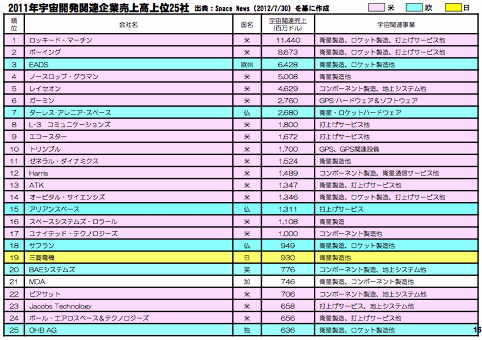













.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)





.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
